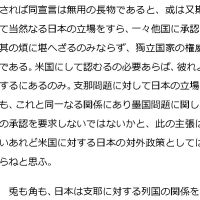福澤諭吉

十一編 名分をもって偽君子を生ずるの論
第八編に、上下貴賤の名分よりして夫婦・親子の間に生じたる弊害の例を示し、
「その害の及ぶところはこのほかにもなお多し」 との次第を記せり。
そもそもこの名分のよって起こるところを案ずるに、
その形は強大の力をもって小弱を制するの義に相違なしといえども、
その本意は必ずしも悪念より生じたるにあらず。
畢竟(ひっきょう)
世の中の人をば悉皆(しっかい)愚にして善なるものと思い、
これを救い、
これを導き、
これを教え、
これを助け、
ひたすら目上の人の命に従いて、
かりそめにも自分の了簡を出ださしめず、
目上の人はたいてい自分に覚えたる手心にて、
よきように取り計らい、
一国の政事も、
一村の支配も、
店の始末も、
家の世帯も、
上下心を一にして、
あたかも世の中の人間交際を親子の間柄のごとくになさんとする趣意なり。
譬(たと)えば十歳前後の子供を取り扱うには、
もとよりその了簡を出ださしむべきにあらず、
たいてい両親の見計らいにて衣食を与え、
子供はただ親の言に戻(もと)らずしてその指図にさえ従えば、
寒き時にはちょうど綿入れの用意あり、
腹のへる時にはすでに飯の支度ととのい、
飯と着物はあたかも天より降り来たるがごとく、
わが思う時刻にその物を得て、
何一つの不自由なく安心して家に居(お)るべし。
両親は己(おの)が身にも易(か)えられぬ愛子なれば、
これを教え、
これを諭し、
これを誉(ほ)むるも、
これを叱るも、
みな真の愛情より出でざるはなく、
親子の間一体のごとくして、
その快きこと譬えん方なし。
すなわちこれ親子の交際にして、
その際には上下の名分も立ち、
かつて差しつかえあることなし。
世の名分を主張する人は
この親子の交際をそのまま人間の交際に写し取らんとする考えにて、
ずいぶん面白き工夫のようなれども、
ここに大なる差しつかえあり。
親子の交際はただ智力の熟したる実の父母と
十歳ばかりの実の子供との間に行なわるべきのみ。
他人の子供に対してはもとより叶(かな)い難し。
たとい実の子供にても、
もはや二十歳以上に至ればしだいにその趣を改めざるを得ず。
いわんや年すでに長じて大人となりたる他人と他人との間においてをや。
とてもこの流儀にて交際の行なわるべき理なし。
いわゆる願うべくして行なわれ難きものとはこのことなり。
さて今、
一国と言い、
一村と言い、
政府と言い、
会社と言い、
すべて人間の交際と名づくるものはみな大人と大人との仲間なり。
他人と他人との付合いなり。
この仲間付合いに実の親子の流儀を用いんとするもまた難きにあらずや。
されども、たとい実には行なわれ難きことにても、
これを行のうてきわめて都合よからんと心に想像するものは、
その想像を実に施したく思うもまた人情の常にて、
すなわちこれ世に名分なるものの起こりて専制の行なわるる所以なり。
ゆえにいわく、
名分の本(もと)は悪念より生じたるにあらず、
想像によりてしいて造りたるものなり。
アジヤ諸国においては、国君のことを民の父母と言い、
人民のことを臣子または赤子(せきし)と言い、
政府の仕事を牧民の職と唱えて、
支那には地方官のことを何州の牧と名づけたることあり。
この牧の字は獣類を養うの義なれば、
一州の人民を牛羊のごとくに取り扱うつもりにて、
その名目を公然と看板に掛けたるものなり。
あまり失礼なる仕方にはあらずや。
かく人民を子供のごとく、
牛羊のごとく取り扱うといえども、
前段にも言えるとおり、
そのはじめの本意は必ずしも悪念にあらず、
かの実の父母が実の子供を養うがごとき趣向にて、
第一番に国君を聖明なるものと定め、
賢良方正の士を挙げてこれを輔(たす)け、
一片の私心なく半点の我欲なく、
清きこと水のごとく、
直(なお)きこと矢のごとく、
己が心を推して人に及ぼし、
民を撫(ぶ)するに情愛を主とし、
饑饉(ききん)には米を給し、
火事には銭を与え、
扶助救育して衣食住の安楽を得せしめ、
上(かみ)の徳化は南風の薫ずるがごとく、
民のこれに従うは草の靡(なび)くがごとく、
その柔らかなるは綿のごとく、
その無心なるは木石のごとく、
上下合体ともに太平を謡(うた)わんとするの目論見(もくろみ)ならん。
実に極楽の有様を模写したるがごとし。
されどもよく事実を考うれば、
政府と人民とはもと骨肉の縁あるにあらず、
実に他人の付合いなり。
他人と他人との付合いには情実を用ゆべからず、
必ず規則約束なるものを作り、
互いにこれを守りて厘毛の差を争い、
双方ともにかえって円(まる)く治まるものにて、
これすなわち国法の起こりし所以なり。
かつ右のごとく、
聖明の君と賢良の士と柔順なる民とその注文はあれども、
いずれの学校に入れば、
かく無疵(むきず)なる聖賢を造り出だすべきや、
なんらの教育を施せばかく結構なる民を得べきや、
唐人も周の世以来しきりにここに心配せしことならんが、
今日まで一度も注文どおりに治まりたる時はなく、
とどのつまりは今のとおりに外国人に押し付けられたるにあらずや。
しかるにこの意味を知らずして、
きかぬ薬を再三飲むがごとく、
小刀細工の仁政を用い、
神ならぬ身の聖賢が、
その仁政に無理を調合してしいて御恩を蒙らしめんとし、
御恩は変じて迷惑となり、
仁政は化して苛法となり、
なおも太平を謡わんとするか。
謡わんと欲せばひとり謡いて可なり。
これを和する者はなかるべし。
その目論見こそ迂遠なれ。
実に隣ながらも捧腹(ほうふく)に堪えざる次第なり。
この風儀はひとり政府のみに限らず、
商家にも、
学塾にも、
宮にも、
寺にも行なわれざるところなし。
今その一例を挙げて言わん。
店中に旦那が一番の物知りにて、
元帳を扱う者は旦那一人、
したがって番頭あり、
手代ありて、
おのおのその職分を勤むれども、
番頭・手代は商売全体の仕組みを知ることなく、
ただ喧(やかま)しき旦那の指図に任せて、
給金も指図次第、
仕事も指図次第、
商売の損得は元帳を見て知るべからず、
朝夕旦那の顔色を窺(うかが)い、
その顔に笑(え)みを含むときは商売の当たり、
眉の上に皺をよするときは商売の外(はず)れと推量するくらいのことにて、
なんの心配もあることなし。
ただ一つの心配は己が預かりの帳面に筆の働きをもって
極内(ごくない)の仕事を行なわんとするの一事のみ。
鷲(わし)に等しき旦那の眼力もそれまでには及び兼ね、
律儀一偏の忠助と思いのほかに、
駆落(かけお)ちかまたは頓死のその跡にて帳面を改むれば、
洞(ほら)のごとき大穴をあけ、
はじめて人物の頼み難きを歎息するのみ。
されどもこは人物の頼み難きにあらず、
専制の頼み難きなり。
旦那と忠助とは赤の他人の大人にあらずや。
その忠助に商売の割合をば約束もせずして、
子供のごとくにこれを扱わんとせしは旦那の不了簡(ふりょうけん)と言うべきなり。
右のごとく上下貴賤の名分を正し、
ただその名のみを主張して専制の権を行なわんとするの原因よりして、
その毒の吹き出すところは人間に流行する欺詐(ぎさ)術策の容体なり。
この病に罹(かか)る者を偽君子と名づく。
譬(たと)えば封建の世に大名の家来は表向きみな忠臣のつもりにて、
その形を見れば君臣上下の名分を正し、
辞儀をするにも敷居(しきい)一筋の内外(うちそと)を争い、
亡君の逮夜(たいや)には精進(しょうじん)を守り、
若殿の誕生には上下(かみしも)を着し、
年頭の祝儀、菩提所(ぼだいしょ)の参詣(さんけい)、
一人も欠席あることなし。
その口吻(こうふん)にいわく、
「貧は士の常、尽忠報国」
またいわく、
「その食を食(は)む者はその事に死す」などと、
たいそうらしく言い触らし、
すはといわば今にも討死(うちじに)せん勢いにて、
ひととおりの者はこれに欺かるべき有様なれども、
竊(ひそか)に一方より窺えば、
はたして例の偽君子なり。
大名の家来によき役儀を勤むる者あれば、
その家に銭のできるは何ゆえぞ。
定まりたる家禄と定まりたる役料にて一銭の余財も入るべき理なし。
しかるに出入(しゅつにゅう)差引きして余りあるははなはだ怪しむべし。
いわゆる役得にしもせよ、賄賂(わいろ)にもせよ、
旦那の物をせしめたるに相違はあらず。
そのもっともいちじるしきものを挙げて言えば、
普請奉行が大工に割前(わりまえ)を促(うなが)し、
会計の役人が出入りの町人より付け届けを取るがごときは、
三百諸侯の家にほとんど定式(じょうしき)の法のごとし。
旦那のためには御馬前に討死さえせんと言いし忠臣義士が、
その買物の棒先(ぼうさき)を切るとはあまり不都合ならずや。
金箔付きの偽君子と言うべし。
あるいはまれに正直なる役人ありて賄賂(わいろ)の沙汰も聞こえざれば、
前代未聞の名臣とて一藩中の評判なれども、
その実はわずかに銭を盗まざるのみ。
人に盗心なければとてさまで誉(ほ)むべきことにあらず。
ただ偽君子の群集するその中に十人並みの人が雑(まじ)るゆえ、
格別に目立つまでのことなり。
畢竟この偽君子の多きもその本(もと)を尋ぬれば古人の妄想にて、
世の人民をばみな結構人にして御しやすきものと思い込み、
その弊ついに専制抑圧に至り、
詰まるところは飼犬に手を噛(か)まるるものなり。
返す返すも世の中に頼みなきものは名分なり。
毒を流すの大なるものは専制抑圧なり。
恐るべきにあらずや。
或る人いわく、
「かくのごとく人民不実の悪例のみを挙ぐれば際限もなきことなれども、
悉皆(しっかい)然るにもあらず。
わが日本は義の国にて、
古来義士の身を棄てて君のためにしたる例ははなはだ多し」と。
答えていわく、
「まことに然り、古来義士なきにあらず、
ただその数少なくして算当に合わぬなり。
元禄年中は義気の花盛りとも言うべき時代なり。
この時に赤穂七万石の内に義士四十七名あり。
七万石の領分におよそ七万の人口あるべし。
七万の内に四十七あれば、
七百万の内には四千七百あるべし。
物 換(か)わり星移り、
人情はしだいに薄く、
義気も落花の時節となりたるは、
世人の常に言うところにて相違もあらず。
ゆえに元禄年中より人の義気に三割を減じて七掛けにすれば、
七百万につき三千二百九十の割合なり。
今、日本の人口を三千万となし義士の数は一万四千百人なるべし。
この人数にて日本国を保護するに足るべきや。
三歳の童子にも勘定(かんじょう)はできることならん」
右の議論によれば名分は丸つぶれの話なれども、
念のためここに一言を足さん。
名分とは虚飾の名目を言うなり。
虚名とあれば上下貴賤 悉皆(しっかい)無用のものなれども、
この虚飾の名目と実の職分とを入れ替えにして、
職分をさえ守ればこの名分も差しつかえあることなし。
すなわち政府は一国の帳場にして、
人民を支配するの職分あり。
人民は一国の金主にして、
国用を給するの職分あり。
文官の職分は政法を議定するにあり。
武官の職分は命ずるところに赴きて戦うにあり。
このほか、
学者にも町人にもおのおの定まりたる職分あらざるはなし。
しかるに半解半知の飛び揚がりものが、
名分は無用と聞きて、
早くすでにその職分を忘れ、
人民の地位にいて政府の法を破り、
政府の命をもって人民の産業に手を出だし、
兵隊が政(まつりごと)を議してみずから師(いくさ)を起こし、
文官が腕の力に負けて武官の指図に任ずる等のことあらば、
これこそ国の大乱ならん。
自主自由のなま噛(かじ)りにて無政無法の騒動なるべし。
名分と職分とは文字こそ相似たれ、
その趣意はまったく別物なり。
学者これを誤り認むることなかれ。