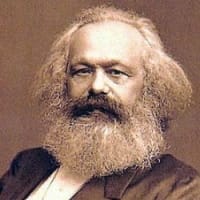取引動機と予備的動機を満たすために保有する現金量をM1、投機的動機を満たすために保有する現金量をM2としよう。これら二つの現金区分に、二つの流動性関数L1とL2を対応させる。L1は主として所得水準に依存し、L2は主として現行利子率と期待の状態の関係に依存する。そうすると、
M=M1+M2=L1(Y)+L2(r)
となる。ただし、L1は所得Yに対応する流動性関数で、M1を決定し、L2は利子率rの流動性関数で、M2を決定する。したがって検討すべき事柄は、(一)Mの変化とYおよびrとの関係、(二) L1の形状を決めるもの、(三) L2の形状を決めるもの、これら三つである。
このL2はどのように決定されるか?(あるいはされないか)
ここでケインズは債券市場を例に取っている。後に出てくるが金融市場はアメリカでは株式、イギリスでは債券のようである。
以下に引用するが〔〕内訳注は取消線を引いた。誤読である。
第二に、rのどのような低下も非流動性の期間収益――これは資本勘定上の損失の危険を相殺するための、一種の保険プレミアムとなる――〔が相殺しうる利子率の上昇〕を減少させ、その減少幅は旧利子率と新利子率のそれぞれの平方の差に等しい。
たとえば、長期債権の利子率が4パーセントだとするとさまざまな確率を勘案したうえで、長期利子率の年上昇率がその4パーセントすなわち0.16パーセントを超えるおそれはないと思われるかぎり、流動性を手放したほうが有利である。けれども利子率がすでに2パーセントにまで低下していたら、期間収益が相殺しうる利子率の上昇は年率わずか0.04パーセントにすぎない〔利子率の上昇率が0.04パーセントを超えると予想されれば、期間収益は利子率の上昇分(証券の資本損失分)を相殺しえず、流動性で保有したほうが有利になる〕。実際このようなことが主因となって、おそらく利子率はあまり低い水準にまでは下がらないのである。将来起こることは過去に起こったこととは違うと信じるに足るだけの理由がないかぎり(たとえば)2パーセントの長期利子率では、希望よりは怖れが優勢となり、しかもこの利子率では、期間収益は怖れのごく一部分を相殺するだけである。
これではわからないので、取り消し部分を削除し、ケインズの原文のみとする。(*)は筆者注となる。
第二に、rのどのような低下も非流動性の期間収益――これは資本勘定上の損失の危険を相殺するための、一種の保険プレミアムとなる――を減少させ(*1)、その減少幅は旧利子率と新利子率のそれぞれの平方の差に等しい(*2)。
たとえば、長期債権の利子率が4パーセントだとするとさまざまな確率を勘案したうえで、長期利子率の年上昇率がその4パーセントすなわち0.16パーセントを超えるおそれはないと思われるかぎり、流動性を手放したほうが有利である。(*3)けれども利子率がすでに2パーセントにまで低下していたら、期間収益が相殺しうる利子率の上昇は年率わずか0.04パーセントにすぎない。実際このようなことが主因となって、おそらく利子率はあまり低い水準にまでは下がらないのである。将来起こることは過去に起こったこととは違うと信じるに足るだけの理由がないかぎり(たとえば)2パーセントの長期利子率では、希望よりは怖れが優勢となり、しかもこの利子率では、期間収益は怖れのごく一部分を相殺するだけである(*4)。
*1:期間収益(the current earnings from illiquidity)非流動性(債権)のことであるから、現に保有している債権の期間収益は減少しない。債券価格を上昇させるが…。訳注は減少するのは「が相殺しうる利子率の上昇」としたがこれもおかしい。流動性を手放そうかどうか、の問題であるから債券価格の上昇により、流通している(売りに出ている)債権の現在時点での将来収益を減少させる。との意味である。流動性の保有者から見た話なのだ。
*2:平方の差に等しい??? 旧利子率と新利子率を債券価格に割り戻して考えるとこうはならない。なにか深遠な数式でも隠れていそうだが、たとえば、利子4%分だけを再投資しようと考えた場合、利子が4%以上に上昇するならば債券を売って乗り換えたほうがいい。つまり4%×4%=0.16%が限界ということである。債券は年間4%の収益であって複利にはならない。逆にこれ以下なら、保有し続ければいいし、もっと上がれば元本割れということもありうる。訳注のように割り戻して考えると4%×4%=0.16%の意味がわからん。読者は一度旧利子率と新利子率(例えば5%と4%)を債券価格に割り戻して考えてみていただきたい。
*3:4%の4%、ここが重要。債券の収益の再投資の話である。ここは「流動性を手放した方が有利」要は債券は「買い」だと言っている。0.16%を超える期待があるなら「売り」となる。
*4:利子率が低下すると、相殺しうる利子率の変動幅は小さくなり投資家は過敏になる。不況の時ほど金融の不安定性は増す。
ぐだぐだ書いたがここまでは前ふりで、不況になるほど流動性選好が高まり状況をさらに悪化させるということを踏まえておけばいい。この章の白眉は、だからこそだが、次に出てくる公開市場操作について言及しているところである。
大体においてこの章は引用もされないし、言及もされない。経済学者を自称する諸君はよくわからないままに「なかったこと」にしているんじゃないか?
諸君!理解できないことは理解できていないと自覚することである。なかったことにすればそこから先に進めはしない。