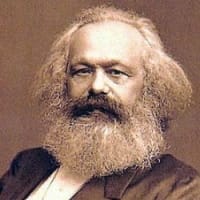人々はなぜ現金を保有するのか? 流動性への動機
この章でのケインズの理論は“実は”簡明である。さらに「流動性の罠」について言及がある。実際にケインズが行っていることは金融市場の分析である。
まず第一撃で
ここで、第13章で予備的に導入した流動性への動機について、さらに分析を深めておかなければならない。これから論じようとすることは、従来、貨幣需要という見出しで時折論じられてきたものと実質的には同じである。それはまた貨幣の所得速度と呼ばれものとも密接なかかわりをもっている。というのも、貨幣の所得速度とは大衆が所得のうちどれほどの割合を現金でもつかの測度にほかならず、貨幣の所得速度が高まるのは流動性選好が減退する兆しと見ていいからである。けれどもそれは〔流動性選好と〕同じものではない。なぜなら、人々が流動性と非流動性の選択を行うのは蓄積された貯蓄のストックに関してであって、彼らの所得についてではないからである。
ポートフォリオをどう組むか、という話だったよね。
ともあれ、「貨幣の所得速度」という言葉は、全貨幣需要が所得に比例している、あるいは所得とある一定の関係をもっていると誤って受け取られかねない。しかるにこのような関係は、後に見るように、大衆の保有する現金の一部についてのみ言えることであり、〔全貨幣需要と所得との関係として所得速度を理解すると〕利子率の果たす役割が看過されることになる。
と手厳しいが、これは現代正統派にも当てはまる。「大衆の保有する現金の一部についてのみ言える」消費する予定の現金にしか当てはまらないことを、全ての貨幣に適用するから、ただそこにある現金を見逃しているのだ。
何回か書いたように現代正統派は流動性選好の概念を受け入れた瞬間にケインズの軍門に下るしかない。だから慎重に排除されている。
現金保有の目的は?分析に値するのは投機的動機
一般理論の論旨に沿うと
まず、現金保有の目的を、所得動機、取引動機、予備的動機、投機的動機に分けていくが、そのうち所得動機、取引動機、予備的動機は「現金保有の費用(利子や銀行手数料等)に大きな変化がある場合を除くと、それほど重要な要因とは思われない」として検討の対象は投機的動機に絞られる。この投機的動機は利子率に敏感で次のようなことになる。
投機的動機を満たすための貨幣需要の全体は、経験の示すところによれば、利子率が少しずつ変化すれば通常はそれに対して連続的に反応する。つまり投機的動機を満たすための貨幣需要の変化を、さまざまな満期日の社債や公債の価格の変化によって与えられる利子率の変化に関係づける連続的な曲線が存在するのである。
ここでケインズが言っている「投機的動機」をバブルの発生と消滅という文脈でとらえてはならない。生産が活動の中にある通常の経済活動以外の、専ら金融市場において安く買って高く売ろうとする行為のことを指している。金融市場にいくら回すのかというのが投機的動機なのだ。
投機的動機による現金保有をどのように分析するのか? ⇒投機とそれ以外で分ける
取引動機と予備的動機を満たすために保有する現金量をM1、投機的動機を満たすために保有する現金量をM2としよう。これら二つの現金区分に、二つの流動性関数L1とL2を対応させる。L1は主として所得水準に依存し、L2は主として現行利子率と期待の状態の関係に依存する。そうすると、
M=M1+M2=L1(Y)+L2(r)
となる。ただし、L1は所得Yに対応する流動性関数で、M1を決定し、L2は利子率rの流動性関数で、M2を決定する。したがって検討すべき事柄は、(一)Mの変化とYおよびrとの関係、(二) L1の形状を決めるもの、(三) L2の形状を決めるもの、これら三つである。
つまり所得のうちいくらが現金保有に回るかという「流動性関数」はM1とM2で違うという話である。
所得動機は、厳密に貨幣の所得速度に対応するからここでは省かれている。分析の道具はもうあるということだ。あえて言うなら、M0=L0(Y0)と書けるが関数の形状も分かっている。所得の一定割合で所与の比率であり、利子率や貨幣量との関係で大きな変化もしない。
では現金保有量は所得と利子率からどのような影響を受けるのだろうか?
Mの変化とYおよびrとの関係(現金保有量と所得と利子率の関係)
取引動機、予備的動機を経常的動機と名づけ、投機的動機と経常的動機の二つとする。
M1:投機的動機:金融市場へ投入するかどうか
M2:経常的動機:取引動機と予備的動機
貨幣量の増加はまず所得Yの増加となる。逆も真である。⊿Yは経常的的動機の必要分を超過し、その超過分は投機的動機にまわるだろう。その結果利子率rは低下し(現金保有のことを言っているので投資需要は満たされている。投機的動機の増大は単純な需給関係から利子率を下げる)M2およびYを増加させる。増加した貨幣量⊿Mは⊿M1と⊿M2によって吸収され、新たな均衡状態に達する。よって
Mを一定量変化させたときのrの変化は、rの変化によるM1とM2それぞれの変化の合計が最初のMの変化に等しくなるほど十分なものでなくてはならないことになる。
つねに ⊿M=⊿M1+⊿M2
という、そんなことが、いつも必ず起きるのだろうか? と問うているのである
詳しくは、 第5編 貨幣賃金と物価 を待て。
所得の流通速度(貨幣の所得速度と同意)
現金保有量と所得の関係は単純な一次関数とみなされておりM/Y=Vは一定とされる。だから検討していない。
投機的動機による現金保有は? L2の形状を決めるもの
われわれは第13章で、利子率の将来の成り行きに関する不確実性こそは、人々に現金払を保有させる流動性選好の一型式L2の、唯一納得しうる説明であることを見た。もしそうなら、M2は利子率rと明確な量的関係をもたないことになる。肝腎なのは、rの絶対的水準ではなく、人々の依拠する確率計算に徴して相当安全な水準と見られているrからの乖離の度合いである。
にもかかわらず、期待の状態を、それがどのようなものであれ、所与としたときには、rの低下がM2の増加をともなうと考えられる理由が二つある。
第一に、何がrの安全水準かについて一般的な見解が変わらないとすれば、rのいかなる低下も「安全」利子率に対する相対的な市場利子率の引き下げとなり、したがって非流動性〔債券〕の危険を増大させることになる。
利子率には、これ以上下がると人々が非流動性を持とうとしないという下限がある。したがって市場利子率の低下は「危険の増大によって」流動性選好を高める。ここでは安全利子率としているが、将来に対する不確実性から人々が求める利子率ということにしておこう。
簡単に言えば額面5%の債権を持っているときに市場利子率が4%に低下すれば、債権保有者の行動は一つ、借り換えしかない。借り換えができないときには企業価値毀損のリスク(債権保有者の将来性への不安)が発生する。どちらにせよ保有している債券の将来は赤信号になる。引用の第一があれば第二がある。その第二が難読である。言っていることは簡明なんだが説明が難読である。
次項に譲る。