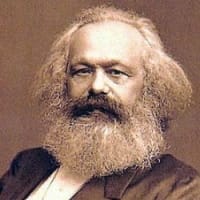金融的準備(内部留保)が雇用に及ぼす影響
社会全体として見ると、将来の消費を準備しうるのは金融的手段ではなく、ただひとえに現在の物的生産物のみである(ケインズ)
貯蓄は投資に回されてこそ意味を持つ。ただただ積み上がっていくだけの現金は将来に何も、もたらさない。
ふたたび少し長く引用する。
少し本題から逸れたようである。しかし、すでに資本の大規模なストックを有している社会では、消費のために通常使用することのできる純所得に到達するまでにその所得からいかに大きな額の控除を行わなければならないか、この点を強調しておくことは重要である。というのも、このことを見過こすと、消費性向の足を引っ張る重し、大衆が純所得の非常に大きな割合を消費する傾向にある場合でさえ存在する重しを、過小評価することになりかねないからである。
消費は、わかり切ったことを繰り返すなら、あらゆる経済活動の唯一の目的であり目標である。雇用の機会は総需要の程度によって限界を画されている。総需要を生み出すのは現在の消費あるいは将来の消費に対する現在の備え〔投資〕、ただそれだけである。〔将来の〕消費のために前もって備えをしておくのかいくら利益であるとはいえ、その消費を果てしなく将来に先延ばしすることはできない。社会全体として見ると、将来の消費を準備しうるのは金融的手段ではなく、ただひとえに現在の物的生産物のみである。われわれの社会組織と企業組織が将来用の金融的準備と将来用の物的準備とを区々に引き裂き、その結果、前者を確保しようとする努力が必ずしも後者をともなうものでなくなるとき、そのかぎりにおいて、堅実金融主義は総需要を減少させ、それゆえ福祉を損ねることにもなる。事実このことを立証する例は山とある。しかも前もって備えをしておく〔将来の〕消費が大きくなればなるほど、なおいっそうの備えをあらかじめしておくのはますます困難になり、需要の源泉としての現在の消費に依存する度合いはますます高くなる。だが具合の悪いことに、所得が増加すると所得と消費の開きはますます大きくなる。後に見るとおり、何か新しい便法でもないかぎり、この難題に対する解決策は存在しない。残るはただ失業―所得と消費の残差〔貯蓄〕が、今日生産するのが有利な将来の消費のための物的準備〔投資〕にちょうど等しくなるまで〔所得を減少させ〕、われわれを貧しくするところの失業である。
社会全体として見ると、将来の消費を準備しうるのは金融的手段ではなく、ただひとえに現在の物的生産物のみである。
この議論は積み上がった年金資産にも応用できる。
年金資産は何に「投資」されるべきであろうか?
この問題に処方箋はあるのだろうか?
********************************************
リフレ派は「異次元の金融緩和」を推進した。当時、リフレ派は「貨幣に対する選好が高まる(消費や投資に向かない)のは貨幣が希少性を持っているからである。お札を刷って配ればインフレが起き、その結果公的債務も実質上減っていく。経済は大躍進する」云々、の議論を展開していた。
当時あまりにも素朴、稚拙、世間知らずの議論に仰天したものだったが、政権の心をつかみ日銀総裁の首をすげかえることまでして異次元の金融緩和は実行された。しかも、日本の金融財政政策としては類を見ないほどの徹底ぶりであった。だから、政策が中途半端だったという言い訳は通用しない。
政権がその政策を採用したのは「財政再建」という緊縮政策と矛盾しなかったからである。リフレ政策と緊縮政策は相性が良かった。貨幣を潤沢に供給すればすべての問題は決着する、財政再建は今まで通り進めよ、と主張したのだから。
彼らは、何を間違えたのか?あるいは何を知らなかったのだろうか?
8年間のリフレ政策の結果を見て次はどういう手を打つべきだろうか?
現状ではリフレ政策の検証すら行われていないのである。
まさに経済学の落日である
しかし
ミネルヴァの梟は黄昏に飛び立つのだ