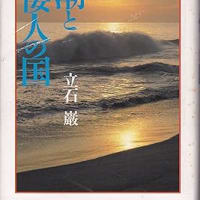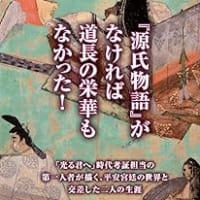新島襄はその後アメリカを訪問した木戸孝允に会った。岩倉具視を団長とする欧米視察団である。木戸は新島の人物に惚れ込み、そのプロテスタンティズムの清潔さを見た。幕府とともに消えゆく武士道をそこに見つけたのだ。福沢諭吉は著作「西洋事情」で敬虔という日本語をPietyの訳語として生み出している。プロテスタントの精神が明治の精神と共通する、というのは、両者の数々の接点を見つけられそうである。
明治維新というのは侍によって行われた革命だったといわれている。薩長が幕府側の勢力を一掃したのだが、その後の廃藩置県で侍はその地位を失う、つまり失職した。明治維新を戦ったのは侍だったのに、戊辰戦争が終わって故郷に帰ってみれば侍はなくなったといわれて怒らなかった武士はいなかったのではないか。士族反乱は全国で起きた。江藤新平も佐賀の乱を起こし、明治維新の10年後には西郷隆盛も西南の役で死ぬ。侍がなくなった後、武士道を懐かしむ元武士たちがいた。内村鑑三と新渡戸稲造、それぞれ「代表的日本人」と「武士道」という著作を残している。廃藩置県で武士が亡くなって武士道が書き物として確立されたともいえる皮肉なものである。
明治憲法は伊藤博文が中心となり、伊東已代治、井上毅が起草した。明治19-22年のことである。立憲国家のお手本はイギリス、フランス、ドイツ(プロイセン)であった。三権分立を定め、言論、著作、集会、結社の自由を認めた。昭和になって問題になるのは統帥権の独立、三権から独立して天皇の直属、しかし天皇には指図をしたり法令を作ったり人を罰する機能はなかった。イギリスでは行政府の長である首相が軍隊の最高指揮者であり、プロイセン憲法と同じ統帥権独立を規定したのが明治憲法であった。陸軍と海軍の大臣は行政権のみを持ち統帥権は持たなかった。統帥権は陸軍は参謀本部、海軍は軍令部が持ち、首相とは別に天皇を補弼し勝手に戦争を引き起こすことができたのである。これが満州事変であった。プロイセンも第一次世界大戦はカイゼルが統帥権を行使して国を滅ぼした。明治憲法は伊藤博文が全く意識しない形で統帥権という時限爆弾を仕込んでしまったといえる。明治憲法発布は1889年、時限爆弾が破裂したのは満州事変勃発の1931年とすると、42年という長期のの時限爆弾であった。
「明治」という国家〈下〉 (NHKブックス)