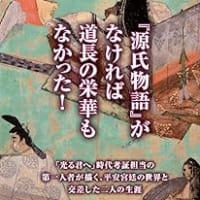方丈記の作者、鴨長明は1155年京の賀茂御祖(下鴨)神社の生禰宜であった鴨長継の子として生まれた。順調であれば父の跡をついで禰宜になるはずだったと思われるが、父が早逝、長明の人生は暗転した。父方の祖母を頼ってあとを継いでいたがその祖母も他界。鴨家と縁が切れてしまった長明は小さな庵に一人住まいを始めた。和歌には才能を見せ、34歳には千載集に1首が掲載される名誉に浴した。和歌の師は金葉集の選者である源俊頼の子俊恵。46歳になった長明は後鳥羽院主催の正治百首の歌人として選ばれ、以後、後鳥羽院の歌壇の一人として歌合に参加した。後鳥羽院に認められたのちは、新古今和歌集選集のための編集委員である和歌所の寄人に任命された。長明を評価していた後鳥羽院は下鴨神社の摂社である河合社の禰宜に推奨するが、神社統括の祐兼の反対に遭い望みは絶たれた。
50歳にして出家した長明は、その後は東山の真葛原、都の北東にある小野、そして洛南の日野で方丈を構えた。日野で描かれたという方丈記には隠遁生活の素晴らしさが記されるが、思いを遂げられなかった悔しさも滲む。1211年には鎌倉で実朝と謁見、和歌、琵琶などを披露したと思われるが、召し抱えられることなく帰京。方丈記では前半で都での生活は災難が多く、所詮はつまらないものとし、後半で草庵での生活を理想的と評した。京における安元の大火(1177年)、治承のつむじ風と福原遷都に伴う貴族たちの大混乱(1180年)、養和の大飢饉(1181年)では仁和寺の隆暁法印が死者の額に「阿」の字を書いて成仏を祈ったという。その数、京の東半分で42300人だった。元暦の大地震(1185年)と災難は続き、京は住みにくいところと嘆く。自身への自己評価は高かったが、職には恵まれなかった。冷静な観察眼、論理的思考、明快な筆致、繊細な感受性が方丈記には溢れている。方丈記完成4年後、長明は62歳でこの世を去った。
徒然草の作者兼好は1283年頃神祇官として仕えた卜部家の分家に卜部兼好(かねよし)として生まれた。父は治部少輔、兼好も20歳前後から蔵人として後二条天皇のもとに出仕、左兵衛佐となる。その後、後二条天皇が逝去すると兼好も30歳頃に出家、兼好(けんこう)となる。出家後は修学院、小野、比叡山などでの隠遁生活を送った。祖父の代から縁の深い関東に度々下向、武蔵の金沢にはしばらく住んだこともある。徒然草には関東での見聞がいくつか記される。40歳代には都に戻り、歌人、文化人として活躍、二条派の歌人として和歌四天王と称され、続千載集、風雅集などの勅撰集に入集された。
40歳代に描かれたと思われる徒然草は同時代には読まれず、室町時代になり歌人正徹に見出され(1431年)称賛されたのが評価の始まり。吉田姓は兼好没後に卜部氏が吉田神社に仕えたことで呼ばれるようになったとされる。各パラグラフは短く簡潔で、平安時代の書き物、特に枕草子を強く意識していたのではないか。内容としては、人生、政治、恋愛、友情、住居について叙述、その後無常、自然、出家、教養、財産、教訓、人間、芸術、文学、人生、体験、回想などについての考えを述べている。
季節の移り変わりの十九段。4月8日の灌仏会、賀茂の祭、5月の菖蒲のころの田植え、6月の夕顔を蚊遣り火、三十日の祓え、7月の七夕、そして夜気の冷え始める頃の雁の鳴き声、萩の下葉が黄色くなる頃、そして早稲の田を刈り上げて干す秋は思い深くなる。野分の吹く朝は興趣あるものだ。こうした枕草子や源氏物語にあるようでもある風情を楽しむことは良い。冬枯れの有り様はそうした秋にも劣らない。紅葉のちる様、霜が白く降りている朝、鑓水からも水蒸気が立様は面白い。12月に行われる宮中での御仏妙の法会、諸陵墓への奉幣使の出発なども情趣深く、新春の諸行事も誠に結構なもの。大晦日の追儺、元旦の四方拝、都大路の家々に門松が立てられるさまも情趣深いものである。
親鸞は1173年日野有範の子として生まれた。9歳で出家、比叡山で20年修行、法然の弟子となる。「南無阿弥陀仏」を唱えることで成仏できるとした専修念仏は人々から熱狂的に支持されたが、旧来の仏教からは警戒され非難された。「悪人こそが往生できる」とした悪人正機説、「生前どんな悪事を働いても念仏を唱えることで本願を遂げられる」とした「本願ぼこり」などの親鸞の教えは誤解をされやすく、他宗派から攻撃される。親鸞死後はさらに異説が唱えられ論争と混乱を招いたため、弟子の唯円が親鸞の教えと誤解を生む内容の解説をまとめたのが歎異抄。前半で親鸞の言葉を集約、後半では異説を紹介して、親鸞の真意を解説している。本書内容は以上。