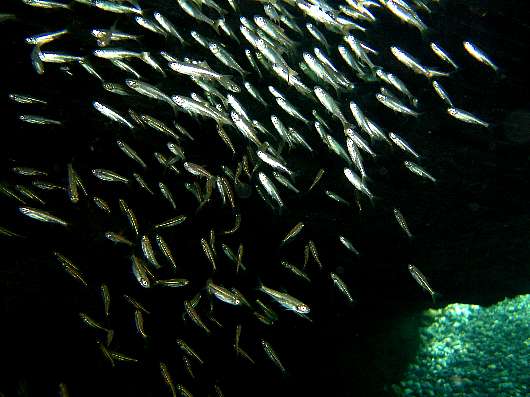以前山陰で確認した『イシドジョウ
Cobitis takatsuensis 』です。
またまた出会うことが出来ました!
前回である程度生息環境を絞り込んでいたので、割と楽に発見できました。
前の記事でも書きましたが、日本固有の小型のシマドジョウ属の魚類で、中国、四国、九州地方にのみ分布しています。
河川の上流から中流の、礫が積み重なる水通しのよい淵尻に生息しており、近年流域開発や河川事業による淵の消失、礫底の目詰まりなどで生息地は縮小しています。
前回の記事でfossil1129さんから「黄金色!」というコメントを頂きましたが、本当に他のドジョウ類とは一線を画す色をしています。

画像ではそれ程派手な色には見えませんが、実際フィールドで潜ってみると、凄く目立ちます。見ただけで「イシドジョウ!」と同定可能です。

数は少ないながらも精一杯生きています。
『生き物の生息環境を創出し、その生き物を保全する。』
文章にすればすごく簡単ですが、これ程困難な事は無いというのが携わっていての正直な感想です。
魚は水があれば大丈夫という訳ではもちろんなく、水温・水深・流況(流れの速さや方向、乱れの状況)・濁り・底質(川底が石・砂・泥など)・水質といった物理・化学条件と、餌となる生き物、生息場を同じくする生物及び外敵の状況といった生態系の条件や、生育の場、産卵の場、隠れ場などなどその生息のための必要十分条件は数え上げればキリがありません。
物理・化学条件についてはある程度は満足させる事が出来ても、生態的な条件となるとなかなか人間が思うようには創出できません。ある程度の知見や資料を駆使しても、それはあくまでも人間サイドが考える事であって、生物がこうして欲しいと言っているそのものズバリではないので...
しかし泣き言を言ったり言い訳をしても仕方が無いので、出来る限り良好な環境を創出し、生物を保全できる事を夢見て頑張るしかありません。

以降は清流域に住む『イシドジョウ』とは違い、一般的な普通の『ドジョウ』の
“はなし”です。
泥鰌(ドジョウ)といえば、童謡の「どじょっこふなっこ」「どんぐりころころ」に歌われたり、泥鰌掬いの「安来節」に登場したり、柳川鍋として食用にされたり...古くから日本人と馴染みの深い淡水魚の一つです。
ドジョウと日本人との関わりを考えると、稲作文化が切っても切り離せない役割を果たしています。稲作が始まって以来、水田は重要なドジョウの産卵場所となっています。
春になり水が温んでくると川や池沼に棲むドジョウは浅場に集まってきて、田んぼに水が張られると生息地と水田をつなぐ水路を通って水田内に進入し、一斉に産卵を行います。
もちろん一生を河川や池沼内で過ごし、岸際の浅場や植物帯で産卵を行うドジョウもいますし、一生を水田内で過ごすドジョウもいます...
んっ?田んぼは秋の刈入れ前から春先まで水が無いのでは...
大丈夫です。ドジョウ(泥鰌)は『泥生』という字を当てられるように、泥の中に潜って長期間仮眠状態で過ごせるのです。
泥は他の土や砂に比べ保水に優れ乾燥に強いため、ドジョウが潜っていても大丈夫な訳です。また田んぼに水がある時期は、水温の上昇も早いため卵から孵化までの時間も短くて済み、プランクトンや藻類、ユスリカの幼虫などの餌にも事欠きません。
その分外敵となるタイコウチ、ミズカマキリ、ゲンゴロウ、ヤゴ等水生昆虫や水鳥も集まってきますが...
つまり水田環境で一つの生態系(生態網)が構築されていた訳です。
しかし、食糧増産・機械化導入の目的で田んぼが幾何学的に整えられ(圃場整備)、合わせて水路もコンクリートの三面張り等に整えられ、田んぼ⇔水路⇔河川・池沼の間に大きな落差が設けられました。つまり水路での生息や両方の往来が出来なくなったわけです。
あとは推して知るべし、ご存知のようにドジョウのみならず水生昆虫も激減した現状があります。その要因としては農薬の使用等もあげられますが。
(ただ、圃場整備により風土病が根絶した例もあります...これはまたの機会に)
その後国の減反政策で休耕田となる田んぼが続出したり、田んぼが畑になってしまったり、生物にとっての生息の場が悪化した上に減少していった訳なのです。その時々の人間の都合で振り回されているんですね。
現在田んぼに「どじょっこ」や「ふなっこ」を呼び戻すために、田んぼと水路の行き来を可能にするような『水田魚道』の開発等も行われていますが、さらには水路内に植物が生えたり、ある程度流れが緩やかになるような工夫も必要ですね。
<in 山陰 >