雨の中頑張って潜ったお陰でちょっとした成果がありました。
『オヤニラミ』とかなり接近する事が出来ました。
潜っていて魚を見つけたときは、ほぼ相手もこちらを見つけています。
水中で急な動きをしたり近づきすぎるとモチロン魚は逃げていきます。
また、水中で音を立てるのも禁物です。
接近するためには、ギリギリ近寄れる距離を見極めて、出来るだけゆっくり近づく必要があります。
この近寄れる距離というのも、それぞれ種ごとに異なっているようです。
コレばっかりは経験が必要です。

時にはこちらに興味を持って正面を向いてじっとにらめっこをする場合もあります。
アゴから背びれ方面、体の上部に続く白い模様が印象的です。

普通『オヤニラミ』は川底や周囲に何も無い場所には居らず、上画像のように石の横や、下画像のように水草の脇など“物陰”を好む魚です。

この『オヤニラミ』が棲む場所は、川底近くの水温が水面よりかなり低いんです。
それは、上流の水が伏流し(地下を通り)、この辺りから湧き出しているからです。
こういった“湧水(伏流水)”があるということは、河床に泥などが堆積せず、底質が礫や砂である事の証明でもあるため、夏場でも水温の上昇を抑え清冽な水を供給している生物にとって快適な環境です。
下画像の『オヤニラミ』の周囲の河床には銀色の粒、つまり“気泡”がたくさん確認できます。
これは“湧水”により冷水を好む緑藻や水草が繁茂し、それらが光合成により酸素を供給するためです。
もちろんそれは魚にとっても快適な環境となります。

この『オヤニラミ』ですが、体の中にさらに魚がいると言われます。

 Click
Click 

上画像を見ると、エラの後縁の緑の模様が目の部分で、側線上の白い線が背中の輪郭を示しています。
よく見ると本体の尾鰭の付け根で白い線がちょっと向きを変え、しっかり尾鰭も描いています。
さらに本体の目から後方に口が描かれています。
(かなりタラコ唇ですが...笑)
これってやはり敵を威嚇する(驚かせる)ためのものなのでしょうか?
何気ない川の小魚にも実に興味深い事実があります。
< 中国地方の川 >















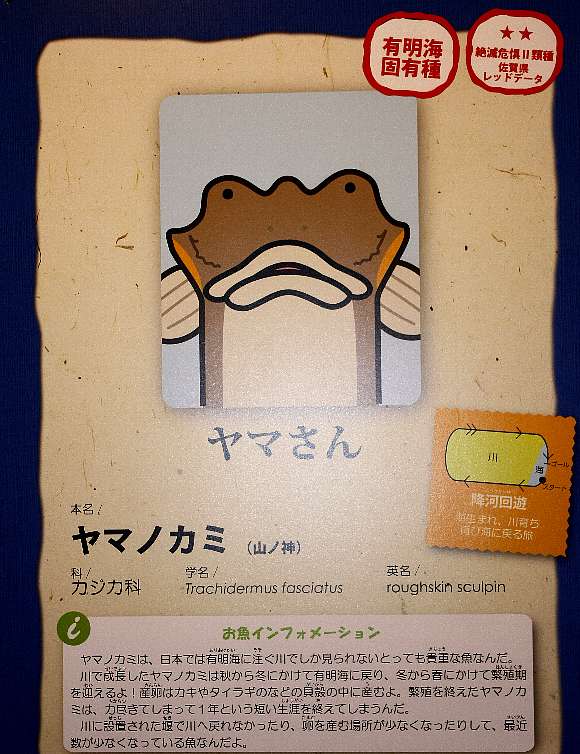














 Click
Click 































