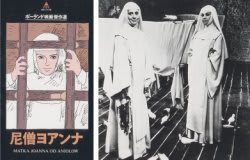
17世紀のポーランド、小高い丘に立つ壁に囲まれた尼僧院。地元の人々から“天使”と慕われていた院長ヨアンナと尼僧たちが悪魔にとりつかれる。前任神父の死の知らせを受けた敬虔な童貞僧スリンが悪魔払いのため尼僧院に単身のりこむという設定は、あの『エクソシスト』を彷彿とさせる。なにせ1961年に撮られた作品なので、悪魔にとりつかれた尼僧の首がぐるぐる回ったり、口から緑色のゲロを吐いたりするグロテスクなシーンは皆無。美しいヨアンナの顔が振り向き様に邪悪な表情に変ったり、尼僧が両手を広げながらクルクルと回ったりする程度のかわいらしい演出だが、特撮じゃない分かえってリアルに見えてくる。
よく半径30メートルのエリアしか描いていない作品をスケールが小さいとけなす人がいるが、この映画の場合、舞台が尼僧院(聖域)と宿屋(俗世)の2箇所だけという濃密な世界観がかえって功を奏している。悪とは元々人間の精神に内在するものではないか、そもそも何をして悪というのか。ユダヤ教のラビがスリン神父に問いただした究極の質問が、作品の重要なテーマとなって深く掘り下げられているからである。この辺は、(ワイダやポランスキーというよりは)宗教をベースに人間の内面を深くえぐったカール・ドライヤーやベルイマンの作品に共通するのかもしれない。
こっそり尼僧院を抜け出して宿屋をちょくちょく訪れて息抜きをしている若い見習の尼僧にだけがなぜか悪魔がとりつかない。この尼さん、こともあろうに宿屋の主人が出す酒に口をつけ歌をうたって大はしゃぎ。挙句の果てに行きずりの男と恋に落ち一晩を共にした後捨てられてしまうという、世俗にまみれきった女なのである。キリスト教的には堕落=悪ということになるのだろうが、この若い尼僧と聖女として屋根裏部屋に監禁されてしまうヨアンナを“男に捨てられた女”として同一視すると、まったく別の見方ができるから面白い。
人として自然な男女の恋愛を堕落=悪と決めつける古めかしい宗教観に疑問をなげかける本作品は、イエジー・カワレロヴィッチの二項対比的な構図がとにかく素晴らしい傑作である。ATGのオープニングを飾っただけあって、芸術性とエンターテインメント性(商業性)のバランスというかサジ加減が絶妙なのだ。悪魔が乗り移った(女の愛を知った)神父がデビルウィング?で飛び立った(であろう)シーンや、神を祝福するはずの鐘の音が故意に消されていたシーンなども非常に意味深で、二度見三度見しても新たな発見がありそうな奥深い1本である。
尼僧ヨアンナ
監督 イエジー・カワレロヴィッチ(1961年)
〔オススメ度



 〕
〕
よく半径30メートルのエリアしか描いていない作品をスケールが小さいとけなす人がいるが、この映画の場合、舞台が尼僧院(聖域)と宿屋(俗世)の2箇所だけという濃密な世界観がかえって功を奏している。悪とは元々人間の精神に内在するものではないか、そもそも何をして悪というのか。ユダヤ教のラビがスリン神父に問いただした究極の質問が、作品の重要なテーマとなって深く掘り下げられているからである。この辺は、(ワイダやポランスキーというよりは)宗教をベースに人間の内面を深くえぐったカール・ドライヤーやベルイマンの作品に共通するのかもしれない。
こっそり尼僧院を抜け出して宿屋をちょくちょく訪れて息抜きをしている若い見習の尼僧にだけがなぜか悪魔がとりつかない。この尼さん、こともあろうに宿屋の主人が出す酒に口をつけ歌をうたって大はしゃぎ。挙句の果てに行きずりの男と恋に落ち一晩を共にした後捨てられてしまうという、世俗にまみれきった女なのである。キリスト教的には堕落=悪ということになるのだろうが、この若い尼僧と聖女として屋根裏部屋に監禁されてしまうヨアンナを“男に捨てられた女”として同一視すると、まったく別の見方ができるから面白い。
人として自然な男女の恋愛を堕落=悪と決めつける古めかしい宗教観に疑問をなげかける本作品は、イエジー・カワレロヴィッチの二項対比的な構図がとにかく素晴らしい傑作である。ATGのオープニングを飾っただけあって、芸術性とエンターテインメント性(商業性)のバランスというかサジ加減が絶妙なのだ。悪魔が乗り移った(女の愛を知った)神父がデビルウィング?で飛び立った(であろう)シーンや、神を祝福するはずの鐘の音が故意に消されていたシーンなども非常に意味深で、二度見三度見しても新たな発見がありそうな奥深い1本である。
尼僧ヨアンナ
監督 イエジー・カワレロヴィッチ(1961年)
〔オススメ度




 〕
〕























