「内的独白」内的独白(internal monologue, monologue intrieur)の手法の先駆者であるエドゥアール・デュジャルダンによると、「登場人物のもっとも内奥の、もっとも無意識に近い思考——論理的に組み立てられる以前の、言いかえればまさに生れつつある状態の思考を、最小限の構文による直接的語句を用いて表現する」ことであり、多少矛盾するが「作者の干渉を抑制し、登場する人物そのものが自分自身を表現していくこと」を意図している。
この「内的独白」という小説技法が西洋に登場するのは、一九二〇年代のことである。
ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』をはじめ、プルーストやヴァレリー・ラルボーの小説が当てはまる。
これより以前に、ウィリアム・ジェームズが『心理学原理』(1890)の中には「意識の流れ」(stream of consciousness)という文学(心理学)用語があり、ある意味で、この「内的独白」と密接に関連している。
Stream of consciousness is a narrative device used in literature "to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind. Another phrase for it is 'interior monologue'. " The term "Stream of Consciousness" was coined by philosopher and psychologist William James in The Principles of Psychology (1890): consciousness, then, does not appear to itself as chopped up in bits ... it is nothing joined; it flows. A 'river' or a 'stream' are the metaphors by which it is most naturally described. in talking of it hereafter, lets call it the stream of thought, consciousness, or subjective life.
デイヴィッド・ロッジ「小説の技巧」(白水社、柴田元幸・斎藤兆史訳、1997)の中で、「意識の流れ」と「内的独白」を同じものとしている。
『・・・読者は、ちょうど誰かの頭の中にコードを差し込み、肉体的刺激や観念連想によって被験者の脳裏に呼び起こされる印象、思考、疑問、記憶、空想などを無限に録音し続けるテープをヘッドホンで傍受している格好になる。・・・』
『意識の流れ』は、日本大百科全書の解説によると、
作中人物の心理の動きをできる限り直接的に表現しようとする実験的な手法をさす。主として20世紀モダニズム文学の作家たちが用いた。名称の由来は、ウィリアム・ジェームズが『心理学原理』(1890)のなかで、人間の意識は断片的な塊(かたまり)をつなぎ合わせたものではなくて、いつも切れ目なしに流れているのだから、「思考、意識、または主観的生命の流れ」とよぶのがいいと主張したことによる。イギリスの女流作家メイ・シンクレアMay Sinclair(1863―1946)が、ドロシー・リチャードソンの連作『巡礼』(1915~1938)を評してこのことばを用いたのが定着した。作中人物の独白体を用いる点では内的独白(internal monologue, monologue intrieur)の一種であるが、思考を劇的にまたは論理的に整理して説明するのではなく、知覚、印象、感情、記憶、連想、知的思考など、意識の働きのいっさいを、生成消滅のままに、論理的な脈絡にとらわれずに表現する。文頭の大文字、句読点などの表記上の約束や、統語法はしばしば無視される。
心理の動きを正確に写実的に表現しようとする点では、リアリズム小説が到達した一つの帰結であるといえるが、ことばによって整理される前の意識の状態を提示しようとする点では、本来表現しえないものを表現する試みであり、リアリズムを超えるものを目ざしている。
ことばが意味伝達の役割から解き放たれて、独自の機能を営み始める動機がここに生じる。この手法を用いた代表的な作家には、前記リチャードソンのほか、エドゥワール・デュジャルダンdouard Dujardin(1861―1949)、バージニア・ウルフ、ウィリアム・フォークナーらがいるが、もっとも典型的な例としては、ジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』(1922)最終章における、人妻モリーの夢うつつの独白をあげることができる。
と定義(解説)されている。
優れた解釈としては、北海道大学の伊藤崇先生のhttp://finnegans-tavern.com/hce/bb/042-
『/042-内的独白について』が大変参考になりました。
エドゥアール・デュジャルダン 鈴木幸夫・柳瀬尚紀(訳) 1970 内的独白について:その出現 起源 ジェイムズ・ジョイスの作品における位置 思潮社
さらに下記のような「日本心理学会」の無料講座もあり(年内の講座は終了しています)、文藝の解釈から「心理学」へと接近するのも良いのではと考えます。
http://www.psych.or.jp/event/sympo2016_koukousei.html
高校生のための心理学講座シリーズ(日本心理学会)
■ 心理学と社会――こころの不思議を解き明かす――
概要
高校生のための心理学講座は,これまでの心理学への誤解を解き、心理学は科学的根拠に基づく科学的思考を育てる学問ということをご理解いただくためのものです。2012年度から始まりましたこのシリーズは、毎年多くの参加者から、大変ご好評をいただいております。今年度も“高校生”と“高校の先生方”を対象に、1人でも心理学分野に興味を持つ方が増えることを期待して,「高校生のための心理学講座」を開講いたします。多くの方のご参加をお待ちしております。
対象
心理学に興味のある高校生,進路に悩む高校生,心理学の知識を現場で活かしたい教職員の方向けの講座です。
参加無料です。是非,ご友人の方もお誘いいただき,一緒にお申し込みください。
http://www.psych.or.jp/event/sympo2016_koukousei.html










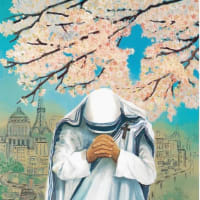




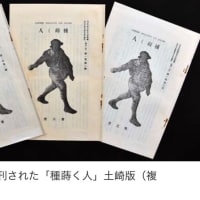
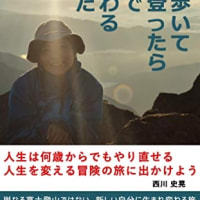


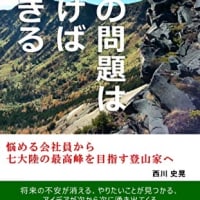
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます