推敲
賈島赴挙至京、
騎驢賦詩、
得「僧推月下門」之句。
欲改推作敲。
引手作推敲之勢、未決。
不覚衝大尹韓愈。
乃具言。
愈曰、「敲字佳矣。」
遂竝轡論詩。
【唐詩紀事巻四十】
賈島、挙に赴きて京に至り
賈島は、科挙の(試験を受ける)ために都・長安にやってきて、
驢に騎りて詩を賦し、
ロバに乗りながら詩を作っていると、
「僧は推す月下の門」の句を得たり。
「僧は推す月下の門」という句ができました。
推を改めて敲と作さんと欲す。
(しかしこの)「推す」を改めて「敲(たたく)」という文字にしたいと思いました。
手を引きて推敲の勢を作すも、未だ決せず。
(そこで)手動かして推すと敲くの仕草をしてみたもののまだ決まりません。
覚えず大尹韓愈に衝たる。
(そうしているうちに)思わず大尹(都の長官)の韓愈(の列)に突っ込んでしまいました。
乃ち具に言ふ。
(賈島は)そこで、(列に突っ込んでしまった理由を)詳しく説明しました。
愈曰はく、
韓愈が言うことには、
「敲字佳矣。」
「敲という文字が良い。」と。
遂に轡を並べて詩を論ずること之を久しくす。
そのまま(二人は)乗り物を並べ(進みながら)詩についてしばらく論じていました。
韓愈
かんゆ
(768―824)
中国、唐の文学者、思想家。字(あざな)は退之(たいし)、文公と諡(おくりな)される。自称した出身地によって昌黎(しょうれい)先生とよばれ、最終官によって韓吏部(りぶ)という。幼年にして父母を失い、長兄韓会(かんかい)に養育された。792年(貞元8)の進士。地方の節度使の属官を経て、803年、監察御史となり、京兆尹(けいちょういん)(首都の行政長官)李実(りじつ)を弾劾したが、かえってそのため陽山県(広東(カントン)省)令に左遷された。翌804年召還され、その後、主として国子監に勤務。817年、呉元済(ごげんさい)の反乱のとき、司令官裴度(はいど)の副官として行軍司馬となり、平定の功によって刑部侍郎となる。819年、憲宗皇帝が仏骨を宮廷に迎えたのを諫(いさ)めて、皇帝の怒りに触れ、潮州(ちょうしゅう)(広東省)刺史(しし)に左遷されたが、翌820年憲宗が崩じ、召還されて吏部侍郎にまで至った。長慶4年12月2日卒す。
文学上の功績の第一は、散文の文体改革である。それまで普通行われた対句(ついく)を中心としてつくられる駢文(べんぶん)に反対して、対句など形式の拘束から自由でありながら、しかも達意の文体をつくりあげ、古代文体の復活という意味で「古文」と称し、友人の柳宗元(りゅうそうげん)らとともに推し広めた。とくに、人物の伝記を述べるいわゆる碑誌伝状に優れ、従来のこのジャンルの作品が類型的な千編一律であったのを、それぞれ対象に即して個性的な文章を簡潔に書いた。唐代では古文はまだ支配的文体にまで至らず、駢文と並び行われる程度であったが、宋(そう)代以後、中国の散文文体の主流となり、彼の文章はその模範とされる。第二に、詩において叙情的テーマに限定せず、議論を展開したり、事実を詳細に記述したり、幻想を具象的に描写するなど、知的な興味を精練した表現で表すことを試み、作風を異にする白居易(はくきょい)と並んで、韓白と称され、当時の代表的詩人であった。その詩は、「文を以(もっ)て詩と為(な)した」といわれ、ときに散文的で難解との批判もあるが、題材の拡張とともに、宋代の詩に与えた影響は大きい。
思想の方面では、儒家思想を尊重して、堯(ぎょう)・舜(しゅん)・禹(う)・湯(とう)・文・武・周公・孔子・孟軻(もうか)という道統の説を提出し、仏教・道教を排撃した。古典研究において、経書の思想内容に重点を置き、『論語』と並んで『中庸(ちゅうよう)』や『孟子(もうし)』を尊重するなど、宋の性理学の先駆者とされ、李(りこう)との共著『論語筆解』2巻が存する。詩文は、『昌黎先生集』40巻、外集10巻、遺文1巻に収められ、宋の魏仲挙(ぎちゅうきょ)編五百家注、朱熹(しゅき)(朱子)『考異』などの注解がある。[清水 茂]
『清水茂注『中国詩人選集11 韓愈』(1958・岩波書店) ▽原田憲雄著『漢詩大系11 韓愈』(1965・集英社)』
月下推敲
げっかすいこう
意味 詩文の字句や表現を深く考えて、何度も修正して仕上げること。
月の光照らされた門を開ける動作を「推(お)す」と表現するか、「敲(たた)く」と表現するか、考えをめぐらせるという意味から。
中国の唐の詩人の賈島が、科挙の試験を受けるために驢馬に乗って移動している時に、詩を作りながら考えていると、都知事の韓愈の行列にぶつかってしまった。
韓愈に事情を話すと、その考えていることに意見を出し、二人は打ち解けて仲良くなったという故事から。
出典 『唐詩紀事』「四十」
賈島
かとう
(779―843)
中国、中唐期の詩人。字(あざな)は浪仙。范陽(はんよう)(河北省)の人。初め僧となり無本と名のったが、のちに還俗(げんぞく)。長江(四川(しせん)省)主簿(しゅぼ)から普州(四川省)司倉参軍に転任し、843年(会昌3)に州の官舎で65歳の生涯を閉じた。「僧は推(お)す月下の門」の句が浮かんだものの、「推す」がいいか「敲(たた)く」がいいかと苦吟していて韓愈(かんゆ)の行列にぶつかり、「敲く」がよかろうと教えられたという「推敲(すいこう)」の故事は有名。五言律詩に長じ、「怪禽(かいきん)広野に啼(な)き、落日行人(こうじん)を恐れしむ」(「暮(くれ)に山村を過(よぎ)る」)といった荒涼とした詩句に特色がある。晩唐から五代にかけて多くの詩人が賈島の詩を学んだ。宋(そう)の蘇軾(そしょく)は、「郊寒島痩(そう)」(孟郊(もうこう)は寒々(さむざむ)とし、賈島は痩(や)せている)と評している。『賈浪仙長江集』10巻がある。
賈島赴挙至京、
騎驢賦詩、
得「僧推月下門」之句。
欲改推作敲。
引手作推敲之勢、未決。
不覚衝大尹韓愈。
乃具言。
愈曰、「敲字佳矣。」
遂竝轡論詩。
【唐詩紀事巻四十】
賈島、挙に赴きて京に至り
賈島は、科挙の(試験を受ける)ために都・長安にやってきて、
驢に騎りて詩を賦し、
ロバに乗りながら詩を作っていると、
「僧は推す月下の門」の句を得たり。
「僧は推す月下の門」という句ができました。
推を改めて敲と作さんと欲す。
(しかしこの)「推す」を改めて「敲(たたく)」という文字にしたいと思いました。
手を引きて推敲の勢を作すも、未だ決せず。
(そこで)手動かして推すと敲くの仕草をしてみたもののまだ決まりません。
覚えず大尹韓愈に衝たる。
(そうしているうちに)思わず大尹(都の長官)の韓愈(の列)に突っ込んでしまいました。
乃ち具に言ふ。
(賈島は)そこで、(列に突っ込んでしまった理由を)詳しく説明しました。
愈曰はく、
韓愈が言うことには、
「敲字佳矣。」
「敲という文字が良い。」と。
遂に轡を並べて詩を論ずること之を久しくす。
そのまま(二人は)乗り物を並べ(進みながら)詩についてしばらく論じていました。
韓愈
かんゆ
(768―824)
中国、唐の文学者、思想家。字(あざな)は退之(たいし)、文公と諡(おくりな)される。自称した出身地によって昌黎(しょうれい)先生とよばれ、最終官によって韓吏部(りぶ)という。幼年にして父母を失い、長兄韓会(かんかい)に養育された。792年(貞元8)の進士。地方の節度使の属官を経て、803年、監察御史となり、京兆尹(けいちょういん)(首都の行政長官)李実(りじつ)を弾劾したが、かえってそのため陽山県(広東(カントン)省)令に左遷された。翌804年召還され、その後、主として国子監に勤務。817年、呉元済(ごげんさい)の反乱のとき、司令官裴度(はいど)の副官として行軍司馬となり、平定の功によって刑部侍郎となる。819年、憲宗皇帝が仏骨を宮廷に迎えたのを諫(いさ)めて、皇帝の怒りに触れ、潮州(ちょうしゅう)(広東省)刺史(しし)に左遷されたが、翌820年憲宗が崩じ、召還されて吏部侍郎にまで至った。長慶4年12月2日卒す。
文学上の功績の第一は、散文の文体改革である。それまで普通行われた対句(ついく)を中心としてつくられる駢文(べんぶん)に反対して、対句など形式の拘束から自由でありながら、しかも達意の文体をつくりあげ、古代文体の復活という意味で「古文」と称し、友人の柳宗元(りゅうそうげん)らとともに推し広めた。とくに、人物の伝記を述べるいわゆる碑誌伝状に優れ、従来のこのジャンルの作品が類型的な千編一律であったのを、それぞれ対象に即して個性的な文章を簡潔に書いた。唐代では古文はまだ支配的文体にまで至らず、駢文と並び行われる程度であったが、宋(そう)代以後、中国の散文文体の主流となり、彼の文章はその模範とされる。第二に、詩において叙情的テーマに限定せず、議論を展開したり、事実を詳細に記述したり、幻想を具象的に描写するなど、知的な興味を精練した表現で表すことを試み、作風を異にする白居易(はくきょい)と並んで、韓白と称され、当時の代表的詩人であった。その詩は、「文を以(もっ)て詩と為(な)した」といわれ、ときに散文的で難解との批判もあるが、題材の拡張とともに、宋代の詩に与えた影響は大きい。
思想の方面では、儒家思想を尊重して、堯(ぎょう)・舜(しゅん)・禹(う)・湯(とう)・文・武・周公・孔子・孟軻(もうか)という道統の説を提出し、仏教・道教を排撃した。古典研究において、経書の思想内容に重点を置き、『論語』と並んで『中庸(ちゅうよう)』や『孟子(もうし)』を尊重するなど、宋の性理学の先駆者とされ、李(りこう)との共著『論語筆解』2巻が存する。詩文は、『昌黎先生集』40巻、外集10巻、遺文1巻に収められ、宋の魏仲挙(ぎちゅうきょ)編五百家注、朱熹(しゅき)(朱子)『考異』などの注解がある。[清水 茂]
『清水茂注『中国詩人選集11 韓愈』(1958・岩波書店) ▽原田憲雄著『漢詩大系11 韓愈』(1965・集英社)』
月下推敲
げっかすいこう
意味 詩文の字句や表現を深く考えて、何度も修正して仕上げること。
月の光照らされた門を開ける動作を「推(お)す」と表現するか、「敲(たた)く」と表現するか、考えをめぐらせるという意味から。
中国の唐の詩人の賈島が、科挙の試験を受けるために驢馬に乗って移動している時に、詩を作りながら考えていると、都知事の韓愈の行列にぶつかってしまった。
韓愈に事情を話すと、その考えていることに意見を出し、二人は打ち解けて仲良くなったという故事から。
出典 『唐詩紀事』「四十」
賈島
かとう
(779―843)
中国、中唐期の詩人。字(あざな)は浪仙。范陽(はんよう)(河北省)の人。初め僧となり無本と名のったが、のちに還俗(げんぞく)。長江(四川(しせん)省)主簿(しゅぼ)から普州(四川省)司倉参軍に転任し、843年(会昌3)に州の官舎で65歳の生涯を閉じた。「僧は推(お)す月下の門」の句が浮かんだものの、「推す」がいいか「敲(たた)く」がいいかと苦吟していて韓愈(かんゆ)の行列にぶつかり、「敲く」がよかろうと教えられたという「推敲(すいこう)」の故事は有名。五言律詩に長じ、「怪禽(かいきん)広野に啼(な)き、落日行人(こうじん)を恐れしむ」(「暮(くれ)に山村を過(よぎ)る」)といった荒涼とした詩句に特色がある。晩唐から五代にかけて多くの詩人が賈島の詩を学んだ。宋(そう)の蘇軾(そしょく)は、「郊寒島痩(そう)」(孟郊(もうこう)は寒々(さむざむ)とし、賈島は痩(や)せている)と評している。『賈浪仙長江集』10巻がある。










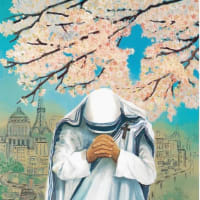




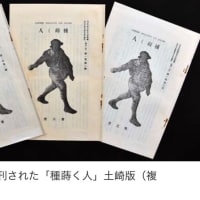
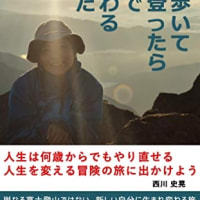


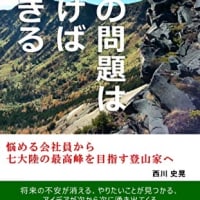
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます