キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
第6章
山小屋
山小屋
キャンディとテリィは子どもたちが起き出す前の早朝に出発することになった。これはポニー先生が特に主張したことで、その日は後でキャンディに手伝ってほしいことがあるからというのが理由だった。
それ故にキャンディは、ポニー先生から丸一日分の食糧が入った籠を渡された時に驚きを隠せなかった。
「ポニー先生、山小屋までは1時間くらいしかかからないし、おもちゃを探して帰ってくるだけだから、遅い朝食までには戻って来られるのよ」 キャンディはその大きな籠をいぶかしげに見た。
「お客様にひもじい思いをさせるわけにはいきませんからね、キャンディ。それに、今日はお天気もよさそうですからグランチェスターさんを山小屋の周辺の散歩にお連れしてはどうでしょう?」 刺繍の施された布をかけながら、ポニー先生はその籠を用意した理由を説明した。
「山小屋の周りの森は、今の季節になるとまるでクリスマスのポストカードのような美しさですからね。冬のピクニックにはもってこいではないですか?」 レイン先生がポニー先生に口添えをした。
ポニー先生とレイン先生が協力体制を組んでしまうとそれに逆らうことは不可能だったので、キャンディは目を見開いてあきれたように肩をすぼめ、籠を手に外へ出た。外ではテリィがすでに待っていて、キャンディの姿を見るとすぐに歩み寄った。
「アラスカにでも行くのかい?」 テリィは半笑いを浮かべて質問した。
「わたしに聞かないでよ。先生たちがこうと決めたら誰にも止められないんだから」 キャンディはひそひそ声で言った。テリィは籠をつかんで車の後部座席に置いたが、その手袋をはめた手がキャンディの手に触れた時に彼女の体に走った震えには気づかなかった。
それ以上は何も言葉を交わさずに、二人は山小屋に向けてポニーの家を出発した。車が走り出すと、ポニー先生とレイン先生はしばらく玄関で手を振っていた。
「わたしたちがしたことは、これでよかったのでしょうか?」 レイン先生はポニー先生に聞いた。
「もちろんですとも! 問題を解決するためには二人きりの時間が必要なのですよ」 ポニー先生は笑顔で答えた。「それに今日は冬晴れの一日になりそうですよ。午後に二人が戻ったら、どこでクリスマス用のホワイトフラワーを手に入れるか相談することにしましょう。わたしを信用してくださいな、レイン先生」
車が最後のカーブを曲がって見えなくなるのを眺めながら、先生たちは共犯者の笑顔を交わした。

キャンディは道を囲む常緑樹の葉を眺めていた。車が道を走るにつれ、松や樫の木がパレードの兵隊さんのように目の前を行進しているように見えた。キャンディはテリィと目を合せるのが怖くて運転席の方を見ることができなかった。何を話していいのかもわからなかったので、ただ黙ってぼんやりと動く景色を見ていた。車を走らせてから20分以上の間、キャンディに聞こえたのは自分の心臓が鼓動する音だけだった。
(わたしったらバカみたいだわ!) キャンディは自分に言い聞かせた。(どうしてこうやってはにかんだ少女みたいに振る舞っているの?……嫌だ! 頬が熱くなってきた! 顔が真っ赤になっていたらどうしよう!)
キャンディはしばらく目を閉じて、感情をコントロールしようと深い呼吸をした。心臓の鼓動がやっと少し鎮まると、テリィの方に顔を向けた。
テリィはなめし革のトレンチコートの下にネイビーブルーのタートルネックのセーターを着て、いつものフォーマルな帽子の代わりに耳覆い付きのハンチング帽をかぶっていた。そんなカジュアルな服装を見て、キャンディは何年も前のこんな冬の朝、車でマンハッタンを案内してくれた若い頃のテリィを思い出していた。キャンディはその姿に見とれずにはいられなかった。テリィを見ていると、至福のような感覚が心に染み込んでくるのだった。
「どうしてそんな笑顔なんだい?」 テリィが沈黙を破って聞いた。
「わたしが?……笑顔だなんて……自分ではわからなかったわ……お天気が良いから気分も良いのかもしれないわね」 キャンディはとっさに説明を考え付いて答えた。
「それがきみの長所だな」 テリィは真っ直ぐ道を見ながら言った。
「笑顔が?」
「おれが言いたいのは、状況がどうであれ明るくいられることさ」 そう言ったテリィの声には憧憬の思いが込められていた。
「じゃあテリィの長所は見るもの会う人すべてをばかにすることね」 キャンディはテリィの気分を明るくしようとウィンクしながら言った。
「それって長所なのか?」
「ほら、見て!」 キャンディはテリィの言葉をさえぎって言った。「着いたわよ! すばらしい景色でしょ?」
テリィは山小屋のポーチの前に車を停め、キャンディが玄関に走っていくのを見ながらそのまま車中にしばらく留まった。キャンディはライディングコートの下にズボンをはき、ベレー帽をかぶっていた。そんなボーイッシュな服装でも女性らしく見えるキャンディを、テリィは不思議に思った。彼女の瞳の中の何かが、あるいはクルクルしたカールの髪や動作が自分にとってこよなく魅力的で、もしキャンディが麻袋を着ていたとしても魅かれてしまうだろうとテリィは結論付けた。
テリィは車から降り、キャンディに続いて山小屋の中に入った。
そこは豪邸ではなかったが、居心地のよい家具が備えられ、そこかしこに面白い装飾が施されていた。丸太の色と木目が空間に温かみと奥行き感を与え、たくさんの窓から差し込む日差しで室内はとても明るかった。広い居間には大きく座り心地の良さそうな長椅子と、その両側にお揃いの肘掛け椅子が石造りの暖炉の周りに置いてあるだけだった。正面の壁には、おそらくアルバートさんが外国を旅行した時に撮ったものだろうと思われる、異国情緒に溢れた白黒の風景写真が飾られていた。床には毛の長い分厚いラグが敷かれ、ラグの薄いクリーム色が家具の濃い焦げ茶色を引き立たせていた。部屋の片隅には不思議な置物が飾られた小さな本棚があり、山小屋の所有者の趣味を反映した書籍が収められていた。ジュール・ヴェルヌの小説、デイヴィッド・リヴィングストンの伝記、ダーウィンの測量船ビーグル号での南米からオーストラリアへの航海記などの書籍がテリィの目に留まった。
(アルバートさんらしいな) テリィは思った。
食堂を兼ねたメインルームには片側に堅い杉で作られた荒削りなテーブルが配置されていた。テーブルにかけられたカラフルなテーブルクロスと籠皿に入れられた乾燥したラベンダーの穂がその部屋の中にある唯一女性らしいもので、キャンディが置いたものだとわかった。調理器具が揃った台所と奥に部屋がもう一つあり、階段が2階の寝室へと続いていた。
「大おじさまの隠れ家は気に行った、グレアムさん?」 キャンディがいつもの明るい調子で聞いた。「大おじさまはウォール街やダウ・ジョーンズの重圧から逃れるためにここを利用するのよ。ここに居る間はテリィが昔に出会ったアルバートさんに戻るの」
「ここには一人で来るの?」 テリィは知りたい気持ちと、アルバートさんのことを話すことに気が進まない気持ちの両方を抱えながら聞いた。
「そうよ、一人で来るの。アルバートさんがここで一人静かに過ごす間は誰も邪魔してはいけないの。わたしやジョルジュでさえよ」
「ジョルジュ?」 テリィは眉を上げ、問いたげな表情で言った。
「ジョルジュ・ヴィレルはアルバートさんの個人秘書で親友でもある人よ。テリィも一度会ったことがあるわ。わたしがセントポール学院に入学するためにイギリスへ渡る時、ジョルジュが付き添って来てくれたから」
「おれはほとんど覚えていないな」 テリィは台所に飲み水の入ったガラス製のデミジョン瓶がいくつか置いてあるのを見ながら言った。
「先週ここに来た時に食糧の備蓄をしたのよ」 キャンディはテリィが聞きたがっていることを察知して説明した。「アルバートさんがシカゴに戻っているし最近とてもストレスを抱えているから、いつでもこの山小屋を使えるようしておいたの」
「実業家の生活も大変そうだな」 テリィは気さくに感想を述べた。
「そうね……でも今は、そろそろおもちゃの車を探した方がよくない?」 キャンディはポニー先生の忠告を思い出し、話題を変えて提案した。
「そうだな。どこから始めたらいい?」
「わたしは2階の寝室を探すから、よかったら台所と居間の周辺を探してみて」
「あの奥の部屋は?」
「あそこはアルバートさんの暗室よ。現像液とか機械類が置いてあるから、子どもたちと来る時には鍵をかけて入れないようにしておくの」
「じゃあおれはこの辺を探してみるよ」
こうして二人がそれぞれおもちゃの車を探し始めると、すぐにその探し物は見つかった。ステアがリネン類を収納する手作りの荷物入れに、その青いおもちゃの車とぬり絵の本を置き忘れていたのだった。遠出の目的が達成されるとキャンディは朝食をとることを提案し、テリィが車から食糧の入った籠を持ってくると申し出た。
テリィは外に出ると、空がどんよりとしていて鈍い風が吹き始めていることに気が付いて驚いた。そして、天気が変わる可能性があるからだけでなく、自分自身とキャンディのためにも山小屋には長く留まらない方がいいだろうと考えた。この数か月間、キャンディと二人きりになれる機会を夢にまで見てきたが、皮肉なことに今その機会が目の前にあってもテリィはためらっていた。自分が想像していたよりも物事は複雑になってきていて、キャンディと話をする前に、テリィは自分一人でそれらの事柄について考える時間が必要だと感じていた。
実のところ、昨晩テリィは自分自身の過去について何度も思いを巡らせ、しかもその過去が自分の未来に突然として暗い影を落としていることを考えて眠れなかったのだ。夜が明けるころになっても、キャンディに自分の人生の中の最も暗いエピソードを話すべきかどうか迷っていた。テリィはこれまで、二人が別れた直後の落胆を乗り越えた後は、キャンディは比較的平穏な人生を歩んでいるのだろうと想像していた。しかし昨日、そのキャンディから彼女が経験した辛い時期の話や、彼女を憎んできた人物から強迫すら受けていた話を聞いて、そのような困難な時期に彼女の盾としてその場にいることができなかった自分を単純に許すことができなかった。もしそのまったく同じ時期に自分がどんな生活を送っていたかをキャンディが知ったら、彼女は自分を許してくれるだろうか? そのことは隠しておくべきなのだろうか?
キャンディはその暗い過去を知らないからこそ、自分の求愛を全面的に受け入れてくれたのではないのか。昨日キャンディの過去の話を聞く前までは、彼女はいつでも自分の求婚を喜んで受けてくれると確信していた。そうでなければキャンディは、これまでの彼女に対する自分の自由奔放な振る舞いを、あのように許してくれているはずがなかった。しかし、もしキャンディが自分のアルコールとの葛藤を知ってしまったらどうだろう? もしそのことを彼女に告げたら彼女は自分を拒絶するだろうか? どうすればいいのだろう? そのことに関して何らかの決断をするためにもテリィは冷静になる必要を感じていたが、キャンディと二人きりでいる今の状況では無理だった。どんな小さな誤算も、自分にとって一番大切な夢を《再び》閉ざしてしまうかもしれないのだ。
キャンディは小さな梯子を上って貯蔵室の中の探し物に忙しくしていて、テリィが外から戻ってきたのに気付かなかった。キャンディは小屋の中ではコートを脱いでいたので、ズボンの形からくっきりと浮き上がる体の柔らかな曲線をテリィは眺めることができた。女性がズボンをはいている姿は当時めずらしく、たとえその形が体にぴったりしていなくても、その目新しさが男性の目を引いた。
(ズボンか!) テリィはフラストレーションを感じながら思った。(どうしておれが冷静にならなければならない今日に限って、しかもこんな二人きりのときにズボンなんだ!?)
「何を探しているんだい?」 テリィは一度咳払いをして喉を整えてから聞いた。
「砂糖漬けの瓶よ……あったわ……ほら!」 キャンディは首尾よく探し物を見つけたことを喜んで言った。「ポニー先生が、焼いたパンを籠に入れてくれたから、このアプリコットの砂糖漬けが合うと思ったの」
キャンディは梯子を降りながらテリィの方を見るために体をひねったが、その時にあり得ないことが起きた――梯子を踏み外したのだ。キャンディは体のバランスを保とうとして腕をバタバタさせた。
気付くとキャンディは、梯子から落ちる前に助けようと走り寄ったテリィの腕の中にいた。
「まさにターザンそばかすも三段梯子から落ちる、だな。練習不足かい、お猿さん?」 テリィはキャンディの目をじっと見つめたままアプリコットの瓶を台所のカウンターに置き、かすれた声で言った。
キャンディは何も言い返せなかった。足はもうしっかり地についていたので、これ以上抱き合っている必要がないことは十分わかっていたのだが、テリィの腕の中にいる今そこから動くことができずにいた。つかの間キャンディの心は、テリィに身を預けてしまいたいという自然な欲求と、きちんと話をするまではこれ以上テリィの自由にはさせないという決意の間で揺れた。今テリィは自分の体をしっかりと抱きしめていて、キャンディはそこを離れるのが名残り惜しかった。
テリィの方でもその瞬間にそれまでの決意などすべて忘れて、キャンディの緑の瞳の中に自分自身を見失っていた。テリィは人差し指でキャンディの下唇をなぞった。触れるか触れないほどの感触だったにも関わらず、キャンディの体はまたも震えた。
「この唇はもっと頻繁に、たっぷり口づけをされるべきだ」 テリィは再びキャンディに口づけをしようとしてささやいた。
「テリィ……お願い」 キャンディは顔をそむけながら弱々しく抵抗した。「止めて」
「おれが何かしたのか?」 テリィは不満げに言った。
「そういうことじゃなくて……ただ……ただ、またあなたが自分の中に閉じこもってしまうなら、今こうしてわたしに近づくのはずるいわ。わからない?」 キャンディはテリィの抱擁から離れると、ようやくその話題を切り出した。
キャンディの言葉に表情を曇らせて、テリィも体を離すと手でこぶしを握った。
「わかるでしょ?」 キャンディは訴えた。「わたしにはまったく見当もつかない理由から、あなたはわたしが言ったりやったりしたことの何かが間違っていると思うとすべての意思疎通を閉ざしてしまうのよ。お互いに伝え合わなければならないことが、とてもたくさんあるというのに……」
「きみはそんなふうに思っているのか? おれがきみを罰するために沈黙していると?」 テリィは自分の反応に対するキャンディの解釈に驚いて聞いた。
「だってそうでしょ、テリィ? 2日前の夜だって、アルバートさんとの電話でわたしに腹を立てたのでしょう?」
テリィの顔が一瞬色を失った――自分が嫉妬で青ざめていたことを否定できるだろうか?
「おれは世間で言うほどいい役者じゃないってことだな」 テリィはしぶしぶキャンディの見解を受け入れた。
「たぶんあなたがばかばかしい位に嫉妬深くなっている時にはね」 キャンディは胸の前で腕を組みながら思わず言った。
「きみが思うほど単純なことじゃないよ、キャンディ」
「それならわたしに説明してみて。話してよ、テリィ。わたしがあなたの立場を理解しようともしない理不尽な人間に見える? 昨日わたしの何があなたを嫌な気分にさせたのか話してちょうだい。わたしが何をしたの?」
テリィは罪の意識を感じていたたまれない気持ちだった。自分の内面的な葛藤が、それとは知らずキャンディに、自分が彼女に腹を立てていると思わせてしまったのだ。
「そうじゃないんだ、キャンディ。おれは……間違った印象を与えてしまったなら……謝るよ」 テリィは自分を恥じながら言った。「おれがあの日の夜に嫉妬していたのは事実だ」 テリィは思い切って認めた。そのような嫉妬は根拠のないものだという確信を得たくて、その目は必死にキャンディの瞳を追い求めた。そしてそこに純粋な愛情だけが宿っているのを見て勇気を得ると、さらに話を続けた。
「でも昨日は……まったく別の理由だったんだ、キャンディ。おれはきみにじゃなくて、自分自身に腹を立てていた」
「どういう意味?」 キャンディはテリィの言葉に混乱して強く聞いた。
テリィは目を閉じた。キャンディのその表情には見覚えがあった。そこには、明確な回答を聞かなければ許さないという意思が現れていた。自分がこのことについてもう数日ゆっくり考えたいと思っていたのと同じくらい、キャンディには待つつもりがなかった。もう逃げ道はない。自分の過去をこれ以上隠しておくわけにはいかない。キャンディはすべて知りたいと主張するだろう……そして遅かれ早かれそうなるのだ……話さなければならない。
「昨日……」 テリィはためらいながら話を始めた。「きみがマーチン先生と出会った時のことを話してくれた時、おれは……おれは想像以上にきみを失望させることになってしまったと気が付いた……おそらく、あがないきれないほどに……もしかしたら、おれたちが一緒にいることも不可能になるくらいに……。おれの過ちがいずれおれたち二人の間に立ちはだかることになるだろう」
「失望? テリィ、そんなふうに言わないで。いつあなたがわたしを失望させたの? 二人の間にたちはだかるものって何なの?」 キャンディが言い返した。テリィの緊張と恐れが一瞬ごとに大きくなっていった。
「わからないのか? きみがマーチン先生と出会ったのはおれたちが別れたすぐ後のことだろ?」 テリィが聞いた。
キャンディは一瞬言葉を失った。テリィが二人の過去の関係について公然と言及するのはそれが初めてだった。
「まぁ……それは……そうだけど……」 混乱と一層の緊張でキャンディは口ごもった。「でも……それがどうしたというの?」
「キャンディ、きみにはおれの気持ちがわからないのか?」 テリィは強く聞いた。そして深いため息をつくと、自分の言葉の意味を説明するための勇気をかき集めた。「……長い間、おれの肩には自分自身が犯した間違いの重みがのしかかっていた。信じてくれ……この10年間は、おれたちが離れ離れになったことを後悔するには十分な時間だったよ。今はっきり言えることは、おれが人生の中で犯した最悪の過ちは、ニューヨークでのあの夜におれが勇気を出さなかったことだ……おれはきみを行かせるべきじゃなかった……これは確かなことだ……でも、それでも昨日まで、おれのそんな思慮に欠けた決断がきみの人生に与えてしまった影響について、おれはちゃんと理解していなかった。おれはもっと戦うべきだった……おれたち二人のために……おれのためだけじゃなく、きみのためにも」
「でもテリィ、ああする以外に方法がなかったことはあなたも良くわかっているはずよ。もし他に解決方法があったなら、わたしがあなたをあきらめることに納得したと思うの?」 自分がこれまで抱いてきた確信がテリィの言葉の激しさと衝突するのを感じながらキャンディは言い返した。「スザナは……彼女は……あなたを必要としていたわ! あれは、あなたの義務だったのよ!」 キャンディは、長年に渡ってしがみついてきた見せかけの道理をもとに主張した。
「義務の話はやめてくれ、キャンディ。おれはもうその言葉は聞きたくもない! 間違った義務感のために、おれはおれたち二人の青春を無駄にしたんだ」 テリィは声を荒げ、体を窓の方に向けながら言った。
「どうしてそんなことが言えるの? スザナはあなたを愛していたのよ、テリィ! あなたのために犠牲になった人が不幸せになることがわかっていながら、わたしたちが一緒になることはできなかったはずよ」 キャンディは、自分のあの時の決断を正当化するただ一つの確信をまだ手放すことができずに再度言い返した。
テリィは一瞬ためらった。スザナに関する本当のことを、どの程度キャンディに話すべきか迷った。真実がキャンディをさらに傷つけることになりはしないか? キャンディをそのような衝撃から守るべきなのか? それとも正直に話すべきなのか? テリィは話を続けるための正しい言葉を探して、この激しい会話の中で初めて目を伏せた。
「おれだって何年もその同じ偽りで自分自身を納得させようとしたんだ、キャンディ」 テリィはキャンディを見つめてついに話し始めた。「でもきみを再びピッツバーグで見た時、きみをおれの腕の中に抱いた瞬間、おれはそんな幻想をすべて払いのけた。あの晩きみはおれにスザナは幸せだったのかと聞いた。そしておれは、彼女は確かに幸せだったと言った。でもそれは、彼女が利己的な精神を持った人間だったからだ。おれが示すことができたほんのわずかな愛情を受け取って幸せだと言えたのは、彼女がそういう人間だったからなんだ。スザナには人を思いやったり共感する心というものが欠落していた。でなければ、彼女が深く愛していると言ってはばからないこのおれが、その間ずっと惨めな思いをしているのを知りながら幸せを感じることはできなかっただろう。もしスザナがおれを哀れと思ってきみのもとへ行かせてさえくれていたら……でも彼女にはおれの気持ちなどどうでもよかった。スザナは自分のことしか考えていなかったから」
「テリィ、そんなことあり得ないわ!」 キャンディは恐怖のためにはっと息が止まった。キャンディにとって、これまでスザナは無私と自己犠牲のかたまりのような存在だったのだ。しかしテリィの言葉からはまったく別の女性の姿が明かされていた。
キャンディはためらいながらダイニングテーブルまで歩くと、震える手でテーブルをつかみながら椅子に腰を下ろした。10年前に自ら下した決断をこれまで支えてきた唯一の考えは《テリィはスザナといて幸せになれる》というものだった。ピッツバーグでテリィは、彼のスザナに対する愛情は熱烈なものではなく、そのため彼女の死を嘆いてはいないと公言した。その時もとても衝撃を受けた。しかし、10年前のニューヨークの夜からずっと惨めだったという告白や、そんなテリィの気持ちに目をつぶるほどスザナが利己的な人だったという事実は、それとは全く違う次元の話だった。
テリィは落ち着きのない様子で右から左へ行ったり来たりしながら、キャンディの瞳が曇っていくのを観察した。キャンディが感じているだろう衝撃は理解できたので、その重苦しい話を再開するまでしばらく時間を置いた。
「スザナは……あなたがずっと不幸せだったことを……知っていたというの……? わたしにはとても……信じられない……あなたの苦しみを知っていながら……それに対して何もしないなんて」 キャンディはほとんど囁くような声で口ごもった。
キャンディは、スザナから何年も前に送られてきた手紙の内容をぼんやりと思い出していた。この新たな真実の前では、その手紙はまったく違う意味を持つことになる。キャンディは今初めて自分がだまされたように感じていた。
「そんなの嘘よ」 急に胃にむかつきを感じながらキャンディはつぶやいた。
「きみがいくら否定しようが真実は変わらないんだ、キャンディ」 キャンディの前に立ってテリィは続けた。「おれは、きみがスザナのことを高潔な人間だと考え、彼女のそばでおれが幸せになれると信じたがっていたのを知っているから、この真実をきみに言わずにおこうかと迷った。でもキャンディ、おれはもう間違いを犯したくはない。あの事故が起きた時、おれがきみにそのことを伝えなかったことから全てが間違った方向に進んでしまった。きみはおれに話をしてくれと言った。だから正直に言うが、おれはずっと幸せではなかった」
キャンディは顔を上げ、涙で溢れる瞳でテリィを見た。
「幸せになるという約束を守れなかったという意味でおれはきみを失望させてしまった」 テリィは声を抑えて続けた。「幸せは絶え間なくおれをすり抜けていってしまったから……。それどころか、きみと別れた後おれは何カ月も地獄のような日々を過ごした。おれがあの時に死んでしまわなかったのは、きっと神様がきみの祈りを聞き届けてくれたからとしか考えられない。でも、その苦しみの原因を作ったのはおれ自身の行動であり決断だったことは自分が一番よく知っていた。だからおれは自分の運命を受け入れて、スザナの欠点や、彼女がこの悲惨で低俗な物語の中で演じた役割を許した。ある意味では、精神がねじくれて病んでいたスザナはおれに相応しかった……惨めさと孤独の中で過ごした一年一年がおれに相応しかったように……でもきみは違う……こんなろくでもない男のためにきみが苦しんで涙を流したのだとしたら、それはおれの責任だ……おれは……」
「もう止めてテリィ!」 キャンディはテリィの目を再び見ながら激しい勢いで止めた。「あなたが一人で責任を負うようなことはさせないわ。もしわたしたちがしたことが間違いだったと言うなら、わたしにも罪があるもの。あの夜去って行ったのはわたしだった――あなたが止めても振り返りもしなかった。あなたは自分の間違いの話をするけど、わたしはどうなの? わたしがあなたにあの決断をさせたのよ。わたしがあなたを不幸に追いやったようなものだわ。そうでしょ?」 キャンディはそう言い返すと、自分自身の言葉の重みに気づいて叫んだ。「あぁ神様! わたしは何ということをしてしまったの?」 キャンディは両手で顔を覆った。
しかしテリィはキャンディに責任があるなどと考えたことは一度としてなく、そうするつもりもなかった。
「違うよ、キャンディ。おれがもっと努力すべきだった。おれがもっと主張すべきだった……おれが……駅まで走ってきみを引き止めるべきだった。だがおれは何をした? あの忌まわしい病院の部屋に留まり……動けなくなって……衝撃を受けて……スザナのそばにいると約束したんだ……きみを一人にして。教えてくれ、キャンディ。ニール・ラガンがきみに嫌がらせをした時おれはどこにいた?」
「テリィ……ニールは……ニールは嫌がらせなんてしてないわ……ちょっと大げさよ」 キャンディは落ち着きなく答えた。
「大げさ? ならどうして口ごもる?」 テリィは容赦なく聞いた。「おれは信じないよ、キャンディ。きみはいつも嘘が下手だった。昨日話を聞いた時、おれはきみが実際に起きたことの半分も語っていないと感じた。それに、おれはラガンの腐った心根をよく知っているから、あいつがきみをどんな目に合わせたのか大体想像はつく。きみは、あいつにされた酷い仕打ちを他愛ないことにしようとしているが、あいつはきみをくじけさせ追い込もうとして職を奪ったんだぞ。きみが義務のことを言うなら、おれの一番の義務はきみがラガンから嫌がらせを受けていたとき、別の女性のそばにいるのではなく、きみのそばにいて守ることだったんだ。おれはその点でもきみを失望させてしまった」
「あなたは自分につらく当たりすぎているわ、テリィ。あの時にわたしを助けるなんてできなかったと思うし、それに頼れる人がいなかったわけじゃないわ。昨日話したようにマーチン先生とわたしはお互いに助け合っていたし、それに……アルバートさんもアーチーもいてくれたから……」
「おれが去って行ったことで他の男たちがきみの助けをしなければならなかったと聞いて、きみはおれが慰められるとでも思っているのか?」 テリィは憤った。「当時金がなくて問題を抱えていたマーチン先生でさえきみに手を差し伸べた。おれはどうだ? きみが大変な時におれがどこにいたか知りたくないか、キャンディ?」
「テリィ、こんなのよくないわ。もう過去のことを問題にする必要はないと思うの……少なくともこんな形では……」 キャンディはこの会話が向かっている方向に青ざめながら言った。
「必要ない? こんなにも過去が立ちはだかっているのに! 昨日おれは……おれたち二人には過去が……おれの過去が……重すぎるし大きすぎると気がついた」
「どういう意味?」 キャンディはさらに青ざめながら聞いた。
「もしきみがおれの本当のことを知ったら……おれがどれだけ臆病者でどれだけ落ちぶれたかを知ったら、きみはおれと今ここにいないだろう。おれがどんな人間に成り下がったかを知ったら、きみは愕然とするだろう」
「テリィ……そんな言い方は止めて……あなたは必要以上に自分自身を傷つけているわ」 キャンディは懇願した。
「おれに話をしろと言ったのはきみだよ。知ってるかい? マーチン先生がきみを助けるために勇敢にアルコール依存に立ち向かっていた時、おれは泥酔していたよ。おれはスザナを振り切ってきみを取り戻すために立ち向かう強さがあるのか、それとも交わした約束を守るべきなのかがわからずに酒におぼれていったんだ。おれたちが別れた後、おれは何か月も酒浸りになって、その過程で俳優としての人生もだめにするところだった。それが決断力のない哀れなおれの行き着いた先ってわけだ。おれがその月日に何をして、どのようにおれ自身の尊厳や、自尊心や、純粋さを失ったか、きみの清らかな耳にはとても聞かせられないと思うだろうよ、アードレーのお嬢様。きみがもしあの時のおれを見たら、きっときみはおれのことを恥じて、出会ったことすら後悔しただろう」
「わたしは見たわ!」 見知らぬ力を体に感じ、立ち上がって泣きながらキャンディは叫んだ。「わたしはあなたを見たわ!……あのようなあなたを見るのは確かにつらかったけど、だからといってあなたへの思いは変わらなかった!」
今度はテリィが呆然とする番だった。
「おれを見た?」 テリィはすすり泣くキャンディに近寄り、肩を掴むと信じられない思いで聞いた。そして、テリィは突然理解した。「……あれはきみだったんだ!……あのまぼろしは結局きみだったんだ!」
キャンディはおずおずと涙でいっぱいの目を上げて、かすかに頷いた。そして深く息をすると、勇気をもって話した――
「あなたが悲嘆にくれて状況に負けてしまったからといって、わたしがあなたを愛する気持ちは変わらなかったわ。それどころかわたしはもっとあなたを愛するようになったの。なぜならあなたがアルコール依存を乗り越えたのを見た時、わたしはあなたが立派に悪魔に打ち勝ったとわかったから。……おちぶれた芝居小屋であなたを見た時、わたしはあなたがきっと立ち直ると信じていたわ……わたしはあなたがその状況を乗り越える人だと信じてた……わたしはあなたがいつかは誇りを持って、本来いるべき場所に戻ると信じてた。あなたがストラスフォード劇団に戻って、『ハムレット』がブロードウェイでもイギリスでも大成功したと聞いてもわたしは驚かなかった。わたしには、あのどさまわりの芝居小屋の時からわかっていたから」 キャンディはここで一息ついて表情を翳らせた。「ただ、あなたからスザナのことを聞いた今、わたしがただ一つ後悔するのはあの場で再びあなたを行かせてしまったことだわ。わたしは一人立ち去る代わりにお芝居が終わるのを待つべきだったのよ。あなたの腕に飛び込んで、わたしがどれだけあなたを愛しているか伝えるべきだったのよ……でも今それをするわ、テリィ……わたしはあの時も今もあなたを愛しています。わたしはずっとあなたを愛してきたの。そしてこれからも……あなたが再びわたしの人生からいなくなったとしても……でも……お願いだからいなくならないで。わたしはニューヨークで嘘をついたわ。わたしはあなたがいなければ本当に幸せになんてなれないの」 キャンディが全身全霊で哀願していることがテリィにはわかった。
テリィは恍惚としていた。誰かが自分をこのように絶え間なく、完全な信頼の中で愛することがあるとはこれまで想像したこともなかったのだ。
「どうしてそんなことが言える? おれはきみに相応しくないということがわからな……」 テリィは言葉を言い終えることができなかった。その言葉はこれまで経験したことのないような情熱的でほろ苦い口づけで覆われた。
(キャンディがおれに口づけを……自分の意志で……何があってもおれを愛していると……この世に神はいたのか!) テリィが理性的な思考能力を失う前のわずかな考えだった。
キャンディは両手でテリィの顔を挟み、がむしゃらに唇を押し付けていた。それはまるでテリィが激しい後悔の念にかられながら過ごした日々の苦い思い出を消し去ろうとするかのようだった。等しいひたむきな情熱で、テリィも徐々にその口づけに応え始めた。
互いの腕が相手の体を探し求めしっかりと抱き合った。口づけを重ねる度に喜びと解放感が増し、その輝かしい瞬間がしばらく続いた。しばらくしてキャンディの重い吐息からすすり泣きが漏れた。口づけの中にしょっぱい涙の味がして、テリィは唇でその涙をふいた。
「泣かないでくれ、キャンディ」 口づけをしながらテリィは囁いた。「わかったから……もう……わかったから。おれはあの日きみのまぼろしを見たと思った……今みたいに泣いているきみを見た……もしあれがまぼろしでなくて本当にきみだとわかっていたら、おれはあの時どうしていたかわからない……恥ずかしさのあまり逃げ出してしまったかもしれないし、あるいは後悔してきみの元へ走ったかもしれない。ただ……きみのまぼろしを見ておれにわかったのは……あのおちぶれた場所に居続けることはできないということだった。……あの状況から抜け出すのは……戻って一からまたやり直すのは簡単じゃなかったが、おれはきみのためにそれをした。間違った考えから、またスザナの元に戻るという過ちを犯してはしまったけれど、それでもきみのためだったんだ。あのどさまわりの芝居小屋の日からは、おれが弱さに打ち勝ったどんな小さな勝利も、あらゆる努力も、それに続く成功も、おれはそのすべてをきみに捧げていた。なぜなら……きみは……いつだっておれにとってただ一人の……おれにとって……」 テリィは一瞬ためらったがキャンディの先の告白に勇気を得て言った。「きみは、おれが愛するただ一人の女性だから……あの船の上できみを一目見た時からずっと……おれは直観的にわかっていた……きみを愛しているということが。5月に送った手紙の中できみにそのことを伝えようとした。おれの愛は変わっていないと」
「あぁテリィ!」 キャンディは胸が張り裂けそうな声ですすり泣いた。
テリィはキャンディを落ち着かせようと胸に抱きしめた。何がキャンディにそのような激しい感情を引き起こさせたのかわからず、その理由を知りたかった。
「ターザンそばかす……おれが何を言った? もう泣くなよ」 テリィはキャンディを優しく抱きしめながら聞いた。
二人はしばらく抱き合っていた。テリィに優しく撫でられてキャンディのすすり泣きが徐々に治まっていった。
「違うのよ、テリィ……あなたは何も悪いことは言ってないの」 落ち着いて話ができるようになってからキャンディは言った。「ただ……初めてあなたの口から愛しているという言葉を聞いたから……わたしがどれだけその言葉をあなたから聞きたかったか、あなたにはわからないのよ」 キャンディは正直に言った。
「じゃあこれからはもっと頻繁に言うと約束するよ。きみが聞き慣れて泣き出さないようにね」 テリィはわずかに唇を曲げ、かすかな笑顔を作って言った。
その時、激しい突風が先ほどテリィがきちんと閉め忘れたドアを押し開けた。二人は抱擁を解いて玄関へと走った。呆気にとられる二人の目の前で、凍るような激風が予期せぬ猛威で森に吹き荒れていた。
「信じられないわ!」 キャンディは驚いて言った。「ここに着いたときは晴れた青空だったのに……どうしてこんな吹雪になったのかしら?」
「わからないけど、キャンディ、この分じゃあと数時間はここから動けないよ」 テリィはキャンディを守るように自分の体に抱き寄せながらそう言ったが、暴風の勢いを見て言い足した。「すべての窓のシャッターを閉めた方がいいな」 コートを羽織るとテリィは外に出て行動を開始した。
風に煽られて外壁にバタバタと打ち付けられ始めたシャッターを閉めるテリィの姿をキャンディは目で追った。テリィがシャッターを一つ一つ閉めていると、キャンディは間もなく小屋の中が真っ暗になってしまうことに気がつき、貯蔵室にロウソクを取りに行った。テリィが小屋に戻って玄関の鍵を閉めた時には、室内はすでにロウソクの明かりでほの暗く照らされていた。キャンディは背中を向けて暖炉に薪を積み重ねていた。
「おれがやるよ」 テリィはキャンディに代わった。
「じゃあわたしはお湯を沸かしてくるわ。お茶でも飲みましょうよ。レモンなしで我慢してもらわなきゃならないけど」 キャンディははにかんだ笑顔で言った。
テリィは無言で笑顔を返した。キャンディが自分の嗜好をわかってくれていることが嬉しかった。暖炉に火をつけながらテリィの目はちらちらとキャンディを見た。キャンディは雪用のブーツを脱ぎ、靴を履かずに部屋の中を歩き回っていた。テリィはそのような他愛のない光景に二人の間の親密さが増している証拠を見て、歓喜の波が魂を揺らすのを感じた。
これから何時間も、もしかしたら一晩中二人きりでこの山小屋に留まらなければならないことは明らかで、その考えにテリィの頭の中の警報が鳴った。二人の間のあらゆる誤解が解かれた今、残るは一つの重大な質問だけだった。幸いこの吹雪のお蔭でそのための時間はたっぷりあった。しかし問題はその後のことだ。今日は紳士でいることは至難の業だとテリィは思った。
数分後、暖炉で火がぱちぱちと燃える中、二人はテーブルに座って紅茶を飲みながらその朝ポニー先生が籠に入れてくれたパンを食べていた。先ほどの熱烈な会話で張りつめた緊張をゆっくりほぐしながら、二人だけの心地よい沈黙に身を委ねていた。外では風がうねりを上げて吹き荒れ、気温が劇的に低下していた。
「これは通常の吹雪じゃないな。暴風雪の勢いがある」 テリィが沈黙を破って言った。「戦争が始まった年にもニューヨークでひどい暴風雪があったのを覚えている。確か3月の初めの頃だったよ。当時おれたちはリア王の稽古をしていたんだが、数日間休まなければならなくなった。暴風が電柱をなぎ倒して一晩中停電になってしまって、ニュージャージーとの連絡網も絶たれたんだ」
「たぶん今回はそれほどひどくならないわよ。数時間で治まってくると思うわ」 二人で一緒にテーブルを片付けながらキャンディが冷静に言った。「ここに数日留まることになったとしても二人分の水と食料は十分あるから。心配しないで」
テリィは密かに――自分が心配しているのはそのことではないのに……と心の中で考えていた。
*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします















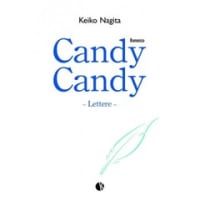









この喜びを上手く表現出来ない自分が悲しい限りです。
翻訳という作業はとてつもなく大変だろうと拝察致します。
そう申し上げながら続きをとても楽しみにしています。
掲載されていた月刊誌の発売日を指折り数えていた子供の頃よりも楽しみにしているかも知れません。
本当にいつもありがとうございます。
これからも応援させてください。
次の更新は2日後くらいになると思いますので楽しみにしていてください。告白はまだまだ続きますよ~。
ちぇる様がおっしゃていたように私も子供の頃、漫画のキャンディの続きが楽しみで楽しみで・・そんな昔を懐かしく思い出しました。
こんなに素敵なお話。翻訳してくださらなければ出会えませんでした。
骨の折れる翻訳を頑張ってして下さって、本当にありがとうございます。
感謝してもしきれません。
更新、とても楽しみで待ち遠しいです。
でも、あまり無理はなさらないようにして下さいね。・・あれ?待ち遠しいとか言ってて矛盾してますね(笑)
これからも、楽しく拝読させて頂きますので
応援してます!応援するぐらいしかできなくてゴメンナサイ(涙)
あまりに、更新が嬉しくてコメントせずにはいられませんでした!
ブログ主もリアル世代なのでなかよしが毎月楽しみでした。妹がりぼんを買って交換して読んでました。
今思えば至福の時間でした。でもあまりに昔のことなので、当時の自分がステアの死の回をどう受けとめたのかとか忘れているんですよね。
当時の懐かしい平和な(世界はどうあれ子どもでしたからね)時代を思い出していただければ幸いです。
このファンフィクの作者さんはとても中立の視点で物事をみたり議論を組み立てることのできる方なので、特に説得力があるお話しになっているのかもしれません。ラテン系のドロドロメロドラマ海外ファンフィクもありますから
それぞれお国柄が出ていて面白いですよね。
朝からすっかりキャンディとテリィに感情移入しています。
私も皆様同様、毎月お小遣いを握りしめ本屋に走っていたのを思い出します。
ブログ主様の労力と時間を心に留め置きながら読んでいきたいと思います。本当に有難うございます。
あとご存知でしたら教えていただきたいのですが、キャンディキャンディはイギリスやオセアニアでは放映されなかったのでしょうか?
昔は近所に小さな書店がたくさんあって、月間漫画誌がドーン!と平積みされてましたよね~懐かしいです。
アメリカ人の方から以前聞いた話では、英語圏でキャンディキャンディが放送されたのはハワイだけなのだそうです(裏付けはとっていませんが)。ハワイでテスト放送をしてメインランドへ……という構想だったのかもしれませんね。だから正式な英語版のアニメもマンガもないそうです。
続きが気になります。
毎回楽しみにしてます。
もう感無量な思いで読ませて頂きました。
キャンディとテリィの病院での別れは、子供だった当時からずっと納得行かなく、子供心に初めて切なさを芽生えさせました。
それが、大人になった今このブログと出会い、読ませて頂いてテリィとキャンディの告白・言葉・思いを聞いて、私の胸に長年支えてたものまでも、ゆっくりと溶けて行くようです。
ブログ主さま。どうかお願いです。翻訳されている話の結末がまた二人を分かつものだったとしても、終わりはキャンディとテリィをハッピーエンドに導いて下さいますように…。
さいごに。
ハンドルネーム褒めて頂いてありがとうございます♪
『眼鏡越しのそら』はドリカムのむか~し昔のアルバムに入ってる曲名なんです。
゛大嫌いだった眼鏡外せない どんなときも―″と歌いだしを聴いて、この歌は私のことだわ!…と思ったものでした。
いまの私は眼鏡越しでなく、ちゃんと見れてるかな。