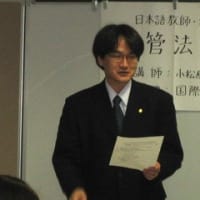2009年6月3日改正、7月1日施行
第2項「二葉」⇒「一葉」
第6条の2
法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
在留資格認定証明書の交付申請も原則は本人出頭、本人申請です。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
申請に必要な添付書類が定められています。
⇒別表第三
3 法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
原則は本人出頭・本人申請ですが、通常、在留資格認定証明書の交付申請時には本人は入国していませんから、本人が入管に行くことはできません。そこで、代理人が必要となりますが、どのような人が代理人として認められるのかが定められています。
⇒別表第四
4 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人(当該外国人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
上記の「公益法人の職員」「弁護士又は行政書士」「法定代理人」は外国人本人あるいは代理人の代わりに申請書等を提出することができます。この場合、本人あるいは代理人は出頭する必要はありません。
「公益法人の職員」「弁護士又は行政書士」なら誰でもできるわけではなく、「公益法人の職員」の場合は「地方入国管理局長が適当と認めるもの」、「弁護士又は行政書士」なら「弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの」であることが必要です。
5 第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
第2項「二葉」⇒「一葉」
第6条の2
法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
在留資格認定証明書の交付申請も原則は本人出頭、本人申請です。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
申請に必要な添付書類が定められています。
⇒別表第三
3 法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
原則は本人出頭・本人申請ですが、通常、在留資格認定証明書の交付申請時には本人は入国していませんから、本人が入管に行くことはできません。そこで、代理人が必要となりますが、どのような人が代理人として認められるのかが定められています。
⇒別表第四
4 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人(当該外国人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
上記の「公益法人の職員」「弁護士又は行政書士」「法定代理人」は外国人本人あるいは代理人の代わりに申請書等を提出することができます。この場合、本人あるいは代理人は出頭する必要はありません。
「公益法人の職員」「弁護士又は行政書士」なら誰でもできるわけではなく、「公益法人の職員」の場合は「地方入国管理局長が適当と認めるもの」、「弁護士又は行政書士」なら「弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの」であることが必要です。
5 第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。