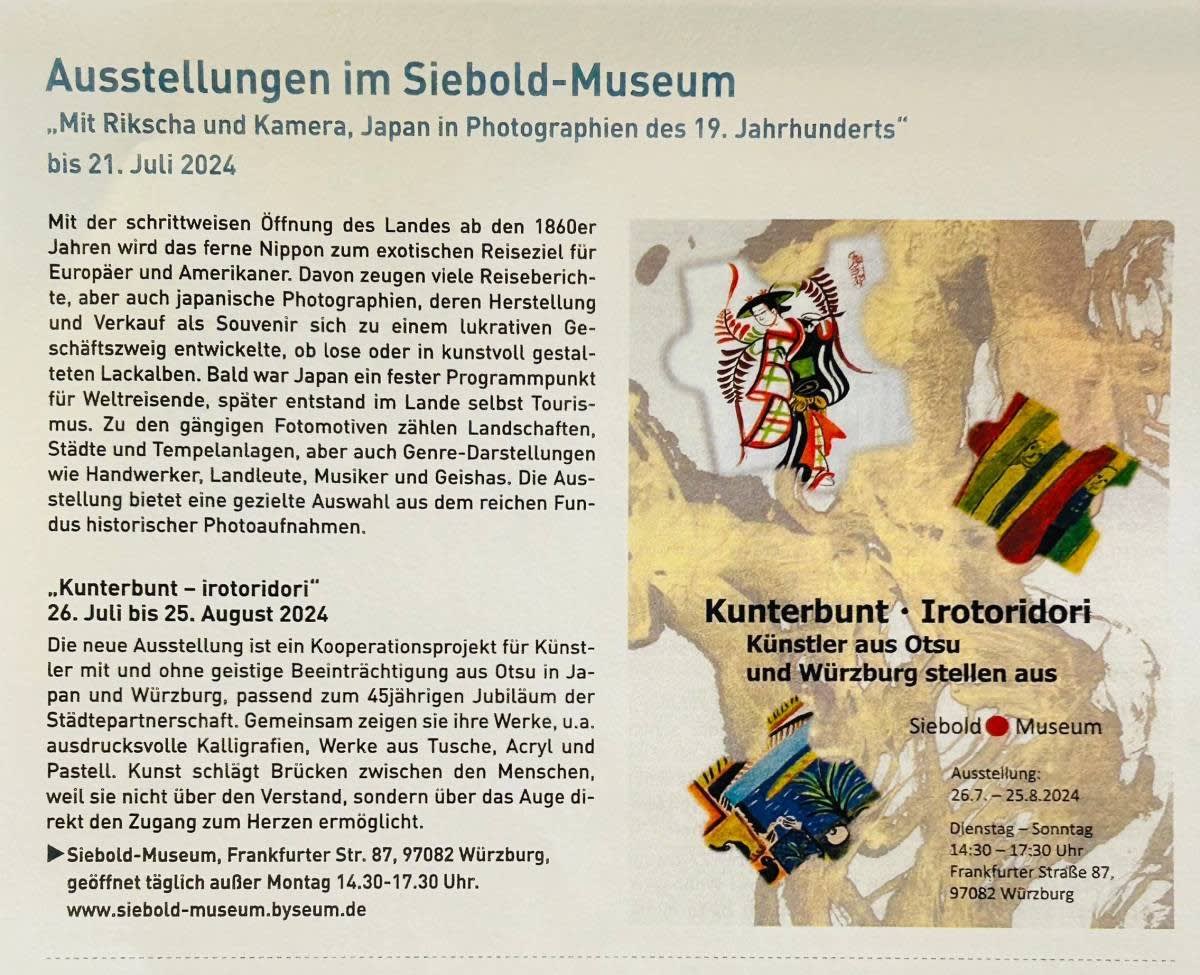NPO法人専攻科滋賀の会の講師・理事の福角 窓月(ふくすみ そうげつ)先生が、約1か月に亘る書道を通じたドイツでの作品展示・文化交流活動より無事帰国されました。渡独にあたりお世話になりました関係者の皆様、専攻科滋賀の会の関係機関の方々に帰国のご挨拶を含め、活動報告を以下にお知らせいたします。ご高覧のほどよろしくお願いいたします。
このたび、我が滋賀県大津市とドイツ・ヴュルツブルク市の姉妹都市提携45周年の記念すべき年に、ヴュルツブルク市のシーボルト博物館に於いて「日本の書と大津絵」展を開催させていただけましたこと、大変光栄なことでした。素晴らしい機会をいただきました両市の皆様に心より感謝申し上げます。
この展覧会は、昨年5月にヴュルツブルク市からスポーツ少年団の皆様とともに来日されました通訳のバーバラ・ローホッフさんとのお出会いがきっかけで実現の運びとなりました。まさに「出会いは宝」です。
異国の地で、ダウン症の池田真優子(いけだまゆこ)さん、深尾篤範(ふかおあつのり)さんとともに参加し、またご縁のある「なかまのみなさん」(専攻科滋賀の会「スクールなかま」・五箇荘ダウン症親子の会・安土小の皆さん・勤務校の生徒たち)の作品も展示し、現地の障害のあるアーティストさんたちとの交流展が出来たことは、夢のような出来事でした。
先人の方々が歴史と伝統を築き、日独の架け橋となって相互理解や文化交流を通して国際交流の発展に大きな役割を果たしてこられましたが、そのバトンを私たちがいただきましたことは大変有り難いことでした。
現代の多様化社会においては、変化を前向きに捉え柔軟に対応するとともに、これまでの既成概念を打ち破り、新しい価値観を生み出していく力が求められています。
私は誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて、国や地域、人権やジェンダー、障害の有無等、様々な多様性を積極的に受け入れ、社会に存在するこれらのあらゆるバリアを取り除いていく活動が大切だと考え、今回もユニバーサルな展覧会になることを目指しました。微力ではありますが、異文化交流を通して相互理解を図り、友好の一助となることを願っての開催でした。
常々「食物は身体の栄養、芸術は心の栄養」をモットーに「芸術に壁なし」の思いで活動してきたので、それを異国の地で実現出来た喜びは格別で、今回の展覧会は一生忘れられない経験となりました。
7月26日~8月25日まで、1ヶ月の展覧会は、「光陰矢のごとし」、まさにあっという間でした。「邯鄲(かんたん)一睡夢のごとし」で、帰国してみればあれは夢だったのかと思われるような充実した日々の連続でした。
シーボルト博物館はとても立派な素晴らしい展示場です。私の作品は大きくて日本ではなかなか展示することが難しいのですが、その博物館は天井が高く、作品が喜んでいるように感じられました。
7月26日、金曜日、夕方から軽食パーティを兼ねたオープニングセレモニーがありました。現地の皆さんは平日の勤務を終えて疲れていらっしゃるはずの時間帯ですが、たくさんの方々が参集してくださいました。
市長代理を兼ねた議員の方や博物館館長のご挨拶を受けて、招待していただいたお礼のご挨拶をさせていただきました。挨拶のあと、15名の方が日本の曲やドイツの曲をハープで演奏してくださり、日本側の私たちは書道パフォーマンスをさせていただきました。
私は袴姿で「龍」を、池田真優子さんは琴で演奏された「星に願いを」のメロディーにあわせて古代文字「星」を、深尾篤範君はソーラン節を踊りながら「龍」を、それぞれ大きな紙に大きな筆で披露させていただきました。
真優子さんと篤範君はいつも以上に楽しげで自信に満ち、キラキラと輝いているように見えました。会場の皆さんは初めて見る書道パフォーマンスに驚きつつ、拍手喝采して喜んでくださいました。
展覧会はちょうど現地の方々のバケーションの期間で、大勢の方々で溢れかえるということはありませんでしたので、見に来てくださった方々と楽しくコミュニケーションしながら、作品の説明をすることが出来、様々な質問に答えることも出来ました。ドイツの方は丁寧に見てくださり、どのようにして書いているのか、作品の言葉の意味なども聞かれ、次々と質問をしてくださいます。
現地の障害を持たれているアーティストの方々との交流展でもあったので、ご家族の方から「ダウン症の人に日本ではどのように書道を指導しているのか?ドイツの障害を持っている人にも書道体験をさせてもらえるか?この文字はどういう意味があるのか?」などいろいろと質問されました。
展覧会期間中、8回の書道教室がありました。基本的にはヴュルツブルク市のホームページやシーボルト博物館から申し込みを受け付けての教室でしたが、当初4回の書道教室が、口コミで広がり参加者も増え、回数も増えました。想定外の人数だったので、日本から準備していた紙が不足し、急遽全紙(140㎝×70㎝)を半紙サイズにカットするなど工夫が必要でした。
1回1時間半の書道教室は毎回袴姿で行いましたが、初めて袴姿を見る方から、「おお!」と歓声があがります。自分自身も気合いが入ります。
通訳をしてくださっていたバーバラさんの知り合いの方々も含めて、茶道、華道、太鼓、日本語、合気道、民俗学など日本文化に関心のある方々や、展覧会の作品を見て興味のある方々が参加してくださいました。中には漢字やカタカナで自分の名前が書ける方もいらっしゃいました。日本に来たことがある方もない方も、またひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字のことを知っている方も知らない方も様々でしたが、豊かな日本の文字や日本の文化に対する関心が高いように感じられました。
筆の使い方を伝え、筆に慣れるために、自分の名前を筆で書いていただき、自己紹介タイムをとることで、初対面の方々も少し打ち解け合ってくださいます。
「愛」という文字を、書き順を伝えながら書いていただきました。皆さん、出来上がった作品を誇らしげに持って帰っていかれました。書き上がった作品は結婚記念日にパートナーに贈る、娘の誕生日にプレゼントする、という方もいらっしゃいました。中には自分やパートナーの名前を漢字にして書いてほしい、というリクエストもありました。
今回、現地のダウン症の方々やご家族も書道教室に参加してくださり、交流できたことは幸せな時間でした。交流展に出展している方とそのご家族の書道教室では、「愛」という漢字は画数も多く、ダウン症の方にとっては書くのが負担になると考え、○と棒線で出来た古代文字の「星」という文字を書いていただきました。日本でもダウン症の方に書道を指導させていただいているので、国は違っても、同じ指導方法で書いてもらいました。
書き上がった時、歓声をあげながら達成できた喜びを全身で表してくれたEさん、何度も思いっきりハグしてくれたP君、ニコニコと喜んで何度も握手してくれたCさんたち、そしてそれぞれのご家族の嬉しそうな表情は今も脳裏に焼き付いています。喜んでいただけることが何よりのご褒美です。
遠方の職業訓練学校でも書道教室をさせていただきました。その後、その先生方が遠方にもかかわらず再び展覧会場に来てくださり、再度書道教室に参加してくださるなど、とても嬉しい出来事もありました。
書道教室がご縁で自宅に招いて家族総出のパーティをしてくださったRさん一家、着物を着て書道作品をお土産に伺ったらたいそう喜んでくださいました。
花束を持って何度も展覧会場に来てくださったRさん、手紙や似顔絵を描いてプレゼントしてくれた7歳のMさん、6歳のA君。一生懸命折り紙を教えてくださったCさん、華道教室、太鼓サークル、合気道や茶道教室の方々、他にも様々な職業の方々が書道教室に参加していただきましたが、毎回同じことをするのではなく、全紙(140×70)や半紙、葉書など、紙のサイズを変えたり、筆の大きさを変えたり、またロウ書きやカラー染色した紙を使用するなど、その時々の参加者のニーズによってバリエーションに富んだ作品になるよう心がけました。
毎回最後に「楽しかった方は拍手をしてください」というと、サービス精神旺盛な皆さんは大きな拍手をしてくださいます。私の一番嬉しいご褒美のひとときで、日本文化普及、異文化交流の絆を深める小さな一本の糸になれたことを味わえる瞬間でした。
今回、滋賀県内の高校で教えていたドイツ在住の卒業生が6時間かけて2回も展覧会に来てくれて、14年ぶりに会えたことや、日本から、世界一周の旅の途中で展覧会に足を運んでくださった知り合いが展覧会や書道教室に参加してくださったこと、会場にあるピアノを演奏してくださったピアニストさんや歌を歌ってくださった方々と出会えたことをはじめ、心を通わす出会いをたくさん経験し、大変嬉しい時間を過ごせて感激しました。
最終日には、「この作品の前で写真を撮りたい」と言って、深尾篤範君、池田真優子さんの作品の前に立った10歳の少年にその理由を尋ねると、「僕のお姉さんもダウン症です。」と教えてくれました。いろいろと話した後、好きな作品があればどうぞ、と伝えました。すると「何が書いてあるのかわからないけれど、これがいい」と言って選んでくれた作品が「古代文字 亀」であることを伝えると、彼は思わず飛び上がって喜んでくれました。そばでニコニコしていた彼のお父さんが「息子は亀を飼っています」と教えてくれました。
「明日お姉さんを連れて来たい」と言われましたが、残念ながら翌日は休館日で、搬出した作品を日本に発送するので会うことは叶いません。別れを惜しみつつ搬出作業にかかりました。
言葉は通じなくても、書道という芸術を通して、お互いが心を通わせ、異文化理解を深める瞬間にいることを実感できたことはとても幸せな経験でした。
今回、滞在中終始ドイツ人の通訳士、バーバラ・ローホッフさんに大変お世話になりました。昨年、大津でバーバラさんと出会っていなければ、今回の展覧会は存在しませんでした。
ドイツではバーバラさんとはほぼ毎日のように会っていました。展覧会中の通訳をはじめ、書道教室や観光、お買い物、あらゆることでお世話になりました。ドイツ人でありながら日本語も上手で、なんと裏千家の茶道教授の免状も持っていらっしゃる方です。多くの大切なご友人を紹介していただき、展覧会を盛り上げてくださいました。ご自身が加入されている太鼓教室、華道教室にも参加させていただき、なかなか出来ない体験をさせていただきました。
ご自宅にも招待していただき、高齢のお母様の手作りのお料理とケーキをご馳走になりました。ケーキは最高に美味しかったです。
温かいおもてなしに感激しつつ、招かれて初めて彼女の自宅が展覧会場から大変遠いことを知り、この遠い距離をいとわずいつもはるばる来てくださっていた彼女の深い思いやりに敬服しました。
何より一生忘れられないエピソードは私が携帯電話を小高い教会に忘れた時、走ってその教会に戻り一生懸命探してくださったことです。真昼の時間帯、階段が何段もある小高い教会に二度も足を運ぶことは誰もが嫌がるようなことですが、嫌な顔一つされず、駆け上ってくださったことに深く感銘を受けました。
結局携帯電話は善意の方が警察に届けてくださって出てきて事なきをえましたが、バーバラさんは昼食を食べる時間もなく、その後仕事に行かれました。感謝してもしきれません。
今回、異国の地で書道文化を広めることができたことは夢のような出来事でした。ささやかながら異文化交流が出来、小さな細い糸ではありますが、絆を深める1本の糸になれたことを実感できたことは何にも代えがたい貴重な経験でした。
ここには書き切れないほどたくさんの方とのお出会いがあり、一つ一つが心の中の大切なページに収まって、思い返すと温かい気で満たされます。
三日月滋賀県知事様よりお祝いメッセージがドイツに届き、シーボルト博物館の方々にも大変喜んでいただきました。早速ドイツ語に翻訳し、展覧会場に展示してくださいました。
無事に展覧会を終えることが出来たのも終始、通訳者として、また友人として支えてくださったバーバラ・ローホッフさんや、家族のように親身に対応していただいたシーボルト博物館の皆様方、そしてかかわってくださったたくさんの皆様方のおかげです。感謝の念で一杯です。
池田さん親子や深尾さん親子とドイツ展をご一緒出来たことは何にもまして私にとって大変嬉しいことでした。
池田真優子さんのお母様から以下の体験談が届きました。
「昨年、福角先生から『ドイツに行かない?』とお声をかけていただき、ちょっと迷いはありましたが、これが最後の海外旅行のチャンス!と判断し、『行きます』と返事をさせてもらいました。
まずパスポートの取り直しから。半年かけてあれやこれやと想定しながら準備を整えました。
結論は、思い切って行って良かった!!
『行かずに後悔よりも行って後悔』とまで覚悟していましたが、ドイツーヴユルツブルクを体感しました。風景・お人柄・食べ物・・・。予想通り、いいえ期待以上でした。まずはアパートを借りての生活でしたので気分的に気楽に過ごせました。
シーボルトミュージアムでのドイツの方々との交流、「書」のワークショップもとても暖かく受け入れてもらい、細やかな配慮も嬉しかったです。
初日にオープニングセレモニーがあり、ダウン症の方を含む音楽グループの交流もありました。ヘルマン・ハープの音色がとても素晴らしく歌を添えて演奏してくださいました。
観光も出来ました。ローザンベルグの街では、ロマンチック街道の石畳を踏みながらゆったり流れる時間を過ごしました。また、ヴユルツブルク宮殿を案内していただいたときは、特に頭上の大天井に圧倒されました。きらびやかな近代ビルはほとんどなく、三角屋根のレンガの家・・・宮崎駿の世界が続いていました。
最後に忘れられないエピソードです。
約9日間の滞在を終えてあっという間の帰国当日、荷物を持ってヴユルツルク駅へ。深尾親子と池田親子が帰国します。ずっとお世話をしてもらったバーバラさんが事前にタクシーも手配してくれていました。荷物も運び、電車が来るのを待っている時、私のリュックがないことに気づきました。そうや、アパートに忘れている、どうしよう、タクシーで戻らないと…、
と慌てているとき救世主のバーバラさんが現れて(見送りに来てくれました)『私がアパートへ取りに行きます!!』アパートの鍵ボックスの番号を聞いてすぐさま自転車で取りに行ってくれました。わずか10分後、荷物は私の手元に。
バーバラさんはごく自然に手を差し伸べてくれました。感謝しかありません。
ドイツは最後まで良い思い出ばかりです。」
(以上 池田真優子さんのお母様 池田弘美さんの体験談)
深尾篤範さんのお母様からは、帰国してからこのようなエピソードが届きました。
「今日は町内の地蔵盆があり、夕方少しだけ参加しました。そこで、近所のおばさんに出会い、あつのりが『ドイツに行ってきたんだよ』と話したので、あつのりのパフォーマンスの動画やお軸の作品をお見せしたら、感動の涙を流されました。
『小さいときは大変やったけど、あっ君、成長したね~』とおっしゃっていただけました。」
(以上 深尾篤範君のお母様 深尾智子さんより)
心温まる嬉しいお話でした。
面白い出来事、書けていないエピソードはてんこ盛りですが、それはまたいつかの機会にとっておきます。
今回の展覧会を通して「書道」という芸術の力がドイツの方々の心に響き、微力ではありますが、距離を縮められたと実感できたことは大変嬉しいことでした。
「出会いは宝」であるとつくづく思います。お金では買えない多くの珠玉の体験ができたのも貴重なお出会いのおかげです。
一昨日、二つの大きな航空荷物が自宅に無事に届きました。専攻科滋賀の会の皆さんの作品も入っていたので、書道教室に間に合いほっとしました。
そして昨日はヴユルツブルク市長のクリスティアンシュハルト様から暖かくご丁寧なお便りが届きました。一介の日本人に対しても心を配っていただけたことは、大変有り難く光栄なことでした。
1学期末、勤務している高校の生徒たちに、「もしかしたら退職しなければならないかも」と伝えていたので、2学期初日、たくさんの生徒たちが心配して書道室に会いに来てくれました。「あぁ良かったぁ!」と口々に言ってくれ、嬉しいひとときでした。配慮していただきました管理職の先生には本当に感謝しています。
大津絵の佐藤先生も一緒に展覧会をしました。日本文化をドイツの方々と楽しめたことは大変幸せなことでした。
最後になりましたが、この展覧会に向けてご尽力いただきました多くの皆様に心より厚く御礼申し上げます。
「出会いは宝」をあらためて実感しました。様々なご縁に心より感謝申し上げます。そして今後ともご指導の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2024年9月8日
書家 福角 窓月(ふくすみ そうげつ)拝
(以上)
【御参考】