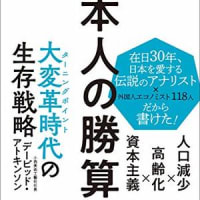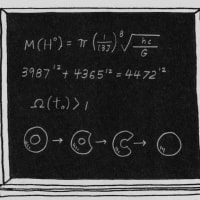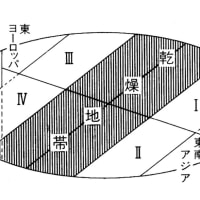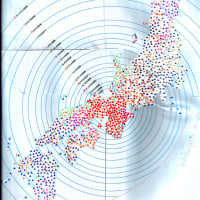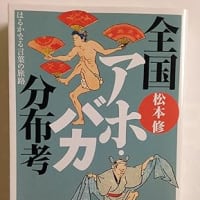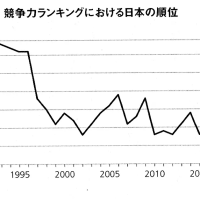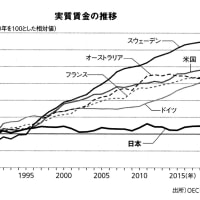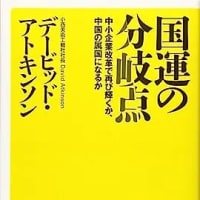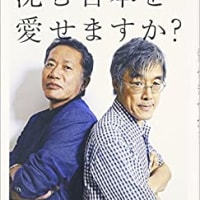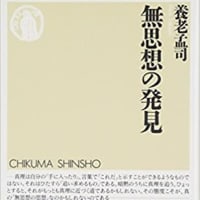恋愛と不倫の系譜
ここ2,3年、政治家や芸能人の不倫騒ぎが世間をにぎわしている。多くの不倫を暴いた週刊文春は、記事や写真の迫力から“文春砲”というニックネームまで頂戴した。世論は概して恋愛には寛容だが、不倫に関しては不寛容である。一方で、個人のことだから放っておいていいのではないかという声が(小さく)あがっている。つまり、声は上がっているが、世論の大勢にはなっていないということだ。

(写真は、ミッテラン元大統領)
恋愛といえば、やっぱりフランスが本場だろう。もう35年も前のことになるが、当時のミッテラン大統領に隠し子がいる、というニュースが入り、ある通信社の記者が突撃取材をした。大統領に「隠し子がいるそうですね?」と問いかけると、彼は“Et alors?”と答えたそうである。直訳すれば「それがどうした?」という軽いノリなのである。言外に「何の問題があるの?」と言っている。フランス滞在の長い記者は、黙って引き下がった。フランスにおいて、婚外恋愛とか私生児とかは、われわれが息をしているように、普通の出来事なのである。しかも、ここが肝心だが、恋愛を認めるなら不倫や私生児は当然のように跋扈(ばっこ)する、と当のフランス人たちが思っていることである。(だから国は同棲であっても結婚と認めるし、そうして生まれた子供には分け隔てなく養育手当てを支給する。先進国で唯一、出生率の上がったのがフランスだったことは周知の通り)
フランス革命の成果は、革命前の貴族が味わっていた奔放な性生活が庶民にまで下りてきたこと-という皮肉な見解を披瀝したのは鹿島茂氏であった。彼によると、恋愛は12世紀に「発明」されたもので、その発祥は貴婦人に対する騎士たちのプラトニックラブである。ドン・キホーテが架空のドゥルシネア姫に恋し、常に戦果を姫に捧げるのは、この風習をなぞったもの。
ただし、ドン・キホーテはともかく、恋愛はプラトニックだけで済むようなヤワなものではない。そこには、精神的に犠牲をいとわないという気高さとともに、肉体的にもひとつになりたいという欲望が渦巻く。フランスでは、奥方と主人の寝室を遠くに離し、双方に外から寝室に入れるような階段をつけて、文字通り霊肉一致の恋愛が楽しめるようにした。これでフランス人の大好きな婚外恋愛への道をつけたのである。そのための理屈は後述する。
ひるがえって、わが国ではどうか? 仏教では「愛」は煩悩である。男女の愛もそうだが、親子の愛情も煩悩であるというのである。「親の欲目」とは親の愛が煩悩であることを端的に示した常套句である。明治維新で西洋の風俗が紹介されるまで、日本に「恋愛」はなかった。明治25年に、北村透谷が「恋愛は人生の秘鑰(ひやく=鍵のこと)なり」と宣言し、初めて恋愛の概念を紹介したのである。それまで恋愛らしき事象を表す言葉としては「恋煩い」しか日本にはなかった。

(写真は、北村透谷)
よく考えてみると、「恋煩い」とは絶妙のネーミングである。煩悩の果ての病気。言いえて妙である。ためしに、結婚前、最高潮に盛り上がっている二人に「彼(彼女)の良いところはどこですか?」と尋ねたら「全部です!」と確信を持って答えるだろう。この時点で、恋愛中の二人は認知症を患っていると判断せざるを得ない。全部が美点だって! そんな訳なかろう! と第三者は思う。しかし、本人たちは大真面目である。

(写真は、スタンダール)
この症状に名前をつけたのが小説『赤と黒』を書いたスタンダールだった。彼には『恋愛論』という著書もある。その中で彼は「結晶作用」を力説した。何もないところに、恋人はいろんな結晶を貼り付けていくのである。男の臆病は慎重という結晶に変わり、無謀は大胆という結晶になる。ボロを出すまいとしている女の無口は結晶作用がはたらいて、見守る優しさへと変貌する。粗忽は活発という結晶に変わる。
「赤い糸で結ばれている」という妄信が信じられる。前世からの約束があったような気がすることもある。私が見聞きしたすごい例では、「私たちは魚だった頃に知り合ったの」という詩があった。2億年以上も前から二人はこうなる運命だった、というのである。第三者的に言えば誇大妄想である。江戸時代の大人が聞いたら「しょうがねえなあ。恋煩いだもの」とあきらめるだろう。
結晶化や妄想の後遺症は深刻である。誰だって時間がたてば現実に気づく。どんな恋も長くて3,4年で冷めるのが通例である。通常はこの期間に子供が生まれ、恋愛から家族愛へとうまく切り替えていく。そのときには恋愛時のような熱病風の症状はない。改めて考えると、とにかく二人がくっついて子供を設けるよう、生物的にプログラムされた熱病が恋愛であるような気もする。神様か、それとも神様のような存在が、人類を根絶やしにしないように仕組んでいるような気がするのである。この熱病がなければ、人類の出生率はガクンと下がるだろう。
当初の話題に戻って「不倫」である。恋愛が病気ならば、不倫は必至である。よく「恋に落ちる」という。「落ちる」に「堕ちる」を当てる人もいるが。要するに不慮の事故だというのである。事故であるからには、発生は場所を問わないし、時間も問わない。人の身分(既婚か未婚かなど)を問わない。秩序もないし、ましてや道徳的な規範もあるはずがない。「不倫は必至」と書いたのは、その意味である。
読者の中には、キリスト教が「愛」の宗教だというので、恋愛を勧めているなどと勘違いしている向きもあるかもしれない。しかし、キリスト教の「愛」は静かに持続すべき人類愛のようなもので、熱病のような恋愛とは異なる。もちろん、不倫は固く禁じられている。「汝、姦淫するなかれ」と。前に述べたとおり、仏教は「愛」を煩悩として退けている。
それじゃ、現在の恋愛→不倫の盛況はどういうことなのか? 前出の鹿島茂氏は興味深い考察をされている。フランスで小説に描かれた恋愛はすべて不倫である、というのですね。鹿島氏はフランス文学の泰斗、信じざるを得ません。本職は19世紀フランス文学、特にバルザックの研究家であるが、エッセイも面白く『乳房とサルトル』『ナポレオン・フーシェ・タレーラン』など、必読の書は多い。


(写真は、鹿島茂『乳房とサルトル』『ナポレオン・フーシェ・タレーラン』)
では何故、恋愛が不倫に発展したか? 以下は『乳房とサルトル』からの受け売りです。キリスト教(特にカトリック)では、性に快楽を求めることは厳禁である。性は子孫を残すためだけにある、というのが教えです。性に快楽を感じることは汚らわしい、ということ。こりゃ、困りますねえ。そこで助平な貴族たちが考え出したロジックがこう。汚らわしい行為を汚らわしい相手(つまり売春婦)と行うなら問題はなかろう。こうして教義にはアリの一穴がうがたれました。女性も黙ってはいない。といって、当時はホストクラブがあるわけもなく、いきおい様々な婚外恋愛が発展した、というわけ。貴族の女性のサロンはさまざまな文化の発信地でもあり、婚外恋愛の仲介地でもありました。
日本の事情はどうだったのでしょう? 武士と町人では、だいぶ違います。武士階級の生活は儒教が基本、不義密通は男女の身体を重ねて四つに切ってもいいという教えですから、不倫はもってのほか。一方、町人はというと、江戸の町が男8女2くらいの割合だったそうで、女はもてた。つい誘惑に乗ることは結構あったらしい。田舎へ行けば、夜這い(夜に忍び込む)という風習があって、これも女の意向次第で、戸を開けておいたり閉めておいたり。儒教に縛られたCHINAや韓国のような不自由はなかった。古代からのおおらかさを受け継いでいた、ということです。

(写真は、近松門左衛門)
もっとも「恋愛」というような意識はなかったでしょう。多分、色好み…といったとらえ方をしていただろう。そんな中にあって、近松門左衛門の心中物は特筆に価する。死をもいとわない道行きは純愛物と見てもよく、明治になってからヨーロッパの恋愛が受け入れられたのは、この下地があったからではないか。

(写真は、バーナード・ショウ)
ただ、近年の不倫ばやりは、古代からの血脈が、70年前から始まった戦後の自由かぶれによって拍車をかけられたもの、と見ることが出来る。皮肉な発言で知られるバーナード・ショウはこう言っている。「自由は常にお尻のあたりから始まる」とね。でも、不倫が可能なのは、女性に生活力がついてきた証拠。目出度いとしておきましょう。日本の現状では、恋愛は欧米風に肯定しているが、不倫については儒教や仏教の教えを守っているようだ。ケースバイケースという日本人らしい態度で、原理主義から離れているところがいい。
ここ2,3年、政治家や芸能人の不倫騒ぎが世間をにぎわしている。多くの不倫を暴いた週刊文春は、記事や写真の迫力から“文春砲”というニックネームまで頂戴した。世論は概して恋愛には寛容だが、不倫に関しては不寛容である。一方で、個人のことだから放っておいていいのではないかという声が(小さく)あがっている。つまり、声は上がっているが、世論の大勢にはなっていないということだ。

(写真は、ミッテラン元大統領)
恋愛といえば、やっぱりフランスが本場だろう。もう35年も前のことになるが、当時のミッテラン大統領に隠し子がいる、というニュースが入り、ある通信社の記者が突撃取材をした。大統領に「隠し子がいるそうですね?」と問いかけると、彼は“Et alors?”と答えたそうである。直訳すれば「それがどうした?」という軽いノリなのである。言外に「何の問題があるの?」と言っている。フランス滞在の長い記者は、黙って引き下がった。フランスにおいて、婚外恋愛とか私生児とかは、われわれが息をしているように、普通の出来事なのである。しかも、ここが肝心だが、恋愛を認めるなら不倫や私生児は当然のように跋扈(ばっこ)する、と当のフランス人たちが思っていることである。(だから国は同棲であっても結婚と認めるし、そうして生まれた子供には分け隔てなく養育手当てを支給する。先進国で唯一、出生率の上がったのがフランスだったことは周知の通り)
フランス革命の成果は、革命前の貴族が味わっていた奔放な性生活が庶民にまで下りてきたこと-という皮肉な見解を披瀝したのは鹿島茂氏であった。彼によると、恋愛は12世紀に「発明」されたもので、その発祥は貴婦人に対する騎士たちのプラトニックラブである。ドン・キホーテが架空のドゥルシネア姫に恋し、常に戦果を姫に捧げるのは、この風習をなぞったもの。
ただし、ドン・キホーテはともかく、恋愛はプラトニックだけで済むようなヤワなものではない。そこには、精神的に犠牲をいとわないという気高さとともに、肉体的にもひとつになりたいという欲望が渦巻く。フランスでは、奥方と主人の寝室を遠くに離し、双方に外から寝室に入れるような階段をつけて、文字通り霊肉一致の恋愛が楽しめるようにした。これでフランス人の大好きな婚外恋愛への道をつけたのである。そのための理屈は後述する。
ひるがえって、わが国ではどうか? 仏教では「愛」は煩悩である。男女の愛もそうだが、親子の愛情も煩悩であるというのである。「親の欲目」とは親の愛が煩悩であることを端的に示した常套句である。明治維新で西洋の風俗が紹介されるまで、日本に「恋愛」はなかった。明治25年に、北村透谷が「恋愛は人生の秘鑰(ひやく=鍵のこと)なり」と宣言し、初めて恋愛の概念を紹介したのである。それまで恋愛らしき事象を表す言葉としては「恋煩い」しか日本にはなかった。

(写真は、北村透谷)
よく考えてみると、「恋煩い」とは絶妙のネーミングである。煩悩の果ての病気。言いえて妙である。ためしに、結婚前、最高潮に盛り上がっている二人に「彼(彼女)の良いところはどこですか?」と尋ねたら「全部です!」と確信を持って答えるだろう。この時点で、恋愛中の二人は認知症を患っていると判断せざるを得ない。全部が美点だって! そんな訳なかろう! と第三者は思う。しかし、本人たちは大真面目である。

(写真は、スタンダール)
この症状に名前をつけたのが小説『赤と黒』を書いたスタンダールだった。彼には『恋愛論』という著書もある。その中で彼は「結晶作用」を力説した。何もないところに、恋人はいろんな結晶を貼り付けていくのである。男の臆病は慎重という結晶に変わり、無謀は大胆という結晶になる。ボロを出すまいとしている女の無口は結晶作用がはたらいて、見守る優しさへと変貌する。粗忽は活発という結晶に変わる。
「赤い糸で結ばれている」という妄信が信じられる。前世からの約束があったような気がすることもある。私が見聞きしたすごい例では、「私たちは魚だった頃に知り合ったの」という詩があった。2億年以上も前から二人はこうなる運命だった、というのである。第三者的に言えば誇大妄想である。江戸時代の大人が聞いたら「しょうがねえなあ。恋煩いだもの」とあきらめるだろう。
結晶化や妄想の後遺症は深刻である。誰だって時間がたてば現実に気づく。どんな恋も長くて3,4年で冷めるのが通例である。通常はこの期間に子供が生まれ、恋愛から家族愛へとうまく切り替えていく。そのときには恋愛時のような熱病風の症状はない。改めて考えると、とにかく二人がくっついて子供を設けるよう、生物的にプログラムされた熱病が恋愛であるような気もする。神様か、それとも神様のような存在が、人類を根絶やしにしないように仕組んでいるような気がするのである。この熱病がなければ、人類の出生率はガクンと下がるだろう。
当初の話題に戻って「不倫」である。恋愛が病気ならば、不倫は必至である。よく「恋に落ちる」という。「落ちる」に「堕ちる」を当てる人もいるが。要するに不慮の事故だというのである。事故であるからには、発生は場所を問わないし、時間も問わない。人の身分(既婚か未婚かなど)を問わない。秩序もないし、ましてや道徳的な規範もあるはずがない。「不倫は必至」と書いたのは、その意味である。
読者の中には、キリスト教が「愛」の宗教だというので、恋愛を勧めているなどと勘違いしている向きもあるかもしれない。しかし、キリスト教の「愛」は静かに持続すべき人類愛のようなもので、熱病のような恋愛とは異なる。もちろん、不倫は固く禁じられている。「汝、姦淫するなかれ」と。前に述べたとおり、仏教は「愛」を煩悩として退けている。
それじゃ、現在の恋愛→不倫の盛況はどういうことなのか? 前出の鹿島茂氏は興味深い考察をされている。フランスで小説に描かれた恋愛はすべて不倫である、というのですね。鹿島氏はフランス文学の泰斗、信じざるを得ません。本職は19世紀フランス文学、特にバルザックの研究家であるが、エッセイも面白く『乳房とサルトル』『ナポレオン・フーシェ・タレーラン』など、必読の書は多い。


(写真は、鹿島茂『乳房とサルトル』『ナポレオン・フーシェ・タレーラン』)
では何故、恋愛が不倫に発展したか? 以下は『乳房とサルトル』からの受け売りです。キリスト教(特にカトリック)では、性に快楽を求めることは厳禁である。性は子孫を残すためだけにある、というのが教えです。性に快楽を感じることは汚らわしい、ということ。こりゃ、困りますねえ。そこで助平な貴族たちが考え出したロジックがこう。汚らわしい行為を汚らわしい相手(つまり売春婦)と行うなら問題はなかろう。こうして教義にはアリの一穴がうがたれました。女性も黙ってはいない。といって、当時はホストクラブがあるわけもなく、いきおい様々な婚外恋愛が発展した、というわけ。貴族の女性のサロンはさまざまな文化の発信地でもあり、婚外恋愛の仲介地でもありました。
日本の事情はどうだったのでしょう? 武士と町人では、だいぶ違います。武士階級の生活は儒教が基本、不義密通は男女の身体を重ねて四つに切ってもいいという教えですから、不倫はもってのほか。一方、町人はというと、江戸の町が男8女2くらいの割合だったそうで、女はもてた。つい誘惑に乗ることは結構あったらしい。田舎へ行けば、夜這い(夜に忍び込む)という風習があって、これも女の意向次第で、戸を開けておいたり閉めておいたり。儒教に縛られたCHINAや韓国のような不自由はなかった。古代からのおおらかさを受け継いでいた、ということです。

(写真は、近松門左衛門)
もっとも「恋愛」というような意識はなかったでしょう。多分、色好み…といったとらえ方をしていただろう。そんな中にあって、近松門左衛門の心中物は特筆に価する。死をもいとわない道行きは純愛物と見てもよく、明治になってからヨーロッパの恋愛が受け入れられたのは、この下地があったからではないか。

(写真は、バーナード・ショウ)
ただ、近年の不倫ばやりは、古代からの血脈が、70年前から始まった戦後の自由かぶれによって拍車をかけられたもの、と見ることが出来る。皮肉な発言で知られるバーナード・ショウはこう言っている。「自由は常にお尻のあたりから始まる」とね。でも、不倫が可能なのは、女性に生活力がついてきた証拠。目出度いとしておきましょう。日本の現状では、恋愛は欧米風に肯定しているが、不倫については儒教や仏教の教えを守っているようだ。ケースバイケースという日本人らしい態度で、原理主義から離れているところがいい。