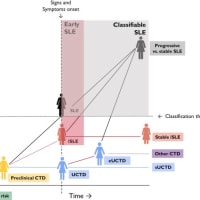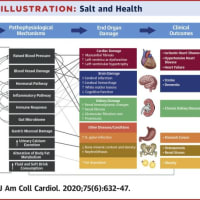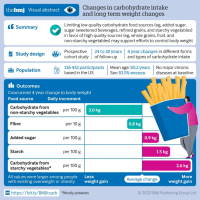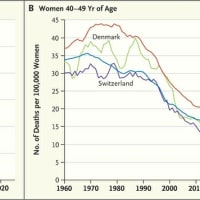認知症の予防、介入、ケア:ランセット常設委員会の 2024 年報告書
Lancet 2024; 404: 572-628
うつ病
2020 年のランセット委員会では、うつ病と認知症との関連はおそらく双方向的であり、認知症が現れる前の数年間は認知障害の原因となり得ると、発表された研究に基づいて結論づけた。一方、認知症のリスクがうつ病の治療によって影響を受けるかどうかを検討した研究はほとんどなかった。
新しいメタアナリシスでは、うつ病があらゆる原因の認知症と関連していることが明らかにされたが、研究間で異質性が高かった(RR 1.96, 95%CI 1.59-2.43, I2 = 96.5%, 27 件の研究)。その結果、うつ病を有する人の認知症リスクは、うつ病を有しない人に比べて高いことが確認された(RR 2.25, 95%CI 1.69-2.98, I2 = 82.8%, 図 6)。
図 6. うつ病診断後 10-14 年後のうつ病でない人と比較した認知症発症リスクについてのメタ分析
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/fulltext?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet#
参加者の年齢を特定した 6 つの研究のベースライン平均年齢は 63 歳であった。これらの研究は効果の大きさにおいて不均一であったが、参加者の年齢、性別、社会経済的状態、併存疾患をマッチさせた研究を含め、うつ病患者の認知症リスクの増加を一貫して報告していた。同様に、うつ病と診断された成人 246,499 人(年齢中央値 50.8 歳、IQR 34.7-70.7)とうつ病でない 1,190,302 人を対象としたデンマークの症例対照研究では、うつ病のない人と比較して、うつ病のある人では全体的に認知症リスクが高いことが報告されている(HR 2.41, 95%CI 2.35-2.47) 。この関連は、うつ病でない人と比較して、うつ病評価の指標日と認知症との間の間隔が 20~39 年より長い人(1.79, 1.58-2.04)、および初期(すなわち、18~44 歳;3.08, 2.64-3.58)、中期(すなわち、45~59 歳;2.95, 2.75-3.17)、または後期(すなわち、60歳以上;2.31, 2.25-2.38)にうつ病と診断された人においてもみられた。41,727人の双生児を対象としたスウェーデンの全国研究(18 年間の追跡調査)では、中年期(オッズ比 [odds ratio: OR] 1.46, 95%CI 1.09-1.95)、晩年期(2.16,
1.82-2.56)、終年期(2.65, 1.17-5.98)のうつ病で認知症リスクが高かったことが報告されている。
全体として、これらの研究は、うつ病がすべての成人年齢において認知症のリスクを増加させることを示唆しているが、晩年においては、その関連性の一部は前臨床認知症によるものである。したがって、中年期のリスクは明らかであるため、うつ病を中年期のリスク因子として分類している。
スウェーデンの研究では、一卵性双生児と非一卵性双生児との間に差はなく、認知症リスクは遺伝的リスクや早期生活環境によって説明されないという結論に至った。うつ病と認知症リスクとの関連メカニズムは不明であるが、うつ病はセルフケアや社会的接触の減少につながる可能性がある。また、うつ病が認知症を増加させるメカニズムとして、コルチゾールの過剰分泌が海馬の萎縮や炎症反応を引き起こすという仮説もある。
うつ病に対する介入に関する UK Biobank の研究では、ベースライン時に認知症のない 50〜70 歳の 354,313 人が、中央値 11.9 年(IQR 11.2-12.6)追跡され、うつ病と診断された人(n = 46,280)は認知症の発症リスクが高かったことが報告されている(HR 1.51, 95%CI 1.38-1.63)。薬物療法(n=14 695;0-77、0-65-0-91)、心理療法(n = 2151;0.74, 0.58-0.94)、または併用療法(n = 5281;0.62, 0.53-0.73)によりうつ病の治療を受けた人は、未治療群よりも認知症になる可能性が低かった(治療全体のHR 0.69, 0.62-0.77)。寛解した未治療群では、うつ病のない群に比べて認知症のリスクは高くなかった(0.84, 0.56-1.24)。この研究は、以前のエビデンスよりも大規模で長期間のデータを提供したが、観察研究のバイアスの影響を受ける可能性がある。しかし、このような長期の RCT が行われる可能性は低い。うつ病の薬物療法と治療が認知症リスクを減少させるという知見は、QOL のためにも、将来の認知症リスクを減少させるためにも、うつ病を治療することの重要性を示唆している。
外傷性頭部損傷
我々は、2020 年のランセット委員会において、TBI 後のあらゆる原因による認知症リスクのメタ解析を行った(RR 1.84, 1.54-2.20)。最初の解析は、21 件の研究、合計 8,684,485 人を含み、TBI と認知症リスクの OR は 1.81(95%CI 1.53-2.14)であった。32 件の研究(n = 7,634,844)のメタアナリシスでは、TBI 後の認知症リスクは 1.66(95%CI 1.42-1.93)と報告されている。
したがって、TBI リスクは認知症の危険因子である他の健康行動と関連している。フィンランドの大規模全国前向き縦断研究(n = 32,385)では、学歴、喫煙の有無、飲酒、身体活動、高血圧など、認知症の他の危険因子を調整した後、重大な TBI(すなわち、3 日以上の入院)と認知症との関連は弱まった(HR 1.51 [95%CI 1.03-2.22] から 1.30 [0.86-1.97])と報告されている。
脳震盪 (concussion) と軽度 TBI(mild TBI: mTBI)は、しばしば同じ意味で使われる用語である。mTBI と認知症リスクに関する研究は少なく、定義に一貫性がないなど、方法論上の問題もある。全国患者登録を用いた以前のコホート研究では、1 回の mTBI でも認知症リスクが増加すると報告されている(OR 1.63, 95%CI 1.57-1.70)。 2020 年のランセット委員会以降、あるコホート研究では 15 年間にわたる mTBI による認知症リスクの増加は報告されていないが、WHO 基準を満たす mTBI の既往歴を報告した 3,149,740 人を含む 5 件の研究の系統的レビューとメタアナリシスでは、アルツハイマー病リスクの増加が同定されている(RR 1.18, 95%信頼区間 1.11-1.25)、mTBI がアルツハイマー病に 10 年以上先行した数少ない研究(n = 2,307)を含む感度分析でも、信頼区間は広がったが、TBI 後の認知症リスクの増加が同定された(2.02, 0.66-6.21)。
スポーツの中には(例えば、ラグビー、アメリカンフットボール、アイスホッケー)、頭部への接触やむち打ちが頻繁に起こり、事故やスポーツの一部として低頻度で TBI が起こる可能性のあるスポーツ(例えば、サイクリング、乗馬、ボクシング)よりも、反復性 TBI のリスクが高いものがある。プロやアマチュアのサッカー選手やラグビー選手は、一般の人々よりも神経変性疾患を患ったり、神経変性疾患により死亡したりすることが多いという懸念が高まっているが、これは、時折起こる重度の TBI や、他者との身体的接触やフットボールのヘディングによる頻繁な mTBI に関連している可能性がある。コンタクトスポーツにおける脳震盪リスクをランク付けしたメタ分析では、主にアメリカ(n = 66)から報告された脳震盪率に関する 83 件の研究が特定され、カナダとイギリスからはそれぞれ 5 つの研究が報告されている。ラグビーの脳震盪率が最も高く(1 万試合あたり 28~3 回)、次いでアメリカンフットボール(1 万試合あたり 8~7 回)、アイスホッケー(1 万試合あたり 7~9 回)、レスリング(1 万試合あたり 5~0 回)であった。大学スポーツの脳震盪率は高校スポーツよりわずかに高かった(1 万試合あたり 3~8 回の脳震盪に対して 3~7 回の脳震盪)。
プロサッカー選手として長くプレーし、ヘディングの頻度が高いポジションにいる人ほど、頭部外傷を負いやすく、認知症のリスクが高いというエビデンスがある。60 人の選手を対象としたある小規模な研究では、元プロサッカー選手の認知能力は推定ヘディング頻度と逆相関していたと報告している。英国のスコットランドで行われた大規模な研究では、7,676 人の元サッカー選手のうち 386 人(5.0%)が神経変性疾患を発症したのに対し、年齢、性別、地域の社会経済的地位でマッチさせた 23,028 人のうち 366 人(1.6%)が発症したことが報告されている(HR 3.66, 95%CI 2.88-4.65)。このリスクの増加は、ヘディングの頻度が高いディフェンダーや 15 年以上プロとしてプレーしている選手で最も高く、ゴールキーパーで最も低かった。フランスのプロサッカー選手を対象とした研究では、全死因死亡率は国民より低かったが(標準化死亡率 0.69, 95%信頼区間 0.64-0.75)、死亡したサッカー選手の認知症死亡率は非選手より高かった(3.38, 2.49-4.50)。 スウェーデンのトップリーグに所属する 6,007 人の男性サッカー選手(ゴールキーパーを除く)と、性別、地域、面積をマッチさせた対照参加者を対象としたコホート研究では、サッカー選手はあらゆる原因の認知症のリスクが高かったが(HR 1.62, 95%CI 1.47-1.78)、運動ニューロン疾患やパーキンソン病のリスクは高くなかったと報告している。全死因死亡のリスクは、サッカー選手では対照群よりも低かった(0.95, 0.91-0.99)。同様に、70 歳までは元ラグビー日本代表選手の方が全死亡率は低かったが、中央値 32 年の間に、元ラグビー選手 412 人中 47 人(11%)、対照群 1,236 人中 67 人(5%)が神経変性疾患と診断された(2.67, 1.67-4.27)。
TBI は直接的に認知症を引き起こしたり、悪化させたりする。TBI 後の長期的な神経変性の病理学的機序として考えられるのは、タンパク異常(例えば、リン酸化タウやアミロイド β)の早期生成を促進する軸索損傷、ミクログリアの活性化、皮質の萎縮などである。TBI と意識消失の既往がある人の脳病理を評価したコホート研究を 3 件同定したが、神経病理との関連については研究間で一貫性がなかった。剖検を受けた 1,589 人を対象とした研究では、意識消失を伴う TBI 歴のある人では、レビー小体病変と海馬硬化が増加したが、プラークや neurofibrillary tangle は増加しなかったと報告している。241 人を対象とした Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative 研究では、TBI 歴のある 41 人は、TBI 歴のない人に比べ、アミロイド β 沈着の増加、皮質の菲薄化、認知機能障害の発症が 3~4 年早まることと関連していることが確認された。対照的に、60 歳以前に意識喪失を伴う TBI を受けた 80 人を対象とした英国の集団ベースの研究では、70 歳頃までに、頭部外傷のない 395 人と比較して、アミロイド β 沈着、海馬容積、皮質厚に差はなかったが、認知力が低く、脳容積が小さかった。神経画像と神経変性の体液バイオマーカーを用いた現在進行中の研究は、外傷後認知症や慢性外傷性脳症を含む他の神経変性障害の異なるサブタイプを持つ人々における神経病理学の重複するパターンと異なるパターンの両方を同定するのに役立つかもしれない。
全体として、TBI は認知症リスクを増加させ、おそらく TBI を受けていない人よりも 2~3 年早く認知症が発症することを示唆している。このような神経変性疾患のリスクによって、スポーツが一般的に健康に良いというメッセージを曖昧にしてはならない。例えば、適切な頭部保護具、ヘディング練習や衝撃の大きい衝突の制限、TBI 直後のプレーの防止、場合によっては傷害を減らすためのルールの見直しなどによって、頭部傷害から保護することは、現在、個人および公衆衛生の優先事項であるべきである。一部のスポーツ団体や政府機関は、こうした政策を実施し始めている。
喫煙
我々は以前、晩年の喫煙が認知症リスクの上昇と関連することを報告した(HR 1.6, 1.2-2.2)。新たなエビデンスによると、中年期の喫煙は晩年の喫煙よりも認知症の危険因子が強いようであるが、これはおそらく心血管疾患や喫煙に関連した癌の治療が改善され、喫煙者が認知症を発症するほど長生きする機会が増えたためであろう。Zhong らによる大規模なメタアナリシスでは、中年期の喫煙は認知症リスクを増加させたが(RR 1.30, 95%CI 1.18-1.45, 37 件の研究)、元喫煙者ではリスクの増加はみられなかったと報告している。フラミンガム心臓研究(n = 4015;21 年間の追跡)では、成人初期(すなわち、33-44 歳;HR 1.42, 95%CI 0.05-3.60)に喫煙を開始した人の認知症リスクが最も高いことが確認された。 ARIC 研究(25 年追跡;n=15,744;1.41, 1.23-1.61)や Whitehall II 研究(32 年追跡;n = 9,951;1.36, 1.10-1.68)のような他の長期コホート研究も、中年期(すなわち、平均年齢 44.9 歳[SD 6.0])の喫煙者における認知症の過剰リスクを報告している。デンマークの一般集団では、合計 61,664 人を含む 2 件の前向きコホートのプール解析で、中年期の喫煙者の認知症リスクは、非喫煙者に比べて男性(3.2, 1.4-7.4)および女性(1.7, 1.1-2.8)で増加したことが報告されている。
Whitehall II コホートの 32 年間の追跡調査では、社会経済的状態で調整した結果、喫煙者(HR 1.36, 95%CI 1.10-1.68)は喫煙経験のない人に比べて認知症リスクが高いが、元喫煙者(0.95, 0.79-1.14)はそうではなく、認知症リスクにおける社会経済的不平等は喫煙によって部分的に媒介されることが確認された。同様に、2 年間にわたって喫煙状況を評価した 789,532 人を対象とした韓国の全国調査では、元喫煙者は喫煙継続者よりもあらゆる原因による認知症リスクが低く(0.92, 0.87-0.97)、65 歳以前に喫煙していた成人(0.8, 0.7-0.9)では、65 歳以上で喫煙していた成人(1.0, 0.9-1.0)よりも顕著であったと報告している。 心房細動患者の認知症リスクを検討した韓国の別の集団研究でも、現在喫煙している人と比較して、禁煙した人では認知症リスクが減少したことが報告されている(0.83, 0.72-0.95)。これらの研究は、禁煙が喫煙継続者に比べて認知症リスクを減少させることを示唆している。現在、喫煙は中年期の危険因子(2020 年のランセット委員会のように晩年期の因子ではなく)と考えるべきであり、禁煙の有益な効果は勇気づけられるものである。
心血管危険因子
心血管疾患の合併ではなく、心血管疾患の危険因子を個別に検討することにした。脳卒中と認知症は、教育を受けていない、運動頻度が少ない、高血圧、心臓病、社会的孤立などの危険因子を共有しているが、これらの危険因子を持つ人の中には、神経病理学的に認知症を発症しない人もいる。これは認知症を発症する前に亡くなっているという場合もある。
いくつかの研究では、心血管危険因子の組み合わせが認知症リスクに及ぼす影響について検討されている。Life's Simple 7 グループでは、理想的な心血管健康因子(すなわち、BMI、食事、喫煙、身体活動、血圧、コレステロール、グルコース濃度)を定義しており、この指数のスコアが高いほど認知症リスクが低いことと関連している。同様に、中国では、追跡調査時の平均年齢 72 歳(SD 6.6)の 29,072 人を対象とした 10 年間の縦断的研究が行われ、記憶力の低下が緩やかであることは、6つの因子のうち少なくとも 4 つを持っていることを意味する健康なグループに属していることと関連していることが報告された: すなわち、健康的な食事(すなわち、対象となる 12 品目の食品のうち少なくとも 7 品目を食べている)、身体運動(すなわち、週 150 分以上の中強度の運動または週 75 分以上の強度の運動)、積極的な社会的接触(すなわち、オンラインを含む週 2 回以上の社会的接触)、積極的な認知活動(すなわち、週 2 回以上の認知活動に従事している)、喫煙をしたことがない、または 3 年以上前に禁煙している、飲酒をしたことがない(すなわち、毎日の飲酒量がワイングラス 1 杯未満である)。 この関連は、APOEε4 キャリアと非キャリアの両方に当てはまった。
LDL コレステロール
メタアナリシスでは、中年期における高 LDL コレステロールは認知機能低下、あらゆる原因による認知症、アルツハイマー病の危険因子であるが、後期高齢者では危険因子ではないというエビデンスが一貫性はないものの高所得国から得られている。
65 歳未満の成人の LDL コレステロールを 12 ヵ月以上追跡調査した、合計 1,138,488 人が参加した英国の 3 件のコホート研究のメタアナリシスでは、LDL コレステロールが 1 mmol/L 増加するごとに、あらゆる原因による認知症の発生率が 8%増加することが報告されている(効果量 1.08, 95%CI 1.03-1.14, I2 = 0.3%)。 1,890 人の参加者を対象とした研究では、LDL コレステロールが高い(すなわち、3 mmol/L 以上)ことは、認知症リスクの増加と関連していることが報告されている(HR 1.33, 95%CI 1.26-1.41)。 中央値 7.4 年(IQR 4.6-10.4)追跡された UK Clinical Practice Research Datalink の大規模コホート(n = 1,853 ,954)においても、ベースライン時の LDL コレステロール高値は、同様にあらゆる原因による認知症のリスク増加と関連していた(LDL コレステロールの SD 増加[すなわち、1.01 mmol/L または 39 mg/dL の増加]あたり調整率比 1.05, 95%CI 1.03-1.06)。このリスクは、ベースライン時に 65 歳以上であった人よりも、ベースライン時に 65 歳未満であった人の方が、10 年以内に診断された認知症(1.10, 1.04-1.15)およびベースライン時から 10 年以上経過した認知症(1.17, 1.08-1.27)について強かった。平均年齢 58 歳(SD 13.0)から追跡した 94 ,184 人を対象としたデンマークのコホート研究では、食事ガイドラインを守っていない人(すなわち、果物、野菜、魚のすべてを週 3 皿以上食べる、砂糖入り飲料をほとんど飲まない、ソーセージなどの調理済み肉をほとんど食べない、テイクアウトをしない)は、LDL コレステロールが高い可能性が高かった。中央値 9 年(範囲 <1-15)の追跡調査後、これらのガイドラインの遵守度が低い人は、遵守度が高い人よりもアルツハイマー病以外の認知症を発症する可能性が高かったが(HR 1.54, 95%CI 1.18-2.00)、アルツハイマー病を発症する可能性は高くなかった。また、脂質低下薬を服用している人は認知症リスクを増加させなかった。 4,392 人を対象とした米国の研究では、HDL コレステロールの増加が認知症の発症を予防することが報告されている。
一方、21,000 人以上(平均ベースライン年齢 76 歳)の個人参加者を対象としたメタ解析では、総コレステロール、LDL コレステロール、HDL コレステロールと認知機能低下との間に関連は認められなかった。この結果は、スタチンの使用や APOE ε4 の有無で層別化しても変わらなかった。
過剰な脳内コレステロールは、脳卒中リスクの増加、脳アミロイド β およびタウの沈着と関連しており、LDL コレステロールと認知症の関連性の潜在的なメカニズムを示唆している。
食事と運動に関する個別カウンセリングは、LDL コレステロールを減少させる効果は小さい。スタチンは、アルツハイマー病の分野での研究の焦点となっており、コレステロールを減少させるだけでなく、抗炎症作用や抗酸化作用があるため、潜在的な効果が期待されている。36 件のコホート研究のメタアナリシスでは、スタチンの使用は、未治療の高コレステロールと比較して、あらゆる原因の認知症(OR 0.80, 95%CI 0.75-0.86, I2=97.5%)およびアルツハイマー病(0.68, 0.56-0.81, I2 = 94.5%)のリスク低下と関連しており、男女間に差はなかった。晩年に投与されたスタチンに関する RCT のコクラン・レビューでは、認知症リスク(1 試験)、認知アウトカム(2 試験)のいずれにも効果がみられなかった。55~80 歳の 6,373 人の参加者のデータを用いてエミュレートされた試験では、スタチンの持続的使用は認知症または死亡の 10 年リスクの低下と関連するが、スタチンの開始のみでは関連しないことが確認された。
全体として、中年期の高 LDL コレステロールは認知症の危険因子であるという、質の高い、一貫した、生物学的にもっともらしいエビデンスが存在する。2019 年の WHO ガイドラインでは、認知機能の低下や認知症のリスクを軽減するために、中年期の脂質異常症の管理が提案される可能性が示唆されているが、エビデンスの質は低い。観察研究のメタアナリシスは不均一であるが、認知症リスクに対するスタチンの有益性を示している。
運動不足、運動、フィットネス
我々は以前、運動と認知症の関連は双方向性である可能性が高いというバランスのとれたエビデンスがあると結論づけた。身体活動は人の生涯にわたって変化し、病気になると減少する。2020 年のランセット委員会以降、身体活動と認知症の関連を調査した 58 件の研究(n = 257,983)の系統的レビューとメタアナリシスにより、ベースライン年齢に関係なく、少なくとも 20 年の短期および長期追跡調査において、身体活動はあらゆる原因による認知症(RR 0.80, 95%CI 0.77-0.84)およびアルツハイマー病(0.86, 0.80-0.93)のリスク低下と関連していることが確認された。平均 10.9 年(SD 8.5)の短い追跡調査(0.79, 0.66-0.95)では、運動により血管性認知症のリスクが減少した。メタアナリシスでは、さまざまな強度の運動が対象とされ、極端な運動不足からある程度の運動量に移行した場合にリスクの減少が最も大きかった。36 歳から 69 歳までの間に 5 回の身体活動を記録したコホート研究(n = 1,417)では、すべての年齢で身体活動をしていることが、身体活動をしていない場合よりも 69 歳時の認知機能の向上と関連しており、持続的な身体活動で最も強い関連がみられたと報告している。中央値 24.5 年(IQR 24.1-25.0)追跡調査され、10 年の間隔をおいて週 2 回身体活動量を評価された 29,826 人の前向き研究では、個々に最適と推定される身体活動量を維持している人は、持続的に不活発な人に比べて認知症リスクが減少し(HR 0.75, 95%CI 0.58-0.97)、身体活動量を最適レベルまで増加させた人(0.83, 0.72-0.96)も同様であったと報告している。 1,718人の女性を対象に中央値 11.9 年(範囲 0.6-13.5)にわたって行われた縦断的研究では、身体活動レベルが高いほど認知機能の低下が少ないことが報告されているが、糖尿病と高血圧で調整した場合はそうではなかった。
RCT では、平均年齢 78歳(SD 2)、女性 450 人(48%)、男性 495 人(52%)の計 945 人の参加者を、5 年間の対照群、週 2 回の中強度継続トレーニング、週 2 回の高強度インターバルトレーニングに無作為に割り付けた(2:1:1)。5 年後、対照群 494 人中 474 人(96%)が国の身体活動ガイダンスを遵守し、176 人(75%)が中強度インターバルトレーニング介入を遵守し、164 人(76%)が高強度インターバルトレーニング介入を遵守していた。認知機能(β 0.26, 95%CI -0.17~0.69)、MCI のオッズ(OR 0.86, 95%CI 0.66~1.13)に群間で有意差はなかった。中強度または高強度の運動を組み合わせた群の男性は、対照群の男性参加者よりも MCI のリスクが減少し(0.68, 0.47~0.99)、認知スコアがわずかに高かった。酸素摂取量を維持または増加させるのではなく、ピーク酸素摂取量を減少させた参加者は、酸素摂取量が安定している参加者と比較して MCI のオッズが増加した(1.35, 0.98~1.87)。しかし、この結果は正確ではないと推定されている。この結果は、身体運動が認知に及ぼす影響に関する RCT の包括的レビューで示されたわずかな認知への有益性と一致している。政策レベルでは、都市設計への介入と質の高い緑地の提供が WHO によって推奨されている。
年齢を問わず運動は認知に有用であるようで、おそらく高血圧の低下と一酸化窒素の増加による血流と機能の変化を通じて、脳の可塑性の向上と神経炎症の抑制につながる。
糖尿病
以前、我々は 2 型糖尿病が晩年における認知症発症の危険因子であることを述べた。新しいエビデンスによると、発症年齢には違いがあり、中年期の糖尿病発症は認知症リスクを増加させるが、必ずしも晩年期の糖尿病発症が認知症リスクを増加させるとは限らない。10,095 人の参加者を対象とした前向きコホート研究では、2 型糖尿病の発症年齢が5歳下がるごとに、発症時年齢が 70 歳を超えるまで認知症リスクが増加した(HR 1.24, 95%CI 1.06-1.46)。糖尿病が高齢期における認知症の危険因子ではないのか、あるいは有意な危険性を示すエビデンスがないのは、追跡期間が短く研究が少ないからなのかは不明である。WHO は、晩年の糖尿病は脳の健康と認知症リスクに有害な影響を及ぼす可能性があると結論づけている。長い罹病期間とコントロール不良の糖尿病は認知症のリスクを高める。
糖尿病が認知症リスクを増加させるメカニズムについての理解は不完全である。糖尿病において長期的に微小血管および大血管の合併症が起こることは確実であり、糖尿病が認知症リスクを増加させるメカニズムには、脳卒中リスクを含む血管の要素が含まれている可能性が高い。インスリン抵抗性は糖尿病とアルツハイマー病をつなぐ共通の分子メカニズムであり、アミロイド β の毒性、タウのリン酸化亢進、酸化ストレス、神経炎症の増加をもたらす。 全身性炎症マーカー(CRP など)の増加は、糖尿病に関連した認知症リスクの増加と関連していた。
糖尿病の効果的な治療がそれ自体認知症リスクを改善するかどうかは不明であり、特に大量の経口薬やインスリンの服用は糖尿病の重症度の上昇に関係している。しかし、標準的な糖尿病コントロールと比較して、厳格で集中的な治療を行っても認知症のリスクは減少しない。ある種の抗糖尿病薬を服用している人は、認知症のリスクが低い可能性を示唆するエビデンスもある。異質性が報告されていない 27 件の研究(1,590,757 人)の系統的レビュー、メタアナリシス、ネットワーク解析によると、コホート研究では、SGLT2 阻害薬(OR 0.41, 95%CI 0.22-0.76)、 GLP-1 受容体作動薬(OR 0.34, 95%CI 0.14-0.85)、DPP-4 阻害薬(OR 0.78, 95%CI 0.61-0.99)は認知症リスク低下と関連していたが、スルホニル尿素薬はリスク上昇と関連していた(OR 1.43, 95%CI 1.11-1.82)。 メトホルミンはリスクの減少にも増加にも関連しなかった(0.71, 0.46-1.08)。英国のプライマリケアにおける研究では、メトホルミンを開始した糖尿病患者 114,628 人の認知症リスクは、糖尿病治療薬を服用していない 95,609 人よりも有意に低かったことが報告されている(HR 0.88, 95%CI 0.84-0.92)。 2 型糖尿病患者を対象とした GLP-1 受容体作動薬に関する 3 件の RCT とコホート件の研究のメタアナリシスでは、プラセボ投与群との比較で(15, 820 人;HR 0.47, 95%CI 0.25-0.86)、デンマーク全国コホートとの比較で(120 054人;0.89, 0.86-0.93)無作為に割り付けられた GLP-1 受容体作動薬投与群で認知症率が低いことが確認された。 2 型糖尿病患者 819,511 人、平均追跡期間 4-5 年(範囲 1.3-7.2)の観察研究の別のメタアナリシスでも同様の結果が報告されており、SLGT2 阻害薬使用者ではその後の認知症が少なかった(3 研究; RR 0.62, 95%CI 0.39-0.97, I2 = 82.5%)。また、GLP-1 受容体作動薬(4 試験、0.72, 0.54-0.97, I2 = 91.3%)、DPP-4 阻害薬(7 試験、0.84, 0.74-0.94、I2 = 88.6%)では、これらの薬剤を使用していない人に比べて、その後の認知症が少なかった。ただし、これらの解析では高い異質性が報告された。 糖尿病患者が薬物療法を受けていないのは、薬物療法を行わなくても糖尿病が十分にコントロールされているからかもしれないし、治療が十分でないからかもしれない。GLP-1 受容体作動薬の予防効果については、RCT によるエビデンスも存在する。台湾の集団において、傾向一致させた 31,384 組(糖尿病と慢性腎臓病のマッチングを含む)を 5 年間追跡調査したところ、メトホルミンを服用している人は、服用していない人に比べて認知症の発症リスクが 72%低かった。メンデルランダム化やターゲットトライアルエミュレーションのような新しい研究デザインは交絡の可能性に対処するのに役立つかもしれない。
減量は糖尿病のコントロールにも役立ち、認知にも影響を与える可能性がある。Look AHEAD 試験では、45~76 歳の 2 型糖尿病で過体重または肥満の 3,751 人をリクルートし、運動量を増やし摂取カロリーを減らす 10 年間の介入を行う群と、糖尿病のサポートと教育を行う群に無作為に割り付けた。この RCT は、中間解析の結果、介入は血管死、心筋梗塞、脳卒中、重症狭心症に影響を及ぼさなかったため中止された。認知的転帰は、ベースラインの教育についてはコントロールしたが認知についてはコントロールせず、追跡時に測定した。HbA1c 濃度と認知機能の間には両群で強い逆相関がみられた。認知機能は群間で差はなく、体重減少とは関連していなかった。体重減少自体は認知症リスクとは関連しなさそうだが、低血糖を起こさずに糖尿病のコントロールは改善することは認知症リスクを減少させる方法であるかもしれない。
高血圧
以前、我々は中年期の高血圧があらゆる原因による認知症、アルツハイマー病、血管性認知症のリスクを増加させるが、認知症になる時期が近くなると血圧が低下する傾向があるというエビデンスについて述べた。縦断的研究のシステマティックレビューでは、血圧は認知症と診断される 5 年前から上昇し、その後低下し始め、体重は診断の 10 年前頃から減少すると推定されている。個人参加者データのメタアナリシスでは、高血圧は高齢になってもリスクであり続ける可能性があることが確認されているが、認知症を発症する人の中には認知症でない人より血圧が低い人もおり、そのためエビデンスはまちまちである。これらのメタアナリシスでは、血圧の変動はカバーされていないが、コホート研究(n = 2234;65 歳以上)では、3、6、9、12 年目に血圧の変動を測定し、収縮期の変動が 1 単位 (?) 増加するごとに認知症リスクが増加し、HR は 1.02(95%CI 1.01-1.04)から 1.10(1.05-1.16)の範囲であったと報告している。
アメリカ黒人の記録血圧は他のアメリカ人グループよりも高く、これがアメリカ白人に比べて認知症リスクが高い一因となっている可能性がある。このリスクは、平均年齢 59.8 歳(SD 10.4)の合計 19,378 人を対象とした 5 件のコホート研究の個人参加者データのメタアナリシスで検討され、その結果、黒人アメリカ人は白人アメリカ人よりも有意にグローバルな認知機能低下が早かったが、累積平均収縮期血圧で調整した後では有意差は認められなかった。
降圧薬に関する RCT のメタアナリシスは 3 件ある。2 件のメタアナリシスでは、降圧薬が認知障害および認知症に対する予防効果を有することが確認され、追跡期間が短い(すなわち、1〜5 年の範囲)1 件では、予防効果は確認されなかった。平均追跡期間 4.1 年(範囲 2.2-5.7 年)の 12 件の RCT(n = 96,158)のメタアナリシスでは、降圧薬を服用している人は、プラセボを服用している人、代替降圧薬を服用している人、または目標血圧が介入群より高い人(OR 0.93, 95%CI 0.88-0.98)、および認知機能障害のみ (高血圧はないが認知機能障害はある人ということか?) (0.93, 0.88-0.99)の対照群より認知症または認知機能障害のリスクが低いことが同定された。2 番目のメタアナリシスでは、プラセボ対照を含む 5 件の RCT(n = 28,008)の個人参加者データ(うち 3 件は最初のメタアナリシスに含まれる)が使用され、治療群ではプラセボ対照群よりも認知症リスクが低いことが同定された(0.87, 0.75-0.99)。前回のメタアナリシスと重複する 3 件の研究を含むコクランレビューでは、介入期間が少なくとも 12 ヵ月である 12 件の RCT(8 件のプラセボ対照試験;n = 30,412)を対象とした。このレビューでは、Mini Mental State Examination(MMSE;5 試験;平均差 0.20, 95%CI 0.10-0.29)で測定された認知機能の変化に対して降圧薬による緩やかなベネフィットがあったが、認知症発生率に差を示すには期間が短すぎたと結論している(4 試験;OR 0.89, 95%CI 0.72-1.09)。 低中所得国および高所得国の人々を含む 17 件の研究(平均年齢 72.5 歳[SD 7.5]、追跡期間 4.3年)の個人参加者データのメタアナリシスでは、未治療の高血圧患者は健常対照者よりも認知症リスクが高いことが同定された(HR 1.42, 95%CI 1.15-1.76)が、このリスクは治療により減弱または消失した(1.13, 0.99-1.28)。ベースライン時に認知症のない 31,090 人の成人からなり、少なくとも 5 年間追跡調査された個人参加者データコホートの 1 件のメタアナリシスでは、いずれかの降圧薬を服用している高血圧患者は、降圧薬を服用していない患者よりも認知症のリスクが低いことが明らかにされた(HR 0.88, 95%CI 0.79-0.98)が、薬剤クラス間の差は確認されなかった。さまざまな降圧薬の効果を直接比較したものは少ないが、ネットワーク解析と系統的レビューにより、アンジオテンシン 2 受容体拮抗薬とカルシウム拮抗薬(calcium channel blocker: CCB)による治療は、他の降圧薬よりも認知症リスクが低いことが確認されている。高血圧が予防的であることを示唆するメンデルランダム化研究は、RCT の所見と矛盾しており、メンデルランダム化研究の所見は生存バイアスの影響を受けている可能性が高い。
肥満と体重
中年期の肥満が認知症の危険因子であることは以前に述べた。肥満と認知症との関連を検討した系統的レビューとメタアナリシスでは、77,890 人の参加者を対象とした 14 件の研究が行われ、中年期の肥満がその後のあらゆる原因による認知症と関連することが明らかにされた(RR 1.31, 95%CI 1.02-1.68)。ウエスト周囲径またはウエスト-ヒップ比によって測定される中心性肥満に関する別の研究では、16 件の研究から 5,060,687 人が参加し、ウエスト周囲径が大きい場合と小さい場合では、認知障害および認知症のリスクが高いこと(HR 1.10, 95%CI 1.05-1.15)が示され、このリスクは他の年齢よりも 65 歳以上の高齢者で大きかった。肥満は運動頻度の低い人に多く、心血管疾患の原因でもある糖尿病や高血圧と関連している。とはいえ、これらのメタアナリシスのほとんどの研究は、高血圧、脳卒中、血中脂質濃度、糖尿病などの健康状態や人口統計学的特徴で調整されており、これらの仲介因子の影響は最小限に抑えられているはずである。
体重減少に関する介入研究のメタアナリシスでは、過体重(すなわち、BMI 25.0~29.9 kg/m2)または肥満(すなわち、BMI 30.0 kg/m2 以上)の参加者を対象とした 13 件の縦断研究(n = 551)および 7 件の RCT(n = 468)が同定された。試験参加者のうち、たとえ 2 kg と軽度であっても意図的に減量できた人は、追跡調査期間中央値 6 ヵ月(範囲 8~48 ヶ月)において認知機能の改善と関連していた (追跡期間が短すぎないか?)。このことは、たとえ減量が肥満状態を変えるのに十分でなくても、健康行動が有益な効果をもたらす可能性があることを示している。これらの改善は、減量手術を受けた人よりも、減量のために食事を変えたり運動したりした人の方が顕著であった。
さらに、BMI が高い人では、コルチゾール濃度の上昇、炎症、健康への悪影響と関連しており、ひいては認知症との関連に寄与している可能性がある。脂肪率が認知症リスクに寄与するメカニズムを理解するためには、さらなる研究が必要である。
データをプールした 19 件の前向き研究の系統的レビューでも、低体重者(すなわち、BMI<18.5;HR 1.26, 95%CI 1.20-1.31)における認知症リスクの増加が同定されている。 39 件の前向きコホート研究における 100~300 万人の個人参加者データのメタアナリシスでは、ベースライン測定が認知症発症の 15 年以上前に行われたコホートでは、肥満は認知症の危険因子であったが、ベースライン測定が認知症発症の 10 年未満に行われた場合には、予防的であった。著者らは、認知症を発症する前に体重が減少することが多いため、この結果は逆の因果関係によるものであると示唆した。低体重は栄養不良と関連している可能性もあるが、低体重は様々な理由で起こりうる。
過度のアルコール摂取
2020 年委員会では、中年期における週 21 英国単位(すなわち、12 米国単位、168 g、アルコール度数 5%の酒なら 480 mL/日×毎日)を超えるエタノールの飲酒は、軽い飲酒(すなわち、14 英国単位未満、アルコール度数 5%の酒なら 320 mL/日×毎日)と比較して、認知症リスクの増加と関連することを報告した(RR 1.18, 95%CI 1.06-1.31)。
英国では、アルコール 1 単位 = 8 g
米国では、アルコール 1 単位 = 14 g
同様に、フランス、英国、スウェーデン、フィンランドからの 131,415 人の参加者を対象とした個人参加者のメタアナリシスでは、交絡因子を調整した後、中年期の飲酒量が多い(すなわち、週 21 単位以上)ことは、軽い飲酒(すなわち、週 1-21 単位)と比較して認知症リスクの増加と関連していた (HR 1.22, 95%CI 1.01-1.48)。 同様に、28 件のシステマティックレビューのレビューでは、(個々の研究で定義された)多量のアルコール使用は、あらゆる原因による認知症のリスク増加および画像研究における灰白質容積の減少と関連すると結論づけている。アルコールによる意識消失は、中等度または大量飲酒者の認知症リスクを増加させた。
高齢者を対象としたいくつかの横断研究では、多量飲酒者と非飲酒者の認知症リスクは同程度であると報告されているが、非飲酒者としてカウントされている人の中には、以前は多量飲酒者であった人もいる。日本の前向き研究では、42,870 人の参加者を 14.9 年間追跡調査し、飲酒しない場合(HR 1.29, 95%CI 1.12-1.47)、および中年期から週 450 g 以上の飲酒をする場合(1.34, 1.12-1.60)は、軽度の飲酒(すなわち、週 75 g 未満)と比較して認知症リスクの増加と関連することを報告している。 15 件の前向きコホート研究にわたる 24,478 人の高齢者(平均年齢 71.8 歳[SD 7.5])の個人参加者データのメタ解析では、151,636 人年の追跡期間中、認知症リスクは、機会飲酒(0.78, 0.68-0.89)、軽度-中等度(1.3-24.9 g/日; 0.78, 0.70-0.87)、中等度から多量飲酒者(25.0-44.9 g/日、0.62, 0.51-0.77)では非飲酒者より低かったが、多量飲酒者(>45 g/日, 9%酎ハイで 500 mL/日)では非飲酒者(0.81, 0.61-1.08)より低くなかった。
また、メンデルランダム法では、飲酒とアルツハイマー病の発症年齢の早期化との間に因果関係があることが示され、飲酒しないこととアルツハイマー病との間の関連は生存者バイアスによるものであることが示唆された。この結果はおそらく、非飲酒者の多くが過去に多量のアルコール摂取や飲酒を妨げる他の病気にかかっていたためであり、過去に多量のアルコール摂取があったことを補正した研究では、非飲酒群に死亡率の過剰がないことが報告されている。
韓国の全国コホート 3,933,382 人を対象とし、3 年間のアルコール摂取量を連続的に評価した研究では、持続的な多量飲酒者(すなわち、30 g/日以上または 3 単位/日、アルコール度数 5%の酒で
600 mL/日以上)は、あらゆる原因による認知症のリスクが増加し(HR 1.08, 95%CI 1.03-1.12)、多量飲酒から中等度レベル(すなわち、15.0-29.9 g/日)に飲酒量を減らすと、持続的な多量飲酒と比較して、あらゆる原因による認知症のリスクが減少した(0.92, 0.86-0.99)ことが報告されている。持続的な軽度(すなわち、15 g/日未満;0.79, 0.77-0.81、アルコール度数 5%の酒では 300 mL 未満)または中等度のアルコール摂取(0.83, 0.79-0.88)または軽度のアルコール摂取の開始(0.93, 0.90-0.96)も、持続的な非飲酒よりもあらゆる原因による認知症リスクの低下と関連していた。全体として、過度の飲酒を減らすこと、または軽い飲酒を継続することは、過度の飲酒と比べて認知症リスクを下げることに関連する。飲酒しないことが認知症リスクを高めるという明確な証拠はない。非飲酒者の過剰リスクに関する観察的証拠は、以前に大量に飲酒し、データ収集時に禁酒し(非飲酒者に分類され)、その後飲酒に戻った人によるものかもしれない。
社会的孤立
以前、我々は認知症の危険因子として、社会的孤立(social isolation) や頻繁でない社会的接触を取り上げた。その後、2 件のシステマティックレビューが、社会的接触の頻度が低いほど認知症リスクが高いことを報告している。最初のレビューでは、8 件の研究、合計 15,762 人が参加し、社会的接触が頻繁でない人の方が頻繁な人よりも認知症リスクが高い(RR 1.57, 95%CI 1.32-1.85)と報告している。2 件目のレビュー(前回のレビューに含まれた1つの研究を含む)では、リスクの増加はより小さかった(1.18, 1.08-1.30)と報告されている。しかし、UK バイオバンクの参加者を対象とした、平均追跡期間 8.8 年と 12 年(SD 1.7)のその後の 2 件の研究では、ベースライン時に社会的に孤立している人(すなわち、一人暮らし、家族または友人と会う頻度が月に 1 回以下、週 1 回のグループ活動に参加していない)は社会的に孤立していない人 (すなわち、上記の基準を満たさない人) と比較して認知症リスクが高いことが明らかになった。
孤独 (loneliness) は、社会的接触が不十分であるという人々の感情に関するものであるため、社会的孤立と関連はあるが、それとは異なる。3~8 件の研究からなる 3 件のレビューにおいても、孤独は認知症リスクの増加と関連していた(RR 1.26 [1.14-1.40], 1.38 [0.98-1.94], 1.58 [1.19-2.09])。 これらの研究のすべてではないがいくつかでは、社会的接触の頻度が低いなどの潜在的な交絡因子を調整した後でも関連が持続することがわかった(図 7)。
図 7. 社会的接触の頻度と認知症発症頻度との関連
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/fulltext?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet#fig7
社会活動への参加 (participation of social activities) も関連しているが、社会的孤立とは区別され、認知症リスクの低下と関連している。連続的な社会活動測定を行った 2 つの研究では、社会活動への参加が減少することは、短期的には認知症リスクが高くなることと関連するが、長期的な追跡調査では関連しないことが報告されている。この所見から、社会活動への参加との関連は、認知症の前臨床期に参加率が低下するという、少なくとも部分的には逆の因果関係によるものである可能性が示唆される。
どのような形であれ、社会的接触は、認知予備能を構築し、健康的な行動を促進し、ストレスや炎症を軽減することによって、認知症リスクに有益な効果をもたらす可能性がある。リスクは、アルツハイマー病の異なる多遺伝子リスクスコアを持つ個人間で一貫していることが報告されており、社会的孤立は、社会的に孤立していない人に比べて、側頭部、前頭部、およびその他の脳領域の灰白質体積の減少と関連していた。
ファシリテーター主導のグループ活動を通して社会的接触や活動への参加を増やす介入は、一般的な認知機能に関して一貫した結果を得ていない。認知を主要アウトカムとする 3 ヵ月の介入に関するフィンランドの 1 件の RCT は、孤独な 75 歳以上の 235 人を採用し、アルツハイマー病評価尺度-認知サブスケールの成績のわずかな有意な改善を示した(100 点あたりの変化の平均差は -2~6 点)が、米国と中国の研究では、ファシリテーター主導のグループ活動が有益であることは示されなかった。グループ活動を含む多領域介入に関する研究では、中集中的な介入による認知機能への影響は小さいことが示唆された(Cohen's d 0-13;平均 MMSE 変化量 0.99 点)。その後行われた多領域介入に関する試験的 RCT では、グループミーティングを通した社会活動や、月 1 回の追加的な社会活動の予定が含まれており、少数ではあったが、24 週時点で全般的な認知機能の改善がみられた(Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status スコアにおける群間差は 6.2 点;p = 0.004)。既存の研究は小規模であり、追跡期間が短すぎるため、多領域介入における社会的要素が認知症発症に何らかの影響を及ぼすかどうかを明らかにすることはできない。
大気汚染
家庭内外の環境における微粒子への暴露は、現在、強い関心を集めている。曝露は生涯にわたるものであり、ライフコース全体にわたる多くの長期的疾患の潜在的な要因である。2020 年のランセット委員会において、我々は、曝露期間、解析における共変量、転帰、バイアスのリスクにおいて研究間でかなりの異質性があるにもかかわらず、粒子状物質による大気汚染、PM2.5(直径 2~5 μm 以下の微粒子)、PM10(直径 10 μm 以下の粒子)が認知症や認知機能障害の危険因子であるという同意が得られたことを報告した。2019 年以降、少なくとも 9 件のシステマティックレビューとメタアナリシスが発表され、いずれも大気汚染が認知症リスクの上昇と関連していると報告している。研究の異質性を管理するために、いくつかのメタアナリシスでは組み入れ基準を狭めている(例えば、あるレビューでは、91,391,296 人を含む 20 件の研究からなるハザード比を提供する研究のみを分析し、PM2.5 の 1 μg/m3 増加あたり 1.03(95%CI 1.02-1.05)の ハザード比を報告している。 積極的な症例確認を行った質の高い研究を用いた 5 件の研究のメタアナリシスから得られた保守的なプール推定では、PM2.5 の 2 μg/m3 増加あたり 1.17(0.96-1.43)のハザード比が報告されているが信頼区間は広く、ヌル値も含まれている。二酸化窒素(10 μg/m3 当たり 1.02 [0.98-1.06])と窒素酸化物(10 μg/m3 当たり 1.05 [0.98-1.13])についてはそれぞれ 5 件の研究から、オゾン(5 μg/m3 当たり 1.00 [0.98-1.05])については 4 件の研究から、プールハザード比が報告されたが、いずれも有意ではなかった。その他の汚染物質については、評価した研究が少なすぎて、メタ解析には至っていない。
高所得国と低中所得国の両方において、大気汚染はしばしば高度で悪化しており、PM2.5 と PM10 の濃度は認知症、MCI、アルツハイマー病と関連している。環境(つまり屋外)と家庭(つまり屋内)の大気汚染には、別個のあるいは相乗的なリスクがあるかもしれない。低中所得国での研究によると、清潔な燃料と比較すると、家庭大気汚染の原因となる代用固形燃料の使用は、中高年(つまり 45~50 歳以上)の認知症リスクの上昇や認知機能低下の加速と関連することが示されている。家庭用の薪ストーブや石炭ストーブは室内空気汚染の原因であり、英国の PM2.5 排出量の 38%を占め、関連する健康リスクもあると報告されている。
1,800 万人以上の参加者を対象とした米国の 7 年間のコホート研究では、認知症リスクと最も強い関連を示した PM2.5 成分はブラックカーボンであったと報告している(1 μg/m3 増加につき HR 1.12 [95% CI 1.11-1.14] )。
スウェーデンの住民 2927 人(ベースライン時に認知症でなかった女性 1845 人[63%]と男性 1082 人[37%];ベースライン時の平均年齢 74 歳[SD 10.7])を対象とした平均追跡期間 6 年の縦断的研究では、1990 年から毎年 PM2.5 と窒素酸化物への曝露量を調べ、心血管疾患(すなわち、心房細動、虚血性心疾患、心不全、脳卒中)が公害と認知症の関連を修飾するか媒介するかを検討し、そうであったと報告している。大気汚染の影響は、これらの既往症のある人では最悪である。
大気環境の改善が認知機能の低下や認知症の発生率に及ぼす潜在的な影響については、新たなエビデンスが得られている。12 年間の追跡調査を行ったフランスのコホート研究では、1990 年から 2000 年の間に PM2.5 の中央値が 12.2 μg/m3 減少したことが、認知症リスクの低下と関連したことが報告されている(HR 0.85, 95%CI 0.76-0.95)。より大きな大気環境の改善(10 年間にわたる PM2.5 と NO2 の減少)は、米国の高齢女性における認知症リスクの低下と関連した。準実験的研究では、中国の大気汚染防止管理行動計画が高齢者の認知機能低下を緩和したことから、厳格な大気清浄化政策が大気汚染に関連する認知機能老化(MMSE で測定)のリスクを低減する可能性が示された。中国の北部と南部におけるセントラルヒーティングに対する政策の違いが大気汚染濃度の違いにつながり、北部のサンプルにおけるより高い大気汚染(すなわち、PM10, NO2, SO2, CO, O3)は、南部のサンプルよりも 42.4%高い認知症リスクと関連していた。
エビデンスが増えるにつれて、研究デザイン、報告、分析を標準化し、比較を可能にし、大気汚染と認知症との関連をより詳細に理解することは価値があるだろう。社会経済的状況、家庭環境、大気汚染への曝露が密接に関連していることを考えると、これらの研究で残存交絡を最小化することは困難である。
全体として、最終的に年間平均 PM2.5 濃度を 5 μg/m3 未満とする WHO 世界大気質ガイドラインの実施を支持する声が高まっている。PM2.5 濃度が 1 μg/m3 上昇するごとに認知症リスクが上昇することから、安全な大気汚染濃度が存在するかどうかは不明である。認知症のサブタイプに関連したリスクや、個々の粒子状物質成分(例えば、黒色炭素、硫酸塩、硝酸塩、アンモニウム)が重要かどうかについてはほとんど分かっていない。
元論文
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/abstract?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet