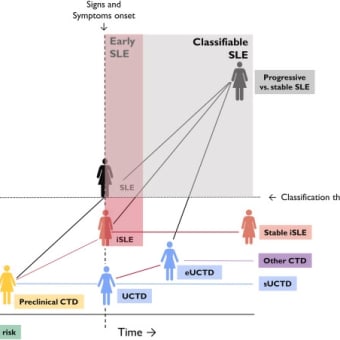化膿性脊椎炎についての総説
Int Orthop 2012; 36: 397-404
化膿性脊椎炎 (pyogenic spondylitis) は神経障害と死亡のリスクがある病態である。化膿性脊椎炎は化膿性脊椎椎間板炎 (pyogenic spondylodiscitis) 、敗血症性椎間板炎 (septic discitis)、脊椎骨髄炎 (vertebral osteomyelitis, 一般的な訳語は化膿性脊椎炎) 、硬膜外膿瘍 (epidural abscess) など広い病態を包含している。罹患率は低いが、増加傾向にある。
診断は、臨床所見、画像所見、血液·組織培養、病理組織学的所見に基づく。
ほとんどの場合は内科的に治療される。外科的治療は 10-20%の症例で必要になる。頚椎前方除圧固定術 (anterior decompression, debridement and fusion) は一般に推奨される術式で、デブリドマンを行い手術後に抗菌薬治療を行えば人工物挿入も許容し得る。
1. 疫学
化膿性脊椎炎は数千年にわたって人類を苦しめてきた疾患であり、紀元前 7000年前のエジプトのミイラからも化膿性脊椎炎の痕跡が見つかっている。
筋骨格系の感染のうち、化膿性脊椎炎は 2-7%を占める。罹患率は 0.2-2/10万·年であり、増加傾向にある。これはおそらく慢性疾患を持つ患者の生命予後の改善と関係している。
感染部位は 95%は椎体または椎間板で、5%が椎弓である。ほとんどは50歳台以上で発症し、年齢とともに発症率が増加する。理由は分からないが、男性は女性の2倍罹患しやすい。
危険因子としては糖尿病、低栄養、薬物乱用、HIV 感染、悪性腫瘍、長期のステロイド使用、慢性腎不全、肝硬変、敗血症がある。蛋白欠乏は T 細胞数を減少させ、サイトカインの産生を低下させる。HIV/AIDS は好中球の機能を低下させ、リンパ球の細胞数と機能を低下させる。ステロイドは液性免疫と細胞性免疫の両方を抑制する。これらは全て脊椎への感染を起こしやすくする。
2. 病態生理
化膿性脊椎炎は通常、血行感染で発症する。動脈からの感染の方が静脈からの感染よりも多く、皮膚、気管、尿生殖器管、消化器、口腔が侵入門戸となる。血流は遅いが豊富な骨髄は細菌が定着しやすいため感染を来しやすい。
隣接する椎体に感染が及びやすいのは脊椎の血流支配で説明できる。椎間板を栄養する動脈は上下の椎体にも血流を送っている。そのため、化膿性椎間板炎では、ふつう隣接する椎体とその間にある椎間板が感染している。
化膿性椎間板炎の病態生理は成人と小児でいくらか異なる。小児では、椎間板内に血流があり、菌血症後に椎間板炎を発症する。成人では、椎間板には血流がなく、細菌は椎間板に隣接する軟骨下の終動脈アーケードから椎間板終板を直接通過して、椎間板内に侵入する。
静脈を介した椎間板への細菌の接種も時に起こり得る。特に骨盤内臓器に由来する敗血症では、腰椎への感染に Bateson の静脈叢は感染経路になり得る。頚椎では、咽頭静脈叢 (あまり一般的な術語ではなさそう)が頭頚部からの感染経路になり得る。
細菌は直接椎体に感染することもあり得る。直接椎体に感染するのは、隣接臓器の感染から直接感染する場合と、医原性に接種される場合とがある。前者の場合は咽頭に隣接する頚椎で起こりやすい。鼻咽頭の悪性腫瘍に対して放射線治療を行うと咽頭後壁が薄くなり、感染に対して脆弱になる。こうなると咽頭内の細菌叢が頚椎に直接感染し得る。
医原性の細菌接種は椎間板造影 (lumbar discography) などの診断目的あるいは治療目的の操作で起こり、脊椎の感染の原因の 14-26%を占める。
結核は脊椎の感染症の原因微生物として最多だった。著者らの施設では 1955-1960年に 2000件の脊椎の感染症があり、うち 59%が結核によるものだった。しかし、最近数十年で脊椎の感染症の原因微生物は変わった。同じ施設で 2004-2008年に行った研究では、脊椎の感染症の原因として結核は 24.2%となり、代わって細菌感染が増えた。
化膿性椎体炎の起炎菌で多いのはブドウ球菌とレンサ球菌であり、全体の 50%以上を占める。尿路感染症に続発する場合は、大腸菌やプロテウスも起炎菌となり得る。薬物乱用者の場合は、しばしばグラム陰性桿菌が分離される。コアグラーゼ陰性ブドウ球菌や緑色レンサ球菌 (Stretococcus viridans) などの弱毒性の菌も免疫不全患者では起炎菌となり得る。外傷患者では嫌気性菌が直接椎体に接種され得るし、糖尿病患者では一般的な起炎菌である。鎌状赤血球貧血 (sickle cell anemia) の小児ではサルモネラ骨髄炎も来し得る。しかし、全体の 1/3 は起炎菌不明である。
どの椎体が感染するかはまちまちで、全ての椎体で感染の報告がある。最も感染が多いのは腰椎で 45-50%、次いで胸椎で 30%、頚椎は 3-20%、残りは仙骨である。
化膿性脊椎炎は治療されないと膿瘍化し、周辺の構造に波及する。脊柱管内に波及すると硬膜外膿瘍を形成し得る。また、椎間板や椎体が破壊され、脊椎が不安定となり得る。その結果、椎体圧潰による脊椎後彎 (kyphosis) や神経圧迫が起こり得る。骨あるいは硬膜外膿瘍による圧排で麻痺が生じ得る。また、敗血症による血栓症や炎症の波及による虚血で脊髄が傷害されることもあり得る。
3. 臨床所見
化膿性脊椎炎の診断は臨床所見、画像所見、培養検査所見に基づく。診断が遅れることは稀ではなく、診断までの期間は 2-12週と幅があり、時に 3ヶ月かることもある。診断が遅れることで骨が破壊され、脊椎後彎、脊髄損傷を来すこともあり得る。
症状は最初ははっきりしないことが多く、90%以上の場合は頚部痛や背部痛という非常によくある訴えのみである。熱はないことが多く、発熱を認めるのは 20%に過ぎない。他の症状としては嘔気、嘔吐、食思不振、体重減少、倦怠感、混乱がある。咽後膿瘍をともなう頚椎の化膿性脊椎炎の場合は嚥下困難を訴える場合がある。四肢脱力、しびれ、括約筋障害 (sphincter dysfunction) は脊髄または馬尾 (cauda equina) の圧排によって起こり得る。虚血や脊髄への直接感染による神経障害も頻度は少ないが起こり得る。Butler らは感染性脊椎炎の患者の 29%のみが神経障害を呈し、そのうち 79%は軽い四肢の脱力だった。
5. 画像検査
脊椎の感染症を疑っている全ての患者に対して非造影の画像検査を行うべきである。これにより、骨破壊の程度や、病態に関連する冠状断、矢状断の脊椎アライメント不整を評価することができる。
初期には画像所見は目立たず、画像変化は緩徐に進行し得る。最初期から認める所見は終板の不鮮明化と椎間の狭小化であり、感染から 2-8週で認めるようになる。多くの患者ではもともと脊椎の変形があるため、感染初期には感染による脊椎の構造変化ははっきりしないことが多い。したがって、画像所見が明らかでなくても臨床所見から化膿性脊椎炎を疑い続けることが重要である。
感染から 8-12週が経過すると骨破壊は明らかになる。椎体侵食像 (scalloping, リンク参照) や椎体陥没 (collapse of vertebral body) が起こり、しばしば局所性の後彎となる (リンク参照)。軟部組織に異常陰影を認める場合は傍脊椎膿瘍による軟部組織の伸展を疑うべきだが、結核性脊椎炎に比べると頻度は少ない。
病初期には核医学検査は放射線による画像検査よりも感度が高い。3相骨シンチグラフィ (three-phase 99m technetium bone scan) は感度は高い (感度 90%) が、特異度は高くない (特異度 78%)。特に、もともと脊椎症や椎間板変性がある高齢者では特異性は低くなる。骨シンチグラフィでは病変の細かい構造はほとんど分からないし、脆弱性骨折や悪性腫瘍でも陽性となる。また脊椎炎が治癒し、血液所見が正常化した後も陽性となり得る。ガリウム骨シンチグラフィ (Gallium-67 citrate scan) の感度 (89%)、特異度 (85%)、正確度 (accuracy, 86%) はテクネシウム骨シンチグラフィと同程度である。インジウム-111標識白血球シンチグラフィ (Indium 111-labeled leukocyte scintigraphy) は特異度は高いが、感度 (17%) はとても低い。これは検査を行う時点では感染は急性期から慢性期に移行しており、局所の白血球が少なくなるからである。偽陰性が多いので、インジウム-111標識白血球シンチグラフィは脊椎感染症の診断には通常用いられない。
磁気共鳴画像診断 (magnetic resonance imaging: MRI) は脊椎感染症診断のゴールドスタンダードである。MRI は特に他の画像検査では所見を認めない病初期で有用である。MRI の感度、特異度、正確度はそれぞれ、96%、92%、94%だと報告されている。化膿性脊椎炎の典型的な MRI 所見は骨髄浮腫を反映して造影効果をともなう T2 強調像高信号、T1 強調像低信号である (リンク参照)。ほとんどの場合は感染は椎間板に近い椎体の前側方から始まる。感染にともなう浮腫は多くの椎体および椎間板に及ぶ。脊椎の新生物も T2強調像高信号、T1 強調像低信号となるが、椎間板に病変があることが感染と新生物とを鑑別するポイントになる。
MRI では病原微生物の診断はできないが、ある種の感染を示唆する所見はある。たとえば、結核性椎体炎では髄膜に感染が及び、造影 MRI では靭帯下に感染が広がり、傍脊椎および骨内に膿瘍を認める。
MRI は反応性変化による信号を感染によるものと誤認することにより、感染の範囲を過大に評価する傾向がある。したがってデブリドマンするべき壊死組織の範囲を評価するには X線写真や CT の方が有用である。
手術後の患者では、創部の T2 高信号と増影効果を認めるので、MRI での評価は難しくなる。椎間板切除術のみの場合は、残存する椎間板や椎体の信号変化はわずかで、造影効果も認めない。初期の椎間板炎では、手術後の通常の変化と所見が重なるが、隣接する椎体の T1 低信号と造影効果を認める場合はより感染らしい。
MRI は脊柱管の内容物 (特に硬膜外と脊髄) の評価ができる唯一で最良の非侵襲的検査である。硬膜外膿瘍は特に神経障害をともなっている場合は外科的緊急である。膿の貯留があれば、T1 強調像低信号、T2 強調像高信号となる。造影すると、T1 強調像で周縁が造影される腫瘤として描出される。腫瘤全体が造影される場合は肉芽組織 (granulation tissue) である可能性の方が高いが確実ではない。臨床的に疑われる場合は膿瘍として扱うべきである。
化膿性脊椎炎診断後に、治療効果の判定のために MRI で経過を追うことについては意見が一致していない。MRI を早期に再検した場合、臨床的には改善しているにも関わらず、画像所見では病変が拡がり、骨破壊が進行しており悪化していると判定されることがあり得る。
MRI は一般に修復変化の始まりに対しては感度が低い。MRI で最初期に認める回復の兆候は軟部組織の炎症の低下と造影効果の低下である。通常、このような兆候を認めるのは適切な治療を開始してから数週間から数ヵ月経過してからである。
造影効果が消退し、信号が正常化することは完全な治癒を示す確かな所見である。ただし、治療開始から1年後も造影効果がある程度残ることもある。持続的な造影効果は椎体よりも椎間板で認めることが多い。骨髄の信号変化は治療が奏功すれば正常化し得る。しかし、線維化と硬化 (fibrosis and sclerosis) を繰り返すと、T1 低信号、T2 高信号が残存する可能性はある。
18-F フルオロデオキシグルコース (18-F fluorodeoxyglucose: 18-F FDG) は感染、炎症、自己免疫、肉芽腫性疾患の局所に集積することが知られている。筋骨格系の感染症の診断に 18-F FDG 陽電子放出断層撮影 (positron emission tomography: PET) を利用した報告がされている。慢性の筋骨格系の感染症 (中心骨、末梢骨) が疑われる 60症例を対象に FDG-PET の診断能を検討したところ、単独の検査としては正確度が高かった。
FDG-PET は脊椎椎間板炎の画像診断の補助として有用であることも示されている。Schmitz らは組織学的に確認された脊椎感染症患者の全てで FDG-PET が陽性だったと報告している。Stumpe らは MRI で検出された腰椎の変性疾患と終板の感染症との鑑別に PET が有用であることを報告した。変性疾患では椎間領域への 18-FDG の集積は認めなかった。一方、5つの椎間領域の全てにおいて、FDG-PET 陽性だった症例はすべて真の終板感染症だった。椎間領域の感染症診断に対する感度、特異度は MRI でそれぞれ 50%、96% だったのに対し、FDG-PET ではそれぞれ 100%、100%だった。
6. 生検
化膿性脊椎炎は経過と血液培養陽性、化膿性脊椎炎として矛盾しない検査および画像所見に基づいて臨床的に診断できる。化膿性脊椎炎の診断確定は感染組織の顕微鏡的、細菌学的所見、培養検査によってのみなされる。
血液培養が陽性でない場合、推奨されている治療アルゴリズムでは、患者の状態が安定していれば、蛍光または CT ガイド下経皮的生検を行うまで抗菌薬投与は差し控えることとされている。内視鏡的生検は感染組織の観察と除去を同時に行うことができる。生検で得られた検体はグラム染色、好気性および嫌気性培養、抗酸菌培養および PCR、真菌培養、組織病理検査を行うべきである。経皮的椎体生検の化膿性脊椎炎診断に対する確度 (accuracy) は 70%だと報告されている。コア生検 (core biopsy, 太い針を用いて行う生検) の方が穿刺吸引細胞診 (fine needle aspiration, 細い針を用いて行う生検) よりも好まれる。
椎体生検が (偽) 陰性となってしまう原因としては、検体量が不十分であることか、抗菌薬が投与されていることが挙げられる。椎体生検が陰性の場合は、抗菌薬投与中止が可能であれば、生検再検を検討しても良い。蛍光または CT ガイド下生検で起炎菌が特定できない場合は開創生検を行うべきである。
7. 非外科的治療
化膿性脊椎炎患者の大部分は非外科的に治療できる。各種培養を提出し、組織生検を行ったら抗菌薬治療を開始するべきである。
著者らの施設では、主な起炎菌であるブドウ球菌、レンサ球菌をカバーするためにペニシリンまたは第一世代セファロスポリンによる経験的治療を行っている。また、免疫不全患者や薬物依存患者では、グラム陰性桿菌もカバーする第三世代セファロスポリンなど広域抗菌薬を追加している。
クリンダマイシン、バンコマイシン、キノロン、テトラサイクリン、ST 合剤 (cotrimoxazole) は骨への移行性が良く、特に β ラクタムに感受性の (抵抗性の誤りか?) 起炎菌による脊椎炎に対しては投与を検討するべきである。リファンピシリンは骨への移行性が良いだけではなく、バイオフィルム中の細菌に対しても抗菌活性があり、β ラクタム系抗菌薬と相乗効果を発揮する。そのためインプラントがあるグラム陽性球菌による化膿性脊椎炎の患者では特に有用である。
抗菌薬の選択は培養結果に基づいて、最適化していく。感染症化科へのコンサルトは、抗菌薬選択を最適化し、感染源を特定するために重要である。
最適な抗菌薬投与期間は定まっておらず、いくつかの研究では 6-8週間経静脈的に抗菌薬を投与することを推奨しており、他の研究では 4週間で良いとしている。抗菌薬投与期間が 4週間に満たない場合は、再発率が受け入れがたいほど高くなる。著者らの施設では、CRP が正常化するまで経静脈的に抗菌薬を投与し (通常 2-4週かかる)、その後経口薬に変更しトータルで 3ヶ月間抗菌薬投与を行っている。
急性期は疼痛が改善するまでは床上安静が推奨されている。疼痛が落ち着いたら、適切なギプス (cast) や支持具 (brace) を用いて歩行を始める。外固定 (external immobilization) は脊椎の安定性を支持し、疼痛の軽減と脊椎の変形予防に役立つ。外固定の期間は脊椎の破壊と変形の程度によって異なり、3-4ヶ月である。変形の進行は最初の 6-8週間に 30%の患者で起こる。
非外科的治療の効果は臨床症状 (発熱、疼痛) 、血液検査所見、画像所見で評価できる。化膿性脊椎炎が寛解すると、血液検査では CRP および赤血球沈降速度は低下し、画像検査では皮質骨の破壊が止まり、骨癒合が始まる。抗菌薬の静脈注射を行っていても炎症反応高値が続く場合は、画像検査を再検して膿瘍の有無を確認し、経静脈的抗菌薬投与を延長するのが良いかもしれない。
非外科的治療は 75%の患者で奏功する。発症から 6-24ヶ月の時点でほとんどの患者は椎間固定 (interbody fusion) を行わずに治療できる。しかし、14%で再発し、症状増悪、神経症状出現、感染拡大、脊椎変形が出現しうる。
8. 外科的治療
化膿性脊椎炎で開創手術が必要になるのは 10-20%に過ぎない。脊髄または馬尾の圧迫による進行性の神経症状が出現した場合は手術の絶対適応である。このような場合は手術を行った方が保存的治療と比べて神経学的予後が良いので、緊急で除圧術を行うことを検討するべきである。
手術の相対的適応は、1. 診断が確定しないので開創して組織を採取する場合、2. 2-3週抗菌薬治療を行っても臨床症状が改善しない場合、3. 脊椎の変形が進行し、生体力学的に不安定となっている場合である。
通常、脊椎の感染症では椎体に感染が及ぶので、前方からのアプローチが推奨される。それにより、感染部位を徹底的に除去し、グラフトまたはケージを挿入して椎体を再建することができる。頭頚接合部に到達するためには経口ないし経後咽頭でアプローチする必要があるかもしれない。中下位頚椎 (subaxial cervical supine) では Smith-Robinson 法(リンク参照) は術野展開に優れる。胸椎の病変については開胸術 (thoracotomy) 行うことで前方からアプローチできる。腰椎の場合は腹腔を経る前方からのアプローチよりも後方からのアプローチの方が好まれる。これは前方からアプローチすると細菌を腹腔内に播種する恐れがあるからである。胸腰椎において椎体前方の病変 (感染を含む) に対して後側方からアプローチ (postero-lateral extra-cavity approach) することが一般に行われるようになりつつある。これにより胸腔や腹腔を経由する必要がなくなるが、硬膜が広範囲に癒着している場合には技術的に難しいことがある。
稀に、骨破壊をともなわない硬膜外膿瘍がある。硬膜外膿瘍は後方アプローチによるドレナージと椎弓切除 (laminectomy) で治療できる。
伝統的に、化膿性脊椎炎に対しては前方除圧固定術が行われてきた。感染巣は徹底的にデブリドマンされ、膿瘍はドレナージされる。デブリドマンは組織修復が行われるように、正常な骨組織からの出血を認めるまで続けるべきである。デブリドマンの目的は、1. 感染組織を除去して自然な治癒過程を促進すること、2. 軟骨下骨からの血流を再開させ、抗菌薬が到達しやすくする、3. 再生肉芽組織の侵入を促進することである。
デブリドマンを行った後は同時または二期的に骨またはケージの移植が行われることがある。自家移植 (autograft)、同種移植 (allograft) 、チタンケージによる前方支柱骨移植 (anterior strut grafting) は膿の大部分を除去した後であれば安全かつ高い成功率で行うことができる。
頸椎の化膿性脊椎炎で膿が多い場合、外科医の中には椎体のデブリドマンのみを行い、ハローベスト (Halo device) で固定しながら 7-14日間の抗菌薬投与を行った後に前固定術を行うことを勧めているものもいる。
前固定は、非外科的治療と比較して、椎体の圧潰を防いで骨の再生を促進し、患者のリハビリテーションを早め、感染の再活性化の頻度を減らす。
Smith-Robinson 法
https://musculoskeletalkey.com/anterior-cervical-approaches/
ハローベスト
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.info.pmda.go.jp%2Fygo%2Fpack%2F100254%2F16200BZZ00140000_A_01_03%2Ffigures%2F100254_16200BZZ00140000_A_01_03_fig02.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.info.pmda.go.jp%2Fygo%2Fpack%2F100254%2F16200BZZ00140000_A_01_03%2F&tbnid=4GuQGA2BI1dfpM&vet=1&docid=VhTyt4d7oKSCfM&w=282&h=369&hl=ja-JP&source=sh%2Fx%2Fim
椎体侵食像
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.15106/J00764.2006302228
第6/7胸椎の化膿性脊椎炎による終板および椎間板の破壊とそれによる後彎
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3282872/figure/Fig2/?report=objectonly
第4/5腰椎の化膿性脊椎炎と硬膜外膿瘍の MRI 所見
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3282872/figure/Fig3/?report=objectonly
元論文
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3282872/