
かなり前のことだが、時々お世話になってる掲示板で「原作有りの映画の場合、原作は読むかどうか」という話題になったことがある。最近は国内外問わずオリジナル脚本より原作付が多くなってきているが、私は基本的に「原作(小説/漫画)と映画は別モノ」というスタンスでありたい、と思っている。更に言えば、原作があったとしても、出来れば知らないでいたい。元ネタを知っていると、別モノと思ってはいても、先入観が邪魔することもあるからだ。特に、その原作になまじ思い入れが強かったりするとタチが悪い。観ている最中、映像との「違い」ばかりが気になり、肝心の映画そのものを楽しめてなかったりすることもあるからだ。
個人的に一番望ましいと思う映画化は「原作の生かし方」が「物語」ではなく「スピリット」であること、或いは原作をベースにしつつ、その映画監督の独自の色をつけ再構築してくれていることだろう(勿論そこには、原作に対する愛なりリスペクトなりが不可欠だ)。そうすれば、観ている方も早々に原作という呪縛から離れて映画そのものに没頭することが出来る。それに下手に原作に拘泥すると、映画ならではの面白さが失せ、中途半端でつまらないものになることがあるしね。
そこで『隣人13号』である。井上三太の代表作といってよいこの作品を読んだときは、かなり強烈なインパクトを喰らった。私は80年代前半以降、熱心な漫画読みではなくなったが、90年代に入ってから読んだ漫画の中では明らかに特別な作品の一つに入る。当時、この作品の後に『殺し屋1』を読んで、似たようなテーマが似たような歳の原作者によって、それぞれのベクトルに向かって進んでいき、それぞれが彼らの傑作となったのが興味深かったことを思い出す。
こと『隣人13号』は、いじめられっ子が二重人格者の怪物となって恐怖の復讐を執行する、という内容もさることながら、その殺戮シーンの、思わず笑ってしまうようなあっけらかんとした残虐さがスゴかった。主人公の村崎十三の別人格である13号は、本当に子供の遊びのように殺人を楽しむ。十三の身体年齢は就職するほどの年齢になっているが、13号は十三が酷いいじめによって深手を受けた小学生で時が止まっているからだ。子供は怖い。純粋と言えば聞こえはいいが、ようするにモノを知らないのだ。限度も知らない。十三を虐め抜いた赤井トールも、どこまでヤるとまずいのか、などと考えたりしなかった。
映画はその原作に対して、正面からのガチ勝負で挑んでいる。オリジナルの「物語」を損なうことなく(登場人物を刈り込んで必要最低限にしているが)、その「スピリット」は当然焼き付けて、尚且つ監督自身の個性をミックスさせて作りあげる。
ここまでやってくれれば、原作がどうこう、なんてのはどうでもよい。これまでCM・PVディレクターとして活動してきた井上靖雄監督、これが長編デビュー1作目とは思えない堂々たる仕事ぶりである。CM・PV出身の監督というと、やもすると独り善がりな映像遊びばかりが悪目立ちして作品として体をなしてない場合もあったりして、映画化決定のニュースを聞いた当初は正直若干の不安もあった。しかし、その後「井上三太自らOK」というニュースを聞いて、それなら期待できるかも、と思い直したのだ。
さすが三太のお墨付き。靖雄監督は、冒頭からえらいテンションで、まずは自分の世界に惹き込む。やがて原作の出来事が、実写としてスクリーンに出現してくる。そのヘヴィかつクール、そして真摯なアプローチが素晴らしい!(ちゃんと乾いた笑いで遊ぶことも忘れてないし)
真摯だからこそ、漫画の中ではオフビートなブラックさを感じさせた部分も、洒落にならない重さで観ている者を圧迫する。その緊張感は、遊園地のビデオテープ再生でマックスになり、そこからクライマックスの教室まで一気になだれこむのである。
そして映画オリジナルのラストシーン。もう一つの、十三の物語・・・私は不覚にもここで少し泣けてしまった。いや、不覚ではない。原作のラストの拡大解釈としても、見事じゃないか。本作がR15指定なんてけしからんよ。むしろ教育的価値の高い内容なのだから、子供こそ観るべし!>断言するのはマズイのか?
勿論キャスティングについても申し分なかった。村崎十三と13号は別人としいうことで、役者も2人に分けたのも効果的だった。十三@小栗旬は、茫洋と鬱屈している雰囲気を見事に現している。彼は気にかけている若手俳優の1人なのだが、使われ方によって良い悪いがハッキリ出てしまう人でもある(あずみ2はちょっとダメな方向だったかも・・・監督が若い男子はどーでもいいからか^^;;)。だから、この役はどうかな~と観るまでは不安もあったが、結果はオッケー! ほぼ無感情な台詞の言い方も的確だった。13号@中村獅堂はクライマックスのノリノリな演技に至るまでの、抑制を効かせた部分が更に13号の天然キ○ガイぶりを際立たせてうまかった。この人はたまにやりすぎなところがあって、私には好きなときとウザイと思うときと分かれるタイプの俳優なのだが、今回はメリハリつけてて良かった。
しかしなんといっても、ベストは元イジメっこ~ヤンキーの赤井トール@新井浩文と、ノゾミ@吉村由美の赤井夫妻にとどめを刺す。新井浩文は本当にうまい役者で大好きなんだけど、ヤンキー役は彼の定番キャラ。しかし今回は自己模倣ナシのリアル・ヤンキーっぷりで、怖かったぐらいだ^^;; 死神@松本実は何気に嬉しかったかも。
・・・・なんだか予想以上に長くなってしまったが、最後にもう一つだけ。私的期待の豪華カメオということで、前述の『殺し屋1』映画化の監督である三池崇史@金田!いやあ~亀甲縛りサービス(?)での登場には大爆笑。メッタ刺しでのひっくり蛙みたいな死体ぶりは自ら演出したのだろうか・・・脚の毛まで剃ってるしなあ(笑)。これが、全体的に冷たく重い空気が支配する本作中、最大のマイ・ブレイクポイントであったことは言うまでもない。
個人的に一番望ましいと思う映画化は「原作の生かし方」が「物語」ではなく「スピリット」であること、或いは原作をベースにしつつ、その映画監督の独自の色をつけ再構築してくれていることだろう(勿論そこには、原作に対する愛なりリスペクトなりが不可欠だ)。そうすれば、観ている方も早々に原作という呪縛から離れて映画そのものに没頭することが出来る。それに下手に原作に拘泥すると、映画ならではの面白さが失せ、中途半端でつまらないものになることがあるしね。
そこで『隣人13号』である。井上三太の代表作といってよいこの作品を読んだときは、かなり強烈なインパクトを喰らった。私は80年代前半以降、熱心な漫画読みではなくなったが、90年代に入ってから読んだ漫画の中では明らかに特別な作品の一つに入る。当時、この作品の後に『殺し屋1』を読んで、似たようなテーマが似たような歳の原作者によって、それぞれのベクトルに向かって進んでいき、それぞれが彼らの傑作となったのが興味深かったことを思い出す。
こと『隣人13号』は、いじめられっ子が二重人格者の怪物となって恐怖の復讐を執行する、という内容もさることながら、その殺戮シーンの、思わず笑ってしまうようなあっけらかんとした残虐さがスゴかった。主人公の村崎十三の別人格である13号は、本当に子供の遊びのように殺人を楽しむ。十三の身体年齢は就職するほどの年齢になっているが、13号は十三が酷いいじめによって深手を受けた小学生で時が止まっているからだ。子供は怖い。純粋と言えば聞こえはいいが、ようするにモノを知らないのだ。限度も知らない。十三を虐め抜いた赤井トールも、どこまでヤるとまずいのか、などと考えたりしなかった。
映画はその原作に対して、正面からのガチ勝負で挑んでいる。オリジナルの「物語」を損なうことなく(登場人物を刈り込んで必要最低限にしているが)、その「スピリット」は当然焼き付けて、尚且つ監督自身の個性をミックスさせて作りあげる。
ここまでやってくれれば、原作がどうこう、なんてのはどうでもよい。これまでCM・PVディレクターとして活動してきた井上靖雄監督、これが長編デビュー1作目とは思えない堂々たる仕事ぶりである。CM・PV出身の監督というと、やもすると独り善がりな映像遊びばかりが悪目立ちして作品として体をなしてない場合もあったりして、映画化決定のニュースを聞いた当初は正直若干の不安もあった。しかし、その後「井上三太自らOK」というニュースを聞いて、それなら期待できるかも、と思い直したのだ。
さすが三太のお墨付き。靖雄監督は、冒頭からえらいテンションで、まずは自分の世界に惹き込む。やがて原作の出来事が、実写としてスクリーンに出現してくる。そのヘヴィかつクール、そして真摯なアプローチが素晴らしい!(ちゃんと乾いた笑いで遊ぶことも忘れてないし)
真摯だからこそ、漫画の中ではオフビートなブラックさを感じさせた部分も、洒落にならない重さで観ている者を圧迫する。その緊張感は、遊園地のビデオテープ再生でマックスになり、そこからクライマックスの教室まで一気になだれこむのである。
そして映画オリジナルのラストシーン。もう一つの、十三の物語・・・私は不覚にもここで少し泣けてしまった。いや、不覚ではない。原作のラストの拡大解釈としても、見事じゃないか。本作がR15指定なんてけしからんよ。むしろ教育的価値の高い内容なのだから、子供こそ観るべし!>断言するのはマズイのか?
勿論キャスティングについても申し分なかった。村崎十三と13号は別人としいうことで、役者も2人に分けたのも効果的だった。十三@小栗旬は、茫洋と鬱屈している雰囲気を見事に現している。彼は気にかけている若手俳優の1人なのだが、使われ方によって良い悪いがハッキリ出てしまう人でもある(あずみ2はちょっとダメな方向だったかも・・・監督が若い男子はどーでもいいからか^^;;)。だから、この役はどうかな~と観るまでは不安もあったが、結果はオッケー! ほぼ無感情な台詞の言い方も的確だった。13号@中村獅堂はクライマックスのノリノリな演技に至るまでの、抑制を効かせた部分が更に13号の天然キ○ガイぶりを際立たせてうまかった。この人はたまにやりすぎなところがあって、私には好きなときとウザイと思うときと分かれるタイプの俳優なのだが、今回はメリハリつけてて良かった。
しかしなんといっても、ベストは元イジメっこ~ヤンキーの赤井トール@新井浩文と、ノゾミ@吉村由美の赤井夫妻にとどめを刺す。新井浩文は本当にうまい役者で大好きなんだけど、ヤンキー役は彼の定番キャラ。しかし今回は自己模倣ナシのリアル・ヤンキーっぷりで、怖かったぐらいだ^^;; 死神@松本実は何気に嬉しかったかも。
・・・・なんだか予想以上に長くなってしまったが、最後にもう一つだけ。私的期待の豪華カメオということで、前述の『殺し屋1』映画化の監督である三池崇史@金田!いやあ~亀甲縛りサービス(?)での登場には大爆笑。メッタ刺しでのひっくり蛙みたいな死体ぶりは自ら演出したのだろうか・・・脚の毛まで剃ってるしなあ(笑)。これが、全体的に冷たく重い空気が支配する本作中、最大のマイ・ブレイクポイントであったことは言うまでもない。










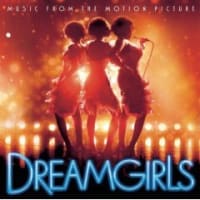

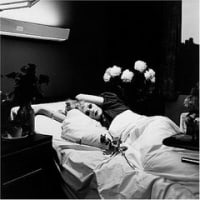
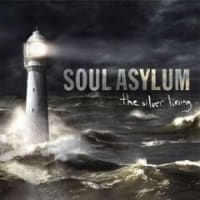

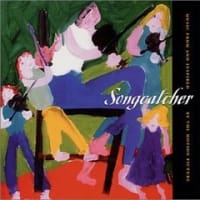
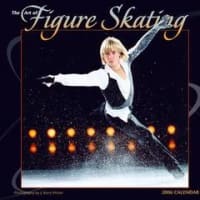
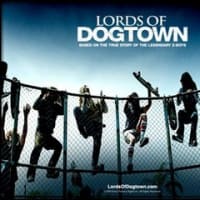
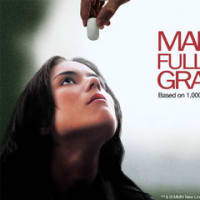
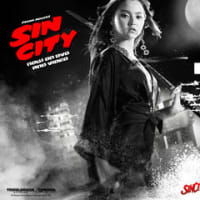
原作は1巻だけ読んで読むのやめたんですが
映画も原作に忠実だったんすね。
漫画もラストはあんなのってことですよね。
微妙。
確かに三池監督はおいしかったですね。
TB&コメント、ありがとうございます。
原作と映画、ラストの「話」は違いますけど「ニュアンス」は同じ、と感じましたね。
この作品自体、読む人によって180度違う感想を持たれるものなんでしょうね。
(私は肯定派ですけど(笑))