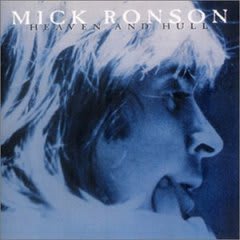『DEMONLOVER』公式サイト(3/12~公開)
試写で観てきました。監督のアサイヤスは、私の中ではマギー・チャンの元夫ってトピックが一番大きい人で(笑)彼女に惚れこんで撮ったとしか思えない『イルマ・ヴェップ』('96)は確かに面白かったです。
今回と同じく音楽にSonic Youthを使ってて、それが映画の内容にはアンバランスでも、映画のスタイルには不思議と合っててね。フランス映画は、ちょっと苦手なタイプの人が多いけど、この人の現代的でお洒落すぎない、尖りすぎてないセンスとかは嫌いじゃない 。あと、使う女優の趣味が合います(大笑)。
今作の主演・コニー・ニールセンは『グラディエイター』にも出てたそうだけど正直印象薄くて覚えていない。でも、とても雰囲気のある色っぽい女優さんだったんですねえ~。彼女がとても良かった。ただ、マギーのときと同じようにラバースーツとか着せられてるので、もしかして「ソレは監督の趣味なのか?」と(爆)。いや、いいんだけどねラバーフェチでも(>断言しちゃマズイでしょっ;;)。あと、スクリーンで観るのは久しぶりのジーナ・ガーションが、少ないシーンながら相変わらずワイルドな色気たっぷりでときめきました。クロエ・セヴェニーは、なんというか、もう彼女は一時期のジュリエット・ルイスみたいに、何をやっても彼女独特の存在感を放つ人なので、ファンは必見でしょう(笑>でも思ったほど目立つ役ではないですが)
肝心の映画は・・・そうだなあ~上記の女優や監督のファン、Sonic Youthファンの一部には普通にお薦めできます。映画の前半に少し出てくる大森南朋くんのファンには微妙かも^^;; いや、彼はいつも通りですけどね。ちなみに、日本のアダルト向けアニメの製作会社の若き社長役。
そう、本作では「これからの日本経済の中心はアニメ、マンガ絡みの(ネットを媒介とした)セックス産業」として注目されている。しかし、これは映画の中ではキッカケに過ぎず、要するに現代では、ネット上でそうしたセックス・暴力(SM)産業は莫大な利益を与えるマーケットであり、それをビジネスとして扱う人間の中のうすら寒いような空っぽさやとか、利益に群がる企業の裏の攻防とか、そこに入り込む暗い欲望であるとか、社会的自己と本当の自己の混乱とか、そういったことが論理的というよりイメージ的に描かれている。
だから、映画に「はっきりしたお話・テーマ」「筋道」「結論」とかが欲しい人にはつまらない、かもしれない。(実際、私の後ろに座ってたおじさんは終わった直後に「駄作だな」と断言)
私はそういうタイプではなく、雰囲気ものでも楽しめるほうなので(笑)それなりに面白かったです。映画としての強度は物足りない部分もあるけど、意欲作とは思えるし。繰り返しになるけど、Sonic Youthの音もいいし。ただ『イルマ・ヴェップ』のときのほうが印象的だったかも・・・。
ちなみに、画像は作中に出てくる拷問サイトHell-Fire Club.com(身も蓋も無いぞ~)から。緊縛モノとかも当然あるんですが(笑)とりあえず、カワイイやつを。
やっぱ、フランス人監督は自分の惚れた女を撮るときが一番いい仕事をするのかもしれない(笑)。
ってことで、別れてもきっと好きな人であるマギー主演の最新作『クリーン』早く観たい!ってことで、日本公開早期実現を熱烈希望です。
※マギー・チャン(張曼玉)…香港出身の女優で、近年の代表作はウォン・カーウァイ監督『花様年華』、ピーター・チャン監督『ラヴソング』、チャン・イーモウ監督『英雄』等。
個人的に、最も愛する女優の1人です。
試写で観てきました。監督のアサイヤスは、私の中ではマギー・チャンの元夫ってトピックが一番大きい人で(笑)彼女に惚れこんで撮ったとしか思えない『イルマ・ヴェップ』('96)は確かに面白かったです。
今回と同じく音楽にSonic Youthを使ってて、それが映画の内容にはアンバランスでも、映画のスタイルには不思議と合っててね。フランス映画は、ちょっと苦手なタイプの人が多いけど、この人の現代的でお洒落すぎない、尖りすぎてないセンスとかは嫌いじゃない 。あと、使う女優の趣味が合います(大笑)。
今作の主演・コニー・ニールセンは『グラディエイター』にも出てたそうだけど正直印象薄くて覚えていない。でも、とても雰囲気のある色っぽい女優さんだったんですねえ~。彼女がとても良かった。ただ、マギーのときと同じようにラバースーツとか着せられてるので、もしかして「ソレは監督の趣味なのか?」と(爆)。いや、いいんだけどねラバーフェチでも(>断言しちゃマズイでしょっ;;)。あと、スクリーンで観るのは久しぶりのジーナ・ガーションが、少ないシーンながら相変わらずワイルドな色気たっぷりでときめきました。クロエ・セヴェニーは、なんというか、もう彼女は一時期のジュリエット・ルイスみたいに、何をやっても彼女独特の存在感を放つ人なので、ファンは必見でしょう(笑>でも思ったほど目立つ役ではないですが)
肝心の映画は・・・そうだなあ~上記の女優や監督のファン、Sonic Youthファンの一部には普通にお薦めできます。映画の前半に少し出てくる大森南朋くんのファンには微妙かも^^;; いや、彼はいつも通りですけどね。ちなみに、日本のアダルト向けアニメの製作会社の若き社長役。
そう、本作では「これからの日本経済の中心はアニメ、マンガ絡みの(ネットを媒介とした)セックス産業」として注目されている。しかし、これは映画の中ではキッカケに過ぎず、要するに現代では、ネット上でそうしたセックス・暴力(SM)産業は莫大な利益を与えるマーケットであり、それをビジネスとして扱う人間の中のうすら寒いような空っぽさやとか、利益に群がる企業の裏の攻防とか、そこに入り込む暗い欲望であるとか、社会的自己と本当の自己の混乱とか、そういったことが論理的というよりイメージ的に描かれている。
だから、映画に「はっきりしたお話・テーマ」「筋道」「結論」とかが欲しい人にはつまらない、かもしれない。(実際、私の後ろに座ってたおじさんは終わった直後に「駄作だな」と断言)
私はそういうタイプではなく、雰囲気ものでも楽しめるほうなので(笑)それなりに面白かったです。映画としての強度は物足りない部分もあるけど、意欲作とは思えるし。繰り返しになるけど、Sonic Youthの音もいいし。ただ『イルマ・ヴェップ』のときのほうが印象的だったかも・・・。
ちなみに、画像は作中に出てくる拷問サイトHell-Fire Club.com(身も蓋も無いぞ~)から。緊縛モノとかも当然あるんですが(笑)とりあえず、カワイイやつを。
やっぱ、フランス人監督は自分の惚れた女を撮るときが一番いい仕事をするのかもしれない(笑)。
ってことで、別れてもきっと好きな人であるマギー主演の最新作『クリーン』早く観たい!ってことで、日本公開早期実現を熱烈希望です。
※マギー・チャン(張曼玉)…香港出身の女優で、近年の代表作はウォン・カーウァイ監督『花様年華』、ピーター・チャン監督『ラヴソング』、チャン・イーモウ監督『英雄』等。
個人的に、最も愛する女優の1人です。