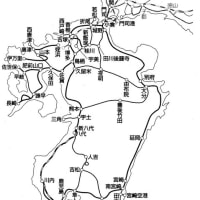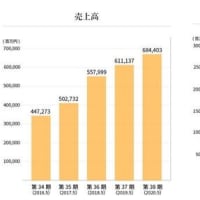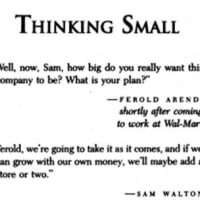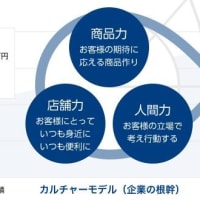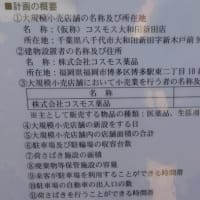東京都知事選(2月9日投票)に細川護熙元首相が出馬する方向となったことを受け、安倍晋三首相に「原発ゼロ」を求める小泉純一郎元首相が細川氏をどの程度支援するかが焦点になってきた。
小泉元首相の唱える脱原発論は、いわゆる「トイレのないマンション」論である。日本に最終処分場は作りようがないのだから原発ゼロというシンプルな 発想である。これに対して、「楽観的で無責任」といった反論に対し,小泉氏は,「最終処分場もないのに原発に依存するほうがよほど無責任」と一蹴する。
事実,いま、全国の原発の使用済み核燃料保管プールの満杯率は平均70%にも達している。原発稼働に伴って膨大に発生し続ける使用済み核燃料を貯蔵する場所の確保は,極めて難しい状況に陥っている。
。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+ Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y+
◆ 東海原発廃炉、5年延長=処分場なく、さらに長期化も-日本原電
日本原子力発電は2012年12月19日,廃炉作業中の東海原発(茨城県東海村)について,完了時期をこれまでの2020年度から2025年度に5年間延長すると発表した。延長は2010年に続き2回目。
東海原発は1998年、国内の商用原発として初めて廃炉が決まったが,放射性廃棄物の処分場は決まっておらず,今回の再延長で廃炉の困難さが改めて示された形だ。
原電によると、2014年度から予定していた原子炉関連設備の解体撤去をする際の装置導入に時間がかかっているため、延長を決定した。廃炉のスケジュールをめ ぐっては、2010年にも3年間の延長を決めていたため、当初の予定から計8年遅れることになる。
◆朝日新聞社 全国定例世論調査では,「原発ゼロ支持60%」
朝日新聞社が2012年11月に実施した全国定例世論調査(電話)では、小泉純一郎元首相が政府や自民党に対し「原発ゼロ」を主張していることについても質問した。この主張を「支持する」は60%にのぼり、「支持しない」の25%を上回った。
source:http://www.asahi.com/articles/TKY201311110621.html
◆週刊ダイヤモンド 世論調査の投票結果 (11/17現在)朝日新聞が実施した世論調査では、小泉氏の原発ゼロの主張について、週刊東洋経済の読者アンケートでは,支持するが78%、支持しないが14%である。

。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+ Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y+
◆原発「トイレなきマンション」と呼ばれる理由-最終処分場」なぜメド立たないのか?/小泉元首相発言で注目
小泉氏が脱原発に転換するきっかけになったのは、フィンランドのオンカロ(洞窟、隠し場所を意味する)と呼ばれる最終処分場を見学したことがきっかけだといわれている。フィンランドに建設されている最終処分場では、花崗岩でできた岩盤を500メートルほど掘り下げ、さらに横穴を広げてそこに放射性廃棄物を処分していく予定となっている。放射性廃棄物はガラスで固化され、さらにステンレスの丈夫な容器に封入される。
しかし放射性廃棄物の中にはプルトニウムのように半減期が長いものが含まれており、安全なレベルまで放射能が減少するまでには10万年近くの歳月がかかるといわれている。それまでの間には、容器は腐食して中の放射性物質は外部に漏出してしまうことから,地下水がなく地層が安定した場所を最終処分場に選択しないと周辺の環境を汚染する可能性が高くなってしまう。
フィンランドの施設は花崗岩の岩盤という非常に条件のよい場所であるが,これでも完全に放射性物質の影響をシャットアウトできるのかは不明である。しかも10万年という時間を考えると、その時に現在の政府はおろか、人類さえも同じ状態で生存しているのか分からない。小泉元首相をはじめとして原発に慎重な人はこの点を憂慮しているわけである。
日本でもフィンランドと同様の処分場を建設することが想定されているが,今のところ、どこに最終処分場を作るのかまだ決定していない。つまりどこにゴミを捨てるのか決めないまま原子力政策を進めているわけである。日本の原発が「トイレなきマンション」と呼ばれるのはこのためである。 ※ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000005-wordleaf-sctch&p=2
 |
原発ホワイトアウト |
|
近未来のある大晦日、折からの爆弾低気圧がもたらした大雪の中で、日本海側から首都圏に繋がる高圧送電線ケーブルが外国人テロリストによって2本ほど倒さ れる。これが原因となる送電停止で新潟県の原発で福島と同様のメルトダウンが生じ,日本国内はコントロール不能な大混乱に陥る。 |
|
| 若杉 冽著 講談社刊 |
◆ 小泉「原発発言」 関連記事
 |
原発に頼らなくても日本は成長できる |
|
発生から2年半を経過しながら依然として”本当の収束”が見えない福島第一原発事故。増え続ける汚染水処理の問題は、日々のニュースに紛れながら伝え続け られています。事故対応は当然のことながら、俎上にあがったままのエネルギー政策再編論議も早急に進めなければならない問題です。今回紹介するのは、経済 学側面からエネルギー政策の処方箋を提示した1冊です。 円居総一著 |
|
| ダイヤモンド社 |