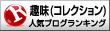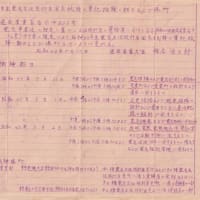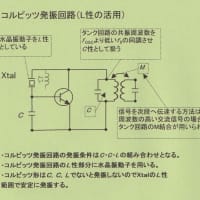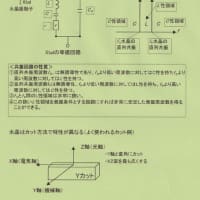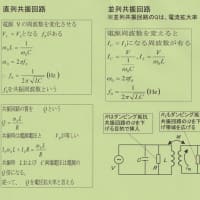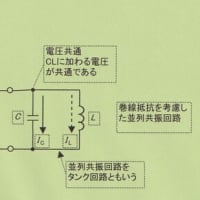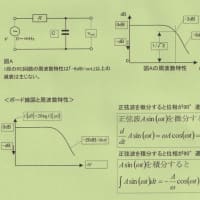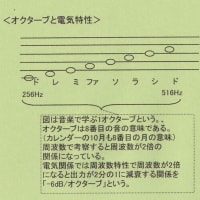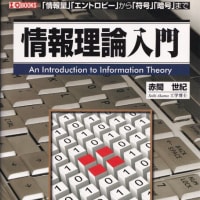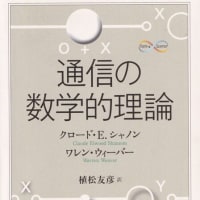リチウムイオン電池の資料の一部を公開します。
リチウムイオン電池の資料作成で気付いたことは、安全性の問題でした。
建物管理を行う技術者は、リチュウムイオン電池の持つ素晴らしい高エネルギー密度と、同時に可燃性溶媒を内蔵し、発煙・発火の危険性があること、その要因の一つであるデンドライトの問題に関する知識が必要と理解されます。
☟コバルトレスの正極材料と、負極材料を使用しデンドライト軽減

作成資料の一部抜粋です(本文はである調)。
1859年にプラテン(仏)によって発明された鉛蓄電池は、信頼性が高く安価であり、定置型および車載用バッテリーとして広く使われてきたが、水を電解液とした二次電池のセル電圧は、水の理論的な分解電圧である
1.23Vの壁があり、2V程度が上限となる。
リチウムイオン電池は、非水電解液を使用するのでセル電圧が4V級でも電解液の電気分解が起ることなく、充放電を繰り返して使用することが可能である。
- 電池の基礎事項
電池は、「自発的に生じる化学反応エネルギーを電気エネルギーに変換する装置」であると理解できる。
実績もあり安価で信頼性の高い鉛蓄電池は、エネルギー密度が70程度と低く定置型の場合は問題ないが、小型・軽量を求められるモバイル用電池や電気自動車およびドローンの動力源用には適さないと考えられる。
2次電池のエネルギー密度を高くする方法は、セル電圧を高くする必要があり分解電圧に左右されない「非水電解液」を使用するリチウムイオン電池が有利である。
- エネルギー密度
- ボルタ電池で考察する電池の基礎(図01参照)
- ファラデーの法則と容量
- イオン化傾向と起電力(図02参照)
- リチウムイオン電池の基本構造と動作
- 正極の材料考察(図03参照)
- 負極の材料考察(図04参照)
- セパレータ
- コバルト酸リチウムイオン電池の充電動作(図05参照)
- コバルト酸リチウムイオン電池の放電動作(図06参照)
- 有機溶媒系電解液(非水電解液)
(1)電解液に要求される諸条件および溶媒の概要
- リチウムイオン電池の安全対策
- デンドライト(dendrite)
デンドライトは樹枝状に生成される結晶構造のことであり、霜や雪の結晶にも見られ自然界に多く存在するが、リチウムイオン電池では、発煙または発火事故の要因になる。
- 正極と負極の容量バランス
正極も負極も満充電に近づくほど発熱量が増加する。経年劣化により過充電になると更に、熱安定性が劣化する悪循環が考えられる。
- デンドライト軽減の新しい技術(図08A、B参照)
1991年に実用化されたコバルト酸リチウムを用いたリチュウムイオン電池は、高エネルギー密度を持つ二次電池として脚光を浴びているが、非水電解液が可燃性であり、発煙、発火の危険性等の問題がある。
安全性と高エネルギー密度を可能にする正電極材および負電極材の開発と並行し、電解物質を固体化した安全性の高い「全固体型電池」が近い将来に市場投入され見通しである。
<リチュウムイオン電池による火災データ>
東京消防庁<安全・安心><リチウムイオン電池搭載製品の出火危険> (tokyo.lg.jp)
<参考文献>順不同
- リチウムイオン電池の設計法、鳶島真一著、科学情報出版1初版
- リチウムイオン電池の安全対策と要素技術、鳶島真一著、科学情報出版2初版2刷
- リチウムイオン電池・全固体電池、櫻井庸司著、科学情報出版11初版
- 固体電池の入門、金村聖司著、科学情報出版8初版
- 日経エレクトロニクス、日経BP、2023年2月号
- 日経エレクトロニクス、日経BP、2024年2月号