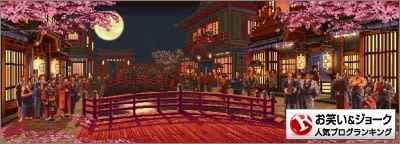こういったランキングに日本の食べ物が必ず入り込んでいることからもわかるように、その地では御馳走だったり、珍味だったりするものが、他の国から見ると「んぐぐっ!」っとなる食べ物がは多数存在する。
多種多様な食文化のなせる業なのだが、ここでは現地で通常食べられているものから、現地でも珍味中の珍味で一部の人しか食さない最恐のものまで15品ほど見ていくことにしよう。なんどかこういったランキングを紹介しているが、いくつか常連が含まれている。カース・マルツゥとか昆虫は確実に常連なので閲覧注意でお願いしたい。
君ならどれを食べてみたい?
15. ヘラジカの鼻のゼリー(カナダ)

カナダの先住民料理レシピを集めた『Northern Cookbook』にもちゃんと載っているメニューである。これは、冒険好きなカナダ人がジビエ料理にひと味工夫を凝らすための実践的なガイドブックにもなっている。
ほかのゼリーミートと同様、これもヘラジカの顔の前半分を使い、煮込んでから冷やして作る。白身と赤身の混じったような塊肉を切り分けて食べる。牛の頭を丸ごとボイルしたヘッドチーズと呼ばれる料理のヘラジカ版といえる。
14. ルーテフィスク(ノルウェー)

見た目は普通に見えるがそのニオイは強烈。ノルウェーの伝統料理で、いわば白身魚(たいていはタラ)の灰汁漬けである。
タラを水につけて塩抜きし、灰汁に浸して、1週間かけてゼラチン状にする。長く浸け過ぎると石鹸のようになってしまうので、注意が必要だ。ルーテフィスクを食するスウェーデンやノルウェーには、その起源についてさまざまな説があるが、どれも本当のことははっきりわからない。
ノルウェーでは特にクリスマス料理として一般的で、灰汁と1週間たった魚の松の木のようなニオイはクセになるんだとか。
13. カース・マルツゥ(イタリア)

イタリア、サルディーニャ地方のウジ虫入りチーズ。カース・マルツゥとは腐ったチーズの意。意図的に投入された生きたうじ虫がうごめき、呼吸し、チーズを消化・排泄することによって、チーズそのものの発酵プロセスを早め、熟成をしている。
EU内でかなりの問題になっているチーズで、最近までは全面的に禁止されていたが、伝統的な食品であるため、通常の健康安全面の基準対象からは事実上免除状態になっている。味はゴルゴンゾーラ風味の強烈なペコリーノ(羊乳のチーズ)のようで、後味にコショウなようなぴりりとした辛みが残るらしい。小さなうじ虫が口の中をうごめく感覚が、しばらくたっても消えないという。
12. 白子(日本)

日本の白子こういったランキングの常連だ。タラ、アンコウ、フグなどの精巣で、脳ミソによく似たぶよぶよした白い珍味だ。生か、軽く炙って食べると非常に美味。滑らかなバターのような舌触りで、これがなんだか知らなければ、舌がとろけそうになるほどおいしい。
精巣を料理として出す国は日本だけではない。ロシア、ルーマニア、シチリアでもあり、国によって料理の仕方、食べ方が違う。ロシアでは、パスタのトッピングとして使われ、ピクルス(酢漬け)にして食べることもある。
11. ヘビ酒(中国・ベトナム・日本)

ヘビをお酒に漬けて発酵させる。珍味というより、精力剤として飲まれる。中国やベトナム、日本などのアジアで見られ、酒自体は飲んでも危険はないが、いまだにほとんどの国では解禁するのは危険とみなされている。
ヘビ酒の記録が最初に出てくるのは紀元前771年の古代中国にさかのぼる。作り方はさまざまあり、ヘビの血や胆汁を加えることもあるが、通常はヘビ丸ごとを薬草やほかの小さなヘビ数匹と一緒に漬けて発酵させる。中国では生きたヘビをそのままビンに押し込めて作る場合もある。
10. コブラ(ベトナム)

ベトナムの珍味である。コブラを目の前でさばくところから始まって、フルコースで全身を食べるプロセス全体が凝ったショーのようになっている。まずは主賓がまだ動いている心臓を食べる。そして、残りもすべて余すところなく、食べやすいようさまざまに調理される。コブラのスープ、コブラだんご、コブラ春巻きなど、まさにコブラづくし。コブラの血が入った赤い酒と、胆汁の入った緑色の酒は、なんとも背筋がぞっとするが、コブラは強力な催淫剤と考えられているそうだ。
9. ウィチェッティグラブ(オーストラリア)

昆虫は世界中の至る所で食べられている優れたタンパク源。オーストラリア産のこの巨大な白いイモムシは、オオボクトウという蛾の幼虫である。
もともとは、オーストラリアのアボリジニたちの間で食べられていた。彼らにとって食糧の少ない砂漠で生きるためのもっとも重要な食材だった。生で食べるとアーモンドのような味がして、揚げると外側がローストチキンのようになり、中身は卵に似て、黄身のような黄色をしているという。
8. バルート(東南アジア)

まだ孵化途中のアヒルなど鳥の胎児をボイルしたもので、殻を割って直接食べる。東南アジアではかなり一般的な料理で、味はとてもおいしい。栄養価も高く、特に妊婦は食べることを勧められる。ただし、危険な細菌が潜んでいる可能性もあり、物議をかもす食べ物でもある。ビールのつまみとして出されることも多いそうだ。
7. ブラッドクラム(中国)

ハイガイは、柔らかい組織の内部にヘモグロビン(血色素)を含んでいるため、ブラッドクラムと呼ばれる。中国の珍味だが、多くの危険と隣り合わせだ。というのは、低酸素の環境でも生きるため、この貝はA型肝炎や赤痢などのウィルスや病気を取り込みやすいためだ。
それでも、2011年に『ニューヨークタイムズ』がぜひ食べるべきと煽り、人々はニューヨークのハイガイは選別されているから安全だと信じたがった。ジューシーで大変に美味なので、貝好きな人はぜひ食べてみたいところだが、血まみれそのものの見た目にまず慣れなくてはいけないだろう。日本では有明海周辺で少ないながら売り買いされているという。
6. スープ・ナンバーファイブ(フィリピン)

催淫剤と言われているこのフィリピン料理には、スープ・ナンバーファイブというやけに控えめな、なにやらまわりくどい名前がつけられているが、雄牛の息子スティックまたは睾丸が使われていて、いかにも効果がありそうだ。これは特に珍しい料理ではなく、フィリピンの主要都市の通りで普通に売られている。
5. タランチュラの唐揚げ(カンボジア)

カンボジアの珍味で、地元の人や観光客向けに唐揚げにするため、特別にタランチュラが育てられている。どこが発祥なのかははっきりしないが、食べ物が不足していたクメールルージュ支配時代に食されていたのではと考えられている。
化学調味料、砂糖、塩などをまぶして揚げると、外はカリカリで、タラやチキンのようなマイルドな味になるらしい。内臓や卵、排泄物の詰まった茶色い肉が出てくる腹の部分は食べないように言われることが多い。
4. ピータン

ピータンは中国料理のひとつで、ウズラ、アヒル、ニワトリ、キジなどの卵を土、灰、塩、もみ殻の中に埋めて、数週間から数ヶ月熟成させたもの。この間、黄身は灰色がかったグリーンに、白みは半透明のダークブラウンになる。アンモニアが発生し、醗酵した尿を思わせるにおいがするため、作る過程で馬の尿が使われていると信じる者もいる。ピータンは特別なイベントがあるときに出されることが多い。味は普通の固ゆで卵とほぼ同じだが、そのニオイは強烈だ。
3. アヒルの血(ベトナム)

Tiet CANH というベトナム料理は、おもにアヒルの血を使ってできた、液体でも固体でもないパンケーキ入りのスープのようなもの。血そのものにピーナッツやハーブが入れてある。北部ではのタンパク質豊富な朝食のひと皿となっている。
アヒルから血を絞り出して、すぐに魚醤を混ぜて、血が凝固するのを防ぐ。作ってすぐに食べるか、冷蔵庫で保存しないと、血のようなどろどろした状態がなくなってしまう。
2. 童子蛋(中国)

中国、浙江省東陽で毎年春に売り出されるこの珍味は、一見ふつうの卵に見える。だが、これは思春期前の少年の尿で煮て作るのだ。そのために、学校のトイレから尿を集め、午前中数時間かけて卵をこれに浸して煮る。昼頃に殻をむいて、再び少年の尿で煮続ける。(詳しい記事はこちら)
幸運と健康にいいと考えられていて、この付近の村では代々食べられてきた。通りの屋台から買う人がほとんどだが、自分の尿を集めて自宅で調理する場合もある。中国政府はこの地域の文化遺産として、この伝統を守っている。
1. サワートゥ(カナダ)

カナダの北西部ユーコン州のホテルのバーで出されるカクテル。その伝説は1920年代にさかのぼるらしいが、このカクテルの中にはミイラ化した本物の人間の足指が入っている。指がぷかぷか浮いているのを横目で
見ながら酒を飲み干し、その指はすくいあげて使い回す。
このカクテルを出しているサワートゥクラブというバーは、長年の間、検体(?)によって集まった10本の足指を実際に使っているという。指がつかった酒を勇気を出して飲み干すための決まり文句まである。"一気に飲もうが、ちびちび飲もうが、いずれにしろ唇は足指に触れる" と。
2013年、このバーから足指が一本なくなった。米国人の客が足指を飲みこんでしまったのだ。彼は500ドルの罰金を払うはめになったが、むしろ喜んで支払ったという。