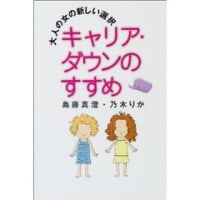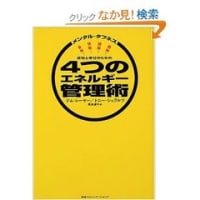先日、夜遅い時間のスカイプミーティングの終了間際に思考が停止してしまったので
「脳みそがウニになりました 」と言ったところ、
」と言ったところ、
その表現がアメリカ在住のコーチには面白かったらしく、
ブログで取り上げられていました。
そういえば、アメリカのお寿司屋さんでウニって見たっけな~
あー。バフンうにが食べたい
さて、スカイプを使って何のミーティングをしているかというと、
コーチング関係の英語を和訳した文書の
言葉や表現チェックを皆でしています
普段の仕事でやっている英文などのチェックとは、
和訳のチェックであることと、
ひとつの言葉に対して色んな人の意見が聞けるという点が大きく違います
普段一人でやっているのと近い作業でも、
こうやって皆でディスカッションをしてみると、
自分の見落としていた点や、視点に気付かされます

たとえば、「research」という単語。
「研究」と訳すべきか、「リサーチ」と訳すべきか


日本人的感覚では、「研究」は学術的な深い研究、
「リサーチ」は「マーケットリサーチ」のように
調査のような広く浅いイメージで使われていると思います。
でも、英語の「research」は両方を含む、幅の広い言葉です。
留学していた時に「研究」のことを「リサーチ」と呼ぶのに慣れていたので、
「リサーチ」=英語の「research」の幅で捉えていたことに、
ディスカッション中に初めて気が付きました
そういうわけで、「research」担当になったrabbitは、
文脈を考えながら、「research」の訳語を一つ一つ確認&修正。
また頭がウニになりました
今朝は初めての「朝ミーティング」を6時半から行いましたが、
朝が苦手なrabbitにとっては、
ミーティング後に加圧トレーニングをする時間もできたので、
早起き 朝時間の有効活用の、よいきっかけになりました
朝時間の有効活用の、よいきっかけになりました
言葉の持つ幅や深さって、言語対言語で1対1じゃないから難しい
でも、面白い
「脳みそがウニになりました
 」と言ったところ、
」と言ったところ、その表現がアメリカ在住のコーチには面白かったらしく、
ブログで取り上げられていました。
そういえば、アメリカのお寿司屋さんでウニって見たっけな~

あー。バフンうにが食べたい

さて、スカイプを使って何のミーティングをしているかというと、
コーチング関係の英語を和訳した文書の
言葉や表現チェックを皆でしています

普段の仕事でやっている英文などのチェックとは、
和訳のチェックであることと、
ひとつの言葉に対して色んな人の意見が聞けるという点が大きく違います

普段一人でやっているのと近い作業でも、
こうやって皆でディスカッションをしてみると、
自分の見落としていた点や、視点に気付かされます


たとえば、「research」という単語。
「研究」と訳すべきか、「リサーチ」と訳すべきか



日本人的感覚では、「研究」は学術的な深い研究、
「リサーチ」は「マーケットリサーチ」のように
調査のような広く浅いイメージで使われていると思います。
でも、英語の「research」は両方を含む、幅の広い言葉です。
留学していた時に「研究」のことを「リサーチ」と呼ぶのに慣れていたので、
「リサーチ」=英語の「research」の幅で捉えていたことに、
ディスカッション中に初めて気が付きました

そういうわけで、「research」担当になったrabbitは、
文脈を考えながら、「research」の訳語を一つ一つ確認&修正。
また頭がウニになりました

今朝は初めての「朝ミーティング」を6時半から行いましたが、
朝が苦手なrabbitにとっては、
ミーティング後に加圧トレーニングをする時間もできたので、
早起き
 朝時間の有効活用の、よいきっかけになりました
朝時間の有効活用の、よいきっかけになりました
言葉の持つ幅や深さって、言語対言語で1対1じゃないから難しい

でも、面白い