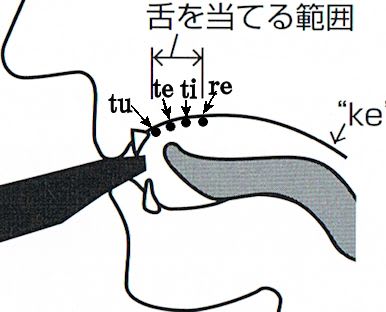良い音を出すには「バカ殿の発音」、は以前書きましたが、さらに強力な呼気を出すコツです。ケーナを吹いた後フルートを吹くとなんと音が出やすいのだ、と感じるのです。低音から高音まで楽に出るのです。さすが長年研究され尽くした楽器。その点ケーナは厄介です。低音が出やすいケーナは高音が出にくく、高音が出やすいケーナは低音が出にくい。どちらがより厄介かと言うと前者だと思うのです。太いケーナはその傾向が強いですが、バカ殿式では間に合わない、その時に有用なのがスリーパーホールド式喉なのです。スリーパーホールドとは何ぞや?プロレスファンなら誰でも知っているのですが(私は大のプロレスファン、ただしG馬場時代の)首を絞める技なのです。息を吐きながら自分の首を絞めてください。息の通り道が狭くなって、カスレ音になります。この状態とバカ殿式を同時にやるとここで息がさらに圧縮されるのです。ただ自分で首を絞めたままにするわけにはいきませんから、自らの喉の調整でスリーパーホールド状態を作るのです。どうやるかと言えば簡単、わざとカスレ声を出すようにするだけです。簡単です。だったらスリーパーホールドなんてやる必要ないじゃん???確かのそのとおり。首を締めたら危険ですのでやめましょう。
いづれにせよケーナの高音はバカ殿式+カスレ声式喉で。この話はケーナに限ったことでして他の笛は良く知りません。(オカリナ類はバカ殿式で充分です)
いづれにせよケーナの高音はバカ殿式+カスレ声式喉で。この話はケーナに限ったことでして他の笛は良く知りません。(オカリナ類はバカ殿式で充分です)