現在進行中のT社入社案内DVDのロケが9月18日終了した。
T社が選んだ若手社員に撮影クルーが付いてまわり、
日々の活動をアポなし飛び込みで取材した。
今から30年前、まだアポなし飛び込み取材がマレだった頃に比べ、
最近は被写体が撮られることに抵抗感がなくなり、
まるでカメラがそこにないがごとく自然体に近い形で取材できるようになった。

これは、ひとつには撮影機材の進化が大きく影響している。
高画質のハイビジョンカメラにも関わらず、コンパクトで、照明ナシでも
結構キレイに撮れる。音声も無線で飛ばせるのでほぼワンマンだ。
カメラマン一人で飛び込めるので、仰々しさがない。
これが30年前だとカメラマン以外に
撮影助手、ビデオエンジニア、録音マン、照明技師など、カメラマンを先頭に
4~5名が金魚のフンのごとく隊列をなし、
しかも煌々とライトを点けてやってくるので、撮られる方は物怖じしてしまう。
近年、戦場報道が写真から動画になってきたのも機材がコンパクトになったからだ。

一昔前はカメラとVTR、そして音声はケーブルでつながれていた
ふたつめは撮影自体がこれまでは「非日常」だったのが、
テレビの多チャンネル化でお笑いタレントが街歩きするだけの
安価型バラエティー番組が多くなってしまったことで、
撮影が「日常」になったことだ。
王子・福山雅治様に対してでも女子高生が「福山くん」と呼ぶ。
お笑いタレントに至っては呼び捨てだ。素人がプロを呼び捨てだ(泣)
今回の取材中にも
「昨日、ウドちゃんがテレビの取材でウロウロしていた」と言っていたぐらい、
一般ピープルが撮られることに慣れてきている。
30年前なら撮影の仰々しさにいかに被写体を慣らすか、
監督の技量が問われたものだ。
日本ドキュメンタリー界のレジェンド・小川紳介監督などは
スタッフと共に被写体の村に何ヶ月も泊まり込み、
コミュニケーションを深めてから撮影に入るなどした。
しかし今は1億総タレント時代。ご時世なのだが、飛び込み取材が楽になった。

さて、T社入社案内DVDだが、
今年の早春から秋にかけて約8ヶ月行われたが、
撮影日数はわずかに5日間。
その内泊まりは1回しかなく、すべてAM6時出発。
2時間かけて現場入り、日帰りの強行軍で撮影した。
13時間にもおよぶ素材を、いよいよ10月から編集することになる。
完成目標は20分だから、まさに整理とは捨てることなり。
この作品は来年度の採用説明会で使うが、実はスポンサーが待ちきれず
今年5月に今年度の採用説明会用として一旦12分に編集した。
ナレーターは私、音楽はフリーユースで対応した。
それでも十分に使用に耐えるから恐ろしい。
その後、初夏に1日、9月17~18日に2日間の泊まりロケをして、
都合5日間でクランクアップした。
手応えは十分にある。編集も楽しみだ。
こんな時はたいてい名作になる。
私は編集前に必ずナレーターを決める。
このナレーターならこうシャベル。あのナレーターならこんな感じと、
ナレーターに合わせて編集する。
ナレーターの個性や間の取り方、読みのスピード等を
編集にあらかじめ反映させる。
だから選んだナレーターによって、
語尾を「です・ます調」にしたり「である調」にするし、
「主観調」「客観調」にもする。
大した話ではないと思うかもしれないが、
「です・ます調」と「である調」では作品の性格がゴロリと変わる。
また主観的ナレーションと客観的ナレーションでは
視聴者の位置まで変わるし、使うカットまで変わってくる。
映像作品は通常、スポンサーにイメージを伝えてから見積を作成し、
ロケに入るのが基本だが、
私の場合はラブレターと意気込み(=口先)だけで
見積提示してロケに突入する。
「ドキュメンタリーとは発見だ」と現場でジタバタするので、
予め頭の中で作った台本は意味を成さない。
撮影中も都度都度で横路に逸れるが、
それこそがスポンサーに近づく唯一無二の近道と確信しているから、
撮り終えてから組み立ることになる。
しかも撮ったものを一通り見たら、さらなる脇道に入ったりする。
「どうする?俺」と撮影素材の解体作業を繰り返して、
撮影前に描いていたイメージに近づける。
勿論、遠ざかることも多々アルし、全く違うこともアル。それでいいのだ。
しかし編集前には絶対に!絶対に!絶対に!ナレーターを決めなければ
編集方針が固まらならない。
実はクランクイン時点で私はナレーターを林順子さんに決めていた。
超ベテランナレーターで、私の節目の作品には必ず登場する。
しかもすべて名作だ。
5月に一時完成した12分モノを早々と7月に郵送している。
しかし、私を悩ませている。
というのも林さんをナレーターに起用した時点で
「です・ます調」「客観張」「泣かせ」となってしまう。
すでに予約を入れた林順子さんに申し訳ないが悩む…
作品のカラーと声質が合うのか?
企業イメージに合うのか?
スポンサーは納得するのか?
視聴者は入社したいと思うのか?
悪魔の囁きに悩まされる。
「どうする?俺」
いずれにしても編集前に決めなければ…。
「どうする?俺」
困った…。。。
T社が選んだ若手社員に撮影クルーが付いてまわり、
日々の活動をアポなし飛び込みで取材した。
今から30年前、まだアポなし飛び込み取材がマレだった頃に比べ、
最近は被写体が撮られることに抵抗感がなくなり、
まるでカメラがそこにないがごとく自然体に近い形で取材できるようになった。

これは、ひとつには撮影機材の進化が大きく影響している。
高画質のハイビジョンカメラにも関わらず、コンパクトで、照明ナシでも
結構キレイに撮れる。音声も無線で飛ばせるのでほぼワンマンだ。
カメラマン一人で飛び込めるので、仰々しさがない。
これが30年前だとカメラマン以外に
撮影助手、ビデオエンジニア、録音マン、照明技師など、カメラマンを先頭に
4~5名が金魚のフンのごとく隊列をなし、
しかも煌々とライトを点けてやってくるので、撮られる方は物怖じしてしまう。
近年、戦場報道が写真から動画になってきたのも機材がコンパクトになったからだ。

一昔前はカメラとVTR、そして音声はケーブルでつながれていた
ふたつめは撮影自体がこれまでは「非日常」だったのが、
テレビの多チャンネル化でお笑いタレントが街歩きするだけの
安価型バラエティー番組が多くなってしまったことで、
撮影が「日常」になったことだ。
王子・福山雅治様に対してでも女子高生が「福山くん」と呼ぶ。
お笑いタレントに至っては呼び捨てだ。素人がプロを呼び捨てだ(泣)
今回の取材中にも
「昨日、ウドちゃんがテレビの取材でウロウロしていた」と言っていたぐらい、
一般ピープルが撮られることに慣れてきている。
30年前なら撮影の仰々しさにいかに被写体を慣らすか、
監督の技量が問われたものだ。
日本ドキュメンタリー界のレジェンド・小川紳介監督などは
スタッフと共に被写体の村に何ヶ月も泊まり込み、
コミュニケーションを深めてから撮影に入るなどした。
しかし今は1億総タレント時代。ご時世なのだが、飛び込み取材が楽になった。

さて、T社入社案内DVDだが、
今年の早春から秋にかけて約8ヶ月行われたが、
撮影日数はわずかに5日間。
その内泊まりは1回しかなく、すべてAM6時出発。
2時間かけて現場入り、日帰りの強行軍で撮影した。
13時間にもおよぶ素材を、いよいよ10月から編集することになる。
完成目標は20分だから、まさに整理とは捨てることなり。
この作品は来年度の採用説明会で使うが、実はスポンサーが待ちきれず
今年5月に今年度の採用説明会用として一旦12分に編集した。
ナレーターは私、音楽はフリーユースで対応した。
それでも十分に使用に耐えるから恐ろしい。
その後、初夏に1日、9月17~18日に2日間の泊まりロケをして、
都合5日間でクランクアップした。
手応えは十分にある。編集も楽しみだ。
こんな時はたいてい名作になる。
私は編集前に必ずナレーターを決める。
このナレーターならこうシャベル。あのナレーターならこんな感じと、
ナレーターに合わせて編集する。
ナレーターの個性や間の取り方、読みのスピード等を
編集にあらかじめ反映させる。
だから選んだナレーターによって、
語尾を「です・ます調」にしたり「である調」にするし、
「主観調」「客観調」にもする。
大した話ではないと思うかもしれないが、
「です・ます調」と「である調」では作品の性格がゴロリと変わる。
また主観的ナレーションと客観的ナレーションでは
視聴者の位置まで変わるし、使うカットまで変わってくる。
映像作品は通常、スポンサーにイメージを伝えてから見積を作成し、
ロケに入るのが基本だが、
私の場合はラブレターと意気込み(=口先)だけで
見積提示してロケに突入する。
「ドキュメンタリーとは発見だ」と現場でジタバタするので、
予め頭の中で作った台本は意味を成さない。
撮影中も都度都度で横路に逸れるが、
それこそがスポンサーに近づく唯一無二の近道と確信しているから、
撮り終えてから組み立ることになる。
しかも撮ったものを一通り見たら、さらなる脇道に入ったりする。
「どうする?俺」と撮影素材の解体作業を繰り返して、
撮影前に描いていたイメージに近づける。
勿論、遠ざかることも多々アルし、全く違うこともアル。それでいいのだ。
しかし編集前には絶対に!絶対に!絶対に!ナレーターを決めなければ
編集方針が固まらならない。
実はクランクイン時点で私はナレーターを林順子さんに決めていた。
超ベテランナレーターで、私の節目の作品には必ず登場する。
しかもすべて名作だ。
5月に一時完成した12分モノを早々と7月に郵送している。
しかし、私を悩ませている。
というのも林さんをナレーターに起用した時点で
「です・ます調」「客観張」「泣かせ」となってしまう。
すでに予約を入れた林順子さんに申し訳ないが悩む…
作品のカラーと声質が合うのか?
企業イメージに合うのか?
スポンサーは納得するのか?
視聴者は入社したいと思うのか?
悪魔の囁きに悩まされる。
「どうする?俺」
いずれにしても編集前に決めなければ…。
「どうする?俺」
困った…。。。



















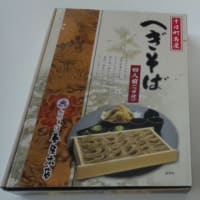
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます