今日は日曜日でした。
日曜日となると、
なんだかバッハが弾きたくなるものです。
(以前にも、同じような書き出しで
記事を書いたことがあるような気がします・・・)
ピアノ弾きにとっては、
バロックで宗教的な調べを堪能するのには
J.S.バッハの音楽はうってつけなのですが、
今日はそんなバッハの鍵盤楽曲の中から
《平均律クラヴィア 第2巻》を開いてみました。
そんな中、
《第9曲 ホ長調E-Dur》
を紐解きながら、そのフーガを目の当たりにして、
バッハの鍵盤楽器以外のための他の曲で、
実に「似ている」ように思える曲を思いついたのです。
それは、
現在シュナイト・バッハ合唱団に参加しながら勉強中の
《ロ短調ミサ曲》の終曲
《Dona nobis pacem(我らに平安を与えたまえ)》
という曲。
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大
(ちなみに、
この曲はミサ曲の途中に出てくる
《Gratias agimus tibi(感謝したてまつる)》
と、
全く同じ音符であることが注目されます。)
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大
「2分の4拍子」???という
滅多にない規模の大きな拍感を有するこの《Dona nobis pacem》と、
《平均律2巻 第9番 ホ長調 フーガ》が「同じ拍感」であること。
さらには、
どちらの旋律も、シンプルな上昇・下降音型という形で
両者が実に良く似ているということを発見したのです。
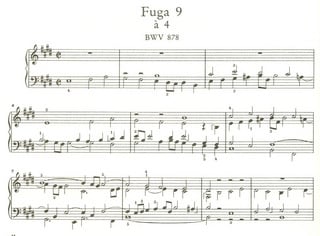 ←クリックで拡大
←クリックで拡大
↑《平均律クラヴィア第2巻 第9番 ホ長調E-Dur フーガ》
鍵盤楽器のための《平均律クラヴィア》を弾きながら、
《Dona nobis pacem》
人類の「平安」を願う、という
孤高の気持ちが反映されるとするならば、
この鍵盤楽器奏者たった一人によってのみ奏される音楽にも、
壮大な、心満たされる音楽の可能性を愉しむことが出来るように
思われたのでした。
同じ作曲家の(あるいは作曲家の枠を超えて)
さまざまなジャンルの音楽を知り、
その相互関係・類似関係を見つけることは、
非常に興味深く・面白く・満足感の高いもののように思われます。

P.S.
ちなみに、この大曲《ロ短調ミサ曲》の最後を飾るこの音楽
《Dona nibis pacem》の
最後の「音符」を初めて見たとき、
なんとも言えぬ壮大さ、まさにキリスト教世界を現す
「神と子と精霊」が「記譜法としても」現されているかのように思われ、
感動したのを思い出しました。
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大
これを歌うとき、これを聴くとき、
すなわち、この大曲の最後に至ったとき、
人は、
きっと、大いなる感動に包まれることができるのではないでしょうか、
バッハは、それを望んで、楽譜に記す方法としても、
その可能性を体現せしめたのかもしれないと、そんな想像が
頭の中をよぎったのでした。
さらにはその感動は、
キリスト教というひとつの宗教の思想でありながらも、
その枠に限定されない、人智を超えた「神」や「精霊」といった
自然界そのもの・あるいはそれを超越するイデアルな世界を
音楽を通して間近に感じることが出来るような、まるで
「奇跡」ともいえる瞬間を、我々・人間・皆に与えられている
普遍的な境地からくるものであるように思われるのです。
日曜日となると、
なんだかバッハが弾きたくなるものです。
(以前にも、同じような書き出しで
記事を書いたことがあるような気がします・・・)
ピアノ弾きにとっては、
バロックで宗教的な調べを堪能するのには
J.S.バッハの音楽はうってつけなのですが、
今日はそんなバッハの鍵盤楽曲の中から
《平均律クラヴィア 第2巻》を開いてみました。
そんな中、
《第9曲 ホ長調E-Dur》
を紐解きながら、そのフーガを目の当たりにして、
バッハの鍵盤楽器以外のための他の曲で、
実に「似ている」ように思える曲を思いついたのです。
それは、
現在シュナイト・バッハ合唱団に参加しながら勉強中の
《ロ短調ミサ曲》の終曲
《Dona nobis pacem(我らに平安を与えたまえ)》
という曲。
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大(ちなみに、
この曲はミサ曲の途中に出てくる
《Gratias agimus tibi(感謝したてまつる)》
と、
全く同じ音符であることが注目されます。)
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大「2分の4拍子」???という
滅多にない規模の大きな拍感を有するこの《Dona nobis pacem》と、
《平均律2巻 第9番 ホ長調 フーガ》が「同じ拍感」であること。
さらには、
どちらの旋律も、シンプルな上昇・下降音型という形で
両者が実に良く似ているということを発見したのです。
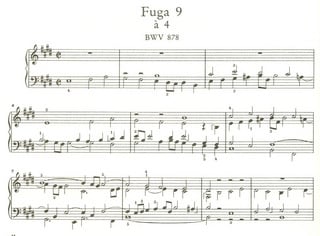 ←クリックで拡大
←クリックで拡大↑《平均律クラヴィア第2巻 第9番 ホ長調E-Dur フーガ》
鍵盤楽器のための《平均律クラヴィア》を弾きながら、
《Dona nobis pacem》
人類の「平安」を願う、という
孤高の気持ちが反映されるとするならば、
この鍵盤楽器奏者たった一人によってのみ奏される音楽にも、
壮大な、心満たされる音楽の可能性を愉しむことが出来るように
思われたのでした。
同じ作曲家の(あるいは作曲家の枠を超えて)
さまざまなジャンルの音楽を知り、
その相互関係・類似関係を見つけることは、
非常に興味深く・面白く・満足感の高いもののように思われます。

P.S.
ちなみに、この大曲《ロ短調ミサ曲》の最後を飾るこの音楽
《Dona nibis pacem》の
最後の「音符」を初めて見たとき、
なんとも言えぬ壮大さ、まさにキリスト教世界を現す
「神と子と精霊」が「記譜法としても」現されているかのように思われ、
感動したのを思い出しました。
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大これを歌うとき、これを聴くとき、
すなわち、この大曲の最後に至ったとき、
人は、
きっと、大いなる感動に包まれることができるのではないでしょうか、
バッハは、それを望んで、楽譜に記す方法としても、
その可能性を体現せしめたのかもしれないと、そんな想像が
頭の中をよぎったのでした。
さらにはその感動は、
キリスト教というひとつの宗教の思想でありながらも、
その枠に限定されない、人智を超えた「神」や「精霊」といった
自然界そのもの・あるいはそれを超越するイデアルな世界を
音楽を通して間近に感じることが出来るような、まるで
「奇跡」ともいえる瞬間を、我々・人間・皆に与えられている
普遍的な境地からくるものであるように思われるのです。





















