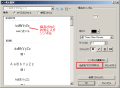前回の続きのような、そうでないような、Q&Aのお話。
けーじ板で回答をつけるということは、ある意味ユーザサポートに近い活動であることがある。
あるとき学会でけーじ板の活動について発表したら、GISソフトウエアベンダー(たしか技術職)の人から質問があった。
「なんでQ&Aなんて、やってるんですか」
かなり前のことなので、表現はもう少し違っていたかもしれないが、Q&Aなんてめんどっちいこと、なんで自ら身を投じているのか、そういう趣旨の質問だったと思う。
なんでって、けーじ板とQ&Aじゃ全然ちがうし、なにより自分が楽をしたいからなんだけど、そういうような答えでは質問をした人は微妙に納得していない感がただよっていた。
確かに、サポセン業務はとても疲労するのはよくわかる。
まだのどかだった時代だけど、私もサポートしていて結構疲れた。自分の無知、無力さに泣き、まだ新人の自分にユーザサポートをやらせる上司を恨んだ(笑)。
でもあるときから、「こんな私が窓口になっちゃう会社なんです。でも、あなたの質問には(時間も体力も他の仕事との兼ね合いも含めて)可能な限り対応しますよ」と、開き直ったけど。
それでも気分的につらい面はあったけど。
例えば、ユーザさんから「サポートしてもらわないと使えないこんなソフト売るおまえが悪い」、「こんなバグだらけのものを売ってどういうことだ」的感情を裏に抱えて質問されると、普通のやりとりですらできなくなる。
私がプログラミングしたのでも、営業したのでもないけれど、現段階で会社の窓口として私がユーザさんとお話をしているのなら、そのようなお話もお聞きする。聞くだけで何もできないことも多いけど、質問を受けた側はできることをやるしかない。
その渦中にいると、ストレスいっぱいの生活が続くこと間違いなし。そんな経験をした人なら、冒頭のような「なんでQ&Aなんて」という質問をするのもよくわかる。
でもね、そこから一歩引いてみると、質問をする人がみんな怒りまくっているわけではないことがわかるはずなのだ。さらに、もう一歩引いて、よく質問されることをみつけてそれを解決する何か、例えばプチ講習会とかを企画すれば、そこでまた一儲けできるはずなのだ。
最前線でユーザさんとお話をしている人には、一歩引くまでの余裕はないのは明らかだ。私も今だからそんなことを思いついただけだし。
もしできるならちょっと上の先輩とか上司とかが、Q&Aのやりとりを元に、今お客さんが何を求めているか分析してみると何か発見があるかもしれない。
しかし、うーん、むっかしいかな(笑)。もろもろ。