
2月11日は日本の「建国記念の日」です!

2月11日は日本の国民の祝日の一つ、すなわち「建国記念の日」です。この祝日は「記念日/きねん日」ではなく、「記念の日/記念の日」であることをご存知ですか?(どちらも同じ意味、つまり記念日です)。「建国記念の日」に「の」が入っているのはなぜですか?「建国記念日」とどう違うのですか?
この記事では、この2つの言葉のそれぞれの意味や、「建国記念日」がいつなのか、日本の祝日となった由来や歴史などを解説します。
日本の「建国記念の日」を垣間見る。

2月11日はもともと「紀元節」と呼ばれ、『日本公文書館』には日本の初代天皇とされる「神武天皇の即位の日」を表していました。しかし、第二次世界大戦後、1948年に連合国最高司令官「GHQ」が「紀元節を開催すれば帝国を中心とした日本国民の団結が高まる」と考え、「紀元節」という言葉は廃止されました。1966年に「建国記念日」が「建国の延長と国家への愛を育む日」と定められた。
日本の「建国」は単なる神話?

日本の公文書館には神武天皇が初代天皇になったと書かれています。 現在の建国記念の日に戴冠したと言われている 。しかし、歴史上、神武天皇は実在の人物ではなく、あくまでも「神話」として位置づけられているようです。神武天皇は実在の人物ではなく神話上の人物であり、2月11日は「正確には日本国家建国の日ではない」と主張する人もいる。
「建国記念の日」の文字に「の」が入っている理由

海外では、独立記念日やフランス革命記念日など、明確に定義できる日時を「記念日」と定義しています。別の例として、インドネシアの独立記念日は、日本から独立した 1945 年 8 月 17 日に定められました。
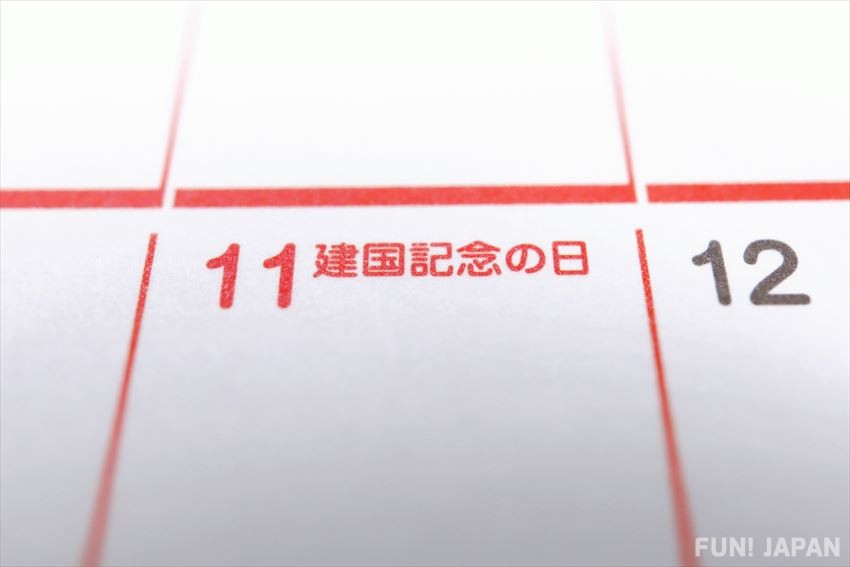
しかし、日本には独立記念日も革命記念日もありません。この国の建国日時を特定することは困難です。そのため、「建国記念日」ではなく、単語の間に「の」を入れて今日を「建国記念の日」として祝うのですが、どちらもニュアンスが異なります。同じものです。
つまり建国記念日は、日本が誕生した「日」を祝う日ではなく、日本の「国」が建国されたことを祝う日なのです。











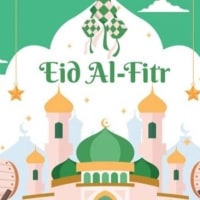








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます