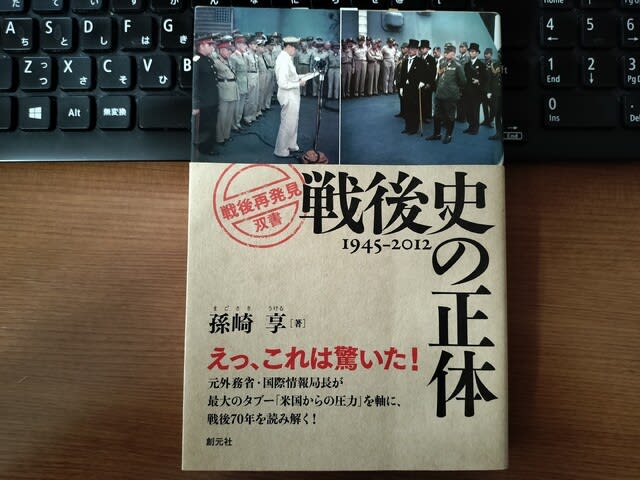青山透子氏の『 日航123便 墜落の波紋 そして法廷へ 』という本を読みました。
未だ全容が解明できていない39年前の事故(事件)についての本です。
内容は
はじめに
第一章 「外国人遺族」
第二章 隠蔽の法則
第三章 情報公開への道
おわりに 次世代へ
というものです。
ネット上では、日航ジャンボ機墜落事故について、臆測も含め様々な話題が飛び交っています。
そんな中、墜落事故の外国人遺族とのやりとりから、この事件を風化させまいとする著者の強い信念が伺える内容でした。
特筆すべきは、その一つ一つが単なる臆測や想像ではなく、専門家の見解をもとに事実を積み上げたものであることです。
筆者自身は、もと日本航空の国際線客室乗務員で、国内線乗務の時日航機墜落事故の客室乗務員と同じグループに所属していました。退職後、接遇教育や人材育成プログラム開発及び講師となった後、日本航空123便墜落事故の事故調査委員会の調査に疑問を持ち、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程を修了、博士号取得されたという方です。
日航123便墜落事故においては、日本では裁判は一切行われず、誰も刑事責任を取らないまま公訴時効が成立している・・・ということに驚きました。
そのため、その全容が未だはっきりしない様です。
そのことにより、事件に関する多くの情報や証拠品は国民の眼に触れることがないままです。
総務省でも「情報公開とは、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。」と謳っているにもかかわらず、その実態は作為的で情報保有者の都合により著しく客観性を損なったものとなってしまったようです。
それ以外にも同様のことは多く繰り返されており、森友の公文書改ざん事件などは論外ですが、ほぼ前文を黒く塗りつぶした文書の公開や、プライバシー保護などと云って米兵の婦女暴行事件を県側に伝えなかったりなど枚挙に暇がありません。
(公開する内容を情報所有側が一方的に決めるという点では、徹底されているとも云えるのですが・・・)
読んでいて多くの発見に出逢える本でした。
発見の一つ・・・『ブラック・スワン理論』