
コロナ、うつ、受験勉強
コロナ以後、勉強だけの学生生活になった。特にこの患者のように、ガリ勉でもなく、学校行事や部活を純粋に楽しむタイプの人にとって、きつい日々だろうと思う。気が滅入って抑うつ的になったとしても不思議じゃない。実際、コロナ以後、自殺者は増加の一途である。コロナが人を殺しているのではない。コロナ対策が人を殺している。行政はいい加減、この現状に目を向けたらどうだ。
治療はどうすればいいか。一番確実なのは、"原因の除去"である。つまり、過剰な(かつ無用な)コロナ対策がなくなって、いつも通りの学校生活、マスク強制や手洗い消毒励行のない日常が帰ってくることが、この人の根本的治療となる。しかし、恐らく今後、かつての日常が戻ってくることはないだろう。マスコミや御用学者に言われるままにコロナワクチンを接種したとしても、「マスクしろ、距離をとれ、三密避けろ」の大合唱が止むことはない。
だとすれば、どうすればいいか。世界が変わらないなら、自分が変わるしかない。「勉強ばかりの毎日なら、いっそ勉強を楽しんじゃうのはどうかな」とアドバイスした。
勉強を楽しむ、ということの意味は、すでに分かっているよね。
競技かるた部所属、というところがいい。たとえば百人一首。あれを暗記の対象として、古文の先生に覚えろって言われたら、こんな苦行ってない。いろんな屁理屈をこねて拒否する人もいるだろう。「今誰も使ってない千年前の古臭い言葉を覚えて何になる。交通標語じゃあるまいし五七五のリズムとかバカみたい」それでも、試験に出るから、ということでどうしても覚えなきゃいけないとなれば、念仏みたいに丸暗記する人も出てくるだろう(本当は念仏にだって意味があるんだけど^^;)。
ところが、内容に目を向けると、どうだろう。「君がため惜しからざりし命さへ 長くもがなと思ひけるかな」"君のためなら死んでもいいと思っていたが、恋愛の成就した今、長く生きたいと思っている"。ラブレターに出てくるフレーズそのものだ。こんな句を送られた女性は、キャーキャー叫んで喜んだに違いない。うれしさのあまり、他の宮中女官に自慢して見せびらかしたかもしれない。これを詠んだ藤原義孝は三十六歌仙の一人、和歌の名手だったが、しかし、20歳の若さで死んだ。「長くもがな」は義孝の実感のこもった言葉でもあっただろう。
無味乾燥な棒暗記の対象と見れば実につまらないが、意味や背景が分かればこんなにおもしろいものはない。百人一首は、ほとんどが恋を詠んだもの、つまり、千年前のラブレター集である。誰がどういう心境で詠んだのか、分かった方がもっとおもしろくなるし、さらに、どういう修辞技法をこらしているのか、どのあたりが句として秀でているのか、選者の藤原定家がどういう思いで百首を選定したのか。知識が深まるほど、だんだん楽しくなる。
学校とか塾の先生は、多分、逆の勉強法を教えると思う。「いいか、試験に出るのはこれだけだ。ここだけ抑えとけ」
先生の気持ちはわかる。何かを暗記するとなれば、暗記量は少なく済むほうがいい。覚えるべき情報量を絞って、「ここだけ覚えとけ」って言われたほうが、一見勉強がはかどるようにも思える。
でもこの勉強法の最大の欠点は、勉強が"作業"になることだ。意味も分からずひたすら棒暗記。こんな勉強、やっちゃダメだよ。
周辺的な情報は、多ければ多いほどいい。遠回りのようだけどそのほうが記憶が定着しやすくて、結局能率がいい。こんなこと、いまさら言われなくても、すでに知ってるよね?
ポケモンの何百種類とあるモンスターを、子供たちは自然と覚えてる。絵柄、名前、いろいろな属性。無理やり暗記したわけじゃない。アイドルおたくの青年。AKBの全員の顔、名前、出身地、誕生日、趣味。そういうデータが頭の中に当然のように入っている。
「こんなに覚えなきゃいけないの?」じゃない。周辺的な情報があったほうがイメージが膨らんで、核心の情報(いわゆる"テストに出る部分")の記憶が、むしろはかどる。
暗記物と思われがちな日本史や世界史でも、年代をやみくもに暗記するだけ、みたいな勉強はいけない。歴史というのは結局人間の歴史なのだから、人間に注目するといい。
たとえば幕末から明治にかけての日本史は、伊藤博文の行動に注目する。「グラバーをスポンサーとする長州ファイブの一人としてイギリスに密航、留学。長州戦争を知り帰国。御所に忍び込み孝明天皇を暗殺。明治維新の立役者で初代内閣総理大臣。ちなみに初代兵庫県知事でもある。無類の女好きだったが、残念、神戸には色町がない。そこで作らせたのが神戸福原の歓楽街。一人身の寂しい神戸在住の男性が福原で女性の情けを受けられるのは、伊藤博文の残した知られざる遺産である」
断言するけど、こんな情報はテストに出ない。グラバーとかのフリーメーソンやロスチャイルドが日本で暗躍した事実は教科書で一切触れられていないし、孝明天皇暗殺説も絶対教えられない。それは、すでに終わった"歴史"ではなく"現代"と直結していて何かと不都合だから、という事情もあるだろう。
でもさしあたり学生にとって大事なのは、こういうのが史実かどうか、ではない。イメージを膨らませてくれる手段として、こういう情報を利用しない手はない、ということだ。
イメージを作って、暗記を少なく。これが勉強の基本だよ。
数学は暗記だ、という主張がある。
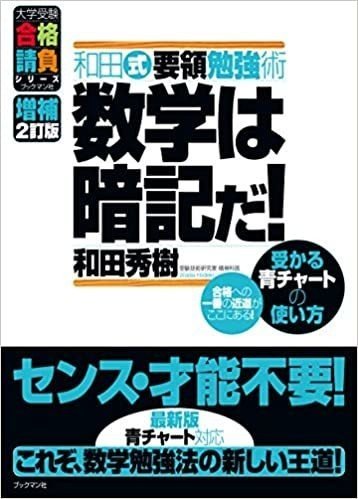
これはひどい。暗記される数学がかわいそうだ。考えるのが数学の楽しさなのに、暗記なんかで済ませたら、楽しみがなくなってしまう。『高級フレンチを噛まずに飲み込む方法』という本があったとしたら、誰しもバカげていると思うだろう。この本は、それと同じくらい、バカげている。
数学を得意になる方法は、ひとつである。それは、数学にどっぷり漬かることだ。わからない問題があれば、簡単に解答を見ないで、ずっと考える。食事をしながら、風呂に入りながら、寝る前にも、ずっとその問題を考える。英語とか国語とか他の科目の勉強してるときは、それに集中すればいいよ、もちろん。でもそれ以外の隙間の時間は、その数学のことをずっと考える。考えた末にピンとひらめいて解ければいいし、一日そんなふうに考えても解けなければ、解答を見る。ろくに考えずにぼんやり解答を読むのとでは、全然理解度が違っているだろう。問題をムダにたくさん解いても意味ないよ。それより、思考の深さだよ。
こんなふうに「毎日ずっと数学の問題を考える」という習慣を何か月も続ければ、そのうち数学のことが好きになっている。
数学者の岡潔が言ってた。「人は極端に何かをやれば、必ず好きになるという性質をもっています。好きにならぬのが不思議です」
勉強は本来楽しいはずなんだよね。自分の知らないことを、知っていく。未知が、既知になっていく。知識が増えたり、思考力が高まったり。こんなに楽しいことってないじゃないの。
勉強が苦しいのは、勉強が本来持っているはずの楽しさを感じられないせいだ。なぜ感じられないのか。それは、勉強を"強制されている"という意識のせいかもしれないし、評価の対象になっているせいかもしれない。
僕は将棋が好きだけど、将棋が学校の必修科目になって『試験に出る定跡』とか覚えさせられたり、僕の勝率の変動について進路指導の先生からいちいちコメントされたとしたら、うんざりして将棋をやめるかもしれない(笑)
いろいろしんどいと思うけど、マイペースでいいからね。周囲の評価なんて気にしなくていいよ。勉強が苦しいって思い始めたら、黄色信号だと思ってね。本来、勉強はそんなのじゃなくて、楽しい奴だから。
うつっぽい感じには、マグネシウムをしっかり摂って、あとゲルマニウムもいいよ。
とにかく気楽にね。
【転載おわり】






















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます