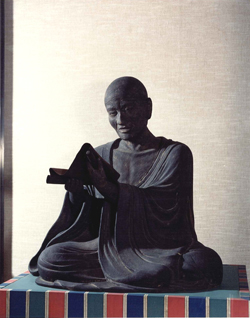15、世界遺産;厳島神社の概説 「厳島神社と清盛の時代感覚」




旅の記録;「日本一周」へリンクします
平安時代の貴族とは、一風変わった清盛の美的感覚、
“猛き者もついには滅びぬ”、平家物語で平清盛を語るとき、武士として又は政治家としての清盛にスポットが当てられることが多いようです。
一般的に歴史イコール政治史になってしまうので、それもやむを得ないのかも知れませんが、人間としての平清盛を語るには、これでは不十分といえます。
其れは清盛はその生涯の中で、単なる“時代の掟破り”の独裁者では成し得なかったであろう、偉大な文化的業績を残しているからです。
平家・清盛はほんの20年ほどの栄華でしたが、そのわずかの間に、平家文化ともいえるものを現出させ、それが今日に伝えられているというのは不思議な感じもするのです。 これらは古い慣習や偏見にとらわれない清盛の非凡さと美的感覚から生み出されたと言ってもよいでしょう。
因みに、平家の時代と言うのは平治の乱の勝利(1159年)から壇ノ浦での滅亡(1185年)まで26年間、または平清盛太政大臣就任(1167年)から平家都落ち(1183年)まで16年間、ほかにもいくつかの考え方があると思いますが、いずれにしても20年程度です。
短いですよね。
一切経を書いた石を沈めて島の基礎とした「経が島」(日宋貿易の拠点である大輪田泊、当時の摂津国に交易の拡大と風雨による波浪を避ける目的で築造された人工島)の改修を行いました。
つまり、船を風から守ろうとしたもので、この島が「経ヶ島」(経の島)とも呼ばれています。
その広さは平家物語によると、「一里三十六町」とあることから、現代の大きさで37ヘクタールほどと推定されています。
工事は六甲山系の山を切り崩した土で海を埋め立てたが、それが難航したために迷信を信じる貴族たちが海神の怒りを鎮めるために人身御供をしたとも言われています。
又、清盛は石の一つ一つに一切経を書いて埋め立てたともいい、従って、この島を「経が島」と呼ぶようになったという。
ただし、実際の工事は清盛生存中には完成せず、最終的な完成は平家政権滅亡後に工事の再開を許された東大寺の重源によって建久年間に完成したとされています。
尚、現在では、度重なる地形変化等により場所が特定できず、凡そ、神戸市兵庫区の阪神高速3号神戸線以南・JR西日本和田岬線以東の地であるとみられている。
同時に、清盛は国家的事業として大輪田泊の大規模な整備を計画しましたが、源平争乱によりほとんど実行されなかったと思われます。
次回、「清盛の美の傑作・厳島神社」

「日本の世界遺産の旅の記録」へリンクします

【小生の主な旅のリンク集】
《日本周遊紀行・投稿ブログ》
NatenaBlog(ハテナ・ブログ) GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ
《旅の紀行・記録集》
「旅行履歴」
日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行
【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群
東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌
【山行記】
《山の紀行・記録集》
「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)
《山のエッセイ》
「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」