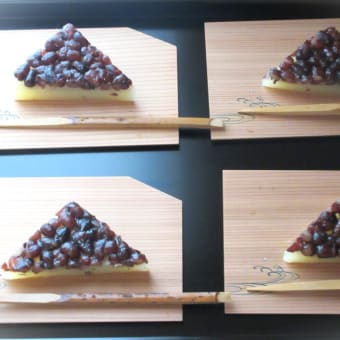今日は
大阪谷町九丁目の願生寺で
毎月行われている
融和会の月釜に出かけて参りました
融和会のお茶会に
参会させていただいたのは
今日が初めてでしたが
常連の茶友は
もう四十年通っているとのこと
大阪の
歴史あるお茶会の一つなのだと
教えていただきました
願生寺は
地下鉄谷町九丁目の駅から
数分歩いたところにありました

今日の席主は
高橋史郎氏でした
寄付きの掛物は
幕末の頃
菅原道真公950年遠忌の際に
大綱和尚によって
書かれたものでした
その前には
分厚い「昭和北野大茶湯」の一冊が
置かれていました
「昭和北野大茶湯」は
天正15年
豊臣秀吉公の開いた「北野大茶湯」から
350年を記念して
昭和11年に
開かれた茶会だそうです
当時お席の顧問をされた
各流派の宗匠方のお顔写真の頁が
開かれておりました
北野天満宮では
「北野大茶湯」に由来して
毎年12月1日に
献茶祭が行われているそうです
今年は
表千家の堀内宗完宗匠が
ご担当されるとのこと
今日の融和会の道具組は
その北野天満宮に因み
「梅」の意匠が
取り合わされていました
本席の掛物は
美しい料紙に
即中斎宗匠お若い頃の筆で
大河内躬恒の歌
「 心あてに 折らばや 折らむ 初霜の
置きまどはせる 白菊の花」
その前には
膳所の砧花入れに
一本の白菊
表千家御家元の
寂しさに寄り添われる
席主様のお気持ちが感じられました
あらためて
お席を振り返りますと
梅と菊のお取合せに
「茶の湯には梅寒菊に・・・」の一節が
ふと思い出されます
いずれにしても
取り合わされたお道具に
席主様の思いが込められた
格調の高いお席でございました