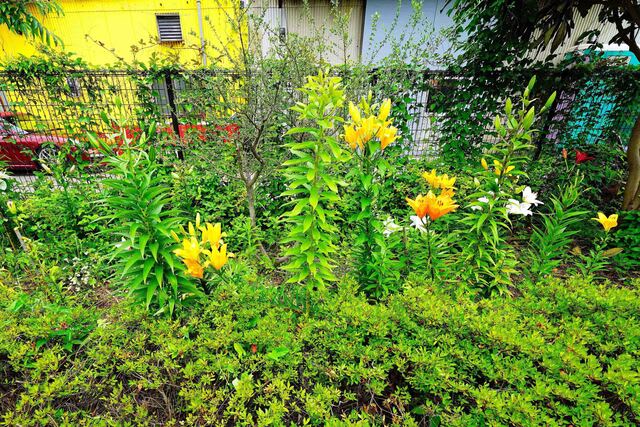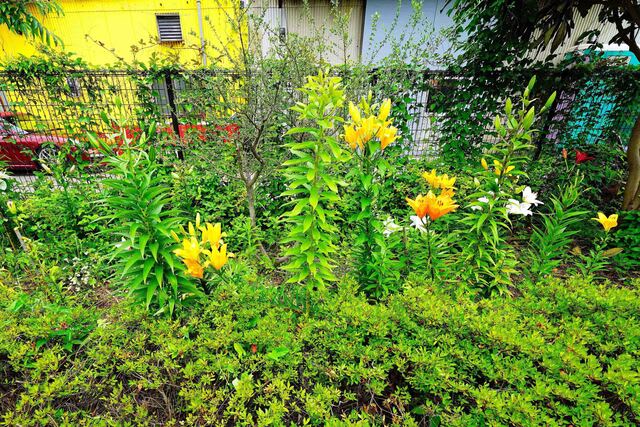新羽地区健民祭実行委員会のこれまでの経緯について(役割については第25回以降)
第25回大会(1998年 平成10年)の長澤茂大会会長 堀内猛実行委員長(第3代体指会長)の時から、組織の内容、全体会を含めたやり方、進め方、競技一覧などの書類の様式は前回の46回大会(2019年 令和元年)まで21年間ほとんど変わっていません。
【健民祭実行委員会実行委員長は体育指導委員連絡協議会会長が務める理由】
横浜市スポーツ振興審議会(昭和37年3月31日条例第8号)での審議に基づいて、昭和40年中ごろから横浜市各地区で健民祭が開催されるようになりました。
この審議会には、横浜市体育指導委員(現スポーツ推進委員)が深く関わっていたことから、健民祭は体育指導委員が中心となって地域のイベントとして実施されてきました。このような経緯から、新羽地区でもスポーツ推進委員(旧体育指導委員)連絡協議会会長が実行委員長を務めています。
○横浜市スポーツ推進審議会条例
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000227.html
【町会長が「参与」となった経緯】
健民祭は、横浜市体育指導委員連絡協議会会長が委員である横浜市スポーツ振興審議会の答申に基づいた横浜市のスポーツ推進施策をその起源としているため、体育指導委員の管轄であった教育委員会から市民局を通して各区役所に対して、区長及び各区体育指導委員連絡協議会が中心になって各地区連合町内会長に健民祭を実施するよう要請されました。体育指導委員の立場としては、「横浜市のお墨付き」である健民祭(運動会)を地区全体で実施するよう連合町内会にお願いをしたものです。
そういった事情から、新羽地区健民祭実行委員長は地区体育指導委員連絡協議会会長が務め、町会長は来賓相当の「参与」として本部役員となった経緯があります。
【中学生のボランティアについて(2018年度で無くなりました)】
15年ほど前に、中学校校長先生より、「子供たちに地域のボランティアを経験させたい。何か手伝えるものはないだろうか。」とのお話しがあり、「ならば、会場が中学校の健民祭なら子供たたちも勝手はわかっているのでいいのではないでしょうか。」ということで始まりました。ただ、いざ学校で募集してみると、当初予定していた野球部だけでなく、他の部活の先生からも要望があって、大変な人数になってしまいました。
あまりにも人数が多くて、実行委員会スタッフだけでは責任を持って面倒みることができないので、校長に相談しましたところ、野球部の顧問の先生が子供たちを統括していただくことになり、改めてお引き受けすることにしました。その後は、毎年度ご意向を確認して、可能とのお返事があれば、「もしよろしければ、今年も若いスタッフのご協力をお願いします。」と、大会会長から依頼するという形で継続していました。
2018年度に合唱コンクールが健民祭の翌週になったことから、2019年からは、このボランティアは進行の放送のみを実行委員会よりお願いさせていただくということになりました。
【新羽地区健民祭実行委員会の役割分担について】
役員は、大会会長(連合町内会長)、実行委員長、副実行委員長2名(青指会長、子供会会長)で、青指会長は進行を務め(ただし、会長本人ではなく青指のメンバーがマイクを握っていました。)、子供会会長は総務と会計を兼務し、町会長の「参与」を含めて11人が「本部」という認識でした。子ども会解散後は、スポーツ推進委員連絡協議会副会長、受付などご来賓を担当される町会役員の方に副会長を依頼。
係は、現場競技関係のスタート、ゴール、用具は体育指導委員が責任者を務め、後方支援系の庶務、賞品、接待、記録は青少年指導員が責任者を務めていました。進行は後に年青少年指導員が責任者を務める係として追加されました。
受付は、連合町内会長が町内に顔の広い各町会で総務などの役員を務めておられる女性の方にお願いして責任者を務めていただいてました。後年、青少年指導員の女性メンバーが責任者を務めてくださることも多くなりました。
ここまでが「実行委員会」という認識です。
会計は、25回大会から連合町内会が決めた責任者、もしくは青指会長が務め、実務は体育指導委員連絡協議会の書記が行いました。この時から、各係への資金の前渡しを「前渡金」と呼ぶようになりました。その後、書記が体育指導委員連絡協議会会長に就任した際、体育指導委員連絡協議会の会計が健民祭の会計責任者を務めています。
子供会会長の役割であった総務は、一時は庶務係が務めることになりましたが、庶務係の責任者であった元青指会長から、「負担があまりにも大きすぎる」との申し出があったことから、体育指導委員の書記が務め、庶務係は廃止されて総務係が追加されました。後に、書記担当が連絡協議会会長に就任したことから、総務係が廃止され、以後実行委員長の役割となっています。
会場設営は、トラックにかかってしまうマウンドを一時的に平坦にしていたことから、長澤英雄元体育指導委員と大森元青指協会長が中心となってトラックの設営を行っていましたが、マウンドの移設ができなくなり、長澤氏が体育指導委員を退任されたため、新たに会場設営係として新設して、引き続きトラックの設営は長澤氏にお願いしています。
町会責任者も当時からありますが、当時は実行委員会の一員でなく、本部役員名簿にも記載されていませんでした。
【全体会で実行委員会が組織されるまでの準備】
第25回当時、長澤茂連合町内会長の下で堀内猛体育指導委員連絡協議会会長が実行委員長、大森洋一青少年指導員協議会会長と白岩金男連合子ども会会長が副実行委員長でした。7月初旬に白岩組の事務所に集合して、当該年度健民祭の実施方針を確認することから健民祭開催への準備が始まりました。
全体会は9月第一週に旧中央町内会館で実施されていましたが、後年は8月最後の週に中之久保町内会館で実施しています。こういった一連の流れと各書類の書式については、当時からほとんど変わっていません。
当時、各町会から本部役員を出していただく際、各町会長の皆さんにはすでに意中の人が決まっていたこともあり、すぐに本部役 員が集まりました。そういった事情もあって、7月に最初の確認をしても9月初旬の全体会までに本部役員名簿を印刷することができました。また、協賛企業についてもほぼ確定していたため、プログラムも全体会までに印刷できました。
しかし、後年は全体会が8月末になり、本部役員を引き受けてくださる方が少なくなったことことから、6月、7月の各町会定例会で本部役員を選出できるよう、ひと月ほど早い6月に各町会に本部役員の選任を依頼するようになりました。
また、プログラムに広告を掲載しているにも関わらず協賛いただいていない企業があったことから、後年は広告ではなく、協賛企業名を掲載するだけになりました。
5月
本部役員要員計画 前年の係責任者より必要と思われる係の人数を確認
スポーツ推進委員連絡協議会で前年度の反省を踏まえて競技内容の確認
6月
各町会に本部役員選出依頼 要員計画に基づき各町会に選任を依頼
必要に応じて前年度の町会責任者から意見を聴取
7月
各町会より本部役員の選任される。
不足分について、OBなど各方面に依頼する。
競技について最終的な詰め、必要あれば町会責任者から意見を聴取
8月
本部役員人員計画 係の責任者を決め、過去の経験、実績、希望などから要員割振る
本部役員名簿作成、ポスター作成、プログラム作成、競技一覧作成 印刷
企業への協賛依頼を作成し一部郵送
健民祭口座より前渡金額を出勤し各係ごとに分ける(会計)
係の責任者に本部役員名簿を配布
係の責任者は自分の係の業務マニュアルを用意
係の責任者は全体会で説明できる準備計画を作成
町会分担金を徴収(会計)
タオルの在庫を確認(会計)
全体会を実施
【全体会】
各係ごとに机を配置。
各係ごとの札を机の上に配置
各係ごとの名簿を会場に掲示。
受付で町会責任者より町会分担金を徴収
受付で町内会掲示板に掲出するポスターを町会責任者配布
受付で各町会の駐車賞を配布
進行は副実行委員長(が多い)
連合町内会長のあいさつ
実行委員長のあいさつ
本部の紹介
参与の退席
各係責任者、メンバーの紹介
各係責任者に活動費前渡金を支払い、駐車証の配布
各係ごとに顔合わせ、打ち合わせ
【実行委員会組織後(全体会終了後)の経緯】
9月
全体会後は、各係ごとに準備が進められます。
実行委員長、副実行委員長で企業回り。副実行委員長と賞品係で協賛物品の回収
⇒近年は企業回りは実行委員長が、物品の回収は副実行委員長と賞品係が実施
※⇒毎年のように企業との関係を構築して賞品をいただける企業を増やし、回収した賞品を賞品係の責任者に引き継いで、健民祭当日までに競技ごとに振り分けるの仕組みは、大森洋一元青指会長が作り上げました。
10月 健民祭前日は13時より前日準備で、テント設営、トラック設営などの準備実施。
<各係の役割>
【総務(実行委員長が兼務)】
当初は、副実行委員長(連合子供会会長)が担当
⇒青指庶務係が引き継ぐ
⇒庶務係の負担増との申し出で体指書記が作業を実施
⇒庶務係廃止して総務係新設し体指書記が責任者に就任
⇒体指書記が体指協副会長に就任したが、そのまま担当
⇒副会長が地区体指協会長に就任したため、実行委員長の職務
〇前年度各係の責任者に必要な要員(人数)を聴取
〇各町会に本部役員選出の依頼
〇係の責任者にヒアリングして本部役員人員計画作成
〇スタッフ不足分をOBなどに依頼
〇本部役員名簿の作成
〇ご来賓者名簿を作成して各町会にチェックの依頼
〇松村整形外科、大角委員に救護のお願いに行く
〇新田小学校特設音楽クラブの出演を依頼
お弁当の数を接待係へ報告
※近年は新田小学校運動会と重なってしまうため出演なし
〇最終的なご来賓名簿を作成して受付、進行、接待へ
〇出場カードの作成(町会割り当て数の確認、町会対抗競技の確認)
〇競技一覧作成(変更箇所については必要に応じて町会責任者を招集し説明)
〇ポスター作成と印刷
〇プログラム作成と印刷(協賛企業名のチェック)
〇駐車許可証の作成
〇ご来賓案内作成
〇賞品・協賛のお願い作成
〇協賛企業お礼状、お弁当引換券の作成
〇協賛企業まわり
〇協賛企業のお願い郵送
〇協賛企業回り
〇賞品、協賛金の回収
〇賞品の賞品係への引継ぎ
〇芳仕者へのお礼状作成
〇最終的にお弁当の調達数を接待係と調整
〇当日の駐車禁止看板、本部、受付、ご来賓席、トイレ、禁煙などの案内板の用意
〇全体会でのポスターとチラシの各町会への配布
〇芳仕者への返礼品(タオル)を調達し、必要数を接待係へ
【会計】
当初は、副実行委員長(連合子供会会長)が担当
⇒25回大会から34回大会まで責任者は連合町内会長の指名、もしくは、青少年指導員協議会会長が務め、実務は体育指導委員連絡協議会書記が担当。35回大会は体育指導委員連絡協議会書記が責任者と実務。36回大会からは、体育指導委員連絡協議会の会計が責任者を務め、実務も担当しています。
46回大会の責任者はスポーツ推進委員連絡協議会会計
〇企業回り用の領収証を準備(近年は総務で準備している)
〇企業回りでいただいた協賛金を実行委員長から回収して入金
〇全体会で各町会から町会分担金を徴収(領収書発行)
〇前回大会の決算書及び各係責任者からのヒアリングで前渡金額を決定
〇前渡金受領証の作成、各係用の決算報告書様式を作成
〇全体会で各係に前渡金を支給し押印された前渡金受領証を保管
〇企業からの協賛金振り込みをチェック
〇当日芳仕者、協賛企業、領収証を準備
〇当日の芳仕者からのお金の入金について、農協さんと調整。
〇芳仕者からの寄付金、協賛企業からの協賛金の管理及び出納簿への記帳
〇反省会で各係の精算
〇各係の出納についてチェック、確認
〇決算書の作成
〇会計監査の監査を依頼
〇会計報告を作成し実行委員長に提出
※高額の領収証であっても収入印紙は不用
【令和4年度における町会分担金の算出根拠になる世帯数について】
※各町会の公平を期すため、毎年4月1日に区役所に報告している世帯数を乗ずる
<健民祭で使っている(令和元年度)世帯数と令和4年度現況報告書記載の世帯数>
南町会 450⇒603 +153
中之久保町内会 430⇒310 △120
大竹町内会 200⇒220 +20
中央町内会 580⇒600 +20
自治会 390⇒415 +25
新羽町内会 600⇒647 +47
北新羽町内会 520⇒550 +30
クリオ新横浜北自治会 290⇒319 +29
【進行】
責任者は青少年指導員
マイクパフォーマンスを得意とする青少年指導員が担当
〇中学校と放送機器、マイクなどの道具の借用について調整
〇放送機器の点検、操作確認
〇借用書の提出
〇生徒の応援がある場合は、顧問の先生と調整
〇総務より競技一覧、ご来賓予定者名簿を受け取る
〇ご来賓の役職と氏名を確認
〇競技の内容を確認
〇入場行進、競技中などで必要な音楽、曲を確認し準備する
〇シナリオの作成
〇当日は開会式(受付と連携してご来賓者の確認・紹介)、競技進行、閉会式
〇競技中は競技総括と連携して進行する
〇競技終盤となったら、記録係に賞状の準備などを助言する。
【賞品】
責任者は青少年指導員
⇒企業回りで協賛企業を開拓し、毎年のように企業との良好な関係を構築して賞品をいただける企業を増やし、回収した賞品を賞品係の責任者に引き継いで、健民祭当日までに競技ごとに振り分ける仕組みは、元青少年指導員協議会会長が作り上げた。
〇協賛のお願い、寄贈書を作成
〇必要に応じてオンラインFAXを契約
※副実行委員長宅にFAXがない場合など
〇実行委員長、副実行委員長で企業回り、協賛企業開拓
〇副実行委員長と賞品係で協賛物品、協賛金の回収
〇総務より競技一覧を受け取る
〇競技ごとに割り振り案作成
〇不足分の調達
〇当日、参加者に手渡すことを想定して、賞品の仕分け
〇賞品渡し場所などについてゴール係と調整
〇退場口、賞品の受け取りのアナウンスについて進行と調整
〇大量の賞品を会場に運ぶ
〇会場で競技順に並べる
〇大会終了後、余った賞品を連合事務所に運ぶ
〇賞品の整理、処分(来年度用、スタッフ配布用、処分)
〇買物ゲームの野菜は用具係、お礼用のタオルは総務
【受付】
各町会役員(総務など)の方が責任者
近年は青少年指導員も責任者を務めている。これまで、責任者はすべて女性
〇芳仕者記載帳(署名用紙)を作成する
〇当日受付用備品を用意
〇当日受付用案内板、案内用張り紙を用意
〇当日受付用テント設営、案内など掲示
〇総務よりご来賓名簿を受け取る
〇進行(ご来賓紹介)とご来賓に関する調整を行っておく
※来られたかどうか、代理が来られているかなど
〇領収書を作っておく
〇花掲示板掲出用紙を準備
〇花掲示板掲出
〇芳仕者名簿作成
〇花掲示板の撤去
【接待】
責任者は青少年指導員
〇ご来賓名簿を受け取り、お弁当の数を確認
〇奉仕者分のお弁当の数を確認
〇本部役員分のお弁当の数を確認
〇お弁当を注文
〇飲物、茶、茶菓子などの注文
〇朝のは配達分とお昼前の配達分について確認
〇ご来賓席の準備、テント設営、テーブルとイスの配置など
〇芳仕者への返礼品、シウマイ弁当、飲物とタオルを紙袋に準備する
〇お弁当をスタッフ、係ごとにわけて配布する
〇ご来賓の案内、飲物などの提供
〇ご来賓席の撤収
〇余った食料品、飲物の処分
【競技総括】【スタート】【ゴール】【用具】
責任者はスポーツ推進委員
※競技総括の下で常に3係は連携して準備を進める。
〇前年度の反省を踏まえて競技の見直しを行う。
〇競技の見直しについて町会責任者に説明する。
〇変更点を総務に伝えて「競技一覧※1」の修正を依頼する。
※1資料の内容は新羽町ホームページ「新羽地区健民祭資料」より参照
〇各係において、全体会で連絡先を確認し、連絡用名簿を作成する
〇打ち合わせ日程等を確認する
〇「第99回健民祭競技説明資料(スタート・ゴール)※2」をもとに競技進行の流れについて3係で共有する。
※2資料の内容は新羽町ホームページ「新羽地区健民祭資料」より参照
〇各担当者ごとに役割のわかる資料「担当者資料※3」を作成する。
※3資料の内容は新羽町ホームページ「新羽地区健民祭資料」より参照
〇当日朝最終的に確認すべきこと、説明することの資料を作成
〇雨天対応の資料を作成
〇前日・当日準備するものの確認 以下、一例
1.トランシーバーの疎通確認
⇒ 必要台数(5台)進行1、スタート1、ゴール1、用具2
2.中之久保町内会
1)会館のサイド冷蔵庫 電源 ON + 飲み物を入れておく
2)慰労会飲み物の準備
① お茶2箱500ml × 24本 × 2
② ビール2箱350ml × 24本 × 2
③ サワー24本350ml × 種類別(6) × 4本
④ 日本酒 1本一升
3)当日に小山洋さんへ渡す⇒ 出場者カード、出場者名簿
4)前年度の優勝種目トロフィの返却(持参)
3.学校への借用書(チェックとコピー)
① 小学校借用書
② 中学校借用書
4.各種資料のチェック
① 町会責任者招集タイミング開会式後、午前終了後、どんでん返し、関所破り
② 進行係確認事項
③ スタート係 変更点1名追加
④ ゴール係変更点1名変更
⑤ 用具係伝達事項グランドボール(筆記セット、ライン表示)
5.備品・持ち物
① ブルーシート
② ストップウォッチ2個綱取り、玉入れ、マラソン、綱引き
③ くじ引き24本綱取り
④ ゴール係記録紙 2セット
⑤ ゴール係(競技説明書)最新版
⑥ スタート係(競技説明書)最新版競技案内文章
6.その他
① 中学生協力者の係への振り分け
② 道路のハードル設置 ※ 用具係で必要なハードル数を把握する
〇ゼッケンの運用について調整する 以下、一例
3.グランドボール12 1~12 用具係⇒スタート係⇒ゴール係⇒用具係
9.バラエティリレー20 1~20 用具係⇒スタート係⇒ゴール係⇒用具係
14. 一般綱引き20 1~20 旧ゼッケンを使用する
17. 関所破り20 1~20 用具係⇒スタート係⇒ゴール係⇒用具係
〇競技総括と司会進行との調整 以下、一例
1. 開会式・・・ 選手宣誓
南町会 ( ○○○○ ○○○○ )※今回は2名で実施
2.準備体操 スポーツ推進委員
※準備体操後に ストレッチ体操をする(担当 スポーツ推進 〇〇)
3.町会対抗競技のスタート時には音楽(放送)を停止する。(ボリュームを下げる)
4.選手招集のアナウンスは必ず、2種目前の競技(午前)からコールをお願いします。
午後は1種目前の競技からコール
5.競技終了後ゼッケンをはずしてから各テントに戻るようアナウンスをする。
①(№3)グランドボール
②(№9)バラエティリレー
③(№14)一般綱引き ※今回より マラソン出入口 にてゼッケンを回収する
④(№17)関所破り
6.町会対抗得点競技の終了後は必ず賞品を受け取ってから退場するようアナウンスする
※特に最初の得点競技(グランドボール)で選手が町会に戻ってしまうので注意
※町会責任者にも当日朝、説明をする
7.買物ゲーム(№4)当日参加者は 当日参加プラカード前に 集合して下さい。
(要 アナウンス)
8.バラエティリレー(№9)の選手招集時には 来賓参加者 にもアナウンスする
※競技の前に 来賓者(議員、学校の先生、町会長 など)を対象に競技デモを実施する
9.ドンデン返しゲーム(№10) 各町会の代表者はフィールドに集合して下さい。
(要 アナウンス)
10.大新羽音頭(№11) 音楽CDの準備歯は尾出会長から入手
踊りは連続2回、一般参加もOK
踊る場所はフィールド内
11.午前競技終了後に各町会の町会責任者は本部前に集合させる。
(要 アナウンス)
① 一般綱引きの対戦順の抽選
②午後 の競技の開始時間の決定
12.昼休み(12:40頃) 午後競技開始の20分前
午前中のマラソン(№6)の結果報告をアナウンスする。
(総括より司会者へ結果発表の用紙を渡します)
13.一般綱引き(№14)は競技結果表を進行係で記入後、
直接【記録係】に渡して下さい。
※時間短縮の為、ゴール係が勝ち負けの発表した内容を【進行係】が競技結果表に記入
14.関所破り(№17)・開始前に町会責任者を本部に集合させる。
(要 アナウンス)
※その他
①徒競走(小学生、一般)とクロスカントリーの1位~3位者はゴール係が引率してピロティへ誘導し、賞品を受け取らせる。4位以下者はすぐにフィールド内で賞品を受け取る。
〇町会責任者へ当日朝説明・確認する内容 以下、一例
1. バラエティリレー(一般)の前にやり方のデモンストレーションを実施します。
⇒ 町会責任者、町会長、学校の先生、来賓者(議員さんetc)を対象に奮ってご参加ください。
2. ドンデンがえしゲーム
⇒ 町会の代表者1名がフィールドに集合してください。
※ 放送でアナウンスがあります
3. 関所破りの役割
① 競技の始まる前に本部前に集合してください。
※ 放送でアナウンスがあります
② スタート位置から前方30メートルところに 机があります。
⇒ 町会責任者は机の後ろに立って ○×△ボールが入った箱をシャッフルする。
③ 選手がつかんだボール、○が出たらそのまま戻る指示をする。
④ 選手のつかんだボール、×の場合は5メートル先のカラーコーンを回るように指示をする。
⑤ 選手がつかんだボール、△が出たらもう一回ボールを取り出すよう指示をする。
(※ △ボールは箱の中に戻さない)
4. 午前競技終了後に本部前に集合
① 一般綱引きのトーナメント抽選会
② 午後の競技開始時間の決定
5. その他
① 競技について、質疑等有る場合は必ず、町会責任者が申し出てください。
⇒ 競技については 競技総括(スポーツ推進委員:斉藤)が申入れを聞きます。
② 最終判断は実行委員長( )
副実行委員長( )
副実行委員長( )が協議して決定します。
〇健民祭反省会での意見を取りまとめる
(文責:新羽地区健民祭実行委員長)
参考:新羽地区健民祭各係マニュアル
地域活動豆知識に戻る⇒https://nippacho.com/knowledge.html