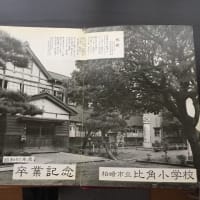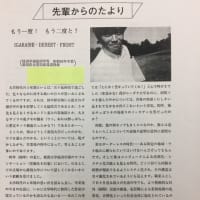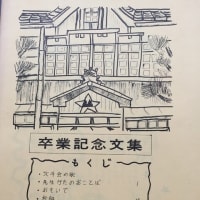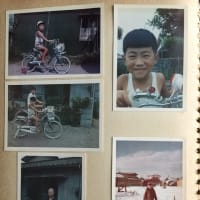●リストラで県本庁唯一の管理職兼務係長へ
平成24年当時の地方自治体においては、肥大化する地方財政が国財政の健全化の足かせの一つになっていることも背景に、国からの公務員定数抑制の要請が強まっており、また、地方としても人件費の抑制が福祉医療など増嵩する政策経費の財源確保にもつながることから、業務の見直しを通じた職員数削減が課題となっていた。
新潟県庁においても、所属単位で多人数を大胆に削減とまではなかなかできないので、毎年のように部局単位で数名程度とリストラが行われていた。ただ、業務の効率化による係単位の職員を6人から5人にするといったスケールメリット追求的な削減は概ねやり尽くしていたので、一般的には課長補佐を一人とする事務系行政分野の組織と異なり、当課のように技術系と事務系の課長補佐二人を擁する所属は、補佐業務の効率化が注目されるようになってきていた。
定数が抑制的に管理されてきた技術職よりも、不況時の救済策的な意味合いなどで時の社会経済情勢等により採用数が退職補充よりも過剰だったりしてきた事務職は定数が膨れがちであったので、どの部局でも事務系補佐はリストラの優先度が一際上がっていた。
それでも、事務系補佐を無くしてしまうというのは、組織運営や労務管理の上で障りがあるので、部内の二つの課の補佐を掛け持ちさせたり、課内の事務系係の係長職と兼務にすることで定数を1人減するのが具体的な方法となって庁内に普及してきた。
農林水産部内でも係長以下の担当クラスの事務職の定数削減案は、乾いたぞうきんを絞るように「もうこれ以上は捻出できない」という状況になっていて、我が地域農政推進課も、いよいよ来年は事務補佐を課内の係長職と兼務とすることで定数を一人減せざるを得ないとの話が内々に固まってきた。
係長との兼務ということになれば、内部牽制の観点などから管理職は適当ではないというのが誰しも常識的に考えることであり、補佐事務を扱いながらも参事という課長級の管理職である私は適任ではなくなる。懐かしの職場での在職も僅か一年で終わりなんだなあなどと、異動内示の日が近づく頃になるとしみじみとしてきたものだ。
ところが、異動内示の日に、私が残留のままで係長との兼務という衝撃の内示が言い渡された。リストラの策が尽きて、本県ではついに課長級管理職が係長兼務などという"掟破り"に手を出すという事態にまで至ったのか、と驚きながら全庁の異動内示情報を見ていくと、課長級で係長兼務の発令が出たのは県本庁で私ただ一人ではないか。
口の悪い知人にとってはまたしても格好のイジりネタだ。「課長級になったのに翌年に係長兼務って、これ実質的に降格左遷だよね」。返す言葉も無くうなだれるしかない。またしても人事に翻弄される私なのだ。ここ4年間を振り返ると、病院局総務課財務係長との兼務で補佐級の課長補佐になり、翌年に専任の課長補佐へ、次に地域農政推進課の参事として課長級に昇任した上で課長補佐事務取扱に、そして課長級で課長補佐事務と係長事務の兼務とは…。なんだか一歩進んで二歩下がるのような職業人生ではないか。
それでも、課長級から格下げにはならなかったことで良しとするか。昔から気持ちの切り替えだけは早い私は、久々の係長実務を面白おかしくやってやるかとの意を決した。不要になった係長の机と椅子を敢えて執務室内に残しておいてもらって、係長としての実務を執り行うときは気持ちのモードを変えるためにもその席に座ることにした。
「パイルダーオン!!」と叫びながら係長席に着座するも目の前の30代の係員達からは全く反応が無く"ずっこけ"てしまう。もはや「マジンガーZ」など知りもしない若い世代を前にスベって私なのであった。"ずっこけ"ももしかして死語か??…寒っ!!
新潟県庁においても、所属単位で多人数を大胆に削減とまではなかなかできないので、毎年のように部局単位で数名程度とリストラが行われていた。ただ、業務の効率化による係単位の職員を6人から5人にするといったスケールメリット追求的な削減は概ねやり尽くしていたので、一般的には課長補佐を一人とする事務系行政分野の組織と異なり、当課のように技術系と事務系の課長補佐二人を擁する所属は、補佐業務の効率化が注目されるようになってきていた。
定数が抑制的に管理されてきた技術職よりも、不況時の救済策的な意味合いなどで時の社会経済情勢等により採用数が退職補充よりも過剰だったりしてきた事務職は定数が膨れがちであったので、どの部局でも事務系補佐はリストラの優先度が一際上がっていた。
それでも、事務系補佐を無くしてしまうというのは、組織運営や労務管理の上で障りがあるので、部内の二つの課の補佐を掛け持ちさせたり、課内の事務系係の係長職と兼務にすることで定数を1人減するのが具体的な方法となって庁内に普及してきた。
農林水産部内でも係長以下の担当クラスの事務職の定数削減案は、乾いたぞうきんを絞るように「もうこれ以上は捻出できない」という状況になっていて、我が地域農政推進課も、いよいよ来年は事務補佐を課内の係長職と兼務とすることで定数を一人減せざるを得ないとの話が内々に固まってきた。
係長との兼務ということになれば、内部牽制の観点などから管理職は適当ではないというのが誰しも常識的に考えることであり、補佐事務を扱いながらも参事という課長級の管理職である私は適任ではなくなる。懐かしの職場での在職も僅か一年で終わりなんだなあなどと、異動内示の日が近づく頃になるとしみじみとしてきたものだ。
ところが、異動内示の日に、私が残留のままで係長との兼務という衝撃の内示が言い渡された。リストラの策が尽きて、本県ではついに課長級管理職が係長兼務などという"掟破り"に手を出すという事態にまで至ったのか、と驚きながら全庁の異動内示情報を見ていくと、課長級で係長兼務の発令が出たのは県本庁で私ただ一人ではないか。
口の悪い知人にとってはまたしても格好のイジりネタだ。「課長級になったのに翌年に係長兼務って、これ実質的に降格左遷だよね」。返す言葉も無くうなだれるしかない。またしても人事に翻弄される私なのだ。ここ4年間を振り返ると、病院局総務課財務係長との兼務で補佐級の課長補佐になり、翌年に専任の課長補佐へ、次に地域農政推進課の参事として課長級に昇任した上で課長補佐事務取扱に、そして課長級で課長補佐事務と係長事務の兼務とは…。なんだか一歩進んで二歩下がるのような職業人生ではないか。
それでも、課長級から格下げにはならなかったことで良しとするか。昔から気持ちの切り替えだけは早い私は、久々の係長実務を面白おかしくやってやるかとの意を決した。不要になった係長の机と椅子を敢えて執務室内に残しておいてもらって、係長としての実務を執り行うときは気持ちのモードを変えるためにもその席に座ることにした。
「パイルダーオン!!」と叫びながら係長席に着座するも目の前の30代の係員達からは全く反応が無く"ずっこけ"てしまう。もはや「マジンガーZ」など知りもしない若い世代を前にスベって私なのであった。"ずっこけ"ももしかして死語か??…寒っ!!
(「地域農政推進課5「リストラで県本庁唯一の管理職兼務係長へ」編」終わり。「地域農政推進課6「農地中間管理機構(農地バンク)の創設」編」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea