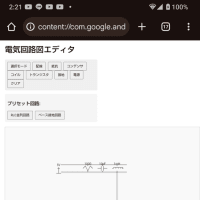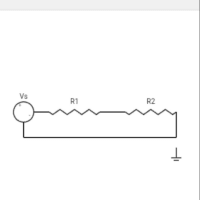裁判で明らかな嘘(バレバレの嘘)をついた代理人弁護士が懲戒処分の対象となるかどうかについては、**原則として懲戒処分の対象となり得ます**。以下に法的根拠と関連判例を説明します。
---
### **1. 法的根拠**
弁護士が虚偽の陳述を行うことは、**弁護士法**や**弁護士職務基本規程**に違反する可能性があります。
特に以下の規定が関連します:
- **弁護士法第56条**(懲戒事由)
弁護士が「職務内外を問わず、その品位を失うべき非行があったとき」は懲戒の対象となります。
- **弁護士職務基本規程第6条**(真実義務)
「弁護士は、裁判所に対し、虚偽の主張または知りながら虚偽の証拠を提出してはならない」と規定されています。
明らかな嘘をつく行為は、**真実義務違反**や**信用失墜行為**として懲戒事由に該当する可能性が高いです。
---
### **2. 関連判例**
#### **(1) 東京第一弁護士会懲戒委員会決定(平成20年)**
- **事案**:弁護士が虚偽の陳述をし、相手方から懲戒請求がなされた。
- **結論**:懲戒(戒告)処分が相当とされた。
- **理由**:
「弁護士は裁判所に対する誠実義務を負い、虚偽の主張は職務規律に反する」と判断されました。
#### **(2) 大阪弁護士会懲戒委員会決定(平成25年)**
- **事案**:弁護士が虚偽の証拠を提出し、訴訟手続きを不当に遅延させた。
- **結論**:**3ヶ月の業務停止**処分。
- **理由**:
「訴訟手続きの公正を害する行為であり、弁護士の職務規律に照らして重大な非行である」と認定されました。
#### **(3) 最高裁判所判例(昭和63年・民集42巻6号)**
- **事案**:弁護士が虚偽の主張を繰り返し、相手方に損害を与えた。
- **結論**:弁護士の責任を認め、**損害賠償請求**が認められた。
- **補足**:
この判例は民事賠償を扱ったものですが、裁判所が「弁護士の虚偽行為を違法と判断した」という点で参考になります。
---
### **3. 懲戒処分の種類**
弁護士会の懲戒処分には、以下のようなものがあります:
1. **戒告**(軽微な場合)
2. **2年以内の業務停止**
3. **弁護士除名**(特に悪質な場合)
「バレバレの嘘」が故意であり、裁判の公正を妨げた場合、**業務停止以上の処分**もあり得ます。
---
### **4. 実務上の注意点**
- **故意・過失の区別**:
単なる記憶違いや誤解による虚偽は懲戒対象とならない場合もありますが、**明らかに故意と認められれば処分の可能性が高まります**。
- **証拠の有無**:
嘘が「バレバレ」であっても、**客観的な証拠(録音・文書等)**がないと立証が困難な場合もあります。
---
### **まとめ**
✅ **代理人弁護士が裁判で明らかな嘘をついた場合、懲戒処分の対象となり得る**。
✅ **判例でも、虚偽の主張や証拠提出に対して戒告や業務停止が科せられた事例がある**。
✅ **悪質性や故意性が高い場合は、より重い処分が選択される**。
具体的なケースでは、**弁護士会の懲戒委員会**や**日本弁護士連合会**の判断が重要となります。