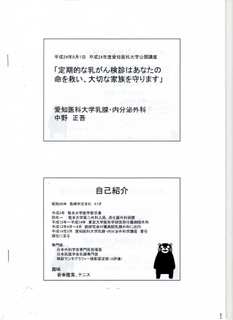甲状腺機能亢進症(バセドウ病)と判定されてから約7カ月経過。
8月の検査ではTSHレセプター抗体が19.6lu/1と基準値2.0>の約10倍になる。この数値は毎回検査ごとに上昇。
その他の重要指標はTSH刺激ホルモン 046684、FT3 2.35、FT4 0.62とすべて基準値内に収まった。
ところが9月の検査でTSH甲状腺刺激ホルモンの値がいきなり、9.8026と跳ね上がりFT4も基準値を下回り始める。
同時に眼球の違和感強まり10月3日の血液検査で、TSH甲状腺刺激ホルモンが16.6460と一気にそれも急激に跳ね上がる。
TSHレセプター抗体はいよいよ上昇して24.1を記録。
ついに担当医が入院してステロイドパルス療法を受けませんか、入院は1カ月という。
取り敢えず入院の方向で病室の確保を確認すると10月9日からOK。
予想していなかったので、担当医への連絡方法を確認し入院手続きはせずに帰宅。
3月から治療に通ってきて、一向に改善しないばかりか、目のほうがどんどんおかしくなって来るということは、全くの予想外だ。私の生活上何か問題があったんだろうか。不思議な気分だと敢えて担当医に言ってみる。
また、9月段階でこの数値が変化しているのは何を意味するのか担当医に確認するが確かな回答なく、さぁー?というのみ。
さすがに心配になり、ネットで甲状腺専門を探し、名古屋市港区の医者へ出向くが、この医者は勝手にしゃべって、勝手に手術医を紹介などと言い出す。こちらの言い分悩みは聞く耳持たず。不思議な医者だ。結構患者もいるがほとんど内科受診者のようだ。ホームページでは結構いい感触だったが、逢ってみないと分からない典型的なだめ医者。
もう一度ネット検索。あった。ありました。見つけました。クリニックの医師履歴から今の担当医の上司であった医師が開業医として自宅近くにいるではありませんか。

10月3日そのクリニックに相談ということで訪問。担当医のことはよく知っていると云う。
今までのデーターすべて提出。症状の悩み訴える。
甲状腺眼症を診断できる医師が名古屋にいない。(ただし、愛知医大、第一日赤に一人ずついるが病院として眼症を専門にしていないので勧められない)
さて、データーのほかに、過去の処方薬の服用状況を見せると、これは甲状腺機能亢進症が逆に低下症に変化しているが、ヨウ化カリューム丸の服用機関が1カ月長すぎること、メルカゾールの投与過剰が見られると判定。
血糖値も上がっているし、現状でやることは、TSH甲状腺刺激ホルモンを下げることだが、メルカゾール(甲状腺治療薬)の処方4錠は多いので3錠にして、チラージンという低下症改善薬を1錠処方するから逢わせて服用するように指示される。
医師曰く、変な感じだろうが、亢進と低下を消しあう作用で早急に改善しないと、眼症改善治療に向かえないと診断される。
また血糖値(HcA1c)もやや高いので、この改善も入院治療に徒(あだ)しているので、担当医はこれも気にしているのだろう判断してくれる。
自分なりに悩んでいたことがやや理解でき、方向が見えてきた。
10月5日日 担当医へ電話。入院キャンセルを申し入れるとそれでは10月10日来院してほしい。眼医者を紹介したいので来してほしいと促される。OK。
10月10日 担当医と面談。第2オピニオンとして東京のO眼科(甲状腺眼症では専門医として極めて優秀のようだ)を受診して、その結果で、あなたが(私のこと)納得する治療をしましょうと提案される。
私が了解できたら、連絡ほしいとのこと。すぐに紹介状を書くからと。
家に帰り家内と相談。賛成。
10月13日 紹介状依頼する。10月17日 紹介状発行するので来院と血液検査をして欲しいと要請される。もちろん了解。
10月17日 病院へ。
血液検査は何とすべての数値が基準地内。(ただし、TSHレセプター抗体は保険で月1回しか認められていないので検査除外)
クリニック処方のチラージン服用とメルカゾール以上減らしたのが効いたようだが 、担当医には言えない。担当医は1カ月分のメルカゾール(120錠分)処方される。仮に余ってもこれから先相当長期に亘って服用せざるを得ないと思うのでそのまま受ける。
、担当医には言えない。担当医は1カ月分のメルカゾール(120錠分)処方される。仮に余ってもこれから先相当長期に亘って服用せざるを得ないと思うのでそのまま受ける。
担当医にネットで調べてので素人判定だが、機能低下症にになったいたのではないか、眼症はTSHレセプター抗体が高い値が影響しているのではないかと聞く。低下症はうなずくが眼症については首を傾げるばかり。
担当医は医局内で私の症状に対し治療方針の検討会を開いた由。
結局、東京O眼科の診断結果で最終治療方針を決定することで了解。
実は、現在の担当医は10月で病院を退職。次のステップに進んでも途中から別の医師があたることになるので、今回は後任の医師も同席。
次回10月24日には東京の診断結果報告書を持って、面談することにした。
帰宅してすぐに東京のO眼科へ電話。
22日月曜日午後1時30分の予約確保できた。
夜、クリニックへ出かける。チラージン継続すべきか相談に。
結局、しばらく今のまま継続しないと直ぐに悪化する可能性があるので、今後の治療が決まるまで服用することを勧められ、処方をもらう。
やれやれだ。そもそも甲状腺が悪くなる原因がいまだに不明だそうだし、治療法も結構経験が必要のようだ。
7年前に初めて発症した時の経験から、少々甘く見ていたことと、医師の力量不足?があいまって、結構深刻な事態に追い込まれた感じ。
途中で担当医に「先生は糖尿が専門では?}と聞いたこともあるが、その時はややキツイ顔で甲状腺も専門ですと答えていたが。
ようやく、先の診療方針が決められるところに近づいてきた。
もう少しの辛抱だが、恐らく九割が他入院の方向性が強いようだ。1か月
今日は朝から涙の量が多い。