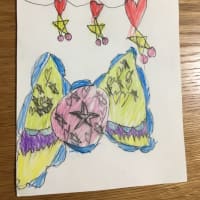前まで住んでいた伊勢を、悠々と流れていた宮川。その川の下流沿いに、宮川医療少年院はある。医療少年院、といっても、医療の必要度、障害の程度はそこまで大きくない子どもが収容される。(必要度の高い子どもは京都医療少年院か関東医療少年院に行く。これらは「病院」の登録がしてある施設である)。
この本の著者は、宮川医療少年院で医師を務めた経験から、「非行を起こす子どもたちは、非行性が強いというより、すべての物事への理解度が低く、そのことに周りが気付かないために配慮もされずに来ていることが原因で犯罪を犯しているのではないか」という感覚を抱く。誰かから挨拶をされないだけで、自分が嫌われている、やり返すしかない、などと考える。イライラした気持ちを発散するすべを知らず、弱い者いじめとして幼女への性的暴行をするーーーなど。
この本は売れているよなので、多くの人には衝撃的な事実だったのかもしれない。タイトルもいいのかも。でも、障害のある人や子どもに接している人にとっては、お十六内容ではないと思う。理解力の低さ、そこからくる認知のゆがみ。これらは、例えば重度の知的障害などよりよっぽどやっかいなのだ。理解力の低さや認知のゆがみを、周囲が知り、対応すれば本人も周りもハッピーになりうるが、周囲が気付かず、本人を責め、認知のゆがみが進んでしまうと、犯罪領域の行為に走りかねない。
「このような子どもたちは、何らかの問題に対して、直ぐに答えを出してしまい明日。時間をかけて”ちょっと待てよ。ほかに方法はないかな”といった柔軟な思考や違った視点を持つことがとても苦手なのです。」
精神科医として、少年院の前には公立病院で勤めていたという著者は、軽度知的障害、境界知能の子どもを、それを主訴として診察したことはなかったという。それはそうである。精神疾患ではないのだ。でも、確実に専門的なサポートが必要なのだ。
発達障害に起因する悩みや苦しみの末に、犯罪や、自傷行為、ひきこもりになる人がいる。こういう人に接していると、著者が言うように、小学校ぐらいの低年齢から、学校教科以外に教えるべきことがあるのではないかと思ってしまう。コミュニケーションや、自分の特徴、他人との違いなどについて。友達や家族と過ごす中で自然に身につけて行ってくれ、というのでは、こぼれて、傷ついて離れてしまう子がいるのだ。
著者が、幼少期から取り組むとよい、としている「コグトレ」は、噂を聞いたことはあるが、実際にワークブックなどを目にしたことはない。買ってみようと思う。