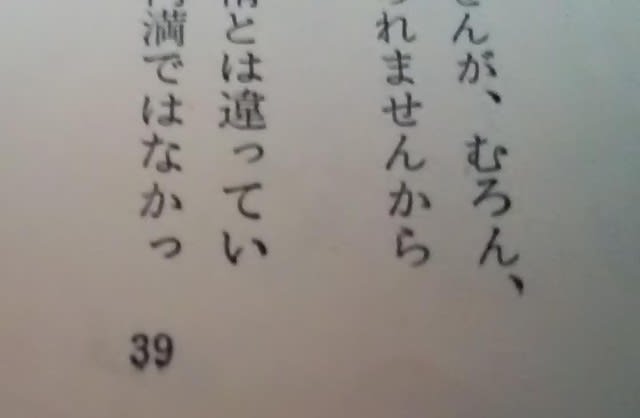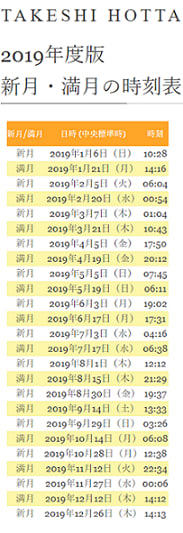災害の多い「平成」でした。
1. 1990年代
1.1. 雲仙普賢岳火砕流
1.2. 平成3年台風19号
1.3. 釧路沖地震
1.4. 北海道南西沖地震
1.5. 1993年米騒動
1.6. 1994年猛暑
1.7. 北海道東方沖地震
1.8. 三陸はるか沖地震
1.9. 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)
2. 2000年代
2.1. 三宅島噴火
2.2. 鳥取県西部地震
2.3. 芸予地震
2.4. 2003年十勝沖地震
2.5. 新潟県中越地震
2.6. 福岡県西方沖地震
2.7. 平成17年台風14号
2.8. 平成18年豪雪
2.9. 能登半島地震
2.10. 新潟県中越沖地震
2.11. 2007年猛暑
2.12. 平成20年茨城県沖地震
2.13. 岩手・宮城内陸地震
2.14. 岩手県沿岸北部地震
2.15. 駿河湾地震
3. 2010年代
3.1. チリ地震
3.2. 2010年猛暑
3.3. 平成23年豪雪
3.4. 新燃岳噴火
3.5. 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
3.6. 長野県北部地震(栄村大震災)
3.7. 福島県浜通り地震
3.8. 平成23年台風12号
3.9. 平成25年台風26号
3.10. 2013年猛暑
3.11. 平成26年豪雪
3.12. 2014年広島市土砂災害
3.13. 2014年御嶽山噴火
3.14. 平成28年熊本地震
3.15. 台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風
3.16. 大阪府北部地震
3.17. 西日本豪雨
3.18. 2018年猛暑
3.19. 平成30年台風21号
3.20. 平成30年北海道胆振東部地震
4. 編集後記
5. 関連記事
1990年代
雲仙普賢岳火砕流
雲仙普賢岳(雲仙岳)は、長崎県の島原半島中央部にある火山。
1989年(平成元年)から、同じ長崎の「橘湾」を震源とした地震が発生していた。
1984年4月より地震が頻繁に起こるようになり、1990年11月、雲仙岳山頂から噴火。
噴火は1990年12月に一旦収まったものの、翌年再噴火。
噴火活動は何度か収まりつつも、1995年3月まで継続。
なかでも一番被害をもたらしたのは、1991年6月3日の噴火である。
長期間にわたって噴火し続けたケースとしては珍しい例。
死者は43名、負傷者は9名。
平成3年台風19号
国際名はミレーレ(Mireille)
青森県では収穫前のリンゴが軒並み落ちてしまったため、りんご台風とも呼ばれている。
これ以降、台風が来る前には事前対策として農作物を収穫するようになった。
釧路沖地震
1993年1月15日20時06分に発生した、マグニチュード7.5の地震。
北海道釧路市で震度6、北海道浦幌町・帯広市・広尾町、青森県八戸市で震度5を観測。
死者は2名、負傷者は966名。
釧路市では各都市と結ばれていた鉄道、国道が不通となり、都市ガスが停止。
そのほかにもライフラインが多く破壊され、復旧までに半年を要した。
北海道南西沖地震
1993年7月12日10時17分に発生した、マグニチュード7.8の地震。
北海道奥尻町で震度6、北海道小樽市・江差町・寿都町、青森県 深浦町で震度5を観測。
震源地が奥尻島のすぐ近くであったため地震発生からわずか4~5分で津波が到達。
奥尻島では、202人が犠牲になった。
地震発生から津波が到達するまでに3分もかからず、多くの人が犠牲になった。
この経験から、気象庁は地震発生からなるべく早く、津波に関する情報を発するようになった。
しかし、情報のスピードを重視したせいで、被害が大きくなってしまった例もある。
それは2011年の東日本大震災であり、地震発生直後は、3メートルの津波がくると発表された。
しかしその後、さらに大きな津波がやってくると修正されたものの、多くの市民が正しい津波情報を入手することができなかった。
1993年米騒動
やませの影響で東北地方の米が軒並み不作となり、翌年の米不足に繋がった。
国内では、不足した国産米の代わりとしてタイ米が販売された。
1994年猛暑
前年の冷夏とは一転し、記録的な猛暑が日本各地で観測された。
大分県日田市で36.0度、京都府京都市、岐阜県多治見市で35.7度を記録した。
北海道東方沖地震
1994年10月4日22時22分に発生した、マグニチュード8.2の地震。
北海道釧路市・厚岸町で震度6、北海道浦河町・足寄町・広尾町・中標津町・羅臼町・根室市で震度5を観測。
地震発生直後に津波警報が発表されたため、北海道での被害は少なかった。
三陸はるか沖地震
1994年12月28日21時19分に発生した、マグニチュード7.6の地震。
青森県八戸市で震度6、青森県むつ市・青森市、岩手県盛岡市で震度5を観測。
激甚災害法(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)が1999年に改正されたことで、「激震災害」であると認定された。
兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)
1995年1月17日5時46分に発生したマグニチュード7.3の地震。
最大震度は7、死者数は6433名。
日本ではじめての、都市型直下地震であり、戦後で二番目に死者数が多い災害である。
震度7は、当時の震度計では計測できない規模である。
1日平均2万人超、3か月間で延べ117万人がボランティアとして被災者を支援。
全国各地から支援や救援が寄せられ、この年を境として日本のボランティア文化が根付いていった。
阪神淡路大震災のあった1995年は「ボランティア元年」と呼ばれ、1998年にはNPO法ができた。
2000年代
三宅島噴火
三宅島は伊豆諸島に位置する、人口約3,000人の島である。
1983年にも噴火しており、平成には2000年6月26日に噴火した。
数日前から、三宅島では地震が起こっており、気象庁は住民に避難を呼びかけ。死傷者はいなかった。
鳥取県西部地震
2000年10月6日13時30分に発生したマグニチュード7.3の地震。
鳥取県境港市・日野町で震度6強、鳥取県西伯町・会見町・岸本町・淀江町・溝口町・日吉津村で震度6弱を観測。
マグニチュードは兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)と同規模である。
芸予地震
2001年3月24日に発生したM6.7の地震。特に広島県西部で被害が顕著であった。
瀬戸内海の安芸灘を震源として発生し、広島県・山口県で大きな被害がみられた。
芸予とは、安芸(広島県)と伊予(愛媛県)のことを指している。
「芸予地震」は1905年にも発生しているため「2001年芸予地震」と区別されることがある。
2003年十勝沖地震
2003年9月26日に発生したM8.0の巨大地震。津波に飲まれて死者行方不明者は2人。
新潟県中越地震
2004年10月23日17時56分に発生したマグニチュード6.8の地震。
新潟県川口町で震度6、新潟県小千谷市・山古志村・小国町で震度6強を観測。
21世紀に入って初めて震度7を記録した地震である。
地震発生後も、最大震度5弱以上の余震が20回近く起こった。
死者は新潟県で68人。
家屋の全半壊はおよそ1万7000棟であるが、もともと雪の多い地域であったことから比較的頑丈な家が多く、被害は予想よりも小さかったという。
ボランティアとして約9万人が参加。
新潟県への義援金は約373億円にのぼった。
福岡県西方沖地震
2005年3月20日10時53分に発生したマグニチュード7.0の地震。
死者は1名、負傷者は約1,200名。
地震翌日には災害ボランティアセンターが設置。
プロ野球チームの福岡ソフトバンクホークスではチャリティオークションやチャリティゲームを実施。
「鷹」繋がりとして、特に被害の大きかった玄界島の小鷹神社に寄付金が渡された。
平成17年台風14号
8月29日に発生し、9月4日に沖縄県上陸。
9月8日に北海道に上陸し温帯低気圧に変わるまでの間、全国各地に甚大な被害を与えた。
平成18年豪雪
2005年11月から2006年2月にかけて発生した豪雪。
青森市では4.5メートルの積雪となった。
スリップや衝突などによる交通事故、落雪による事故が全国各地で多発。
死者行方不明者は150人以上のぼった。
気象庁が豪雪被害を災害として命名するのは、昭和38年1月豪雪以来である。
能登半島地震
2007年3月25日9時41分に発生したマグニチュード6.9の地震。
石川県穴水町・輪島市・七尾市で6強、石川県能登町・中能登町・志賀町で6弱を観測した。
石川県で震度6を観測したのは、観測開始以来はじめてのことであった。
新潟県中越沖地震
2007年7月16日10時13分に発生したマグニチュード6.8の地震。
新潟県長岡市・出雲崎町で6弱を、新潟県柏崎市で5強を観測。
死者は15名、負傷者2,346名にのぼった。
2004年の新潟県中越地震、2007年能登半島地震と震源が近く、発生当初から多くのマスコミで報じられていた。
これらの地震によって引き起こされたものであるのか、独立した地震なのかは意見が分かれている。
2007年猛暑
岐阜県多治見市で40.9度を観測。
そのほか、群馬県館林市、山梨県甲府市、埼玉県熊谷市などで40度越えを記録した。
平成20年茨城県沖地震
2008年5月8日1時45分に発生したマグニチュード7.0の地震。
茨城県水戸市、栃木県茂木町で震度5強を観測した。
茨城県沿岸沖合を震源としている大規模な地震は、1896年、1923年、1924年、1943年、1961年、1965年、1982年と過去に何度も発生している。
岩手・宮城内陸地震
2008年6月14日8時43分に発生したマグニチュード7.2の地震。
岩手県奥州市、宮城県栗原市で震度6強を観測。
他の同じ規模の地震に比べ、建物被害よりも土砂災害が多く発生した。
福島第二原子力発電所4号機において使用済み核燃料プールから飛び散った多少の水が発見された。
東京電力によると、この周辺地域への放射性物質による汚染はなかったという。
被災地に対し、楽天野球団と楽天イーグルス選手会から100万円義援金を提供。
また、楽天の山崎武司選手がホームラン1本に付き10万円寄付するとし、総額280万円を寄付した。
岩手県沿岸北部地震
2008年7月24日0時26分に発生したマグニチュード6.8の地震。
青森県八戸市・五戸町・階上町、岩手県・野田村で震度6弱を観測。
そのほか、青森県・岩手県・宮城県で震度5強が観測された。
はじめは小さな揺れであったが、徐々に揺れが大きくなっていき、1分にもわたって揺れ続けたのが特徴。
発生時刻が深夜であったことから、一部のテレビ局では字幕のみの放送となった。
駿河湾地震
2009年8月11日5時7分に発生したマグニチュード6.5の地震。
静岡県御前崎市・牧之原市・焼津市・伊豆市で震度6弱を観測。
台風9号が接近していたため、早朝ではあったがテレビにて中継が行われていた。
そのため、地震が発生した瞬間にも、中継が行われた。
東名高速道路が路肩崩落により通行止となり、お盆の帰省ラッシュに大きな影響が出た。
2010年代
チリ地震
2010年2月27日3時34分に南米チリで、マグニチュード8.8の地震が発生。
翌日に岩手県大槌漁港に1.4メートル、北海道根室市花咲港に0.9メートル、茨城県神栖市鹿島港に0.8メートルの津波が来襲。
日本の気象庁は3メートル級の津波が来ると予想していたが、実際に来た津波は3メートルに満たなかった。
これが住民の油断を招き、翌年の東日本大震災の被害を拡大したともいわれている。
2010年猛暑
2010年は当初、冷夏になると予想されていた。
猛暑日年間日数で、埼玉県熊谷市、群馬県館林市が41日間を記録。
全国的に猛暑となり、富山県富山市の富山市ファミリーパークでは、ペンギンが熱中症で死亡した。
平成23年豪雪
2010年12月31日から2011年1月2日にかけて発生した豪雪。
北陸地方や山陰地方で特に被害が見られたため「北陸豪雪」「山陰豪雪」ともいわれる。
福井市では25年ぶりに1メートルを超える積雪を記録。
鹿児島市でも25センチメートルの積雪を記録した。
年末年始であったため、Uターンラッシュにも影響し、特急列車が30時間以上立ち往生した。
新燃岳噴火
新燃岳(しんもえだけ)とは九州南部の霧島山中央部に位置する活火山。
2011年1月から4月までにかけて、噴火活動が見られた。
記録に残っているものだけでも1700年代から頻繁に噴火しており、この2011年以降にも何度か噴火している。
2011年の噴火では、火口の東側の512世帯約1,150人が避難。
観光地として有名だった新燃池は消滅した。
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
2011年3月11日14時46分に発生したマグニチュード9.0の地震。
マグニチュード9.0は、日本の観測史上最大規模であり、最大深度7が観測されたのは阪神淡路大震災、新潟県中越地震以来、3回目である。
死者・行方不明者は1万8,434人とされており、第二次世界大戦後最悪の自然災害とも呼ばれている。
犠牲者の多くが津波による被害である。
2011年には個人寄付総額が10182億円と前年の2倍以上に跳ね上がったことから「寄付元年」ともいわれている。
長野県北部地震(栄村大震災)
2011年3月12日3時59分に発生したマグニチュード6.7の地震。
長野県下水内郡栄村で大きな被害が見られたため、「栄大地震」「栄村大震災」とも呼ばれている。
震度5以上の余震が、2011年6月までに6回程起こっている。
東日本大震災の13時間後に派生したため、前日の地震によって誘発された地震であると考えられている。
福島県浜通り地震
2011年4月11日17時16分に発生したマグニチュード7.0の地震。
福島県いわき市・古殿町・中島村、茨城県鉾田市で震度6弱を観測。
東北地方の太平洋沖では、3月11日から地震活動が活発化しており、3月11日の地震によって誘発されたと考えられている。
土砂崩れや停電、火災、高速道路の通行止めなどの被害がみられた。
平成23年台風12号
2011年8月25日に派生し、9月3日高知県に上陸した台風。
岡山県・鳥取県を縦断し土砂崩れ、河川氾濫などの被害をもたらした。
死者・不明者は92人。
被害総額は少なくとも1236億円とされている。
平成25年台風26号
2013年10月11日に発生し、10月16日関東地方に台風。
伊豆大島で甚大な被害が生じたため、「伊豆大島土砂災害」とも呼ばれている。
伊豆諸島西部において幅950メートルにもわたって山の斜面が崩落。
集落が飲み込まれ、36人が死亡、3人が行方不明となった。
2013年猛暑
2013年7月から8月にかけて全国的に猛暑に。
山梨県甲府市では40.7度を観測、高知県四万十市では、観測史上最高となる最高気温41.0度を観測した。
各地で熱中症による救急搬送も多数あった。
平成26年豪雪
2014年2月8日から16日にかけて発生した豪雪。
ソチオリンピックが開催されていた時期でもある。
岐阜県・山梨県・長野県では孤立し、ライフラインや物流が途絶えた。
首都圏では私立大学の入学試験が行われていたため、一部の大学で時間の繰り下げや、日程の振り替えが行われた。
2014年広島市土砂災害
2014年8月20日、広島市北部の安佐北区・安佐南区で発生した土砂災害。
7月30日から8月26日にかけて、西日本を豪雨が襲っていた。
被害のあった集落はかつて「蛇落地悪谷(じゃらくじあしだに)」と呼ばれており、古くから水害が起こりやすいことが指摘されていた。
企業や著名人、個人から多額の寄付が寄せられ、広島市への義援金は約63億円、広島県への義援金は約21億円にのぼった。
サッカーや野球といったスポーツチームからも義援金がよせられ、東京ヤクルトスワローズ選手会からは、マツダスタジアムで行われた広島東洋カープ戦の前に、100万円が手渡された。
2014年御嶽山噴火
2014年9月27日11時52分、長野県と岐阜県の県境にある御嶽山が噴火。
2007年の噴火と異なり、全長が観測されておらず噴火警戒レベルは1であったため、登山客が多くいた。
57人の登山者が犠牲になった。
御嶽山は古くから山岳信仰の対象となっており、全国各地にゆかりのある神社が存在している。
噴火後、信者から多額の義援金が集められた。
平成28年熊本地震
2016年4月14日以降、熊本県と大分県で相次いで発生した地震を指す。
4月14日21時26分、マグニチュード6.5の地震が発生。
4月16日1時25分、マグニチュード7.3の地震。
この時点で、熊本県益城町では震度7を2回観測している。
その後、2016年4月16日3時55分にもマグニチュード5.8、最大深度6強の地震が発生。
震度5以上の地震が、約30回熊本・大分を襲った。
東海大学阿蘇キャンパスの学生寮が倒壊し、学生12人が生き埋めになった。
この地震による被害者数は267人。
LINEでは「熊本地震被災地支援スタンプ」が販売され、売上金全額が義援金となった。
台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風
北海道には8月17日からの1週間で、台風第7号、第9号、第11号が上陸。
8月30日台風第10号が岩手県に上陸。
北海道に上陸する前に、温帯低気圧へとなるのが一般的であるため、1年間で3個の台風が北海道に上陸したのは、統計史上初である。
これらの台風による死者は28人。
ジャガイモやトウモロコシといった農作物へ甚大な被害をもたらし、ポテトチップスの供給不足がおこった。
大阪府北部地震
2018年6月18日7時58分に発生したマグニチュード6.1の地震。
大阪市北区・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市で震度6弱を観測した。
首都直下型地震では、観測史上最大の震度である。
また、関西地方で震度5弱以上を観測したのは、1995年の阪神淡路大震災以降である。
ジャパネットでは、防災グッズを販売し、売り上げすべてを義援金として寄付した。
西日本豪雨
2018年6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に発生した豪雨。
気象庁は「平成30年7月豪雨」と命名している。
台風7号と梅雨前線によって大雨がもたらされた。
豪雨による死者は227人。
特に広島県・岡山県で被害が見られた。
水害で死者が100人をこえたのは平成始まって以来のことであり「平成最悪の水害」と言われている。
特定非常災害特別措置法の対象となった。
なお、地震災害以外では初めてである。
7月10日から、日本赤十字社を通した義援金の受付を開始。
日本航空、サントリー、マツダ、三菱といった一般企業も義援金を寄付。
プロ野球チームでは、義援金をおくるほか、チャリティオークションを実施。
ジャニーズでは災害支援のため『Smile Up!Project』を立ち上げた。
2018年猛暑
埼玉県熊谷市で日本歴代最高となる41.1度を観測、岐阜県下呂市・岐阜県美濃市で41.0度を観測した。
41度をこえたのは、観測史上初である。
熱中症患者が続出し、死者は133人にのぼった。
平成30年台風21号
2018年8月28日に発生し、9月4日に日本に上陸した台風。
最低気圧は915ヘクトパスカルと、非常に強い勢力で上陸した。
最大風速は大阪府関空島で58.1 m/秒。
関西国際空港では、連絡橋にタンカーがぶつかり崩壊。
利用客3,000人と職員2,000人が孤立状態になった。
大阪の御堂筋復旧支援のため、サントリーが5000万円を寄付した。
平成30年北海道胆振東部地震
2018年9月6日3時7分に発生したマグニチュード6.7の地震。
厚真町で震度7、札幌市・千歳市でも震度6弱を観測した。
苫東厚真火力発電所が被害をうけたことから、北海道全域で停電が発生。
北海道全域が停電になるのは、北海道電力創立以来初のことである。
自家発電機を回すことによる一酸化炭素中毒者や、人工透析をしている患者の対応が課題となった。
参考:日本で起きた災害の一覧
編集後記
30年間におこった災害を振り返ってみて、いかがでしたでしょうか。
プロ野球チームがサイン会で義援金を集めたり、チャリティオークションをしたり。
LINEでは全額寄付金になるスタンプが発売されたりと、新しい支援の方法が生まれていっていることがわかりました。
また、過去にも災害が起きていた場所で、再び災害がおきていることもわかりました。
先人たちが辛い経験をしておきながら、また被害がうまれてしまった、というのはとても悲しいことであると感じます。
犠牲になった人たちのために残されたわたしたちができることはなにか、これから生きる人たちのためにできることはなにか、考えてみませんか?
『津波が来たら桜より上に逃げよう』3.11の教えを残す|桜ライン311
※ 記事は「きふる」から。
さようなら、平成!















































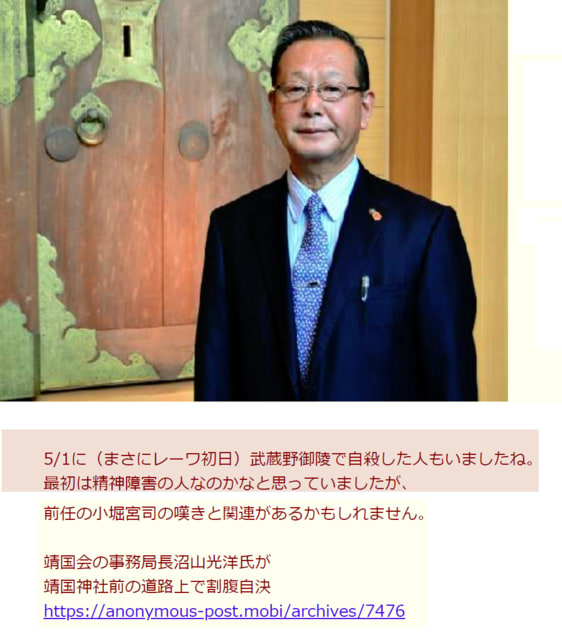













 元気でね! またね!
元気でね! またね!