さすがにこの時代のジャケットはなかなかありません。
あっても、当時のものか、後から作成したものか区別がつきません。悪しからず。なるべく古く、当時のものをと思っていろいろ検索しています。
■エト邦枝
エト邦枝さんは大蔵省に勤めながら、クラシックを勉強。帝国音楽学校を卒業後、原信子に師事。藤原歌劇団や東宝実演部を経て、1947年(昭和22年)、宇佐美エトとしてコロムビアからデビュー。
□ カスバの女 1955年(昭和30年)
当初、芸術プロ製作映画『深夜の女』の主題歌として制作され、レコーディングを終了して発売したものの、肝心の映画が製作中止となり、発売元のテイチクレコードも熱心にキャンペーンすることなく曲は自然消滅の形となり、歌唱したエト邦枝は芸能界を去ることとなった。
その後、1967年(昭和42年)になって緑川アコがカバーして日本クラウンから発売するとこれがヒットとなり、以後は竹腰ひろ子、沢たまき、扇ひろ子らがこぞってカバーして知られるようになる。

■こまどり姉妹
元祖双子デュオ歌手であり、ザ・ピーナッツのポップス歌謡に対して演歌であった。
御年77歳で何と現役で活躍されています。
最近では2014年3月に18年振りの新曲を出しています。
□ 浅草姉妹 1959年(昭和34年)
この曲はデビュー曲である。
当初は「三味線姉妹」だったが、浅草で三味線片手に流していたので、この題名になった。
この時は、まだこまどり姉妹ではなかった。

■コロムビア・ローズ
初代コロムビア・ローズと呼ばれる。
1951年、「第2回日本コロムビア全国歌謡コンクール」で優勝、日本コロムビアに入社。芸名の「コロムビア・ローズ」は会社名と、第2次世界大戦中、日本軍による連合国向けプロパガンダ放送を担い、米軍将兵から「東京ローズ」と呼ばれた女性アナウンサーをヒントに名付けられた。
1952年、「娘十九はまだ純情よ」でデビュー。
「どうせ拾った恋だもの」や「東京のバスガール」など数々のヒット曲を生み活躍するが、1961年に突如引退した。
80歳で車を乗り回し、遠方の歌謡教室まで自ら運転して教えに行っている。
また、2015年7月17日放送の同番組では後輩のこまどり姉妹とお肉を食べている模様が放送された。
□ 娘十九はまだ純情よ 1952年(昭和27年)

□ 渡り鳥いつ帰る 1955年(昭和30年)

□ どうせ拾った恋だもの 1955年(昭和30年)

□ 東京のバスガール 1955年(昭和30年)

前年覆面歌手でデビュー

■スリー・キャッツ
元祖お色気グループとでも呼べる、セクシーな3人組(小沢桂子、佐伯みち子、堀田直江)。
何故セクシーかと言いますと、歌詞に「うっふん、あっはん」という部分がある為!
後年、ゴールデン・ハーフがカバーしてヒットしています。
□ 黄色いさくらんぼ 1959年(昭和34年)

■ディック・ミネ
1934年(昭和9年)、タンゴ楽団「テット・モンパレス・タンゴ・アンサンブル」で歌手兼ドラマーとして活躍していたところを淡谷のり子に見出され、レコード歌手の道を歩むこととなる。
同年創立されたテイチクレコードにてテイチク専属のジャズバンドの計画が持ち上がり、ミネがプレイヤーの人選を行った結果、白人3人、日本人6人となる「ディック・ミネ・エンド・ヒズ・セレナーダス」が東京で結成される。
そして、このジャズバンドと組み、同年8月7日に録音された『ロマンチック』はミネのデビュー盤となった。
その後、テイチクレコードの重役だった作曲家・古賀政男の推薦で、同社で『ダイナ』をレコーディング。
同曲では、自ら訳詞と編曲、演奏を担当。トランペッターとして南里文雄やドラムとして泉君男も参加し、片面にカップリングされた『黒い瞳』とともにテイチク創立以来の大ヒット曲となった。
□ 雨の酒場で 1954年(昭和29年)

■ザ・ピーナッツ
愛知県出身の双子デュオ歌手である。
1959年2月11日、「第2回 日劇コーラスパレード」で歌手デビュー、4月、「可愛い花」でレコードデビュー。
その直後1959年6月17日から1970年3月31日までフジテレビ系の歌謡番組『ザ・ヒットパレード』のレギュラーに抜擢される。
その後1961年6月4日から1972年10月1日まで日本テレビ系の人気バラエティー番組『シャボン玉ホリデー』でメイン司会を務めた。
1975年に引退した。
姉のエミは沢田研二と結婚したが、1987年に離婚し2012年に死去している。
□ 可愛い花 1959年(昭和34年)

□ 情熱の花 1959年(昭和34年)

フランク永井
独特の低音で多くの人を魅了し、歌謡界に大きな軌跡を残したムード歌謡歌手である。
さまざまな「のど自慢大会」に出場し、「のど自慢荒らし」の異名をとったが、1955年(昭和30年)に日本テレビの『素人のど自慢』の年間ベストワンに選ばれたのを機に、ビクターと契約。同年9月に『恋人よ我に帰れ』でデビューした。
□ 有楽町で逢いましょう 1957年(昭和32年)
1957年(昭和32年)の有楽町そごう(2000年に閉店)キャンペーンソングであった『有楽町で逢いましょう』が空前のヒットとなり一躍脚光を浴びた。


□ 夜霧の第二国道 1957年(昭和32年)

□ 羽田発7時50分 1958年(昭和33年)

□ こいさんのラブ・コール 1958年(昭和33年)

□ 夜霧に消えたチャコ 1959年(昭和34年)

□ 東京ナイト・クラブ (フランク永井,松尾和子) 1959年(昭和34年)
長らくデュエットソングの定番であった。


ペギー葉山
幼少時から歌が好きだったことから、声楽を習い音大進学を志す。
しかし次第にFEN放送(現・AFN)から流れるアメリカのポピュラー音楽へ関心を深めていき、青山学院女子高等部(現青山学院高等部)2年の時に映画『我が道を往く』を観た際、劇中で主演のビング・クロスビーが歌う「アイルランドの子守唄」に感動、クラシックからポピュラー・ジャズへの転向を決意。
ほどなく友人の紹介から進駐軍のキャンプで歌い始め、その歌声とセンスを見込んだティーブ・釜萢の口利きで、当時の一流ビッグバンドである渡辺弘とスター・ダスターズの三代目専属歌手として活躍する。
□ ドミノ/火の接吻 1952年(昭和27年)
デビュー曲。

□ ケ・セラ・セラ 1956年(昭和25年)
メリーホプキンの日本語カバー曲である。

原曲。メリーホプキン

□ 南国土佐を後にして (ペギー葉山) 1959年(昭和34年)
もともとは大陸に出兵した地元の陸軍歩兵236連隊内で歌われていた曲ともいわれる。
1953年〜1954年頃に丘京子が、1955年に鈴木三重子がレコードに吹き込んだ。
そして1959年にはペギー葉山が歌い大ヒットした。
1958年にNHK高知放送局テレビ開始の記念番組として「歌の広場」にペギー葉山が登場し歌ったことがきっかけとなり、1959年5月にペギーの歌でキングレコードからシングル発売されると、発売からほぼ1年で約100万枚を売る大ヒットとなった。

□ ラ・ノビア/爪 1962年(昭和37年)

□ 学生時代/鏡 1964年(昭和39年)


□ ドミニク 1962年(昭和37年)

□ 大人とこども 1962年(昭和37年)

□ よさこい時雨 1959年(昭和34年)

□ ユンタ恋しや懐かしや/島原地方子守歌 1960年(昭和35年)
沖縄八重山諸島の民謡。
「安里屋ユンタ」といい、八重山の交唱歌(かけあい歌)のこと。
この民謡を「南国土佐…」風に歌った。
ただ、当時は沖縄返還前(1972年返還)でヒットしなかった。


■伊藤久男
たいへん裕福な家庭で育ち、当時はまだ珍しかったピアノに没頭し、中学の頃にはピアニストを志望するようになる。
しかし、親族には反対されてカモフラージュで東京農大に入学。
程なくして帝国音楽学校に進んだ。
抒情性豊かなバリトンで、昭和10年代前半から戦時歌謡のレコーディングが多く、伊藤久男としての初めてのヒットは1938年(昭和13年)「湖上の尺八」。
その後、「暁に祈る」「白蘭の歌」「高原の旅愁」「お島千太郎旅唄」と連続してヒットを飛ばし、スター歌手としての地位を確立した。
終戦直後は、戦時歌謡を多く歌った責任感から疎開先に引きこもり酒に溺れ、再起不能とも言われたが、1947年(昭和22年)松竹映画「地獄の顔」(監督:マキノ雅弘)主題歌「夜更けの街」でカムバック。
その後は、「シベリア・エレジー」「イヨマンテの夜」「あざみの歌」「山のけむり」「君いとしき人よ」「数寄屋橋エレジー」「ひめゆりの塔」など様々なジャンルでヒットを飛ばした。
□ イヨマンテの夜 1949年(昭和24年)

□ あざみの歌/山のけむり 1951年(昭和26年)

■岡晴夫
浅草や上野界隈の酒場などで流しをしながら音楽の勉強をする。
昭和13年にキングレコードのオーディションを受け上原とともに専属となる。 昭和14年2月「国境の春」でデビュー。「上海の花売娘」「港シャンソン」などのヒットを飛ばし一躍スターとなる。
昭和19年にインドネシア領アンボン島に配属されるが現地の風土病にかかり帰国を余儀なくされる。
戦後は「東京の花売娘」「啼くな小鳩よ」「憧れのハワイ航路」などの大ヒットをとばす。
岡の全盛期は終戦直後であった。
彼の底抜けに明るい歌声が、平和の到来と開放感に充ちた時代にはまったのである。
□ 憧れのハワイ航路 1950年(昭和25年)
自身映画にも出演されていて美空ひばりとの共演であった。

□ 逢いたかったぜ 1950年(昭和25年)

■岡本敦郎
1946年にラジオ歌謡のホームソング「朝はどこから」でデビューした。
この曲は当時、敗戦直後の日本を励ますため朝日新聞が企画した懸賞応募曲である。
明るいその曲調から、広く親しまれ愛唱された曲である。
そして、「白い花の咲く頃」の大ヒットや「チャペルの鐘」「あこがれの郵便馬車」などのヒットを経て、1954年にリリースした「高原列車は行く」は爆発的ヒットとなり現在までの岡本敦郎の代表曲となった。
その後も「ピレニエの山の男」「自転車旅行」「若人スキーヤー」などヒットを飛ばした。多くのラジオ歌謡を吹き込んだことから、ミスターラジオ歌謡の異名を持つ。
□ 白い花の咲く頃 1950年(昭和25年)

□ あこがれの郵便馬車/高原列車は行く 1954年(昭和29年)











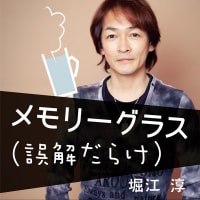















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます