
昨日、Kちゃんがテストの答案を嬉しそうに私に見せてくれました。100点でした。
そのテストの内容は「イースター島には、なぜ森林がないのか~鷲谷いづみ~」という教科書に基いたテストなのですが、私が読んでもとても興味を惹きました。今の小学生の勉強は、現代に沿った内容で刺激になります。私も勉強してみようとつい思ってしまいました。
チリのイースター島は、首都サンティアゴから西に約3800km離れた、太平洋に浮かぶ絶海の孤島で、モアイ像で有名なこの小さな島は、無数の火口が残る火山島です。現在、この島に森林は殆ど見られません。しかし、化石や花粉の研究からポリネシア人たちが初めてこの島に上陸した西暦400年頃には、島全体が森林に覆われていたことが明らかとなりました。
ポリネシア人が上陸する前、大陸から離れていたこの島は鳥類が数多く住み着いていました。哺乳動物がいなかったのは、火山の噴火により出来た島であり、泳いでイースター島に辿り着くことのできる哺乳動物がいなかったからです。ポリネシア人がこの島で初めての哺乳動物だったとも言えます。イースター島の森林は、なぜ、どのようにして失われてしまったのか?
下記、内容を引用しまとめました。
①上陸し生活を始めたポリネシア人は、食糧を生産を行うために農地が必要で森林がを切り開かれた
②農作物だけでなく、島から離れた無人島に漁へ出かける、丸木船を作るため森林から太い木が切り出された。
③部族社会を営むポリネシア人にとって、偉大な祖先を敬うために神格化された王や勇者達の霊を象徴する火山岩の巨石に彫刻を施すモアイ像の製作がさかんだった。モアイ像の製作には、島の石切場から出される巨大な火山岩をときには、10km離れた所まで運び、重さが何トンもある巨大な像を運んで行くのに必要なコロを作るために、森林から木が切り出された。
④長い船旅の間の食糧とするために船に乗せていたラットが、ポリネシア人の上陸に合わせて船から逃げ出してしまい、生態系を崩してしまった。
ラットは島で野生化し、他に餌を奪い合う競争相手も天敵もいない島で爆発的に繁殖、瞬く間に島じゅうに広がり、そのラットが椰子の実を食べてしまって、新しい木が芽生えて育つことができなかったようである。
このようにして、3万年もの間自然に保たれて来た森林は、ポリネシア人が上陸後わずか1200年ほどで、ほぼ破壊されてしまったのである。1722年の、オランダ海軍提督のヤコブ・ロッゲフェーンが、この島を訪れたとき、島の繁栄も豊かな森も過去のものとなっていた。
木は切りつくされてむき出しになり、地表の土が雨や風に流され畑はやせ細って行った。そのため農業生産がふるわず、漁に必要な丸木船を作る材木もなくなり、魚や海鳥を捕ることもできず、島は深刻な食糧不足に陥って行った。
そこに人口爆発が起こる。当時の島には、7千人~1万人を超える人々が、暮らしていたと言われているが、数十年の間に、人口が約4倍にも膨れ上がり、食糧を奪い合う村同士の争いが絶えず、モアイ倒し戦争も起き、島の人口も最も栄えていた頃の1/3にまで減少して行った。
ひとたび自然の利用を誤り、健全な生態系を傷つけてしまえば、文化も人々の心もあれ果ててしまい、悲しい運命をたどる。祖先を敬う文化は様々な民族に共通であるが、数世代後の子孫の幸せを願う文化は一般的でないのかもしれない。
今後の人類の存続は、子孫に深く思いをめぐらす文化を早急に築けるどうかにかかっているのではないだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
↑という、内容を読み終えて、感じたことは、自然は偉大でこの恵みは利用することと同じくらい守っていかなければいけないということではないかと思いました。
自然は壊すのは簡単だけど、治すに時間と労力がかかる。「いつまでもあると思うな親と金」ではないけれど、豊かな自然が常にあるものだと自由にしていると、取り返しのつかないことになると、イースター島の歴史から学べます。
ポリネシア人は利用は上手に出来たけれど、自分たちの子孫と同じくらいに自然を愛し守り育てることが出来ていれば、森林がなくなることはなかったでしょうね。
人間は頭でわかっていても、忘れてしまい行動に定着するまでに時間がかかることがよくあります。例え気づいていても実際に森林を意識することがなければ、守り育むことはいい加減になっちゃいそうです。それが、話のできる人間の子供なら理解はできますが、相手は自然ですから、思い遣る気持ちを話のしない自然に向ける想像力を持つことができていたらよかったのになぁ。。。
自然は与えてくれる一方の存在ですね。私たちが自然に与えることはあまり多くないと思います。人間同士のように会話しないから、思い遣りがないと何が起こっているのか気がつきにくいです。
会話できていたら「ちょっと!ラットが椰子の実食べるから、子供の木が育たないのよ!」って言えたでしょうから、森林もなくなることがなかったですね。
また、ポリネシア人がラットの生態の知識を持ち繁殖と増加、森林の被害に早く気がつけば、対処もできてたかもしれません。
ポリネシア人の食糧として持ち込まれたラットですが、豊富な魚と海鳥へと食文化も変わっていったのでしょうかね?このラットの異常な繁殖を考えると自然界における食物連鎖は、理にかなったものですね。
この島で人間以外の哺乳動物であったラットは、草食動物でラットを食べる肉食動物がいないために増加を辿る一方となりました。ここが絶海の孤島でなければ、ラットを餌とする動物が森を救うことができたのかもしれませんが、持ち込んだラットにより自然界のバランスを崩してしまったのですね。
自然には、どちらかと言うと負担をかけることが多いのかもしれないです。こちらが、与えてもらうばっかりで恩返しができることはないのなら、せめてその自然の恵みに感謝して子供のように守り育むことが、人間のできることだと感じます。
このことから、自然は生命を与えてくれた先祖と同じくらいに、自然を敬うことは大切なんだなーと感じます。敬うとは「相手を尊んで、礼を尽くす」ということですね。
この著者が提唱している今後の人類の存続を、子供たちに託す私たちができることとは何でしょうか?また、「数世代後の子孫の幸せを願う文化」を一般的なものにするにはどうすればよいでしょう。
私なりに考えてみましたが・・・・
自然を人間の思いのままにできるという考えを正して、与えられる資源を尊く思い有難く利用させてもらっているという気持ちと、自然界の掟を神から任されている人間が守ることが、次の世代へ生きて行く子供たちへの貴重な財産になるのだと思います。
幸せを願う文化として大切なことは自然界を神とする、「神」に畏敬の念を持ち、頂いた恩恵に感謝することだと思います。「神」といっても新興宗教の神ではなく私たちの生活に基いた神様です。例えば太陽とか。。。
日本には古来から自然[太陽・地球(水・木・大地・)]を神として敬い、収穫・豊漁などの際には感謝の意味を込めて行う儀式があり、今でも続いています。
ポリネシア人は自分たちの祖先を大切にすることはできたけど、自然を敬うことはしなかったのかもしれないです。
このイースター島の衰微を教訓にすると、子孫の繁栄を望むなら先祖を大切にすることと同じくらいに、自然を神として敬うことができていればよかったのに。。。と思います。
農業に携わっていない人でも、陽の光や水・買って来た野菜や果物から自然の恵みは届いていますから、そのことに感謝できるようになる習慣が大切でしょうね 。
。
自然環境 を大切にしようという運動の奥に必要なのも、意識の奥にある地球や自然への愛情や敬う気持ちがなければ続けることは大変だと感じます。
を大切にしようという運動の奥に必要なのも、意識の奥にある地球や自然への愛情や敬う気持ちがなければ続けることは大変だと感じます。
人間には敬い感謝する対象が必要なのではないか~?と思います。 でなければ、ときに傲慢になり人間さえ良ければいいという考えに傾く危険がある人もいるでしょう。
でなければ、ときに傲慢になり人間さえ良ければいいという考えに傾く危険がある人もいるでしょう。
そうならないように、神や先祖を大切にする存在を意識することで感謝がスムーズに出来て、それが子供たちへの未来にも繋がるのだと思います。
つまり、子孫の幸せを願う文化の究極の答は「与えられたことに感謝する」ことだと思います。
自然を神として、敬うことで自然を大切に守ることが昔からできている日本という国は素晴らしいですね。
この魂は日本人にDNAとして受継がれていると思います。
日本人に生まれたこと。それだけでも誇りが持てます。
イースター島の名前の由来は、復活祭の夜、ヤコブ・ロッゲフェーンにより発見された日がイースター(復活祭)であった為、「イースター島」と名前が付いたと言われています。
今日も読んで頂いてありがとうございます。
※復活祭=キリスト教の典礼暦における最も重要な祝い日で、十字架にかけられて死んだイエス・キリストが三日目によみがえったことを記念する日

そのテストの内容は「イースター島には、なぜ森林がないのか~鷲谷いづみ~」という教科書に基いたテストなのですが、私が読んでもとても興味を惹きました。今の小学生の勉強は、現代に沿った内容で刺激になります。私も勉強してみようとつい思ってしまいました。
チリのイースター島は、首都サンティアゴから西に約3800km離れた、太平洋に浮かぶ絶海の孤島で、モアイ像で有名なこの小さな島は、無数の火口が残る火山島です。現在、この島に森林は殆ど見られません。しかし、化石や花粉の研究からポリネシア人たちが初めてこの島に上陸した西暦400年頃には、島全体が森林に覆われていたことが明らかとなりました。
ポリネシア人が上陸する前、大陸から離れていたこの島は鳥類が数多く住み着いていました。哺乳動物がいなかったのは、火山の噴火により出来た島であり、泳いでイースター島に辿り着くことのできる哺乳動物がいなかったからです。ポリネシア人がこの島で初めての哺乳動物だったとも言えます。イースター島の森林は、なぜ、どのようにして失われてしまったのか?
下記、内容を引用しまとめました。
①上陸し生活を始めたポリネシア人は、食糧を生産を行うために農地が必要で森林がを切り開かれた
②農作物だけでなく、島から離れた無人島に漁へ出かける、丸木船を作るため森林から太い木が切り出された。
③部族社会を営むポリネシア人にとって、偉大な祖先を敬うために神格化された王や勇者達の霊を象徴する火山岩の巨石に彫刻を施すモアイ像の製作がさかんだった。モアイ像の製作には、島の石切場から出される巨大な火山岩をときには、10km離れた所まで運び、重さが何トンもある巨大な像を運んで行くのに必要なコロを作るために、森林から木が切り出された。
④長い船旅の間の食糧とするために船に乗せていたラットが、ポリネシア人の上陸に合わせて船から逃げ出してしまい、生態系を崩してしまった。
ラットは島で野生化し、他に餌を奪い合う競争相手も天敵もいない島で爆発的に繁殖、瞬く間に島じゅうに広がり、そのラットが椰子の実を食べてしまって、新しい木が芽生えて育つことができなかったようである。
このようにして、3万年もの間自然に保たれて来た森林は、ポリネシア人が上陸後わずか1200年ほどで、ほぼ破壊されてしまったのである。1722年の、オランダ海軍提督のヤコブ・ロッゲフェーンが、この島を訪れたとき、島の繁栄も豊かな森も過去のものとなっていた。
木は切りつくされてむき出しになり、地表の土が雨や風に流され畑はやせ細って行った。そのため農業生産がふるわず、漁に必要な丸木船を作る材木もなくなり、魚や海鳥を捕ることもできず、島は深刻な食糧不足に陥って行った。
そこに人口爆発が起こる。当時の島には、7千人~1万人を超える人々が、暮らしていたと言われているが、数十年の間に、人口が約4倍にも膨れ上がり、食糧を奪い合う村同士の争いが絶えず、モアイ倒し戦争も起き、島の人口も最も栄えていた頃の1/3にまで減少して行った。
ひとたび自然の利用を誤り、健全な生態系を傷つけてしまえば、文化も人々の心もあれ果ててしまい、悲しい運命をたどる。祖先を敬う文化は様々な民族に共通であるが、数世代後の子孫の幸せを願う文化は一般的でないのかもしれない。
今後の人類の存続は、子孫に深く思いをめぐらす文化を早急に築けるどうかにかかっているのではないだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
↑という、内容を読み終えて、感じたことは、自然は偉大でこの恵みは利用することと同じくらい守っていかなければいけないということではないかと思いました。
自然は壊すのは簡単だけど、治すに時間と労力がかかる。「いつまでもあると思うな親と金」ではないけれど、豊かな自然が常にあるものだと自由にしていると、取り返しのつかないことになると、イースター島の歴史から学べます。
ポリネシア人は利用は上手に出来たけれど、自分たちの子孫と同じくらいに自然を愛し守り育てることが出来ていれば、森林がなくなることはなかったでしょうね。
人間は頭でわかっていても、忘れてしまい行動に定着するまでに時間がかかることがよくあります。例え気づいていても実際に森林を意識することがなければ、守り育むことはいい加減になっちゃいそうです。それが、話のできる人間の子供なら理解はできますが、相手は自然ですから、思い遣る気持ちを話のしない自然に向ける想像力を持つことができていたらよかったのになぁ。。。
自然は与えてくれる一方の存在ですね。私たちが自然に与えることはあまり多くないと思います。人間同士のように会話しないから、思い遣りがないと何が起こっているのか気がつきにくいです。
会話できていたら「ちょっと!ラットが椰子の実食べるから、子供の木が育たないのよ!」って言えたでしょうから、森林もなくなることがなかったですね。
また、ポリネシア人がラットの生態の知識を持ち繁殖と増加、森林の被害に早く気がつけば、対処もできてたかもしれません。
ポリネシア人の食糧として持ち込まれたラットですが、豊富な魚と海鳥へと食文化も変わっていったのでしょうかね?このラットの異常な繁殖を考えると自然界における食物連鎖は、理にかなったものですね。
この島で人間以外の哺乳動物であったラットは、草食動物でラットを食べる肉食動物がいないために増加を辿る一方となりました。ここが絶海の孤島でなければ、ラットを餌とする動物が森を救うことができたのかもしれませんが、持ち込んだラットにより自然界のバランスを崩してしまったのですね。
自然には、どちらかと言うと負担をかけることが多いのかもしれないです。こちらが、与えてもらうばっかりで恩返しができることはないのなら、せめてその自然の恵みに感謝して子供のように守り育むことが、人間のできることだと感じます。
このことから、自然は生命を与えてくれた先祖と同じくらいに、自然を敬うことは大切なんだなーと感じます。敬うとは「相手を尊んで、礼を尽くす」ということですね。
この著者が提唱している今後の人類の存続を、子供たちに託す私たちができることとは何でしょうか?また、「数世代後の子孫の幸せを願う文化」を一般的なものにするにはどうすればよいでしょう。
私なりに考えてみましたが・・・・
自然を人間の思いのままにできるという考えを正して、与えられる資源を尊く思い有難く利用させてもらっているという気持ちと、自然界の掟を神から任されている人間が守ることが、次の世代へ生きて行く子供たちへの貴重な財産になるのだと思います。
幸せを願う文化として大切なことは自然界を神とする、「神」に畏敬の念を持ち、頂いた恩恵に感謝することだと思います。「神」といっても新興宗教の神ではなく私たちの生活に基いた神様です。例えば太陽とか。。。
日本には古来から自然[太陽・地球(水・木・大地・)]を神として敬い、収穫・豊漁などの際には感謝の意味を込めて行う儀式があり、今でも続いています。
ポリネシア人は自分たちの祖先を大切にすることはできたけど、自然を敬うことはしなかったのかもしれないです。
このイースター島の衰微を教訓にすると、子孫の繁栄を望むなら先祖を大切にすることと同じくらいに、自然を神として敬うことができていればよかったのに。。。と思います。
農業に携わっていない人でも、陽の光や水・買って来た野菜や果物から自然の恵みは届いていますから、そのことに感謝できるようになる習慣が大切でしょうね
 。
。自然環境
 を大切にしようという運動の奥に必要なのも、意識の奥にある地球や自然への愛情や敬う気持ちがなければ続けることは大変だと感じます。
を大切にしようという運動の奥に必要なのも、意識の奥にある地球や自然への愛情や敬う気持ちがなければ続けることは大変だと感じます。人間には敬い感謝する対象が必要なのではないか~?と思います。
 でなければ、ときに傲慢になり人間さえ良ければいいという考えに傾く危険がある人もいるでしょう。
でなければ、ときに傲慢になり人間さえ良ければいいという考えに傾く危険がある人もいるでしょう。そうならないように、神や先祖を大切にする存在を意識することで感謝がスムーズに出来て、それが子供たちへの未来にも繋がるのだと思います。
つまり、子孫の幸せを願う文化の究極の答は「与えられたことに感謝する」ことだと思います。
自然を神として、敬うことで自然を大切に守ることが昔からできている日本という国は素晴らしいですね。
この魂は日本人にDNAとして受継がれていると思います。
日本人に生まれたこと。それだけでも誇りが持てます。
イースター島の名前の由来は、復活祭の夜、ヤコブ・ロッゲフェーンにより発見された日がイースター(復活祭)であった為、「イースター島」と名前が付いたと言われています。
今日も読んで頂いてありがとうございます。
※復活祭=キリスト教の典礼暦における最も重要な祝い日で、十字架にかけられて死んだイエス・キリストが三日目によみがえったことを記念する日
















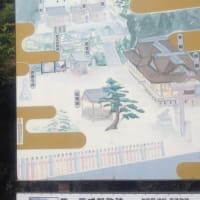



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます