
安曇野を後にして、R278からR158に入った後懐かしの新島々駅へとバックし、改めて上高地方面へと向かう。この道は既に野麦街道である。いくつものトンネルやダムの風景も懐かしい。奈川渡ダムから左へ。ここの入山トンネルは途中で奈川の方面への分岐があるのが面白い。
宮ノ下トンネルには、野麦街道の文字と工女の歩く姿が描かれている。野麦街道へ来た雰囲気にさせられる。

奈川を過ぎて登りに入ると山も色付いた景色だ。林間の道の途中キャンピングカーを追い越す。こんな車で日本中を走る旅が出来るなんて素晴らしいことだ。こんな贅沢を味わってみたい、羨ましいなあ~!!!と思いしばらくするとあれれ石碑が。隣には石室のような姿がある。これは非難小屋(石室)で冬にこの街道を歩く人の避難の為に作られていたものを復旧したものである。さらにその傍には旧野麦街道の案内がある。ここワサビ沢から峠まで約1.3kmとのこと。あとで地図を見ると、現在の車道はえらく遠回りをしていて、旧道は最短距離で峠を目指している。歩いて見たい気持ちも時間的制約で諦め、車を走らせる。

峠に近づくと熊笹の向こうにある色付いた木々の風景が素晴らしくシャッターを押しました。

Wikipediaには;
>峠に群生する熊笹が10年に一度、麦の穂に似た実を付けることがあり、土地の人に
>「野麦」と呼ばれていたことによる。凶作の時にはこの実を採って団子にし、飢え
>をしのいだ。
>また、小説によれば、就労先で妊娠し、厳しい峠越えの最中に子どもを流産する工
>女も少なくなかった。故に野産み峠となり、野麦峠となった、とある。
と説明されていますが、今京都の北山では笹が枯れていて懐かしい風景にも見えました。しかしこの紺碧の空、色付いた木々、笹の緑、これは心に残る風景である。
峠に上がり、非難小屋で軽く蕎麦の昼食。先を急ぐため峠の森へは登れなかったので、「飛騨が見える、、」といいつつ兄の背に負われて死んでいった政井みねさんのお墓には参らず、また飛騨を見下ろすことなく、その写真と像を見るだけで峠を後にする。前方にそびえる乗鞍岳は雲を被っていた。
トップの写真が野麦峠の森の写真です。
標高1672mの野麦峠は飛騨と信州の国境にあり、飛騨と信州・江戸を結ぶ、鎌倉街道、江戸街道の峠であり、ここは江戸直轄領たる飛騨高山から江戸へと向かい、帰る人が歩き、、飛騨鰤の運ばれ、女工さんが年末に雪の道を歩いた峠なのでしょう。地形図を眺めてみると、なるほど昔の人がこの峠越えの道を選んだのが分かる。安房峠を越える道も利用されたはずである。
この峠を越えた人々がそれぞれの思いを抱きながら越えた峠なのでしょう。北山の峠とは標高も遙かに高く、背負われた鰤の重さは鯖の荷の重さより遙かに重く、その苦労に思いをはせるだけである。
今回はあちこち見て歩く従来型のドライブを選んだが、それは所詮通過型の旅行である。峠を感じたいならばその峠を歩いて越さないとその心をつかめないと思う。安曇野を楽しむならそこに滞在しあちこち歩いて廻らないとその良さは分からないのではないかと思っている。あちこちの要所要所をバスや車で通りすぎるツアーはやはり貧しいツアーであり、一つ一つその土地を「体感」する旅行が出来る時間と経済力が欲しいものである。
宮ノ下トンネルには、野麦街道の文字と工女の歩く姿が描かれている。野麦街道へ来た雰囲気にさせられる。

奈川を過ぎて登りに入ると山も色付いた景色だ。林間の道の途中キャンピングカーを追い越す。こんな車で日本中を走る旅が出来るなんて素晴らしいことだ。こんな贅沢を味わってみたい、羨ましいなあ~!!!と思いしばらくするとあれれ石碑が。隣には石室のような姿がある。これは非難小屋(石室)で冬にこの街道を歩く人の避難の為に作られていたものを復旧したものである。さらにその傍には旧野麦街道の案内がある。ここワサビ沢から峠まで約1.3kmとのこと。あとで地図を見ると、現在の車道はえらく遠回りをしていて、旧道は最短距離で峠を目指している。歩いて見たい気持ちも時間的制約で諦め、車を走らせる。

峠に近づくと熊笹の向こうにある色付いた木々の風景が素晴らしくシャッターを押しました。

Wikipediaには;
>峠に群生する熊笹が10年に一度、麦の穂に似た実を付けることがあり、土地の人に
>「野麦」と呼ばれていたことによる。凶作の時にはこの実を採って団子にし、飢え
>をしのいだ。
>また、小説によれば、就労先で妊娠し、厳しい峠越えの最中に子どもを流産する工
>女も少なくなかった。故に野産み峠となり、野麦峠となった、とある。
と説明されていますが、今京都の北山では笹が枯れていて懐かしい風景にも見えました。しかしこの紺碧の空、色付いた木々、笹の緑、これは心に残る風景である。
峠に上がり、非難小屋で軽く蕎麦の昼食。先を急ぐため峠の森へは登れなかったので、「飛騨が見える、、」といいつつ兄の背に負われて死んでいった政井みねさんのお墓には参らず、また飛騨を見下ろすことなく、その写真と像を見るだけで峠を後にする。前方にそびえる乗鞍岳は雲を被っていた。
トップの写真が野麦峠の森の写真です。
標高1672mの野麦峠は飛騨と信州の国境にあり、飛騨と信州・江戸を結ぶ、鎌倉街道、江戸街道の峠であり、ここは江戸直轄領たる飛騨高山から江戸へと向かい、帰る人が歩き、、飛騨鰤の運ばれ、女工さんが年末に雪の道を歩いた峠なのでしょう。地形図を眺めてみると、なるほど昔の人がこの峠越えの道を選んだのが分かる。安房峠を越える道も利用されたはずである。
この峠を越えた人々がそれぞれの思いを抱きながら越えた峠なのでしょう。北山の峠とは標高も遙かに高く、背負われた鰤の重さは鯖の荷の重さより遙かに重く、その苦労に思いをはせるだけである。
今回はあちこち見て歩く従来型のドライブを選んだが、それは所詮通過型の旅行である。峠を感じたいならばその峠を歩いて越さないとその心をつかめないと思う。安曇野を楽しむならそこに滞在しあちこち歩いて廻らないとその良さは分からないのではないかと思っている。あちこちの要所要所をバスや車で通りすぎるツアーはやはり貧しいツアーであり、一つ一つその土地を「体感」する旅行が出来る時間と経済力が欲しいものである。










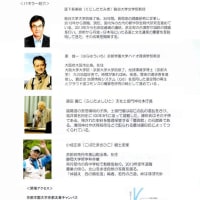
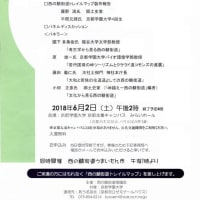
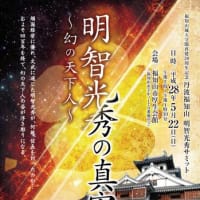


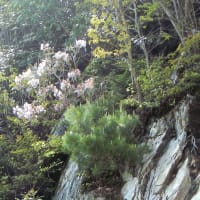


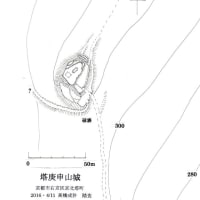

小さな命が歩いてゆく
涙がひとつまた凍り付く
やがて歴史は教えるだろう
幸せなんかどこにもないのを
小さな命はそれでも歩く
幸せは野麦の東
山は高くても
谷は深くても
道は遠くても
夢は途切れても
こんな哀しい現実は映画の中だけであってほしいものです。笹が京北では枯れているとか。原因は何なのでしょうか。秋もいよいよ深まり京北の山々も紅・黄葉に染まり始めたことと思います。今朝は肌寒い秋雨となりました。
春に峠を越えた行女たちは田植えの頃10日ほど帰り、また厳冬の年の暮れに一年の仕事を終えてこの峠を越えたそうです。辛い毎日を過ごした彼女達にとってこの厳しい峠を越えれば懐かしい家族に会えると極楽が待っていたからでしょう。そういった歴史を感じると、黄葉を求めるだけのドライブは気がひけるものがあります。
復元された避難石室の前にはつぎのような一文が紹介されていました;
あゝ野麦峠 山本茂実
しかし雪道の全身はなかなかはかどらなかった。いくら川浦の男衆でも腰まである前夜からの積雪を足でけちらした進のでは、そうはかどるはずはなかった。そうかといって行列の先頭に足の弱い者を立てるわけにはいかない。
先頭は元気の者が選ばれて、川浦衆と一緒に工女は雪を踏み、第一番に行く人の足跡を第二番手がまた踏み、その上をさらに元気な工女たちが続く。こうして三百人、五百人と踏んではじめてそこに道ができる。
吹雪がひときわ激しくタイマツを襲って、幾つかを吹き消して通り過ぎた。もうだれも一言も発する者はなかった。吹雪はタイマツと共に工女衆の歌声も吹き消してしまったのである。
ビュー、ビューと、鋭い刃のように吹雪が梢を通り過ぎる音が聞こえるだけだった。
素敵ないいところに行かれましたねぇ。明治ご維新以来、明治政府にとっては現金収入の三分の一が生糸でした。当社の支社があるリヨンには横浜銀行の前身が早くも明治期に出店していました。リヨンは生糸の一大集積地で、最も重要な産業であったからです。その銀行勤めをして、小説「フランス物語」が若き永井荷風から生まれたのは言うまでもありません。
野麦峠は岡谷の製紙工場まで約140キロの道のりを歩く工女たちの一群が・・・・。13になると出されていましたね。里では、その工女たちの働いたお金を、暮れには必ずアテにしていたようですが、哀史とは、過酷な労働時間や粗悪な食事などが出ていたけれど、誰も待遇が悪いとはひとことも言わなかったとか。哀れでなりません。明治という時代を下支えした女たちの恩恵を感じずにはいられません。
このような美しい紅葉を体験することは一切なかったのでしょうね。今でもその苦衷が伝わって来るように想われてなりませぬ。美しければ美しい風景こそ、直裁に感じられるのです!
この「ああ、野麦峠」の作者、山本茂実の作品ですが、北アルプスの表銀座コースたる喜作新道を開拓した小林喜作を書いた「ある北アルプス哀史 喜作新道」を読んだことがあります。岡谷の工場で働いた工女にしても、マタギたる喜作、皆さん逞しいものだと感心します。
鰤が運ばれた街道、鰤が運ばれるのになぜこの街道が選ばれたのか。富山から諏訪の国へは安房峠を越える道が一番短かったように思うのですが、安房峠を越えてからの梓川の急峻な谷の道はむずかしかったのでしょうか。また佐々成政が越えたざらざら超えで有名な針ノ木峠を越えるルートも商人は利用していた様ですね。地形図を見るのも楽しいものです。
ここ北山にも若狭から綾部へと製糸工場に働きに出た女工さんが越えた峠のルート、尼来峠があります。この峠についてはもう少し調べてから書きたいと思っているのですが、、。
車社会になってからまだ100年は経たない今、それ以前の社会、すなわち街道を歩いた時代を生きてこられた証人達がまだ残っておられますが、その人達もそろそろという年令ですね。車社会以前の社会と以後の社会は革命的な差があると思います。こういった人達が峠をこされた話を聞いておきたい、という気持ちが高まりつつある今日この頃であります。これも硯水亭さまに、民俗学的視点、の大切さをお教えいただいたからに他なりません。
前の会社にいた頃、リヨン近郊の工場と取引したことがあります。とあるクレームが発生しましたのでこちらは深夜まで会社に居残りリオンと電話で連絡をとったのですが、先方のマネージャーは仕事を残したまま帰宅してしまいました。それに比べ岡谷の女工さんの話を硯水亭さまに指摘していただきましたがえらい違いだ。今の経済の危機的状況と結びつけて考えますに、この峠越も単なる昔話でなく、今の社会との関連で考えることが出来ました。ありがとうございました。