ビオトープを作ろうと作業に取りかかったのが2年前、2011年の春、それから2年半、漸く茅のいえの完成式を迎えました。このプロジェクトはある意味永遠に未完成なのですが、活動の中心たる茅のいえの完成を一区切りとすべく、今日完成式が開かれました。
茅のいえをバックに河原林茂吏塾長が挨拶をし、今まで支援頂いた方達へのお礼とこれからの活動や夢について話ました。

50名程の方々がお祝いに駆けつけて下さいました。

この小屋の中心には囲炉裏がありますが、畳に囲まれたのではなく、周囲に丸太の椅子を置いています。写真はありませんが天井は竹造りです。今日のふるまい善哉の鍋などがおかれて雑然としていますが、この囲炉裏を囲んで語り合う機会も増えることでしょう。

壁面には鉾杉塾名物の「唐臼」が置かれています。これは移動可能ですので今後もイベントなどで活躍してくれるでしょう。今日はこれで4臼程餅つきをしました。

小川ゾーンはまだこの状態で、タラの木が数本植わっているのみです。これから一歩一歩仕上げていきます。2年半前、休耕田にスコップで川を掘り、石を運んだのが懐かしく思い出されます。

綺麗な花を咲かせていた蓮も今は枯れた状態です。メダカは雑魚に食べられずに元気かしら。左下にある木枠のブロックには茅の切れっ端が溜めてあるのですが、来年はカブトムシが来てくれるでしょうか。右の方には私の植えた木もあるのですが...
対岸の山の一部が雑木林になっていて今は様々な色に紅葉して自然の移り変わりを感じさせてくれます。春には若い緑が美しく、山桜もその花を見せてくれます。

鮎の開きの一夜干しです。

今日は、この焼鮎、ぜんざい、野菜たっぷりの味噌汁、舞茸の炊いたん、お漬け物、そして赤飯が振る舞われました。代白柿の皮を剥いて貰って軒下に吊り下げていましたが写真を撮るのをわすれてました。椎茸もありましたので、私はこっそりとそれを餅米を蒸している竈の傍で焼いて食しましたがなかなかの味でした。
大勢の方々がお祝いに駆けつけて頂き嬉しかったのですが、その中には遙か大阪からの大学生のグループもありました。周山から自転車で参加頂いたグループも。
宇津で自然薯の栽培で大忙しのフロンティア協会の徳丸氏も時間を割いて参加頂きました。水源の森プロジェクトなども手掛けられていますが、色んな活動の点を今後如何に線にもっていくかなど沢山の構想や夢を聞かせて貰いました。この茅のいえやビオトープを今後どう活用していくか、その活動の中で築かれたネットワークを活かして考えて行かないとと思っています。










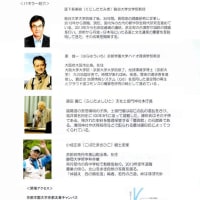
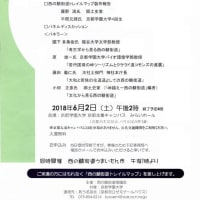
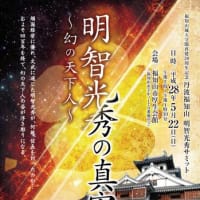


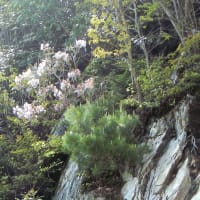


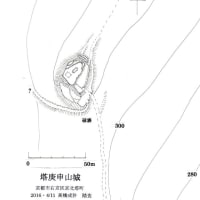


けど、まだまだ成長、発展していく場でもありますね。
1、茅葺きの建物。文句なしに美しいですね。思わず見とれてしまいました。村おこし(このことば、軽い感じで好きではないですが、とりあえず)の拠点ができましたね。
2、囲炉裏。またいいですね。ここでいっぱいやりながら、村の今昔、おのれの今昔について話をするのも楽しいでしょうね。それとも、使用規則があってそんなことはダメですかね?ちょっと泊まってみたい建物ですね。民宿にほしいですね。その際は、3、鮎の開き。さらに自然薯を希望します。この鮎は干した保存用でしょうか。うまそうですね、1尾で2合いけそうです。
ただこの小さな活動に共感して頂いて協力して頂いた人々のネットワークというのは凄いもんだと思い始めました。あちこちでいろんな夢を見て頑張っておられる人が多いことを知ったのも嬉しいことです。
まあどう活用するか、囲炉裏を囲んで話し合って行きますわ。
村おこしって言葉は私もぴんと来ません。こんなもんが出来たからと言って所謂村おこしが出来るはずはありません。あ、村おこしって何やねという疑問を今も持っています。
囲炉裏良いでしょう。でも残念ながら10畳位の狭い空間で全面土間です。宿泊は出来ません。どうしても寝たいなら、竹の天井の上で寝たら、と冗談で言ってます。囲炉裏の暖かさが下からじんわり伝わってくるでしょう(^_・)私がこの天井の上で作業した経験から天井が抜けることはなかろうと思っています。
鮎の開きですけど、丸ごとかぶりつくとまあまあの味でした。ここを美味いもんを食したいと思ってこられてもなかなかサービスを提供出来る態勢があるわけでもありませんのであしからず。でもね、この囲炉裏を囲んでこんな美味いもん食ったよ、酒も美味かったという報告はするかもしれません。乞うご期待(^_・)
いやはや、素晴らしい試みで、感心しています。黒田の記事や古文書の記事など、興味深く読んでいます。話題は何かと湖西や丹波・篠山などが中心となりがちですが、Fujinoさまの記事はとっても貴重です。松上げだって、小浜からのサバを運んだ方への感謝のお地蔵さま祭りですものね。この区域の貴重な発掘はご貴殿によって、まだまだこれからあるのでしょう。時々コメさせて戴いてよろしいでしょうか。有難う御座いました!
私は古文書が読めるわけでなく根源的な研究はできないのですが、足許に眠る遺産を知ることは大切な事だと思っています。
またこの欄でご教示頂ければ嬉しいです。
ただ、
松上げだって、小浜からのサバを運んだ方への感謝のお地蔵さま祭りです
はよく分かりませんが...
先日、鯖街道と納豆餅を関連づけられた投稿を読んだのですが、何じゃこりゃ、などと思っています。
広河原の松上げ(火の用心のために花背の消防団が担当し出動)は精霊送りと火防と豊年の予祝として存在しているわけですが、実は佐々里峠の最上部に、お地蔵さまの祠がありますね。そのお地蔵さまは案外新しく、若狭の七右エ門さんへ対するお地蔵さまなんです。広河原では8月24日の松上げの直前に、佐々里峠の、その祠から、お地蔵さまを七右エ門の峠道を通り担いで来て、集落の観音堂に移します。七右エ門さんにも見せたいわけでしょうね。放り上げ松を投げ、燈籠木に投げて、火を出して、高くあがったほうがいい兆候だとか、やんやの喝采となるわけです。その後観音堂に行き、小踊りを踊り終わりますが、翌日に再び七右エ門地蔵さんを佐々里峠にお返しします。そこでは七右エ門さんに感謝する形で若狭の方角へ向け、お地蔵さまが鎮座しています。広河原では、昭和の初期に活躍した若狭の七右エ門(これは屋号で、実名は大江公平氏のこと)でして、サバを中心に街道稼ぎをした七右エ門さんに感謝し、同様に街道稼ぎをした地元の方々などへも感謝と安全祈願をしたわけです。特にこの広河原地区へは七右エ門さんの功績が大きく、例え留守であってもサバなどの海産物を天井に吊るしておいたとか。京都市内へだけの鯖街道ではなく、山国の方々にとっても、貴重な蛋白源として、イキのいいサバを大変楽しみにしていた証拠でありましょう。特にお地蔵さまを若狭の方角に向けて置いてあるなんて感動ものだと思っています。
そして七右エ門を象徴として、多くの、この地域を廻る街道稼ぎの方々を手厚く供養したのではないでしょうか。朽木市場の丸八百貨店にあるサバの馴れずしやサバ寿司が食べたいです。そしてサバを最も美味しく食べるのは、やっぱり小浜の焼き鯖でしょうか。18年前から始まった鯖街道ウルトラマラソン大会は小浜の小さな商店街の原点から京都・鴨川まで、18里(72キロほど)の駆けっこは針畑越えで行われますが、朝早くからで、平均で12時間掛かるとか。完走記念は焼き鯖一尾。いやぁ羨ましいものだと思っています。
小浜三丁目界隈は昔花街があったわけですが、話し言葉はすべて京訛りを色濃く残していまして、この習慣は何と山形県酒田市にも現存しています。鯖街道=塩街道は文化の波及道としてまだまだ検証されなければなりませんですね。そういう意味ではFujinoさまのご意図と記事は生きた証言として、とっても貴重です。有難う御座いました!
小浜の三丁町界隈は先日もゼミの歴史探訪で訪れました。古い建物が残っていて良い雰囲気なのですが、常高寺から夕方にはお通夜があるから早く来いと急かされたりしてゆっくり見て回れなかったのは残念でした。小浜には立派な仏さんがいっぱいいらっしゃるし、あちこち巡りたく思っています。小浜のボランティアガイドの立派なのはたとえ二人でもガイドしますよと言って貰ったことです。このサービスを利用しない手はないと思っています。またあるきっかけで小浜の歴史を勉強されている会とのコネクションも出来ましたのでいろいろと教えを乞いたいとも思っています。昔は若狭は大陸文化伝来の玄関口であり、京の都と、この北山界隈を通って文化や物資が行き来した、という観点からいろいろな話や、そのルートを調べたいと思っていますし、また昔の街道の復旧も視野に入れています。加うるに酒田と京・大坂の交流にも興味を持っています。海の道ですね。
先日のもみじ遊山には、名田庄の文七踊り保存会の方々にお越し頂いてその音頭と踊りを披露して頂きました。これからはいろんな分野で研究されている人に教えを乞う時間を作りたいと考えています。民俗学的な視点も含めてご教授下さい。ありがとうございました。