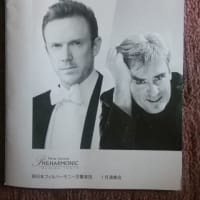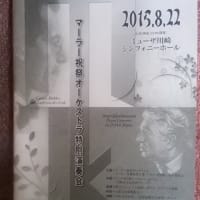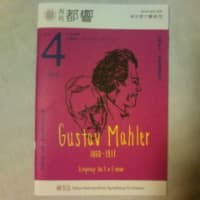マンドリンの演奏会が続いた。
出演者でもある知人から案内を受けたとき、興味を惹かれたのは2点ある。一つは編成、もう一つがプログラムである。
「マンドラアンサンブル」である。編成は
マンドラ・コントラルト:4
マンドラ・テノーレ:6
マンドロンチェロ/リュートモデルノ:3
マンドローネ:2
ヴィオロンチェロ:1
オーボエ:1
クラリネット:2
ハープ:1
オルガン:1
詳細は当日初めて知ったのだが、マンドリンの代わりにマンドラ・コントラルトが高音域を受け持つ、ということは聞いていた。マンドラ・コントラルトのいくつかは通常のマンドラ・テノーレを用い、調弦を変えることで対応したようである。
曲目は
パーセル:シャコンヌ
バッハ:ブランデンブルク協奏曲第6番
エルガー:ソスピリ
フォーレ:レクイエム
である。フォーレには合唱も加わる。
この団体はマンドリン奏者でもある久松 祥三氏が主宰する教室の生徒達によるアンサンブル、という一面も持っており、生徒達及び外部からの参加者によりメンバーは構成されている。
パーセルは先日の東京ツプフアンサンブルでも聴いた曲である。ただ、ツプフではマンドリン属の楽器全てで弦を単弦とし、張りの柔らかい弦を用いてバロック期の柔らかい響きを志向していたのに対し、ここでは通常の状態で演奏しており、よりモダンな響きとなっていた。好き嫌いは人によるのだろうが、サウンドとしては聞き馴染みがあるせいか、こちらの方がよりリラックスして作品世界に入り込めたのは事実である。
続くバッハは難曲であるが、フーガでの受渡しなど随所でバッハならではの立体的な音世界を聴くことができた。ここまでの2曲は指揮者をおかず、久松氏は演奏者として参加していた。ただ、指揮者をおかない合奏にしては奏者間のコミュニケーションが少ないように見受けられ、演奏中に時として合奏の進む方向がはっきりしなくなるような瞬間も無いではなかった。
エルガーで指揮者を迎えてからは合奏が見違えるように求心的に変化した。中音域の充実した編成からはエルガーの世界を体現したような響きが聴かれた。初めて聴く曲であったが、改めてエルガーの素晴らしさに触れることができた。
フォーレでは合唱が圧巻。教会という場所柄、オルガンと合唱を想定した音響効果が考えられているのかもしれないが、素晴らしい響きであった。また、管楽器も特筆すべきであろう。原曲の2管編成のオーケストレーションから、ここでは管楽器はクラリネットとオーボエのみが用いられていたが、要求される多様なニュアンスによく応えていたと思う。特に、サンクトゥスにおける「ホザンナ」を導くファンファーレは出色の演奏だと感じた。
そのサンクトゥス、ピエ・イエズあたりから演奏はフォーレ独特の、静謐な中にも集中力を増し高揚する宗教的な情熱を十分に表出し、終曲イン・パラディスムでは安息の時を描いた。
アンコールも好演であったが、あのレクイエムの静かな感動の後にさらに音楽が必要であったかどうかについては疑問も感じる。
ただ、演奏者・聴衆一体となってフォーレの世界に浸ったひと時であったことは確かである。賞賛に値する演奏会といえよう。
出演者でもある知人から案内を受けたとき、興味を惹かれたのは2点ある。一つは編成、もう一つがプログラムである。
「マンドラアンサンブル」である。編成は
マンドラ・コントラルト:4
マンドラ・テノーレ:6
マンドロンチェロ/リュートモデルノ:3
マンドローネ:2
ヴィオロンチェロ:1
オーボエ:1
クラリネット:2
ハープ:1
オルガン:1
詳細は当日初めて知ったのだが、マンドリンの代わりにマンドラ・コントラルトが高音域を受け持つ、ということは聞いていた。マンドラ・コントラルトのいくつかは通常のマンドラ・テノーレを用い、調弦を変えることで対応したようである。
曲目は
パーセル:シャコンヌ
バッハ:ブランデンブルク協奏曲第6番
エルガー:ソスピリ
フォーレ:レクイエム
である。フォーレには合唱も加わる。
この団体はマンドリン奏者でもある久松 祥三氏が主宰する教室の生徒達によるアンサンブル、という一面も持っており、生徒達及び外部からの参加者によりメンバーは構成されている。
パーセルは先日の東京ツプフアンサンブルでも聴いた曲である。ただ、ツプフではマンドリン属の楽器全てで弦を単弦とし、張りの柔らかい弦を用いてバロック期の柔らかい響きを志向していたのに対し、ここでは通常の状態で演奏しており、よりモダンな響きとなっていた。好き嫌いは人によるのだろうが、サウンドとしては聞き馴染みがあるせいか、こちらの方がよりリラックスして作品世界に入り込めたのは事実である。
続くバッハは難曲であるが、フーガでの受渡しなど随所でバッハならではの立体的な音世界を聴くことができた。ここまでの2曲は指揮者をおかず、久松氏は演奏者として参加していた。ただ、指揮者をおかない合奏にしては奏者間のコミュニケーションが少ないように見受けられ、演奏中に時として合奏の進む方向がはっきりしなくなるような瞬間も無いではなかった。
エルガーで指揮者を迎えてからは合奏が見違えるように求心的に変化した。中音域の充実した編成からはエルガーの世界を体現したような響きが聴かれた。初めて聴く曲であったが、改めてエルガーの素晴らしさに触れることができた。
フォーレでは合唱が圧巻。教会という場所柄、オルガンと合唱を想定した音響効果が考えられているのかもしれないが、素晴らしい響きであった。また、管楽器も特筆すべきであろう。原曲の2管編成のオーケストレーションから、ここでは管楽器はクラリネットとオーボエのみが用いられていたが、要求される多様なニュアンスによく応えていたと思う。特に、サンクトゥスにおける「ホザンナ」を導くファンファーレは出色の演奏だと感じた。
そのサンクトゥス、ピエ・イエズあたりから演奏はフォーレ独特の、静謐な中にも集中力を増し高揚する宗教的な情熱を十分に表出し、終曲イン・パラディスムでは安息の時を描いた。
アンコールも好演であったが、あのレクイエムの静かな感動の後にさらに音楽が必要であったかどうかについては疑問も感じる。
ただ、演奏者・聴衆一体となってフォーレの世界に浸ったひと時であったことは確かである。賞賛に値する演奏会といえよう。