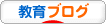ずいぶん久しぶりにブログを更新しますが、その後の近況報告を兼ねて、学校図書館の勉強会のお知らせをさせていただきます。下記のとおり5月12日(日)に神戸で学校図書館の勉強会を開きます。できるだけ幅広い分野で活動しておられる皆さんに話し合いに加わっていただきたいと思いますので、この場でご案内をさせていただきます。
第11回学校図書館自主講座(神戸)
テーマ:「学校文化を変える学校図書館~フィンランドOulu市の実践分析を読み解く~」
日時:5月12日(日) 午前11:20-17:00
場所:新長田勤労市民センター 会議室3
(三ノ宮からJRまたは地下鉄で新長田駅下車、すぐ。新神戸駅から地下鉄で15分)
http://www.kobe-kinrou.jp/shisetsu/shinnagata/
2002年から2004年にかけてフィンランドのオウル市で実施された、情報リテラシーを育む学校図書館プログラムの成果を分析した下記の論文をもとに、学校教育と学校図書館、さらに学校と地域社会との連携などについて考えます。
(英語で書かれているこの論文の内容は、有志が分担して要約したものを配布し、それぞれの担当者が説明します)
オウル市の11の小中学校と3つの高等学校が参加して実施されたこのプログラムは、SLI (the School Library of the Information Society「情報社会の学校図書館」)と呼ばれ、2000年にオウル大学の研修を受けた8人の校長先生が、学校へのICTの導入にあたって情報リテラシーを育む学校図書館の教育的機能に着目したことがきっかけで実現しました。情報専門職としてこのプロジェクトに関わり、コーディネーター及びファシリテーターの役割を果たしたこの論文の筆者Eeva Kurttila-Materoさんは、2004年にプロジェクトを終えてその職を辞した後、11の小中学校から提出された報告書や刊行物を分析し、それにもとづいて2009年に各学校の教師と校長へのインタビューを実施し、教師と校長の意識がどのように変わったかを追跡的に研究しました。そうすることによって筆者は、3年間の集中的な学校図書館プログラムで芽生えたものが、その後、どのように展開し、他の学校にどのような影響を及ぼしつつあるかといった点にも眼差しを向けています。
以下、私がこの論文に注目して、これからの我が国の学校図書館のあり方を考える上で示唆に富むと考えた理由をいくつか挙げておきます。
1.フィンランドにおける実践である
フィンランドは、OECDが実施する国際的な学力テストPISAで好成績を上げていることや教育体制や公共図書館が充実していることでも知られていますが、その一方で学校図書館の発達は遅れていると言われています。そのフィンランドでおこなわれたSLIプロジェクトの分析がどんな意味をもつのかを探りたいと思います。
2.学校文化の変容を目指す取り組みである
学校に新しい教育実践が定着するには、まず教師と校長の意識と行動様式が変わらなくてはならないし、保護者や地域社会の理解と協力も必要ですが、それは一朝一夕に成し遂げられるものではありません。この論文は、SLIが児童の情報リテラシー育成のために学校文化の変容を目指していることに着目し、長期的な展望をもって、個々の教職員が新しい考え方を内面化し、学校全体に新たな文化を醸成していくプロセスに眼差しを向けています。
3.様々なレベルの「協働」と「統合」を目指す取り組みである
「協働(コラボレーション)」に関しては、学校共同体における教師、児童、保護者の相互関係が織りなす様々な形の協働はもちろん、行政と学校と公共図書館を結ぶラーニングコモンズの形成、さらには地域の研究機関、教員研修機関としてのオウル大学の役割にも注目したいと思います。また「統合」については、教科横断的で総合的な学習活動や、その担い手としての学校図書館と教育課程との統合、情報スキルと学習内容との統合、アカデミックな研究から得られた知見と実践知との統合といったことも、この論文の一貫したテーマになっています。
4.ホリスティックな観点に立つ研究である
学校や学校図書館を変化・発展するシステムと捉えて、そのシステムを構成する部分と全体、あるいはシステムとその環境との間の有機的かつダイナミック(動的)な相互関係を記述するために、この論文はヘルシンキ大学のユリア・エンゲストロームが開発した「活動理論モデル」を利用しています。そこから学校図書館の活動に影響を及ぼす重要な要素とその複雑な構造を解き明かす手がかりが得られるのではないかと思います。
勉強会のプログラムと申込方法は下記の通りです。(時間配分は、一応の目安とお考えください)
日程:5月12日(日)11:00-17:00
11:00 開場(受付)
11:20 はじめに(趣旨と日程の説明)
11:30 研究の概要・・・足立正治
12:00理論的背景1
・学校の経営モデルと学校図書館・・・足立正治
・「学び」の理論・・・松田ユリ子
12:30 昼食
13:30 理論的背景2
・学校文化を変える学校図書館・・・天野由貴
14:00 調査結果の分析
・学校文化を変えるツール(教育方法、学校図書館、教師教育)・・・嶺坂尚、細川恵利
・ルール(教育課程、教科書、時間割、規律)・・・松田ユリ子
・仕事の分担(補助職員、図書館担当教員、教師の自律性)・・・山本敬子
15:00 休憩
15:20 調査結果の分析
・コミュニティ(学校共同体、地域社会)・・・米谷優子
・学校経営の対象(リテラシー教育、読書教育、教育の概念)・・・天野由貴
16:00 結論と話し合い・・・松戸宏予、足立正治
参加費:500円(会場費・資料費)
参加申込方法:
自主講座のメンバー以外の方は、下記のアドレスにメールで、氏名、所属、メールアドレス、当日にやりとりできる連絡先をお知らせください。