「図書館雑誌2013.1」の「窓」欄に上田修一慶應大学教授が寄稿しておられる『「調べるのが好き」が七割の社会』という短い文章を読んで、さまざまな想いを掻き立てられた。図書館のレファレンス件数が減る一方で「調べるのが好き」と回答した学生が七割もいるという。検索エンジンとスマートフォンの普及によって調査から達成感を味わう人が増えた。高度な検索スキルを身につけた人たちも増えているにちがいない。という流れから「ネオ・アレクサンドリア(Neo-Alexandria)」ということばが脳裏に浮かんだ。「ネオ・アレクサンドリア」とは、20世紀の終わりに半田智久氏(現在、お茶の水女子大学教育開発センター教授)が近未来の情報環境として描いた開放情報時空の呼称である。半田氏によれば、それは「私たちに必要な情報がコンピュータを介して日常的空間に満たされている状態」であって「私たちはその環境を構築し、その中で共に生きることによって単なる情報取得作業に煩わされることなく、多元的な学びの方向性を獲得し、個々に内在している知恵や技能や創造性といった知とその機能を、より豊かに育む機会を得ることができる」(半田智久著『知能環境論 頭脳を超えて知の泉へ』NTT出版、1996)。そのような社会が完成に近づいているのだろうか。
1995年に起きた阪神淡路大震災からの復興の過程で出会った『知能環境論』は、わたしにとって21世紀を展望する学校と学校図書館を統一的に構想するよりどころとなった。子どもたちにとって(そして教師にとっても)豊かな「知のアフォーダンス」を提供することをめざそう。半田氏によれば「知のアフォーダンスとは、外在知がそれと出逢う人の内在知との関係において取りうる意味と価値、すなわちその個体にとっての知識の可能性を指している」(p.189)。そして「学習者にとって豊かで理想的な知のアフォーダンスとは、個々の学習者が必要としているものが常に十分に広く自由に開放されていて、そこでの活動に心地よい刺激と触発を受け、そこから先に知的な冒険をしてゆこうと動機づけられること、そしてそのときそれに応じられる環境があることである」(p.216)。当時、図書館長と視聴覚課長(現在のメディア情報部長)を兼務していたわたしは、再建計画の中に情報ネットワークの構築を組み込むとともに、無線LANとノートパソコンの導入による図書館機能の拡張と図書館職員をふくめた情報専門職の充実をはかった。
震災から2年後の1997年に再建された学校で図書館が目指したのは、快適な資料・情報へのアクセスと情報サービスの充実をとおして知的な刺激を触発される快適な空間(「知のひろば」)を構築することであった。新しく採用されたスタッフと仕事をはじめたときに目を見張ったのは、専門職としての卓越した調査力と発信力であった。その能力を学校教育の中でどうのように展開し開花させるか。それが、わたしにとって図書館経営の中心となった。手はじめに、レファレンスの充実と生徒(および教職員)の情報活用力の向上を柱として、情報活用教育カリキュラムの立案と実施を図書館が担う体制をととのえた。まさに「調べるのが好き」といって自ら調べることで達成感をもつことのできる子どもたちが育つことを期待したのである。
「窓」の文章を上田教授は、レファレンス件数を増やすよりも『「ディープ」な調べものと図書館の間に道筋をつけることを考えた方がいい』と結んでおられる。一般の人がわざわざ図書館に出向かなくても高度な情報検索までできる社会にあっては、図書館の仕事は、レファレンスは件数を増やすことを目指すよりも一筋縄ではいかない複雑な調べものに特化すればいいということなのだろう。だが、わたしは、あえて、この一文をもう少し深く読み込んでみたい。「ディープ」な調べものとは、どういうことを意味するのか。単に難度の高い調べものということなのだろうか。また、道筋をつけるといっても、図書館と調べものの道筋は、一般的な概念としては、すでについているはずなので、それが最近になって壊れたから修復するということではなくて、これまでにはなかった新たな道筋をつけるとしたらどうなるか。わたしは自分の経験を踏まえて、学校図書館のような持続的な学びの共同体のなかで子どもや教師にたいして行われる情報サービスは、ただ依頼された課題に回答するだけでなく、調べたい(知りたい)動機や問題意識、利用者(依頼者)の背景や文脈により深く踏み込んでかかわることが必要ではないかと考えている。資料や情報は、あくまでも「媒体」であり、きっかけであって、依頼者の真の目的ではないはずだ。わたしたちが本を手にして調べものをする目的は、その向こうにある。だとすれば学校図書館では、ただ「資料・情報を提供する」だけでなく子どもや教師のパートナーとして「課題解決に直接的にかかわる」ことが求められる。利用者のプライバシーへの配慮が必要なことは言うまでもないが、そのような関係性の構築は、もしかしたら大学図書館や公共図書館でも求められることかもしれない。そう考えて、昨年の暮れのブログに「間接サービスから直接サービスへ」という文章を書いた。
ここまで書いてきて、ふと、やはり『図書館雑誌』の「窓」欄に掲載されていて感銘を受けた美しい文章のことを思い出した。調べてみたら、それはビジネス支援にかかわっておられる豊田恭子さんが書かれた「人生を応援する施設」という文章だった(『図書館雑誌』2006.3)。そこには、たとえば、こんな一文がある。「書棚の間を徘徊しながら、図書館員と会話を交わしながら、人は自分だけの「解」探しをする。孤独なはずの作業が、図書館という空気に包まれることで、悲壮感から免れる」。豊田さんによれば、図書館によるビジネス支援の第一の意味は、誰かに教えてもらえるような「解」のない問題を抱えて、ひとり悩み、苦しみ抜いて結論を出さなければならない「孤独な戦いを強いられている世の仕事人たちに、貴方たちは一人じゃない、というメッセージを送ることにある」という。図書館に救われるのは、もちろん「世の仕事人」にかぎらない。人生を思いつめた人、いじめや暴力に苦しむ子どもや教師、・・・「自殺したくなったら、図書館に行こう」いのちを育てる図書館員の群像(虫賀宗博、『世界』2005年8月号)で紹介された能登川町立図書館が思い浮かぶ。そこには、まさに「ディープな」課題に直面している人との間に道筋をつけようとする図書館の姿がある。
 |
知能環境論―頭脳を超えて知の泉へ |
| クリエーター情報なし | |
| NTT出版 |










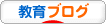


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます