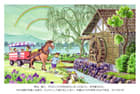私にとって幕末・明治の初期は一番分からない時代でしたが、どういうわけかその時代の作品を描く機会が多いです。
私にとって幕末・明治の初期は一番分からない時代でしたが、どういうわけかその時代の作品を描く機会が多いです。
「浦上のキリシタン物語」から始まって、描いていますが、最近少しだけ背景がわかるようになりました。
女性の小説家の方が、幕末はどうしても大政奉還・尊王攘夷など、難しくなるが、女性の目から見た物をを書けばいいと書いていらっしゃいましたが、一つヒントになりました。 そのつもりでいましたが、どうしても時代背景を入れないと分からないので、難しい訳です。
そのつもりでいましたが、どうしても時代背景を入れないと分からないので、難しい訳です。
ところで、みなさんは直参旗本・家刀自(いえとじ)・小普請・攘夷・佐幕・勤皇などの意味の説明ができますか?
時代劇では説明がなくても見ていますが、まんがとなると、すべてに注を付けなければなりません。
いろいろ勉強んなりますね。
ちなみに、家刀自(いえとじ)とは、女主人のことで、家を切り盛りしている奥さんのことです。










 同じ人物の伝記小説をたくさん読んでいますが、どうしてこうも違うのかと思ってしまいます。
同じ人物の伝記小説をたくさん読んでいますが、どうしてこうも違うのかと思ってしまいます。
ある本では、御父さんは大酒飲みで、息子が結婚した後、新居に子分たちを乗り込ませつぶそうとしたとあったので、そういう人だと思っていました。
ところが、今読んでいる本では、お父さんは、途中で良い人物に変わり、息子の結婚を喜んでいます。
一体どっちが本当なのか? 森有礼の親と妻は、少し離れた所に住んでいて仲良く暮らしていたことが当時の関係者の日記にはありますが、ある方の書かれた小説では、森の親から妻はいじめぬかれたとでてきます。
森有礼の親と妻は、少し離れた所に住んでいて仲良く暮らしていたことが当時の関係者の日記にはありますが、ある方の書かれた小説では、森の親から妻はいじめぬかれたとでてきます。
それに関して、詳しい方がブログで反論されています。
何でもよく調べてまんがを描かないと、とんでもない間違いを描いてしまいます。 ジョージ・ミュラーも、いろんな本が出ていますが、多少の前後関係の間違いや、文章では気がつかないけれど、絵にすると違うのが分かると言う細かい間違いがあります。
ジョージ・ミュラーも、いろんな本が出ていますが、多少の前後関係の間違いや、文章では気がつかないけれど、絵にすると違うのが分かると言う細かい間違いがあります。
それを、これこそ正統と言う本を参考にしながら描いています。
しかし、マーリン・キャロザースさんのまんがはちゃんとした資料に基づいているのと、ご本人に確認しながら描いているので安心です。