 ノートⅡ 「内言語」ノート
ノートⅡ 「内言語」ノート
清田政信にとって詩は方法意識の実践場であった。いや戦場のようなものであった。詩の言葉を紡ぎ出すことと情念が一致して「炎える」詩を書いた。詩は失語を破って発語からうまれた。その至適な作品のひとつ、「内言語」をあげてみよう。
内言語
破滅から翔べ
追いつめられて 辺民の発することばに
わたしはさばかれている
なにゆえ 辺民は流星のように
臓腑を裂いて疾走する
一筋の兇器でなければならないか
なりふりかまわず生きてきて
いつでもくらしのきずなを断てぬわたしの
頭のなかの海へ翔べ
敗走のはてに何かを言おうとすれば
必ず何かを失う
失う意識の終るところが旅立ちのはじまり
言葉を発すれば
かげがえのない少女を失わねばならぬ
あたふたと歩きでる先で
視えない樹が燃える
汀で血が破裂する
臓腑が透きとおる
苦悩のため
透きとおる闇の
球体に近づき きみに近づき
きみでもなく わたしでもない
言葉になるとき
わたしは愛を殺す
暗黙のうちに瀕死のことばよ翔べ
わたしらはことばをうしないつくして愛を知る
感覚の領野をむなしくみたして
巡霊の果てにうずくまり
沈黙のまわりを言葉で囲み
その深処で沈黙の意味を問え
問いの韻律でうねる波の
流砂の根を洗う速度を抽象する
海ぞいの村の 夜の花茎の決債をくぐり
声を忘れて嘔吐する昏迷の朝よ
産声の構図よ
磯臭い母音よ
鳴り響け
巡霊の遊牧民の
昏迷の領野を囲撓する
皎い声のゲリラは撓む根の国の
波止場から わたしの内なる遠景へ
ほとばしる沈黙の 深淵と拮抗する
初々しい発語衝動
この詩が発表されたのが『中央公論』1972年6月号、「特集沖縄の思想と文化」だった。本土ジャーナリズムが復帰する沖縄の内実を吸収する意図で企画した特集に当時の学者、ジャーナリスト、知識人らが答えたようなものだ。
五月十五日・沖縄の経済 (久場政彦)、民衆論(川満信一)、琉球処分から沖縄処分へ(我部政男)、沖縄戦後政治の構図(仲宗根勇)、辺境論(新城兵一)、「空道の思想」とは何か(上原生男)、古琉球の宗教と政治(与那国暹)、王統継承の論理(池宮正治)、言語・文化・世界 (儀間進)、南向きの沖縄文化論( 比嘉政夫)、戦後沖縄の文学( 岡本恵徳)、渇きと豊穣の原思想 (勝連繁男)、沖縄の演劇(中里友豪)、沖縄の芸能(いれいたかし)、内言語-詩(清田政信)、日本国家となぜ同化し得ないか-座談会-( 新川明・岡本恵徳・川満信一)[ほか。
状況の現実に即して沖縄のことを語るこれらの言説のなかで、清田政信の詩は異質だし、異彩だ。しかも、はずれではない。これをつぎのような雑念で読む。
沖縄が復帰するころの時代状況、政治的、社会的状況のなかで書かれたこと。状況における詩と思想の提出が、状況的な言説を深く掘り下げ、個人の言語を深化することで共感域を構築する詩想が貫かれていること。
この年は復帰の年だが、2月に連合赤軍浅間山荘事件や5月に日本赤軍テルアビブ乱射事件があったことを想起する。革命が極限の行動をとる時代。革命運動がおいつめられるようにあらわれた時代。こういう見方はうがちすぎかもしれない。しかし、変革を志向する詩を生きる清田政信が、そういう状況に無知であったと思えない。断片的でありながら状況を深く認知する詩境で書かれたとぼくはみる。もちろん〈テルアビブ〉は時期がずれるので、これをモチーフにしているわけではない。しかし「巡霊の遊牧民の/昏迷の領野を囲撓する/皎い声のゲリラは撓む根の国の」という詩的イメージは背景に中東アラブの緊迫状況から編み出したものではないか。清田にとって、この緊迫感、炎、というのは、詩的心理としてかなうものであったかもしれない。ベトナムと中東は当時の世界の炎の地点だった。これもうがち過ぎかもしれないが。
この詩は『清田政信詩集』(1975年12月)の「眠りの刑苦」に収録されている。(沖縄の)緊張した政治的状況と対峙しながら、状況に隠れる根源的な課題を失うことなく、あくまで自己の詩的思想の声を失わない作品と思う。
「発語衝動」とは失語の対極だ。題名を「内言語」とする詩の展開と意図が隠される。詩や言葉の思想が塗り込められている。情念の言葉で。言葉の場所がどこにあるのか。しかも、言葉が緊迫している。読んでみる。
破滅から翔べ
追いつめられて 辺民の発することばに
わたしはさばかれている
なにゆえ 辺民は流星のように
臓腑を裂いて疾走する
一筋の兇器でなければならないか
いきなり出てくるこの緊迫。失語に従事していた感受性と精神を切り裂く。詩の生成への始まり。詩は準備され発される。始原の導入として読者の感覚を屹立させる。こうまず書き付ける詩人の魂は高いところに生まれている。テンションがはき出す美だ。「わが詩法」でこう書いている。
「自らの生を論理化していると、ひとつの空洞にぶつかる。だがそれはほんとに空洞だろうか。私は否だと答える。論理化という醒めた思考の操作の背後で澱のごとく眠っているものがある。それを夢というもよし、あるいは情念というもよかろう。私はそれをゆさぶるようにして、まず一行の言葉を手に入れる。これが始まりだ。」(わが詩法)
「対象を忘れるほどの夢の充実。そして第一行を瞑目の水先案内として、言葉を拒絶して眠る濃密な原感情。それは生活に深く根ざしながら、決して生活という次元では言葉に顕れない個人史の現在における断面だといえよう。」(〃)
夢も情念もとにかく一行から始めなければならない。詩の生成とは「澱のごとく眠っているもの」をはきだすものだ。そこは明晰という扉なのだ。原感情をゆさぶることで言葉を発生する。こういう詩がはじまることの始原を論理化する言葉にはじめて出会った。詩をはじめる意識が燦々と降り注いでいる。実作者の、なんとも明晰な詩学的言説だ。
開始の導入部に続く「追いつめられて」の圧迫感。「辺民」と「さばき」から導き入れる「臓腑を裂いて疾走する」というイメージ抽出の変貌。ただごとではない。ここはどこだ。言葉は生きられるのか。「辺民」とは誰か。詩に対置する辺民か。辺民は長い歴史と慣習と暮らしと性を結束させて村を持続する自然だ。静かだが強烈な力を持っている。詩人といえども、生活的には辺民のひとりとして生きなければならない。自分のなかの辺民でさばかねばならない。なぜなら辺民は外部でもあるが、外部で格闘するものでもない。内部で格闘するものだ。それは自らの血がひきずっている絶対性と暗い属性だ。詩人が「辺民」を取り出したのは拒絶するためではない。みえざる共感域を構築するものとしての戦略にあるのだ。
「詩のことばが最ものびやかに現出するとき、それは盲目の〈像〉が視覚を回復することであり、一行のことばからはじまって生きられる未成の〈生〉であり、全個人史と絶えずつり合う情念の展開といえよう。したがって生の喪失が深いほど(喪失を感受しているほど)言葉はより垂直に生活の根源へつきささってゆく。」(〃)
しからば「情念」こそが、みえるものを拒否し、未成の生を構築する。詩人はみえるものを信用していない。みえるもので語るのは抑圧体の秩序の世界であり、詩人の「臓腑を裂く」兇器だからだ。みえないもので語るものを見えるもので裁くのは、詩人の言う村の掟であり、法であり国家なのだ。そして生活でさえも。
なりふりかまわず生きてきて
いつでもくらしのきずなを断てぬわたしの
頭のなかの海へ翔べ
「破滅から翔べ」は、ここに着地する。「わたしの頭のなかの海へ翔べ」。生活や生き方の対峙が、詩と反詩の対峙と重なってでてくる。「なりふりかまわず生き」た詩人の姿がでてくる。なにがなりふりかまわずか。詩と生活が相反することか。詩は生活を犠牲にすることもたしかにある。「くらしのきずなを断てぬ」とは生活圏の消去ではなく、「ふり」して生きる世界となる。だから「頭のなかの海」が残されるのだ。そこへ翔ぶしかないのだ。生の喪失をここで復活し、生き生きと表現する準備となる。海はみえる海ではなく、みえない海だ。その海をこうもいうときがあった。
「街に住んでいると夏はいのちが自らを開示する方法ももたずにただ浪費という風俗の中へ衰弱していくようにみえる。だが海へ出るとそういう二分法―衰弱と健康、歓喜と悲哀、物資と生命―は打ち砕かれる。砂丘に立って彼方を見ていると何も見えない。しかし視野をさえぎる〈物〉がないことによってかえって眼線は無限へ向かって投げられる。不思議なものだ。眼は見ることに従属するとき、いつか何も見なくなる。〈見えない〉こと、何ものもないない広がりに佇つことによって何かが見える。」(海への思索)
なるほどなあ。海に佇むとはこういうことか。その海へ詩人は幼い娘をつれて行く。生きていることを確認するために、もだ。だが、その海は「なにものもない広がり」をもって逆に「何かが見える」世界となる。ランボーがいったように「海」と「永遠」は比喩でつながる。
「眼は見ることに従属するとき、いつか何も見なくなる。」とはまさしく誰も実感することではないか。みえるもので支配する世界への反逆として詩は準備されなければならない。また、のちにこう書いている。これは精神の断崖をいっている。危ないことを説明しようとする、この自己分析は心理と病理がおなじであるようにみえる。
「昼何か心に傷を負う。眠りに入るとそれがすぐ夢になっておびやかす。これは現実と夢をへだてる障壁がたいへん希薄になっているのではないかという恐れをいだかせる。これは私の幼年から続く幻覚の資質とシュール・レアリズムによってそれに根拠を得た思いが倍加されて精神が生活からの規制を飛散させたあとにくる症状かもしれない。」(わが病理、1982・3)
みえる生活世界の、眼が従事する世界でなんらかの内面に傷を負った精神が夢にでてくることは誰しもあることだ。肉体だけが生き物でない。眼にみえない精神、心も生き物であること。生命をもっていること。その表出が夢である。それが現実との境界をうしなうとき精神病理とよばれる世界にはいっていく。そこを病理で切ってしまわず、芸術創造の契機にしたのがシュルレアリズムである。精神科医であったブルトンがその力に眼をつけたのはなるほどと思わせる。文学や芸術はみえるもので語るのではなく、みえないもので語るものなのだ。
敗走のはてに何かを言おうとすれば
必ず何かを失う
失う意識の終るところが旅立ちのはじまり
詩を書く=生きるという感覚をもった詩人にとって、詩人は生活社会では敗走者なのだ。勝者は詩を書かないし、書く根拠がない。失う意識の終るところとは敗走者のみが感知する感覚だ。「失う」、これさえも「終わらせる」意識。まさしく、これが「旅立ちのはじまり」なのだ。
(この文章は、沖縄で出されている『脈』81号「特集沖縄の詩人 清田政信」(2014年8月)に書いた「清田政信についてのランダム・ノート」を「改題」して連載しています。)














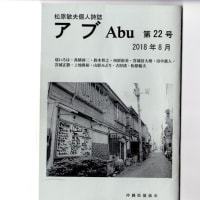
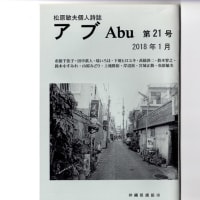




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます