
私はいま、日本小児漢方懇話会に参加しています.
冨田和己先生(こども心身医療研究所)の教育講演は非常に示唆にとむお話でした.冨田先生のいう心身症モデルを私なりに説明しましょう.
このモデルはピラミッド図があり、一番下から、感覚ー>情感ー>知という流れがあるのです.
まず、人間は肉体という物質があります.
そこへ五感という5つの神経チャンネルを使って情報をとりいれます.
NLPではこの五感をV(視覚),A(聴覚),K(触覚),O(嗅覚),G(味覚)と表現します.(味覚、嗅覚はkinestheticを身体感覚として、Kの中に含めることもあります)
そして、この五感のうち、触覚だけがインタラクティブなのです.
自分が相手に触れたら、相手も自分に触れることになります.
視覚は目だけの機能であり、聴覚は耳だけの機能であり、嗅覚、味覚も同様です.これらは情報をうけとりますが、同時発信はしません.
触覚だけが全身にセンサーをもっているのです.
赤ちゃんが母親の乳房にふれ、すいつくことで、母親もまた、赤ちゃんを抱きしめ、お互いを知覚するのです.
この「感覚」こそが「感情」をつくりだします.
五感で得られた情報があるからこそ、そこから私たちは心に感情を創りだします.身体では筋肉運動が展開されます.
そうして、この「感情」にともなって得られた結果の集大成を学んだ結果が「知」というわけです.
「感覚」->「情感」->「知」
というピラミッドがあり、バランスをとるために、「意志」は上向きに伸びようとします.
しかし昨今では「感覚」、「情感」を十分に経験させる前に「知」だけを教えていこうという動きが強いのです.
そのため、
「感覚」->「情感」->「知」が逆ピラミッドになってしまっているのです.
心身症とはそのような状態ではないのか、というのが冨田先生のモデルで、まさに我が意を得たりというところです.
まだ仮説モデルにすぎませんが、
こうした心身症を治癒させるために、「感覚」を刺激する、とくに触覚を刺激する、また感情を自由に表現できる環境を整えるというプロセスは非常に重要だという理由が明確になってきました.
冨田和己先生(こども心身医療研究所)の教育講演は非常に示唆にとむお話でした.冨田先生のいう心身症モデルを私なりに説明しましょう.
このモデルはピラミッド図があり、一番下から、感覚ー>情感ー>知という流れがあるのです.
まず、人間は肉体という物質があります.
そこへ五感という5つの神経チャンネルを使って情報をとりいれます.
NLPではこの五感をV(視覚),A(聴覚),K(触覚),O(嗅覚),G(味覚)と表現します.(味覚、嗅覚はkinestheticを身体感覚として、Kの中に含めることもあります)
そして、この五感のうち、触覚だけがインタラクティブなのです.
自分が相手に触れたら、相手も自分に触れることになります.
視覚は目だけの機能であり、聴覚は耳だけの機能であり、嗅覚、味覚も同様です.これらは情報をうけとりますが、同時発信はしません.
触覚だけが全身にセンサーをもっているのです.
赤ちゃんが母親の乳房にふれ、すいつくことで、母親もまた、赤ちゃんを抱きしめ、お互いを知覚するのです.
この「感覚」こそが「感情」をつくりだします.
五感で得られた情報があるからこそ、そこから私たちは心に感情を創りだします.身体では筋肉運動が展開されます.
そうして、この「感情」にともなって得られた結果の集大成を学んだ結果が「知」というわけです.
「感覚」->「情感」->「知」
というピラミッドがあり、バランスをとるために、「意志」は上向きに伸びようとします.
しかし昨今では「感覚」、「情感」を十分に経験させる前に「知」だけを教えていこうという動きが強いのです.
そのため、
「感覚」->「情感」->「知」が逆ピラミッドになってしまっているのです.
心身症とはそのような状態ではないのか、というのが冨田先生のモデルで、まさに我が意を得たりというところです.
まだ仮説モデルにすぎませんが、
こうした心身症を治癒させるために、「感覚」を刺激する、とくに触覚を刺激する、また感情を自由に表現できる環境を整えるというプロセスは非常に重要だという理由が明確になってきました.

















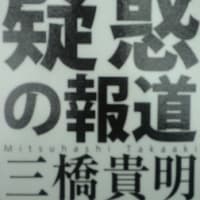
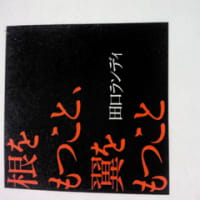

また、私も最近漢方にはまってますが、昨日は匿名患者の漢方なんて飲めない薬を出して何を考えてる云々から始まったクレーム投書にがっくり来てます。女子医・和田恵美子先生(医局の大先輩)に時々、漢方を教わってます。またよろしく、お願いします。
投書はpedftml-cafeには恥ずかしくて書けませんでした。(><)