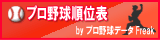☆12月21日はクロスワードの日
1913年のこの日、『ニューヨーク・ワールド』紙が日曜版の娯楽のページにクロスワードパズルを掲載した。それ以前からクロスワードは存在していたが、新聞の連載をまとめた本が1924年に刊行され、世界中にクロスワードパズルが広まるきっかけとなった。
お早うございます。今日もお立ち寄りありがとうございます。☆
12月21日松下幸之助一日一話(松下幸之助.COM)
信用は得難く失いやすい
われわれが何か事を成していく場合、信用というものはきわめて大事である。いわば無形の力、無形の富と言うことができよう。
けれどもそれは一朝一夕で得られるものではない。長年にわたるあやまりのない、誠実な行ないの積み重ねがあってはじめて、しだいしだいに養われていくものであろう。
しかしそうして得られた信用も失われるときは早いものである。昔であれば、少々のあやまちがあっても、過去に培われた信用によって、ただちに信用の失墜とはならなかったかも知れない。しかしちよっとした失敗でも致命的になりかねないのが、情報が一瞬にして世界のすみずみまで届く今日という時代である。
【コラム】筆洗
2014年12月20日 東京新聞TOKYOWeb
▼<まだ魚の時間にゆれてゐた吾子と海抱くわれに雪やはらかく>紺野万里。歌人・松村由利子さんが、科学の魅力を伝える短歌を集めた『31文字のなかの科学』に収められた美しい歌だ
▼魚のような形をした胎児が、まるで生命の進化の道をたどるように形を変え、人間らしい姿になっていく。その命を育む海のような羊水。生命科学者は、そんな神秘的な生命の小宇宙に挑み、多くの謎を解き明かしてきた。のみならず、こんなことまでやってのけるようになった
▼<マウスの背に生える人間の耳ありて愛のオルガンを聴いてゐるなり>米川千嘉子。背中に人間の耳を持つネズミ。何ともグロテスクだが、一九九〇年代に米国で背中から人の耳が生えたようにみえるマウスがつくられたのだ
▼この衝撃的な研究で大きな注目を集めたのが、米国に留学した小保方晴子さんを指導し、「STAP細胞」論文の共著者ともなったバカンティ博士、その人である
▼博士の耳に今聞こえているのは、うつろな響きだろうか。夢の万能細胞発見の報から一年足らず、理化学研究所が、STAP細胞は確認できなかったという検証結果を出した
▼早く忘れてしまいたいような出来事だが、まだ耳をふさぐわけにはいかない。日本屈指の頭脳集団で、なぜこんな悪夢のような事が起きたのか。答えを聞かなくてはならない「なぜ?」が残っている。
☆今朝は晴れています。今日は高校駅伝を応援しています。田舎の世羅高校が男、女供出場しますので応援しています。今日も皆様にとって良い一日で有りますように。☆
1913年のこの日、『ニューヨーク・ワールド』紙が日曜版の娯楽のページにクロスワードパズルを掲載した。それ以前からクロスワードは存在していたが、新聞の連載をまとめた本が1924年に刊行され、世界中にクロスワードパズルが広まるきっかけとなった。
お早うございます。今日もお立ち寄りありがとうございます。☆
12月21日松下幸之助一日一話(松下幸之助.COM)
信用は得難く失いやすい
われわれが何か事を成していく場合、信用というものはきわめて大事である。いわば無形の力、無形の富と言うことができよう。
けれどもそれは一朝一夕で得られるものではない。長年にわたるあやまりのない、誠実な行ないの積み重ねがあってはじめて、しだいしだいに養われていくものであろう。
しかしそうして得られた信用も失われるときは早いものである。昔であれば、少々のあやまちがあっても、過去に培われた信用によって、ただちに信用の失墜とはならなかったかも知れない。しかしちよっとした失敗でも致命的になりかねないのが、情報が一瞬にして世界のすみずみまで届く今日という時代である。
【コラム】筆洗
2014年12月20日 東京新聞TOKYOWeb
▼<まだ魚の時間にゆれてゐた吾子と海抱くわれに雪やはらかく>紺野万里。歌人・松村由利子さんが、科学の魅力を伝える短歌を集めた『31文字のなかの科学』に収められた美しい歌だ
▼魚のような形をした胎児が、まるで生命の進化の道をたどるように形を変え、人間らしい姿になっていく。その命を育む海のような羊水。生命科学者は、そんな神秘的な生命の小宇宙に挑み、多くの謎を解き明かしてきた。のみならず、こんなことまでやってのけるようになった
▼<マウスの背に生える人間の耳ありて愛のオルガンを聴いてゐるなり>米川千嘉子。背中に人間の耳を持つネズミ。何ともグロテスクだが、一九九〇年代に米国で背中から人の耳が生えたようにみえるマウスがつくられたのだ
▼この衝撃的な研究で大きな注目を集めたのが、米国に留学した小保方晴子さんを指導し、「STAP細胞」論文の共著者ともなったバカンティ博士、その人である
▼博士の耳に今聞こえているのは、うつろな響きだろうか。夢の万能細胞発見の報から一年足らず、理化学研究所が、STAP細胞は確認できなかったという検証結果を出した
▼早く忘れてしまいたいような出来事だが、まだ耳をふさぐわけにはいかない。日本屈指の頭脳集団で、なぜこんな悪夢のような事が起きたのか。答えを聞かなくてはならない「なぜ?」が残っている。
☆今朝は晴れています。今日は高校駅伝を応援しています。田舎の世羅高校が男、女供出場しますので応援しています。今日も皆様にとって良い一日で有りますように。☆