
〈危機の時代を生きる――創価学会学術部編〉第1回
感染症を巡る宗教と社会 創価大学文学部教授 井上大介さん
(1971年生まれ。メキシコ国立自治大学大学院博士課程修了。
人類学博士。専門は文化人類学、民俗学、社会学。メキシコ
国立人類学歴史学大学非常勤講師、メキシコ・メトロポリタ
ン自治大学客員研究員、アメリカ・コロンビア大学客員研究
員などを経て現職。
日本宗教学会評議員。創価学会学術部副書記長。支部長)
尾崎洋二 コメント:
私は分断や対立、差別が蔓延するコロナ禍にあって、つくづく
良き人間性と人間関係を支える良き宗教が必要と身に染みて分か
ってきました。
「一国主義」「利己主義」を克服しない限り、コロナ禍やこれ
から起こる未知のウィルス感染症から、人類は打ち勝つことは
できません。
この意味で、良き宗教は必須かと思います。
-------以下 2020年10月7日 聖教新聞--------------
Q1-多くの感染症に立ち向かってきた人類。
その中にあって、宗教は心の支えとなり、乗り越える力を与えてきた。
新たな感染症が猛威を振るう今、宗教はどのような役割を果たし得るのか?
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)は、世界で100万人もの命を奪い、今この時も広がり続けている。
人々の間にこうした不安が漂う中で、宗教はどのように位置づけられてきたか?
感染症を巡る宗教と社会 創価大学文学部教授 井上大介さん
(1971年生まれ。メキシコ国立自治大学大学院博士課程修了。
人類学博士。専門は文化人類学、民俗学、社会学。メキシコ
国立人類学歴史学大学非常勤講師、メキシコ・メトロポリタ
ン自治大学客員研究員、アメリカ・コロンビア大学客員研究
員などを経て現職。
日本宗教学会評議員。創価学会学術部副書記長。支部長)
尾崎洋二 コメント:
私は分断や対立、差別が蔓延するコロナ禍にあって、つくづく
良き人間性と人間関係を支える良き宗教が必要と身に染みて分か
ってきました。
「一国主義」「利己主義」を克服しない限り、コロナ禍やこれ
から起こる未知のウィルス感染症から、人類は打ち勝つことは
できません。
この意味で、良き宗教は必須かと思います。
-------以下 2020年10月7日 聖教新聞--------------
Q1-多くの感染症に立ち向かってきた人類。
その中にあって、宗教は心の支えとなり、乗り越える力を与えてきた。
新たな感染症が猛威を振るう今、宗教はどのような役割を果たし得るのか?
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)は、世界で100万人もの命を奪い、今この時も広がり続けている。
人々の間にこうした不安が漂う中で、宗教はどのように位置づけられてきたか?
A1
WHO(世界保健機関)は4月、信仰コミュニティーに対する“実践的な考察と提言”を発表し、正確な情報の共有による恐怖や偏見の軽減、コミュニティーの強化、精神的連帯などの領域で、宗教団体が貢献し得るとして期待を寄せている。
A2-パンデミックで宗教は二極化しているか?
Q2
創価学会が科学的知見を重視して、人々の集う会合を速やかに中止し、電話やオンラインなどを使っての連携の強化や、機関紙などを通じて専門家による感染症予防対策の啓発活動を展開しているのは、その好例である。
一方、韓国とフランスでは、宗教団体がクラスター(感染者集団)の中心となってしまった。
それぞれの教団では“信仰していれば感染しない”といった幻想を人々に抱かせ、科学的・医学的知見を無視した結果、人々の「密集」状態が無反省に継続された。
まさに、感染症の流行下にあって、宗教は二極化している。
Q3-歴史における二極化は?
A3
こうした二極化は、歴史を振り返っても起きていたことが分かる。
WHO(世界保健機関)は4月、信仰コミュニティーに対する“実践的な考察と提言”を発表し、正確な情報の共有による恐怖や偏見の軽減、コミュニティーの強化、精神的連帯などの領域で、宗教団体が貢献し得るとして期待を寄せている。
A2-パンデミックで宗教は二極化しているか?
Q2
創価学会が科学的知見を重視して、人々の集う会合を速やかに中止し、電話やオンラインなどを使っての連携の強化や、機関紙などを通じて専門家による感染症予防対策の啓発活動を展開しているのは、その好例である。
一方、韓国とフランスでは、宗教団体がクラスター(感染者集団)の中心となってしまった。
それぞれの教団では“信仰していれば感染しない”といった幻想を人々に抱かせ、科学的・医学的知見を無視した結果、人々の「密集」状態が無反省に継続された。
まさに、感染症の流行下にあって、宗教は二極化している。
Q3-歴史における二極化は?
A3
こうした二極化は、歴史を振り返っても起きていたことが分かる。
時代をさかのぼった事例では、3世紀のローマ帝国。
疫病が蔓延した時、ローマの人々の光明となったのは、キリスト教であった。
キリスト教団には医療の知識や技術があり、疫病に苦しむ人たちを看護し、救おうとしたのである。
当時、ローマにそのような集団はなく、病人が快癒すれば、ローマ市民はそこに“キリ
スト教の奇跡”を見たのである。
一方、そんなキリスト教徒も、ペストがヨーロッパに蔓延した14世紀半ばには、社会不
安のスケープゴート(いけにえ)として、ユダヤ教徒にペストの責任を転嫁し、迫害したという歴史が知られている。
さらに、それまで疫病にかかった患者を救済することで信者を獲得してきたキリスト教団も、ペストから人々を救済することは難しく、こうした出来事を通して既存の教団は弱体化し、ルターの宗教改革を筆頭とする“伝統的権威ではなく、各個人の強固な信仰心を重んじる宗教的方向性”が重視されていくこととなった。
Q4-歴史的事例から宗教での対応は?
A4
これらの事例から理解できることは、感染症という社会不安に対し、宗教は一律の対応をしてきたのではなく、各時代の宗教者の解釈と行動によって、ポジティブにもネガティブにも作用してきたという事実である。
現代は感染症の研究も進み、さまざまな感染症がどのような原因で広がるかも分かって
きている。
そうした知見を踏まえつつ、宗教としての価値をいかに発揮できるか。
きている。
そうした知見を踏まえつつ、宗教としての価値をいかに発揮できるか。
そこに宗教の未来もあろう。
Q5-感染症の中での宗教の役割は?
A5
感染症がその他の病と比較し、人々にとって大きな脅威となるのは、当然のことながら「人から人に伝染する」という事実である。
そのことが人々を社会空間の中で「正常」と「異常」に分離し、後者は「隔離」するといった動向と結び付いてきた。
ちなみに、インドの階級制度であるカーストも、マラリアから身を守るための感染症対策として考え出されたとの説がある。
古代インド人は階級の固定化をすることで人と人の交流を制限し、蔓延を限定的にしようとしたのだろう。
もちろん感染症対策において、「隔離」は有効な手段の一つである。
しかし、その「隔離」が身体的なものだけに限らず、差別や精神的隔離、排除になってしまうことは問題ではないだろうか。
昨今の新型コロナウイルスを巡る報道からも、感染者や医療従事者への差別といった心的動向は、見て取れる。
これは人間社会、人間文化というものが、その存在の危機に際し、常にスケープゴートを求め、異質なる他者にその責任を転嫁するという傾向を有しているからである。
他方、宗教は歴史的に、こうした差別に抗する力となり、人々を連帯へと導いてきた。
また病や老化、死をネガティブなものとして排除する傾向に対し、そこにこそ生命尊厳の最も重要な意味があるとするメッセージを発信し、人間の根源的悲嘆を乗り越える原動力となってきたことも事実である。
感染症の話とは異なるが、近年の福祉論では、「ホモ・クーランス(ケアする人)」という言葉が注目されている。
人間は誕生の時も、臨終の時も、自分自身だけで済ますことはできないという考えが基になっており、“人は他者からケアされ、他者をケアする中で生きていく”との概念である。
こうした人間像は、宗教実践における核心であり、時代が変化しても宗教的なものが求められているという証しではないだろうか。
現在は、世の中に“宗教は不要”との風潮もある。
しかし、私はそうは思わない。
分断や対立、差別が蔓延するコロナ禍にあって、他者に尽くす心や一人一人が連帯していく大切さを教え、どのように生きるべきかという根源的な問いに示唆を与える宗教の役割は、より大きなものになると考えている。
また、宗教はそもそも、感染症の歴史の中で発展してきたともいえる。
キリスト教、仏教、イスラム教などの世界に広がった宗教は、中東からインドにかけた地域で誕生したが、この地帯は古くから豊穣な大地である一方、マラリアや天然痘などの疫病の多発地帯であった。開拓が進んで人口が増加し、人々の往来も盛んになると、やがて疫病の大流行に襲われるようになる。
しかし当時、次々と人の命を奪う疫病がなぜ起こるのかは、誰にも分からなかった。
そうした不安にさいなまれる人々の救いとなったのが、宗教であった。
人々は、その中に希望を見いだそうとし、事実、与えてきたからこそ、今でも存在している。
Q6--宗教は人類史において、重要な役割を果たしてきた。
トインビー博士が世界宗教の重要性を強調。
そうした点を踏まえ、これからの世界にはどのような宗教が求められていくのか?
A6
私は今、20世紀の高名な歴史学者アーノルド・J・トインビー博士の知見や態度に学ぶべき点が多いと感じている。
博士は1972年と翌73年に池田大作先生と対談し、この内容は対談集『21世紀への対話』として結実した。(トインビー博士と池田先生との対談集『21世紀への対話』。これまで29言語で出版され、世界で広く読み継がれている)
博士は、ライフワークともいうべき大著『歴史の研究』を61年に完結した後も改訂版を著し、いくつかの理論に修正を加えているが、文明評論家の謝世輝氏によれば、先生との語らいの後に発刊された改訂版では、博士の歴史観に変化が表れているという。
それは、「覇権競争によって生まれる世界国家が、世界宗教を生む」という考え、つまり、世界的な戦争によって、人類がその愚かさから目覚め、初めて世界宗教が生まれるという見方から、「世界宗教の共通の基盤の上に、世界国家(世界連邦)が建設されねばならない」と、従来の主張を変更したことである。
謝氏は、この変化は、池田先生との対談によるところが大きいと述べている。
いずれにせよ、歴史研究に人生をささげた博士が、最晩年に世界国家建設のための宗教の重要性を強調したことは傾聴に値しよう。
この対談集で、トインビー博士は、世界宗教が備えるべき条件として、「自己超克」を挙げた。
これは利己主義に支配された“小さな自分”を乗り越え、周囲の人々の幸福のために尽くす
“大いなる自分”を築くことである。
人類がさまざまな危機を克服し、共生していくためにも、この自己超克を可能にする宗教が不可欠であるというのが、博士の洞察であった。
そうした宗教には、他者を異質な存在として排除するような思想はない。
弱者を包み込む全人類的価値に根差した道義性、倫理観があり、科学や医学などの最先端の知見を学び、生かしていける哲学の深さがある。
そして何より、相手から謙虚に学び、共通点を見いだし、自他共に高め合っていこうとする魂の触発作業がある。
それは、まさに池田先生が世界一級の知性との対話をはじめ、自らの行動を通して示されてきた道ではないだろうか。
創価学会のメンバーはコロナ禍の中、たとえ直接会えなくても、オンラインなどを使って一人一人に寄り添い、友情の絆を強めてきた。
博士は1972年と翌73年に池田大作先生と対談し、この内容は対談集『21世紀への対話』として結実した。(トインビー博士と池田先生との対談集『21世紀への対話』。これまで29言語で出版され、世界で広く読み継がれている)
博士は、ライフワークともいうべき大著『歴史の研究』を61年に完結した後も改訂版を著し、いくつかの理論に修正を加えているが、文明評論家の謝世輝氏によれば、先生との語らいの後に発刊された改訂版では、博士の歴史観に変化が表れているという。
それは、「覇権競争によって生まれる世界国家が、世界宗教を生む」という考え、つまり、世界的な戦争によって、人類がその愚かさから目覚め、初めて世界宗教が生まれるという見方から、「世界宗教の共通の基盤の上に、世界国家(世界連邦)が建設されねばならない」と、従来の主張を変更したことである。
謝氏は、この変化は、池田先生との対談によるところが大きいと述べている。
いずれにせよ、歴史研究に人生をささげた博士が、最晩年に世界国家建設のための宗教の重要性を強調したことは傾聴に値しよう。
この対談集で、トインビー博士は、世界宗教が備えるべき条件として、「自己超克」を挙げた。
これは利己主義に支配された“小さな自分”を乗り越え、周囲の人々の幸福のために尽くす
“大いなる自分”を築くことである。
人類がさまざまな危機を克服し、共生していくためにも、この自己超克を可能にする宗教が不可欠であるというのが、博士の洞察であった。
そうした宗教には、他者を異質な存在として排除するような思想はない。
弱者を包み込む全人類的価値に根差した道義性、倫理観があり、科学や医学などの最先端の知見を学び、生かしていける哲学の深さがある。
そして何より、相手から謙虚に学び、共通点を見いだし、自他共に高め合っていこうとする魂の触発作業がある。
それは、まさに池田先生が世界一級の知性との対話をはじめ、自らの行動を通して示されてきた道ではないだろうか。
創価学会のメンバーはコロナ禍の中、たとえ直接会えなくても、オンラインなどを使って一人一人に寄り添い、友情の絆を強めてきた。
仕事などで、たとえ自分が苦境にあっても、友と励まし合い、共に困難を乗り越えようと奮起してきた。
世界のあの地この地の友には、そうした自己超克の心があふれている。
とりわけ、次代を担う世界の青年たちは先月27日、オンラインでつながり、世界青年部総会を開いた。
“大悪を大善に転じるために立ち上がろう”“一人一人が今いる場所で希望を広げよう”と誓いを燃え上がらせる若人の姿に鼓舞されるものを感じたのは、私だけではないだろう。
世界が分断に向かう今、人類を結び、民衆の連帯をもたらす力の源泉は、世界宗教に求めるほかない。
世界のあの地この地の友には、そうした自己超克の心があふれている。
とりわけ、次代を担う世界の青年たちは先月27日、オンラインでつながり、世界青年部総会を開いた。
“大悪を大善に転じるために立ち上がろう”“一人一人が今いる場所で希望を広げよう”と誓いを燃え上がらせる若人の姿に鼓舞されるものを感じたのは、私だけではないだろう。
世界が分断に向かう今、人類を結び、民衆の連帯をもたらす力の源泉は、世界宗教に求めるほかない。
その連帯の中核として、創価学会への期待は、今後、ますます高まっていくに違いない。










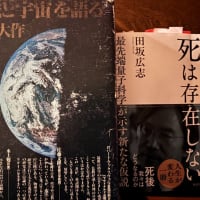









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます